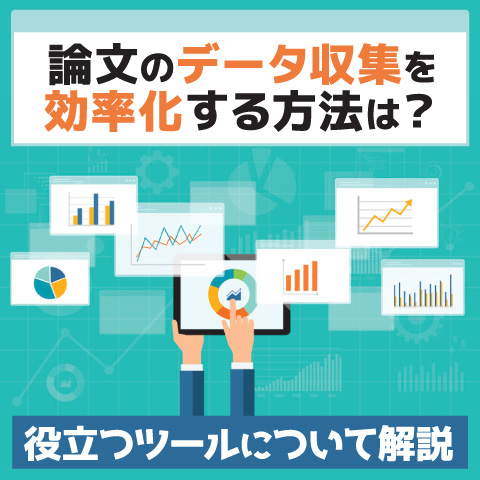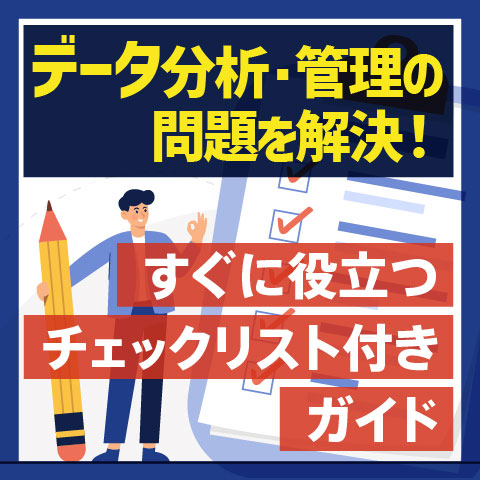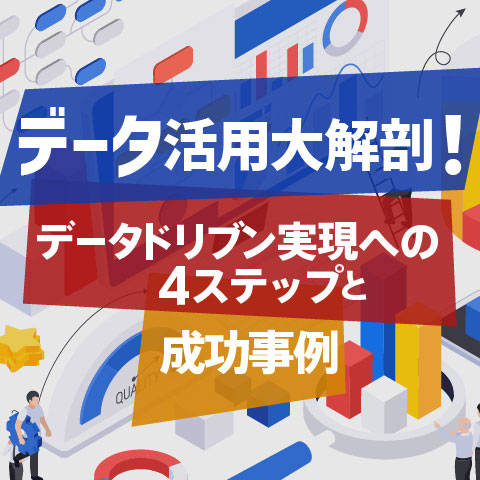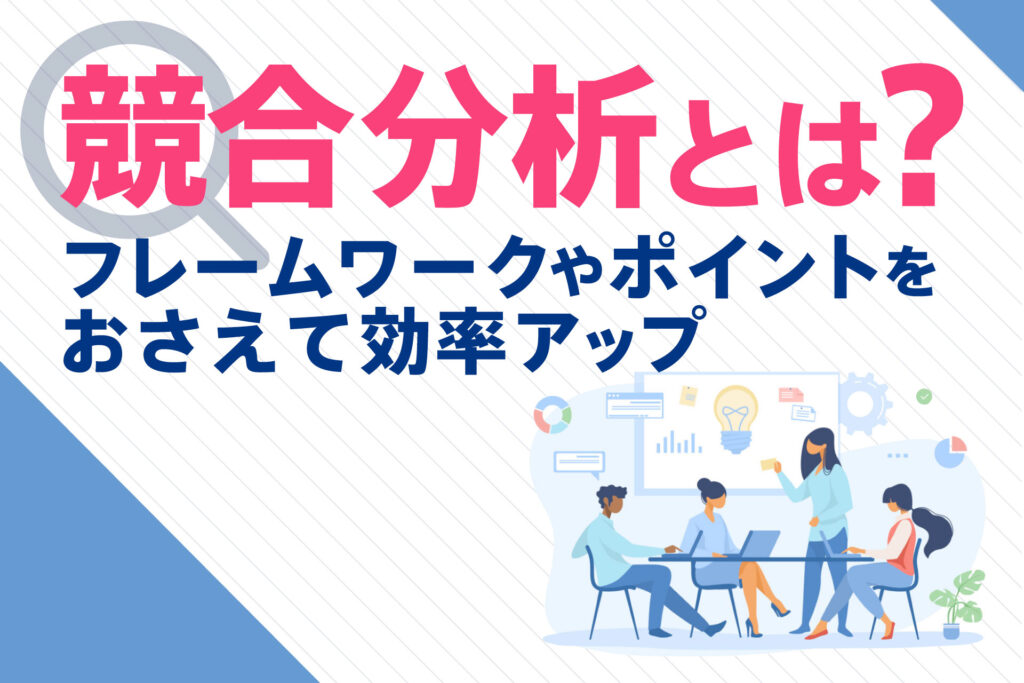
競合分析はマーケティングにおいて非常に重要な作業です。独りよがりにマーケティングするのではなく、敵を知って適切な対応を取らなければなりません。
ただ、意外にも競合分析が知られていないのも事実です。今回は競合分析とはなにか、目的やポイント、効率よくおこなうためのフレームワークを解説します。
競合分析とは
競合分析とは、自社が営業している市場において競合他社の以下に該当するような情報を分析する作業です。
- 事業戦略
- 製品やサービス
- 価格設定
- 販売戦略
- マーケティング戦略
競合分析によって、自社の強みや弱みを客観的に評価し、市場の傾向や動向を把握できれば、自社の戦略立案や改善点の把握に役立てられます。
一般的に、競合分析に時間を掛けることで、自社の市場競争力を高め、戦略的な意思決定を実現できます。その反面、競合分析には適切な情報収集や分析方法の選定が必要で、これを誤ると効果が薄れたりまったく発揮されないこともありえます。
また、競合他社に対する不正確な情報収集や反競争的な行為は法的な問題を引き起こすかもしれません。情報を収集して分析することは重要ですが、やり方に注意する必要があります。
競合分析の目的
競合分析の目的は、自社の商品やサービスが市場でどのように位置づけられているかを理解することです。また、競合他社のビジネス戦略、製品、サービス、マーケティング戦略、販売チャネル、価格設定などを分析して「自社が優位になるために何をすべきか」を判断することが含まれます。
競合分析によって、競合他社が顧客に提供する価値を理解することができ、自社の製品やサービスが差別化できる部分を発見可能です。また、競合他社のマーケティング手法を分析することで、自社のマーケティング戦略を改善できます。他にも、競合他社の成功や失敗を自社の戦略に反映させることもできるでしょう。
さらに、競合分析は市場動向やトレンドを追跡するためにも有用です。市場動向やトレンドを知ることでリスクを最小限に抑えながらその時代にあった戦略を策定することができます。
競合分析の押さえるべきポイント
競合分析のポイントを4つに絞って紹介します。
他社の製品やサービス
競合他社が提供する製品やサービスを詳細に分析し、その機能や価格、パッケージング、マーケティング戦略などを比較検討することが重要です。製品やサービスの強みや弱みを把握すると、自社の製品やサービスを改善する際の方針を決定できます。
顧客の動向
競合他社と自社の顧客動向を把握すると、自社との違いや、自社の製品やサービスに対する競合他社の優位性を把握できます。競合他社の顧客が「何を求めているか」「どのような課題を抱えているか」を分析することで、改善や改良などマーケティング戦略に反映可能です。
他社のマーケティング戦略
競合他社のマーケティング戦略は、自社のマーケティング戦略を改善するために重要です。例えば「どのような広告を出しているか」「どのようなキャンペーンを展開しているか」「価格戦略に傾向はあるか」などを把握します。これにより、現時点で自社のマーケティングはどこに問題があるか把握できるのです。
市場動向
競合他社だけでなく、市場全体の動向を理解することも重要です。市場全体の動向を把握すると、業界トレンドや新興企業の出現など、今後の市場環境を予測できます。市場全体を見ることで自社の戦略をより戦略的かつ有意義なものにすることができます。
競合分析を効率よく行えるフレームワーク9選
競合分析を効率よくおこなうためにはフレームワークの活用が重要です。今回は分析に利用する7種類のフレームワークと、併用できる2種類のフレームワークの合計9種類について解説します。
3C分析
3C分析は、企業が競合他社と差別化し、市場で成功するために必要な要素を評価するものです。「Company(自社)」「Competitor(競合他社)」「Customer(顧客)」の頭文字をとったもので、それぞれの要素を以下のとおり分析し、市場戦略を立てるために利用します。
- Company:自社の強みと弱みを特定し、改善するための戦略を策定する
- Competitor:競合他社の強みと弱みを調べ、自社が優位になれるような戦略を立てる
- Custome:顧客のニーズや行動を把握し、それに基づいて市場に対するアプローチを決定する
STP分析
STP分析のSTPとは「Segmentation(市場セグメンテーション)」「Targeting(ターゲット市場)」「Positioning(ポジショニング)」の頭文字をとったものです。市場を細分化して、最も効果的な市場戦略を立てるために利用されます。市場を理解し、以下のとおり効果的なマーケティング戦略を策定します。
- 市場セグメンテーション:市場を様々なグループに分割し、それぞれのグループに特化したアプローチを立てる
- ターゲット市場:最も重要な市場セグメントを特定し、それに向けたマーケティング活動をおこなう
- ポジショニング:競合他社との差別化を図りながら、市場での独自性を高め
4P分析
4P分析は「Product(製品)」「Price(価格)」「Promotion(販売促進)」「Place(流通)」の4つの要素を評価するためのマーケティングフレームワークです。それぞれの要素から、より効果的なマーケティング戦略を決定します。
- 製品:自社製品の特徴や差別化ポイントを確認や改善するための戦略を考える
- 価格:顧客の需要や競合他社の価格を考慮し、最適な価格を設定する
- 販売促進:広告やセールスプロモーションなどのマーケティング活動に注力する
- 流通:製品をどのように販売するかを決定する
5フォース分析
5フォース分析は、競争環境を評価するためのフレームワークで以下の「脅威(フォース)」を分析します。これらの要素は、競合環境に影響を与える重要な要素であるため、それぞれの要素を評価することで、自社の戦略を立てることが可能です。
- 競合他社:競合他社の強みと弱みを特定して戦略を考える
- 代替製品:代替製品の有無や代替製品との差別化を検討する
- 顧客:競合製品が価格に与える影響を検討する
- サプライヤー:競合他社の存在が製品の価値や価格に与える影響を検討する
- 新規参入者の脅威:新規参入者が市場に参入することによる影響を検討する
PEST分析
PEST分析は、マクロ環境分析の1つで、「政治(Political)」「経済(Economic)」「社会(Social」「技術(Technological)」の4要素を評価するフレームワークです。これらは、企業や組織の周辺環境に影響を与える要因であるため、評価することで市場環境を踏まえた戦略を立てられます。
- 政治:政治的な法律や規制の変化が市場に与える影響を評価する
- 経済:景気やインフレなどの経済的な要因からビジネス環境を理解する
- 社会:生活様式や価値観の変化などから需要やトレンドを分析する
- 技術:最新の技術やITの進化が市場に与える影響を分析する
SWOT分析
SWOT分析は、企業や組織の内部環境(Strengths, Weaknesses)と外部環境(Opportunities, Threats)を分析するフレームワークです。自社の強みや弱みを把握することで、市場環境に対する優位な戦略を立てることができます。
- Strengths(強み):企業や組織の内部的な優位性やリソースを表す
- Weaknesses(弱み):企業や組織の内部的な問題や制約を表す
- Opportunities(機会):市場の成長や新規事業展開など、外部環境から生まれる機会を表す
- Threats(脅威):競合他社や規制環境の変化などを表す
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業が製品やサービスを提供するまでに、どのような価値を付加できているか評価します。各活動が生み出す価値から、競合他社との差別化やコスト削減のための施策を考えるのです。
バリューチェーン分析は、主要な2つの活動である「Primary Activities(主要活動)」と「Support Activities(支援活動)」に分けられ、それぞれ以下を含みます。それぞれを分析することで、企業内部の活動を改善し、より高い付加価値を生み出すための戦略を検討可能です。
主要活動
- Inbound Logistics(入庫物流)
- Operations(製造)
- Outbound Logistics(出庫物流)
- Marketing and Sales(マーケティング・セールス)
- Service(サービス)
支援活動
- Procurement(調達)
- Technology Development(技術開発)
- Human Resource Management(人事管理)
- Infrastructure(インフラストラクチャー)
VRIO分析とは
VRIO分析は、ある企業の資源や能力を評価し、その競争優位性を判断するためのフレームワークです。VRIOとは、「Value(価値)」「Rarity(稀少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織化)」の頭文字をとったものです。この分析では、例えば以下のような質問を使って、企業の能力を評価します。
- これは競合他社に比べて稀少か?
- これは競合他社に模倣されにくいか?
- これは企業の組織によって最大限に活用されているか?
もし、上記の質問に対して「YSE」と回答できるならば、それは企業の競争優位性になりうると考えましょう。一方、「NO」との回答になるならば、改善や強化を検討する必要があります。
ただ、この分析は、外部環境や競合他社の影響を考慮する必要があるものです。そのため、単独で使用するのではなく、上記で紹介した他のフレームワークと組み合わせて使用しましょう。
7S分析とは
7S分析は以下のとおり7つの要素から組織の内部環境を評価するためのフレームワークです。
- Strategy(戦略):組織が達成しようとする長期的な目標や方向性を定義する
- Structure(組織体制):組織の階層構造や権限分配、意思決定プロセスを示す
- Systems(システム):組織が実行するプロセスや手順、制度、情報技術などを示す
- Shared Values(共有価値観):組織の価値観や信念、文化、理念を示す
- Skills(スキル):組織内の人々の専門知識やスキル、経験を示す
- Staff(スタッフ):組織の人員、スタッフの質や数量、雇用形態を示す
- Style(スタイル):組織のリーダーシップや経営スタイル、コミュニケーションスタイルを示す
それぞれの要素が、組織の機能や目的、製品やサービスの開発などにどのように影響を与えるかを考慮するために利用されます。また、影響を明確にすることで、組織全体の強みや課題を把握することが可能です。課題が把握できれば、改善に向けたアクションプランも定められるでしょう。
まとめ
競合分析とはなにかとその必要性や具体的なフレームワークについて解説しました。いくつものフレームワークがあるため、「これは知らなかった」というものも多いのではないでしょうか。競合分析ではこれらを上手く組み合わせて自社や競合他社を評価することが求められます。
ただ、やるべきことが多いため「これは自分で対応できない」ということもあるでしょう。そのような場合はツールを活用してみましょう。例えば、競合監視ツールのTOWAを利用すれば、競合他社のWebサイトから収集したい情報を機械的に収集することができます。毎日複数の競合他社の動向を探りに行く必要がなく、競合他社に動きがあったときのみ通知してくれるため、必要な時に必要なWebサイトをチェックすることができます。是非ご検討ください。