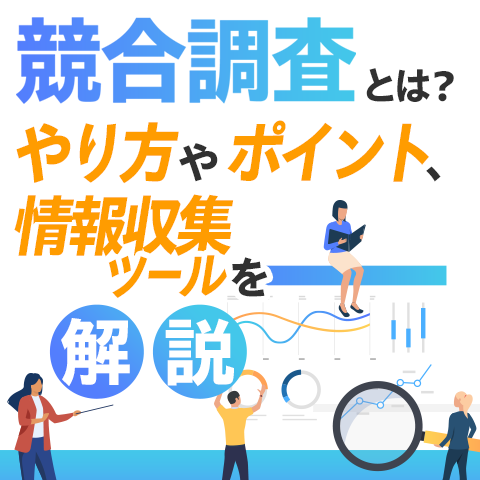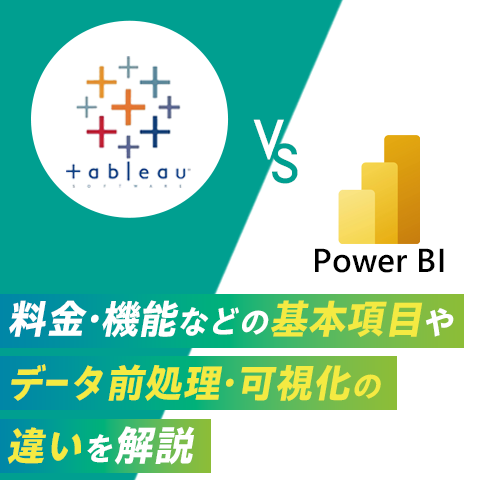企業ではDX推進室などDXの部門が設けられるようになり、これらの業務に従事する担当者の数は年々増えています。ただ、このような部署に配属されても、上手くDXを進められていない人は多いでしょう。特に、担当になったばかりの人は、何から着手すれば良いのか分からないということも多いはずです。
このように、DXが進められていない背景には、データの利活用ができていないことがあるかもしれません。今回は、DXを推進するために重要なデータ利活用について解説します。
データ利活用とは
データ利活用とは、企業が蓄積した膨大なデータを分析したり活用したりして、ビジネスの課題を解決することです。また、これらのデータから新しいビジネスなどを創出することも含まれます。具体的には、データを収集したり整理したりして、それらを分析し、意思決定に活かすことだとイメージすると良いでしょう。
データ利活用の主な目的は、意思決定を今までよりデータに基づいた「データドリブンなもの」にすることです。従来の意思決定は、判断を下す人の経験や勘などに依存する部分が多くありました。これを排除するために、さまざまなデータを活用することが求められています。社内に蓄積されている内部データはもちろん、一般に公開されている外部データも利活用して、より正確な判断を下せるようにするのです。
(参考:総務省「日本企業におけるデータ活用の現状」)
なお、総務省の調査によるとデータの利活用を進められている企業は大企業の90%程度、中小企業の55%程度とされています。ただ、この調査は母体がIT活動に興味がある会社員等であり、やや上振れしていると予想されます。特に中小企業の実態としては、半数以下になるでしょう。
DXとデータ利活用の関係
DXの推進と、データ利活用には大きな関係性があると考えられます。例えばデータ利活用によって新たな情報を得られることで、意思決定のスピードを高められるでしょう。DXは業務の進め方を改革する部分も含めた取り組みであるため、意思決定までのプロセスを改善するために、データ利活用が役立つのです。
また、データ利活用によってビジネス上の課題が明らかになり、これを解決するキッカケになるかもしれません。例えば、データを分析することで、流通コストが想定以上に高まっており、この原因が社内の配送手続きが遅延しがちであることに由来していることがわかったならば、この部分をDXで解決するなどの行動を起こせるのです。
データ利活用の必要性
続いては、データ利活用の必要性をメリットも交えながら解説していきます。
重要な局面での意思決定を改善する
データ利活用によって、重要な局面での意思決定がより正確なものになります。データドリブンなアプローチを採用できるため、意思決定が経験や直感に基づいたものではなく、客観的なデータに基づいたものとなるからです。データという根拠があることで、意思決定のスピードが向上し、なおかつ正確性も高められます。
またデータを基にした意思決定は明確な根拠があることから、周囲の同意を得やすいなどのメリットもあります。そのため、組織内で軋轢が生まれにくいこともメリットと考えましょう。データ利活用によってスムーズな意思決定が促進されるのです。
日頃の業務効率を高める
日頃の業務を効率化するためにも、データ利活用が役立つと考えられます。例えば、特定の業務プロセスに必要な時間を統計的に評価することによって、ボトルネックや無駄を特定することが可能です。製品を入荷してから販売するまでの間に多くの時間を要しているならば、この部分を改善できないか検討することが挙げられます。
また、データを視覚化することでも業務効率を高めることが可能です。例えば、在庫情報を収集してグラフ形式で表示することで、直感的に過不足を把握することが考えられます。データ利活用によって業務上の課題を見つけ出したり、効率よく業務をこなしたりできるようになるのです。
顧客満足度の向上につながる
顧客満足度の向上にもデータ利活用は役に立つと考えられます。顧客データを分析することで、顧客のニーズや行動パターンを詳細に把握でき、パーソナライズされたサービスや製品を提供できるからです。例えば、購買履歴や問い合わせ履歴を分析することで、顧客が必要としているサービスなどを提案できます。結果、顧客体験が向上し、満足度が高まるのです。
データ利活用の方法
データを利活用するためには、順を追って環境を整えることが重要です。どれかが欠けても十分な利活用とはならないため、それぞれについて、対応が必要であると考えましょう。
データ基盤の構築
最初に必要な作業はデータ基盤の構築です。企業内の各システムや部門からデータを統合・管理するための基盤を指します。これが整っていないと、あとから解説するデータ収集やデータ分析、それらの利活用は実現できません。一般的にはデータウェアハウスやデータレイクなどの仕組みを導入し、それらに加えてデータを連携、最終的には分析や可視化できるものを構築します。具体的に、どのようなツールから構築されているかは後ほど解説するため、まずはデータ基盤の必要性だけ認識してください。
データ収集
データ基盤が整ったら、次に重要な作業がデータの収集です。収集するデータは、顧客データや販売データなど内部に蓄積されたものから、Webサイト等の外部で公開されている情報やSNSでの投稿など多岐にわたります。必要なデータの種類と収集方法を明確にして、具体的な収集作業を進めていきましょう。
また、収集したデータの質を確保するために、データクレンジングやバリデーションのツールを導入することがあります。データ基盤やデータ収集のツールに含まれていることも考えられますが、必要ならば、個別に導入しなければなりません。
データ分析
収集したデータを利用して、データ分析を実施し、ビジネスに必要な情報を得ていきます。データを分析できる状態に加工し、専用のツールを利用して分析したり可視化したりするのです。詳細は後ほど解説しますが「Tableau」「Power BI」などのツールを利用することが多くあります。
分析の手法は数多くあるため、どのような目的であるかに応じて適切なものを選択することが求められます。ただ、手法そのものを完璧に習得することは難しいため、ツールで専門的な部分をサポートしてもらうことが現実的でしょう。
分析結果に基づく業務改革・ビジネスモデルの策定
最後に、データ分析の結果を基に業務改革や新しいビジネスモデルの策定へとつなげます。例えば、分析結果をもとに、業務プロセスの改善点を特定し、効率化やコスト削減のための案を検討するのです。また、顧客のニーズや市場のトレンドを分析して、新しい製品やサービスの開発、新規市場への参入を検討することもできます。データドリブンな体制を整えておくことで、市場で競争優位性を得やすくなるでしょう。
データ利活用における課題
データ利活用においては、いくつも課題が考えられるため、その点を考慮して対処できるようにしておきましょう。
利活用するデータ品質やデータ量
データを利活用するためには、データ品質やデータ量を考慮しなければなりません。適切でないデータを分析したり、不要なデータが含まれていたりすると、思うような結果を得られないため注意が必要です。データの品質が高く、十分な量を確保することは、データ利活用の前提条件だといえます。
もし、データ量が不足していると、偏った分析結果になってしまうでしょう。また、データの品質が悪いと事実とは異なった分析結果が提示されてしまうことも考えられます。どちらの場合もデータ利活用の目的を果たせなくなる可能性が高いため、注意しておかなければなりません。
適切な活用手法やアルゴリズムの選択
適切な活用手法やアルゴリズムの選択が難しいことは大きな課題です。例えば、売上データから売上を予測するには「重回帰分析」と呼ばれる手法が使われることがあります。ただ、このような手法が適していることを判断し実際に適用するためには、データ利活用に対して十分な知見が必要です。データ利活用を始めようとしても、十分な知見を持たないことで手法やアルゴリズムを選択できず、効果を実感できないという課題を抱えてしまいます。
データを取り扱える人材の不足
上記の内容に関連する部分ではありますが、データ利活用には専門的な知識が必要とされます。しかし、このような専門的な知識を持つ人材は少なく、思うように確保しづらいことが課題です。データ利活用を進めたいと考えていても、人材不足から思うように進められないケースは多々あります。
特に、近年はデータ利活用の重要性が知れ渡り、多くの企業でデータを扱える人材が求められている状況です。急激に需要が高まったことで、なおさら人材の供給が追いついていません。ただ、データに関連するスキルを持つ人材は年々増えてきているため、折を見て採用したり、社内で人材を育成したりすることが重要です。
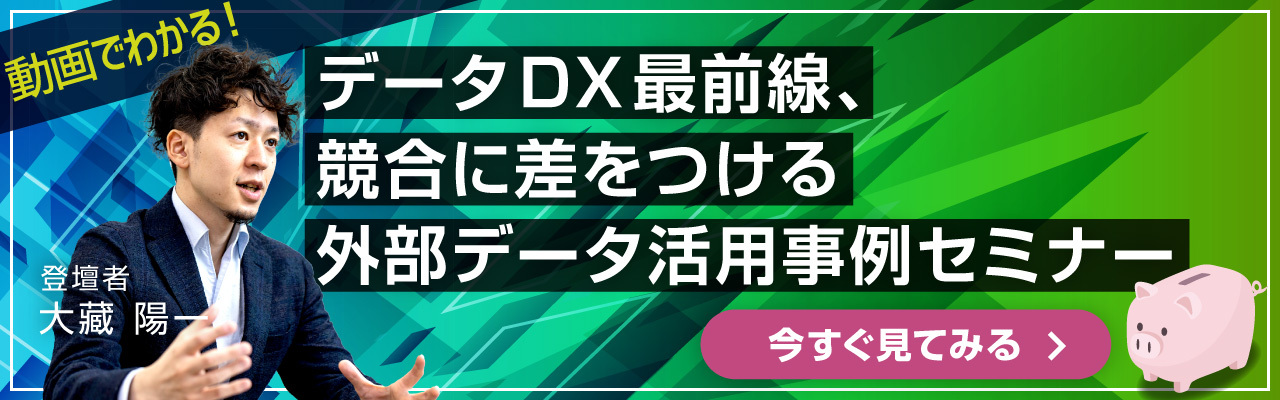
データ利活用の成功事例
データ利活用の成功事例は数多くありますが、今回はイメージしやすいものを3つピックアップして紹介します。
デジタルマーケティング
顧客情報を分析することで、マーケティングの効率を高め、新規顧客を獲得するなどできます。例えば、株式会社ウィルオブ・ワークは、オウンドメディア戦略を通じて新規顧客のリード獲得件数を26〜32.5倍に増加させました。データ利活用によって「アウトバウンドマーケティングからインバウンドマーケティングに変更すべき」との結論を得て、それに沿って方針を変革、実際に売上の増加を実現したのです。
配送時のルート最適化
物流業界ではデータ利活用によって配送時のルート最適化が進められています。例えば、米アマゾンは専用アルゴリズムを開発して、配送ルートの最適化を実施している企業です。今までの配送実績はもちろん、リアルタイムで交通状況や配達先の状況を収集し、それをルートの選定に反映しています。結果、配達時間の短縮や燃料コストの削減、そして顧客満足度の向上などにつながっています。
故障対応や修理手配の効率化
故障対応や修理手配の分野でデータ利活用が進められています。例えば、自動車メーカーのトヨタは、IoTとビッグデータを活用して、故障対応や修理手配をしていることが特徴です。車両のセンサーから収集されるデータを分析して故障の予兆を検知したり、故障が発生した際に素早く部品を手配したりできるようにしています。非常に多くの自動車を製造しているメーカーであるからこそ、対象のデータを分析でき、質の高い利活用となっているのです。
データ利活用のためのデータ収集方法
データ利活用を成功させるためには、十分な量のデータを集めなければなりません。収集の方法にはいくつも考えられるため、代表的なものを紹介します。
社内データの蓄積
まずスモールスタートをするならば、社内のシステムに蓄積されているデータを収集するだけでもデータの利活用が可能です。近年は多くの業務がシステム化されているでしょう。そのため、今まで保存してきたデータを流用すれば、今すぐにでもデータの利活用を始められます。また、現在ではデータが蓄積されていなくとも、これから多くの業務でデータが蓄積されるような仕組みを構築すれば、それもデータ利活用に役立ちます。後ほど解説するデータ構築基盤なども視野に準備を整えていきましょう。
アンケート・調査
アンケートや調査は、データ分析に利用したい情報を直接的に収集したいときに役立つ方法です。例えば、顧客満足度や市場ニーズを把握するために使用され、対象者を絞ることで効率的に必要な情報を集められます。
昔は店頭や街頭で直接アンケートや調査が実施されることが多くありましたが、現在はオンラインアンケートツールが利用されています。素早くアンケートが実施できるだけでなく、回答がデータ化された状態で収集できるため、顧客のニーズや意見をリアルタイムに分析ツールなへ投入、各種計画などに反映することが可能です。
インタビュー
インタビューは、対象者から詳細な意見を引き出したり、回答している様子から定性的なデータを得たりする方法です。対象者は多岐にわたり、一般的には顧客をイメージされますが、場合によっては経営層や現場スタッフなど内部の人間も該当します。
多くの場合、複雑な問題や課題の背景を理解するために役立つ方法で、定量的なデータでは得られない情報が手に入ります。アンケートや調査と組み合わせることで、多角的に情報収集ができ、より具体的なデータ利活用を実現できるのです。
スクレイピング
スクレイピングは、Webサイトからツールを利用して自動的にデータを収集する技術です。Web上には非常に多くのデータが公開されているため、これらの中から必要なものだけをプログラミングによって収集します。例えば、競合他社の価格情報、顧客レビュー、SNSで話題になっている製品(トレンド)などが収集できます。
外部データであるWebデータを収集・分析することで、市場動向を把握したり、競争力を高めるための戦略を立案したりできます。大量のデータを効率的に収集できる方法でもあり、リアルタイムでデータ利活用を実現できる方法としても有用です。

公的データの閲覧
公的機関からデータが公開されている場合は、それを閲覧したりツールに取り込んだりすることが可能です。例えば、天気の変化と売上の関係を分析したいならば「気象データ高度利用ポータルサイト」と呼ばれる公的なデータを参考にすることが考えられます。このデータはダウンロードもできるため、ツールに取り込むことも容易です。
これは一例ですが、公的機関が発信しているデータが多くあり、これらは無料で利用できるものが大半です。閲覧したりデータとして入手したりすることで、データ利活用の幅を広げられます。
データ利活用に役立つツール・サービス
データの利活用を成功させるためには役立つツールやサービスを導入することが重要です。具体的にどのようなツールやサービスを導入すればよいのか紹介します。
データ活用基盤
最初に導入を検討すべきは、データ活用基盤です。その名のとおり、データの利活用に向けた基盤を構築するためのツールであり、データの管理から分析作業などを一括で処理できます。以下で、いくつかのツールやサービスについて紹介しますが、これらがすべてまとまったものをデータ活用基盤と呼ぶと理解しても良いでしょう。これから新規にデータ利活用を進めたいと考えているならば、データ活用基盤を導入することで、一気に必要なものを揃えられます。
ただ、一般的にデータ活用基盤は非常に多くの機能が用意されているため、既に何かしらのツールやサービスを導入していると重複してしまう可能性が高いです。例えば、NECのデータ活用基盤は、以下のような機能を有しています。
- データ連携:ETL・M2M・ストリーム処理
- データ格納:構造化/非構造化データの集約・バックアップ
- データ分析(BI):企業向けBIツール
- データ分析(AI):独自AIを開発したデータの多角的な分析ツール
このような機能を有しているため、既に同様のシステムがあるならば、このデータ活用基盤の導入は適していないでしょう。そのため、現実的にはデータ活用基盤ではなく、以下で解説するような個別のツールやサービスを導入することが多いと考えられます。
ただ、今まで導入しているサービスを一掃してデータ活用基盤に入れ替えることもあり得ます。大規模な作業になりますが、そのような可能性もあることは認識しておくとよいでしょう。
データ収集サービス
データ収集サービスは、データ利活用に向けて新たな情報を収集するために利用します。例えば、Webサイト上に公開されている情報を自動的に集めたり、顧客からのアンケートを実施したりするものです。既に存在しているデータを集めることもあれば、アンケートのように新しくデータを提供してもらうこともあり、その種類は多岐にわたります。
他にも、アンケートなどの調査が必要ならば「Zoho Survey」などのツールを導入するなど、収集したいデータの内容に適したものを選択します。
データ蓄積ツール
データ蓄積ツールは、社内のシステムなどから得られた情報をまとめて蓄積するためのツールです。近年は「データは資産である」との考え方から、できるだけ中長期的に大量のデータを溜め込むという考え方が広まっています。そのため、このような専用の蓄積ツールを利用して、中長期的にデータを残せるようにするのです。
例えば「Wasabiオブジェクトストレージ」は、社内のシステムを接続することで、大量のデータを蓄積できるツールです。それぞれのアプリケーションにデータを蓄積し続けると、動作に悪影響を及ぼす可能性があるため、専用ツールに連携してアプリケーションの負荷を軽減します。また、点在していると活用の負担が大きくなるため、これを軽減するという意味合いもあるのです。
データ分析ツール
データ分析ツールは、蓄積されたデータをさまざまな手法で分析するためのツールです。一般的に、データを分析するためには専門的なアルゴリズムなどの理解が求められます。ただ、これらを完璧に習得することは難しいため、データ分析ツールを利用して、少ない知識でも効率よく分析できるようにするのです。
例えば「Tableau」と呼ばれるツールを利用すればクラスター分析が簡単に実施できます。本来は分析に向けてアルゴリズムを学ぶ必要がありますが、ツールを利用することで画面の指示に従ってデータを読み込ませるだけで良くなるのです。また、分析の前段階として必要なデータ加工なども指示に従うだけで済ませられます。
データ利活用においては、様々な分析手法を利用する必要があり、全てを完璧に理解することは現実的ではありません。そのため、分析ツールを活用して、必要な分析を効率よく進めていきます。
データ可視化サービス
データ可視化サービスは、主にデータ分析した結果をグラフや表など直感的に理解できるものへ変換するサービスです。仮にデータを分析したとしても、その結果が直感的に理解できないものでは、ビジネスに有効活用できません。そのため、視覚的に把握しやすい状況にするために、可視化サービスを活用するのです。
例えば「NECデータ可視化サービス」と呼ばれるサービスを利用すると、経営情報を読み込ませることで、経営者が判断に必要なグラフをアウトプットできます。また、倉庫の位置を設定し、それぞれの在庫情報をデータとして読み込ませると、日本地図上への描写で「どの倉庫にどれだけの在庫が保管されているのか」を示すことも可能です。利用するサービスによって、機能の詳細は変化しますが、様々な観点から、直感的に理解できる資料に変換してくれます。
まとめ
これからの時代、DXを推進するためにはデータ利活用が重要です。DXに向けてデータ利活用を実現したいならば、まずはデータ基盤の構築が求められます。基盤を構築して、自社内で保有しているデータなどを集約しなければなりません。また、自社内で保有しているデータが不足する場合は、外部からデータを収集する作業が必要です。例えば、Webサイトからのデータは誰でも手に入れることができ、素早く活用できる外部データに該当します。このようなWebデータの収集には、自動的にWebデータが収集できるスクレイピング技術の活用がおすすめです。
弊社はデータ収集に向けたスクレイピング代行サービスを提供しています。DXのためにデータが必要ならば、ぜひPigDataへご相談ください。