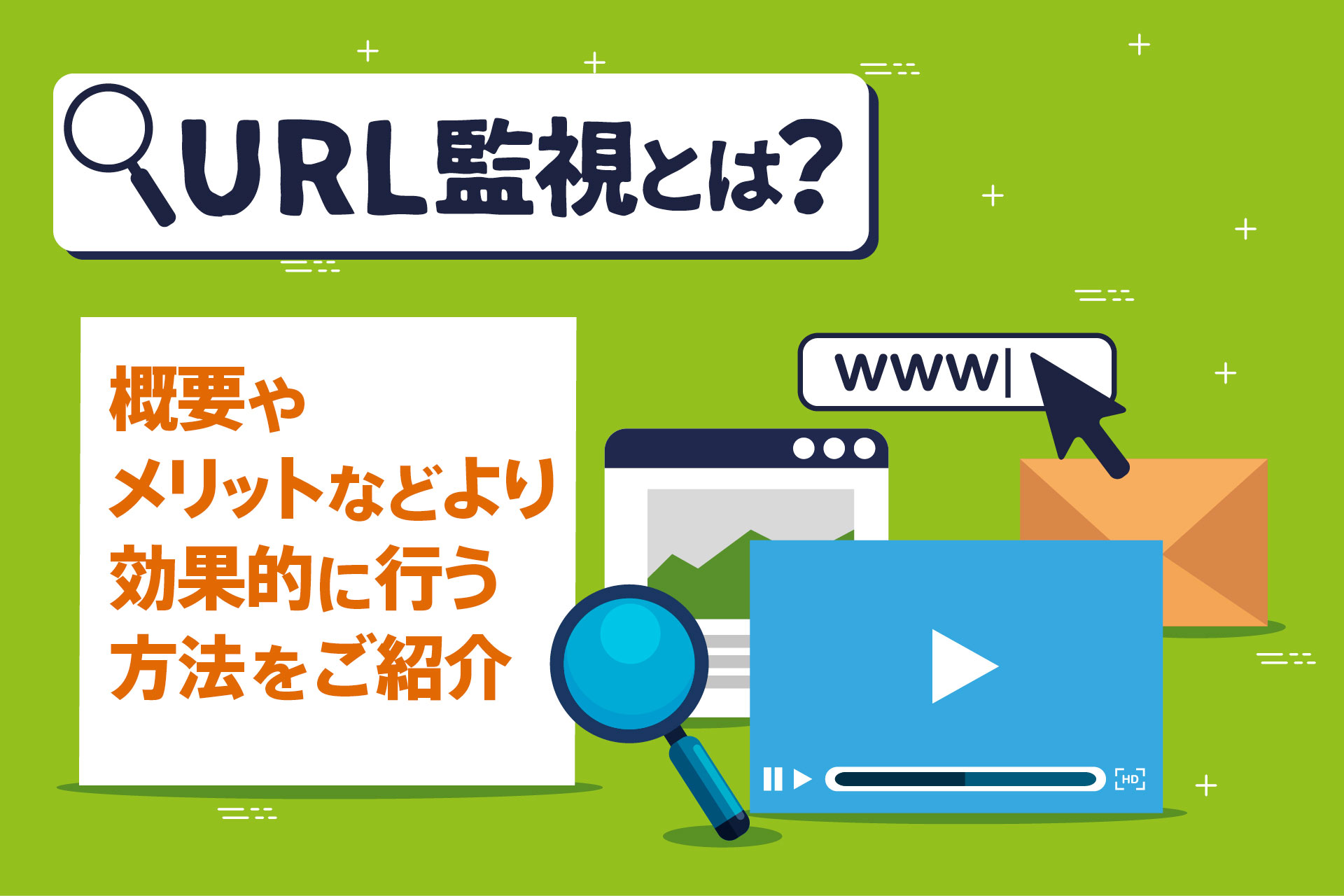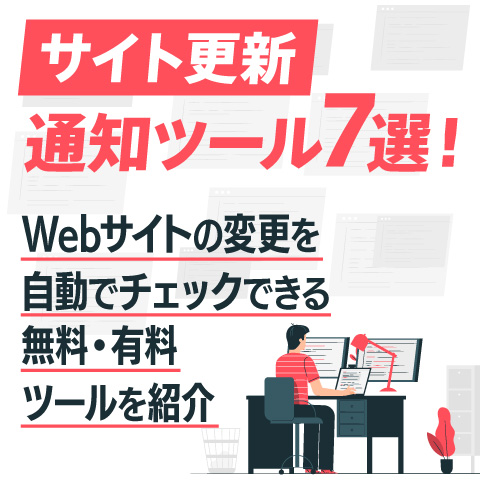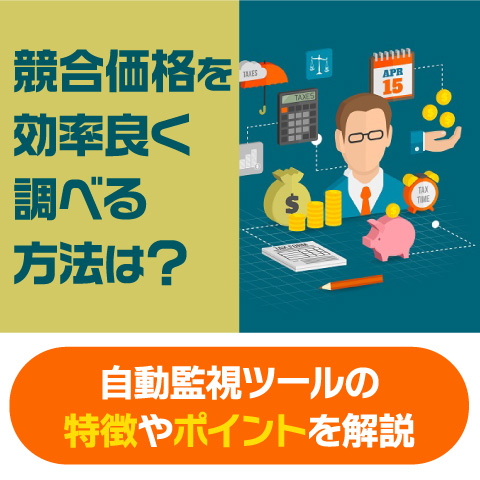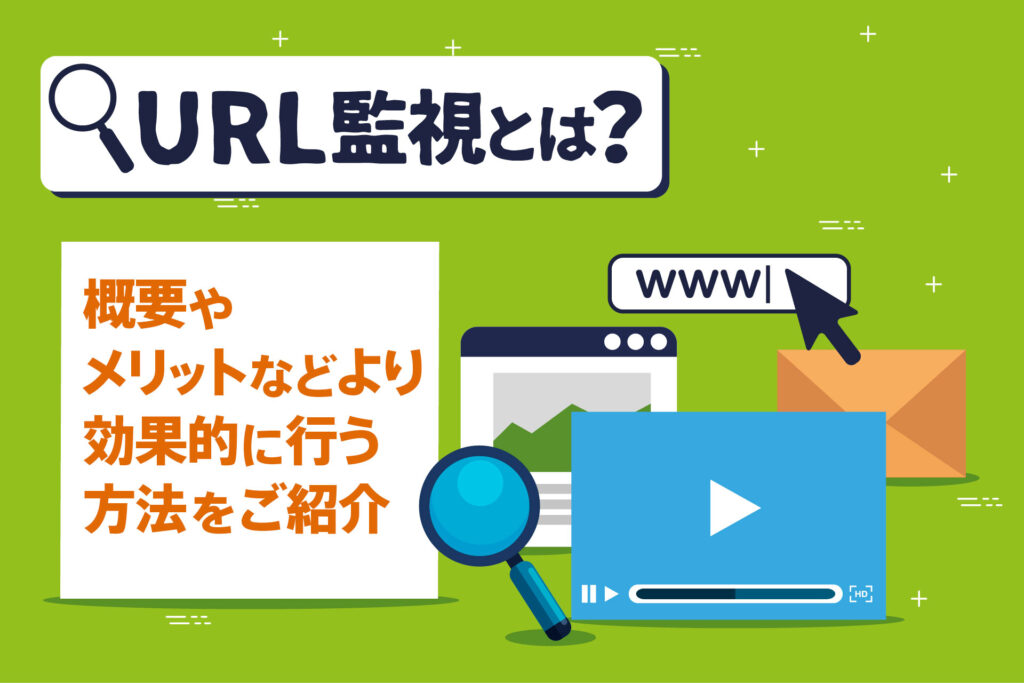
URL監視とは、事前に設定したURLへ継続的にアクセスして、接続できるかどうかなど状況を評価するものです。Webサイトを運営する際には、いくつか監視に関する仕組みを導入する必要があり、URL監視はその一種であると捉えると良いでしょう。WebアプリケーションやECサイトを運営しているならば、URL監視は必須とも言える時代です。ただ、実際にはどのようなサービスであるか理解されていないため、今回は概要からサービスの仕組み、導入のメリットや方法など基本的な知識を解説します。
URL監視とは
最初にURL監視とはどのような作業を指すのか解説します。
URL監視の概要
URL監視とは、特定のURLに対して監視用の通信を発生させ、WebサイトやWebアプリケーションの状況を監視する仕組みを指します。URLに対する通信は、状況に応じて異なった結果を返してくれる仕組みであるため、それを読み取って状況を判断するのです。例えば、正常に動作していることや何かしらサーバーのエラーが発生していることを検知します。
WebサイトやWebアプリケーションを運用する際には「利用者が接続できない」「利用者がアクセスできない」という状況を避けなければなりません。このような事象は、顧客満足度に大きく影響してしまいます。万が一このような状況に陥っても、いち早く返事ができるように、URL監視を活用して状況を把握できるように準備しておくのです。
URL監視が必要とされるケース
URL監視はWeb上に公開されるものであればどのようなものに対しても必要となる可能性があります。利用例を挙げるならば以下の通りです。
- コーポレートサイトの状況確認
- ECサイトの起動確認
- Webアプリケーションのエラー発生チェック
- 問い合わせフォームの動作確認
これらは一例ですが、URL監視が必要とされるケースは非常に多くあります。特に、顧客など組織外の人に対して提供しているWebサイトやアプリケーションでは、必須であると考えて良いでしょう。
死活監視との違い
URL監視と似ている仕組みに死活監視と呼ばれるものがあります。これはURL監視とは少し異なり、サーバーなどの機器が起動しているかや動作しているかを確かめるためのものです。URL監視はWebサイトやアプリケーションなど、利用者が見える部分を監視しますが、死活監視は見えない部分を監視するとイメージすれば良いでしょう。
監視の対象が異なっているため、どちらかだけで良いというものではありません。基本的にはどちらも設定する必要があり、相互に不足している部分を補完することが求められます。Webサイトやアプリケーションの運営においては、なくてはならないものであると考えて良いでしょう。
URL監視を行うメリット
URL監視を実施することによって、以下のようなメリットを感じられます。
Webサイトトラブルへの迅速な対応
監視の中でもURL監視を採用すると、ステータスコードなどに基づいて、Webサイトが起動しているか評価できます。設定次第では、非常に細かい間隔で監視できるため、状況をいち早く検知でき、対策を打てることがメリットです。
Webサイトの監視には様々な手法があり、サーバー自体を監視する生死監視などの方法もあります。ただ、サーバーが起動しているかどうか評価するもので、URLに接続できるかどうかを評価するものではありません。場合によっては、サーバーは起動しているもののURLに接続できないことがあります。
ひとつの監視方法だけを実装しても、効果が不十分な場合があります。そこで、URL監視を組み合わせると、多角的に問題を検知しやすくなるのです。
顧客満足度の向上
URL監視により問題をいち早く検知できれば、顧客満足度の向上に繋げられます。Webサイトが利用できない状況が続くと、顧客満足度は徐々に下がってしまいますが、検知して迅速に改善できればこれを食い止められるのです。これの対応次第では、顧客満足度の向上にも繋げられるでしょう。
ただ、重要なポイントは、検知するだけではなく素早い対処が求められる点です。問題に気づいていながら、それを放置してしまうと、顧客満足度は下がってしまいます。
URL監視の仕組み
URL監視の仕組みを技術的な側面から解説すると以下の通りです。
外部からURLを監視
URL監視は、Webサイトの状況を外部から監視して、問題ないか評価するものです。Webサイトが構築されているサーバー内部で状態を評価するのではなく、外部から評価することに注目しましょう。外部からの評価であることから「外形監視」と呼ばれることもあります。
ただ、外形監視は「可用性」「「パフォーマンス」「トランザクション」など多様な観点からの監視を指した言葉です。しかし、URL監視はこれらの中でも「可用性」を中心に評価します。そのため、URL監視は外形監視の一部と理解することが正しい理解です。
HTTPリクエストを利用した状態の評価
URL監視の基本は、HTTPリクエストを活用した状態の評価と理解しましょう。HTTPリクエストは、簡単な言葉に置き換えると、Webサイトへのアクセスです。実際にURLでアクセスし、接続できるかどうかを監視しています。
接続できたかどうかの判断には、HTTPのステータスコードが用いられます。接続結果に応じて番号が定められていて、例えば接続に成功すれば「200」が応答される仕組みです。また、サーバーへの接続に何かしらの問題があれば「400番台」が応答されるようになっています。
URL監視では、応答されるコードについて事前にどのような処理をするかを定義しています。例えば、400番を受け取った際は問題があると判断するなどと定義しておくのです。
URL監視の方法
URL監視の方法は3種類考えられるため、それぞれについて解説します。
SaaS
近年、利用者が多い方法はSaaSを活用したURL監視です。主にクラウドで提供されているサービスを契約し、ここに監視対象のURLを登録して利用します。SaaSは、事前に定められた条件に従って、登録されたURLを監視するという仕組みです。
SaaSは、導入コストが低く短時間でスタートできるなどのメリットがあります。ただ、提供されている機能しか利用できないなど、制約もあるため注意が必要です。
自前での構築
自分でサーバーを用意し、そこにURL監視のシステムを構築する方法があります。専用のパッケージを購入して導入することも、自社向けに専用のアプリケーションを開発してもらい導入することも可能です。機能面でカスタマイズできることが多く、URL監視に複雑な要望を持つ場合でも対応できます。
ただ、サーバーを用意する必要があるため、これを運用するだけのスキルが必要です。また、サーバーやアプリケーションの準備で、大きな初期コストが発生する可能性があります。
MSP
MSPとは「Managed Service Provider」の頭文字を取ったもので、システムの管理や監視などの運用作業を代行してくれるサービスを指します。本来、運用作業はWebサイトやアプリケーションの所有者が実施しなければなりませんが、一連の作業を引き継いで代行してくれるのです。また、監視内容の設計を依頼したり、レポートを作成してもらえる場合もあります。
基本的には、オーダーメイドの監視サービスであるため、URL監視を含めて柔軟に対応してもらうことが可能です。ただ、コストが高くなりがちであるため、その点は注意しておかなければなりません。
URL監視だけでは補えないサイト運営に必要なこと
URL監視はサイト運営に必要な作業ですが、これだけでは十分ではありません。以下の作業も取り入れていきましょう。
レスポンスタイムの評価
URLにアクセスできることだけではなく、レスポンスタイムの評価が必要です。一般的に、レスポンスタイムが長くなればなるほど、ユーザーの不快感は高まってしまいます。可能な限り、素早くレスポンスできるようにしなければなりません。
レスポンスタイムは、サーバースペックやアルゴリズムによって基本的には決定されます。ただ、サーバーなどにトラブルが発生していると、一時的にレスポンスが悪くなることがあるかもしれません。URL監視に加えて、このような状況を検知できれば、トラブルの発生に素早く対処できます。
サイト改ざんの検知
近年はサイバー攻撃によってWebサイトが改ざんされる場合があり、これを早期に検知しなければなりません。検知が遅れると、アクセスしてきたユーザーに被害を与え、大きな問題が生じる可能性があります。サイト運営では、これを素早く検知する仕組みが必要です。
例えば、ソースコードの中身を監視するツールを利用することで、意図しない変更が発生していないか評価します。何かしら変更があった場合は、改ざんとみなして担当者へと通知することも可能です。
SSL証明書やドメインの管理
サイトのセキュリティを高めるために、SSLを導入しなければなりません。また、URLの元になるドメインを管理しておく必要があります。
例えば、SSLで利用する証明書には有効期限があり、更新を忘れるとセキュリティ効果がなくなります。そのため、有効期限を管理して、常にセキュリティを担保しなければなりません。また、ドメインそのものについても保有期限があり、更新を忘れると所有権が失われてしまいます。
脆弱性の診断
サイトに脆弱性があると、ハッカーなどに攻め込まれてしまうかもしれません。これを防ぐために、脆弱性診断を実施して、いち早く検知しておくことが重要です。
脆弱性診断は、セキュリティ専門会社など、外部に依頼して実施します。専門的な知識が必要となるため、自分たちでは対応できないと考えた方が良いでしょう。
⇒脆弱性診断とは?脆弱性を放置するリスクやおすすめの診断ツールも紹介
タスク管理
決まったタスクが処理できているかを確認するために、タスク管理が必要です。Webサイトを運営していく中でも定型業務が存在します。例えば、特定の日付にお知らせを公開する必要があるならば、そのお知らせが公開できているか、また公開内容に間違いがないかのチェックをする、など抜け漏れなく対応できるようにタスクを管理しておきます。タスク内容をチームで共有できていない場合、担当者がその業務を忘れていた場合はインシデントにも繋がるため、タスク管理はチームで共有できる形式が望ましいでしょう。
WEBサイト運営におすすめのツール
Webサイト運営におすすめのツールをまとめました。
Webサイト更新チェックツール:TOWA
URL監視だけではWebサイトの中身が変化している場合には気づけず、Webサイトが知らずのうちに更新されている可能性もあります。
TOWAはWebページ内のテキスト・HTML・画像・PDFの変更差分を監視できるWebサイト更新チェックツールです。例えば、運営しているサイトにWeb改ざんが行われていた場合、TOWAで監視すれば見落とすことがありません。外部からの攻撃で、内容が改ざんされていないかの検知などにも利用可能です。TOWAは変更箇所や内容をタスクカードとして表示してくれるため、その変化に対するタスクがある場合、「処理済み」「未処理」と分けられるため、どの変更に対してタスクが完了しているかどうかの確認も可能です。
また、自社サイトの内容を監視するだけではなく、法令チェックや競合サイトの更新チェックなどにも活用できます。海外のサイトを含めどのようなサイトでも監視できるため、使い方次第で既存顧客への営業タイミングを掴んだり、競合他社の営業戦略を知ったりするなどの活用もできるでしょう。
死活監視ツール:OpManager
OpManagerは、Webサイトを構築するサーバーなどの死活監視やリソース監視など、ハードウェア面の評価に役立つツールです。URL監視ツールだけでは、ハードウェアに問題が生じているかどうかの評価ができないため、このようなツールも組み合わせるようにしましょう。
基本的には、サーバーが適切に動作し、ユーザーに対してサービスを提供できているかの評価に役立ちます。また、それ以外にもリソースを監視することで、予期せぬ出来事が起きていないかのキャッチが可能です。例えば、リソースの消費が極端に高まっているならば、外部からの攻撃を疑うきっかけになります。行動を起こすトリガーとしての役割も死活監視ツールは担ってくれるのです。
脆弱性診断ツール:Vex
Vexは、Webサイトに脆弱性が残っていないかを評価する脆弱性診断ツールです。脆弱性が残っていると、外部から攻撃される原因となりかねないため、いち早く検知して対処しなければなりません。本来は、専門的な会社に依頼するものですが、ツールを利用することで、素早く自分たちで対処できます。
同等のツールはいくつもありますが、Vexは歴史が長く国内シェアが高いことが特徴です。セキュリティ面は専門知識が多く疑問が生じやすいため、これらをサポートするサービスも充実しています。
まとめ
URL監視は、WebアプリケーションやWebサイト、ECサイトなどの運営者がWebサイトの接続状況を確認するために行う仕組みです。サーバーが停止していないかや、レスポンスが悪くなっていないかなどの評価に利用します。ただ、URL監視はサイトの内容までは評価できないため、自社のサイトが改ざんされている場合は気づくことができません。
しかし、Webサイト更新チェックツールTOWAならWebページ内のテキスト・HTML・画像・PDFまでもが変更されたかどうかを検知できます。そのため、サイトの改善やアップデートについても速やかに把握が可能です。URL監視だけでは難しいWebサイト運営に関わる業務にも対応できるため、是非とも導入をご検討ください。