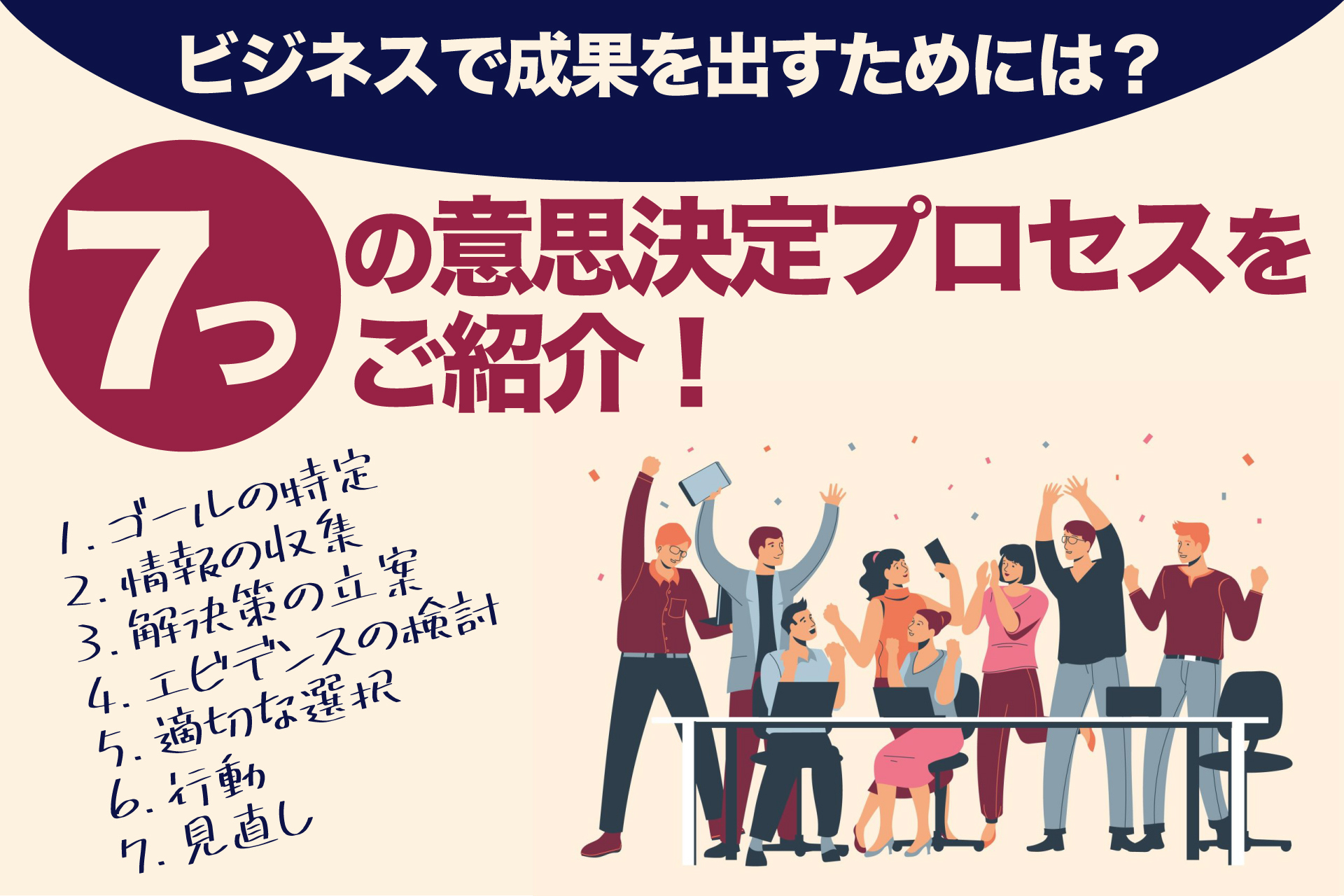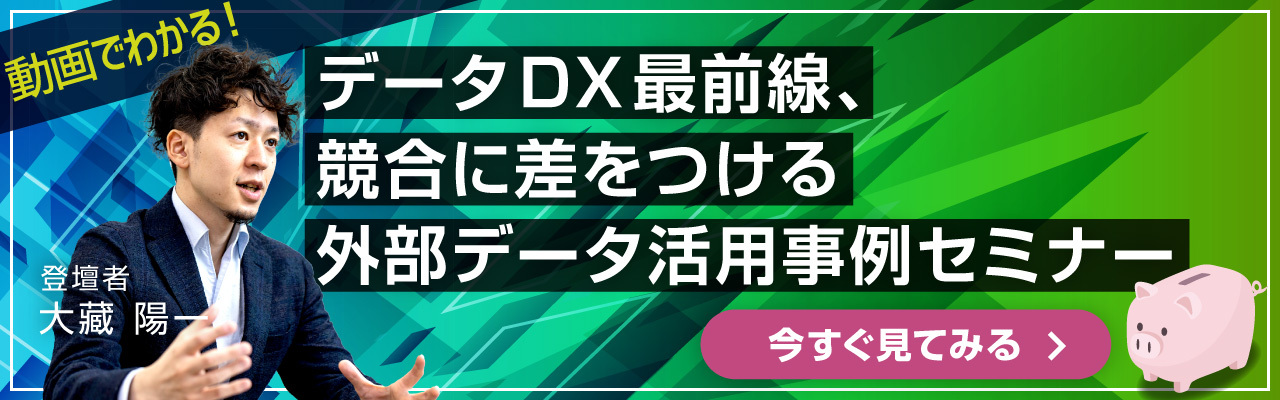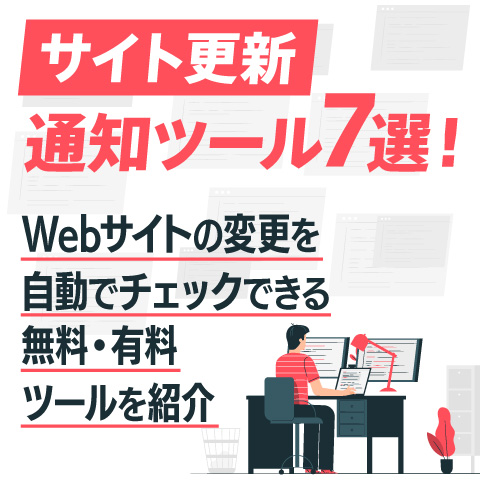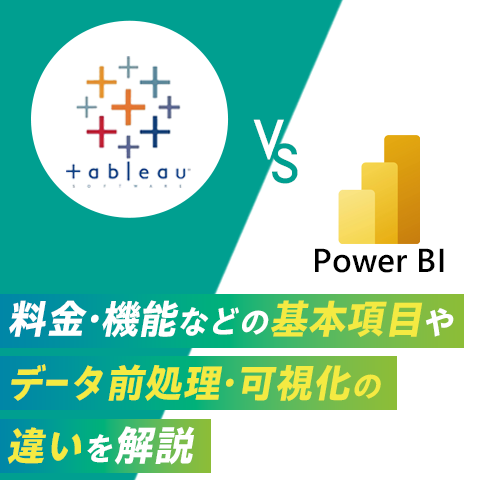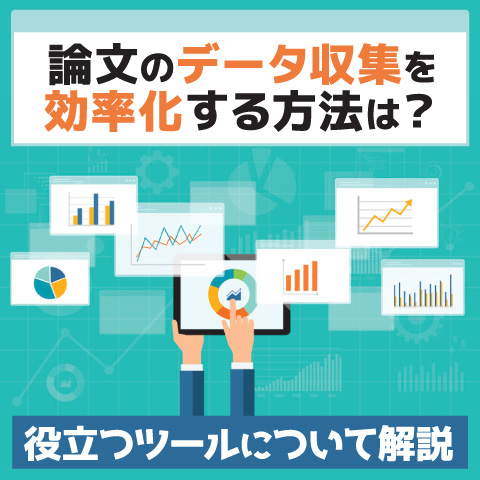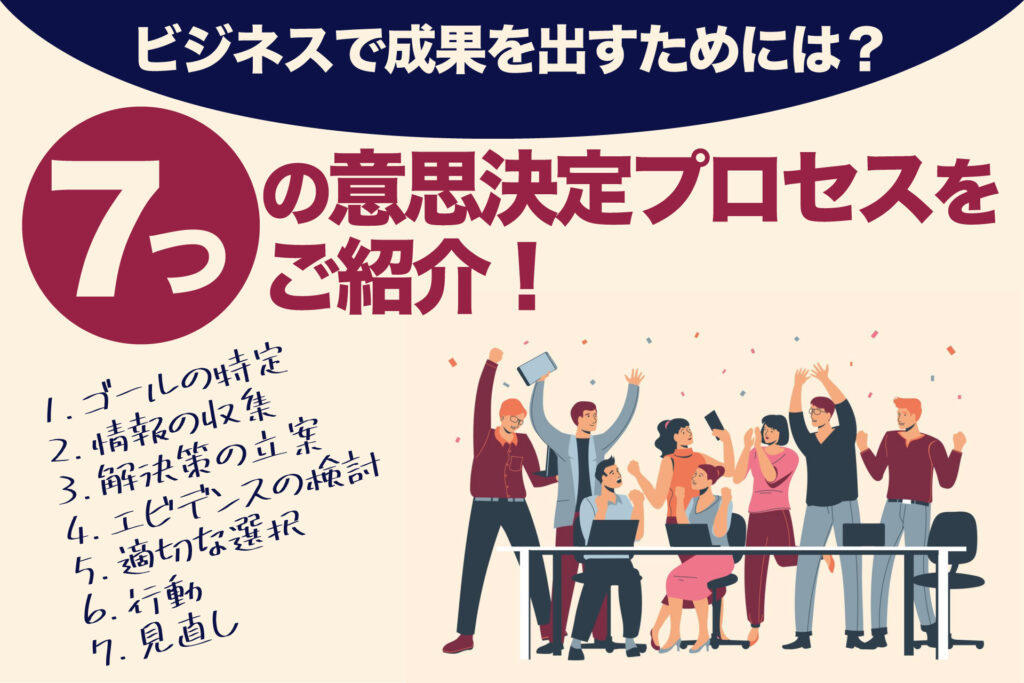
ビジネスにおける意思決定プロセスを改善して、確実に成果を出せるようにしたいと考えている方はいませんか?変化が激しい現代のビジネス環境では、適切な意思決定を迅速に下せるように、プロセスを見直す必要があります。ビジネスにおける意思決定は、企業の収益に直結していることも多いため、収益を向上させるためには意思決定に至るためのプロセスが重要なのです。しかし、意思決定のプロセスを皆瀬するために、どこから手を付ければよいか分からない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、意思決定プロセスに必要となる7つのステップと、重要なポイントについて解説します。この記事を読めば、成果を出せる意思決定プロセスを改善するために、必要な手段が分かるようになるはずです。
ビジネス上での意思決定プロセスとは
ビジネスでの意思決定とは、目標を達成するために、いくつかの選択肢から最適なものを選ぶことを指します。一般的に、ビジネスでは「分岐」のタイミングがあるため、その際にどれを選ぶかが、意思決定であるとイメージすれば分かりやすいでしょう。また、ビジネス上における意思決定プロセスとは、このように選択肢が存在する場合にどれを選ぶかを決定するまでの過程を指します。例えば、エビデンスの検討や代替案の精査といった作業が含まれる、段階的なプロセスです。
現在のビジネス環境はITの急激な成長によって激しく変化しており、これまでの常識があっという間に過去になってしまうので、正しい判断を迅速に下さなければなりません。正しい意思決定が迅速にできなかった場合、時代に対応できず企業は損失を受ける可能性があります。損失を抑えて成功に繋げていくためには、意思決定にいたるまでのプロセスを見直す工程が大切です。意思決定のプロセスを整えておけば、行った意思決定が適正なものだったかどうか、後からでも見直せるようになります。
意思決定モデルの種類
意思決定にはモデルがあり、主要な3種類を解説します。
合理的意思決定モデル
合理的意思決定モデルは、問題解決や意思決定のプロセスにおいて、与えられた情報やデータから最適な選択をおこなうものです。一般的に、目的や目標を数値で表現・評価するもので、最も効果的な選択を合理的に導き出します。利用可能な選択肢をすべて明確にしておき、それぞれの選択肢が持つ潜在的な結果を数値で評価します。
ただ、すべての状況で数値化できるとは限らず、不確実性や複雑性が高い状況では評価が難しくなっています。「合理的な判断」はビジネスにおいて重要視されがちですが、事前に数値化など定量化できることが前提とはなるのです。
直感的意思決定モデル
直感的意思決定モデルは、人間の直感や経験に重きを置く意思決定の方法です。合理的意思決定モデルは主に論理やデータに基づくため、真逆に位置する意思決定モデルと考えて良いでしょう。意思決定者が過去の経験、感覚的な判断、あるいは「第六感」を利用して決断を下すケースが大半です。
ビジネスにおいて、このような意思決定は避けるべきだと考えるかもしれませんが、情報が不完全であったり、時間的な制約があったりする状況において役立つことがあります。また、問題が非常に複雑で一般的なモデルでは評価しづらいときの妥協策として採用することもあります。
認識優先意思決定モデル
認識優先意思決定モデルは、複雑で時間が制約された状況下での意思決定に焦点をあてた方法です。意思決定者が、現在の状況を以前の経験と照らし合わせて認識し、その認識に基づいて行動したり判断したりします。
この場合、意思決定者は状況の観察や認識が重要となります。これにより、過去の経験から最も近いものを見つけ出すことが可能となり、それを踏まえた行動ができるからです。ただ、意思決定者のスキルや過去の経験に大きく依存するものであり、すべての状況下に適したモデルとはいえません。
成果が出せる意思決定プロセスの7ステップ
よりよい成果を出せる意思決定を下すためのプロセスとして、次のような7段階のステップが一般的に採用されています。
- ゴールを明確にする
- 必要な情報を集める
- 解決策を立案する
- データやエビデンスと照らし合わせる
- 複数の選択肢の中から適切なものを選ぶ
- 実際に行動に移す
- より良い意思決定ができないか見直す
1. ゴールを明確にする
まず初めに、意思決定によって解決したい「問題」や「目標」は何であるのか、ゴールを明確にすることが大切です。意思決定プロセスは、ゴールに向かって判断を下すものであるため、これがなければ始まりません。
なお、解決すべき問題を取り違えていたり、問題の範囲を広げすぎたりしてしまうと、その後の意思決定プロセスが乱れてしまいます。また、意思決定プロセスが完了した後に目標の達成が分かるよう、タイムリーで測定可能な目標を設定することが大切です。
チームでの意思決定プロセスの場合、解決すべき問題の捉え方を狭めすぎてしまわないようにするように意識しましょう。例えば、製品の売れ行きが芳しくない状況で「カラーラインナップに問題があるため色について議論する」としてしまうことは枠組みを絞りすぎています。問題は色ではなくデザインや材質かもしれません。
最初から問題を絞り込み過ぎたり決めつけたりしてしまうと、ディスカッションが始まる前からチームメンバーに結論を予想されてしまうかもしれません。これでは、意思決定の質が下がってしまいます。
2. 必要な情報を集める
決断を下す問題や目標を明確にしたならば、意思決定に必要な情報を収集します。企業の現在の状況を明らかにするため、社内の部門評価を行い、成功した点と失敗した点を洗い出しながら情報を集めていきましょう。
また、市場調査や外部コンサルタントからの評価などを行い、外部からの情報も集めていくのも大切です。例えば、ある商品の売上を改善するのが課題である場合、商品のこれまでの売上データや市場における商品の需要などといった情報を収集するとよいでしょう。
ただし、情報を収集しすぎると逆にプロセスが複雑になってしまい、身動きが取り辛くなってしまいます。意思決定を迅速に行うためには、役に立つ情報を絞るという判断も大切です。
3. 解決策を立案する
意思決定に必要な情報が出揃ったなら、問題の解決や目標を達成するための解決策を立案していきます。
通常、問題の解決や目標の達成のための解決策は複数考えられるでしょう。例えば、ソーシャルメディアへ訪れる顧客数の増加を目指すなら、有料のソーシャル広告を用いるなどの手段が考えられます。他にも、店頭で配布するチラシにアカウントのQRコードを載せることで、アクセスしてもらいやすい環境を生み出すことも可能です。1つの効果的な方法を選択するのか、あるいはアイデアを組み合わせるなど、いくつかの解決策を選択肢として検討しましょう。選択肢を3つ以上用意しておけば、意思決定の品質も向上するようになります。
4. データやエビデンスと照らし合わせる
複数の案を立案できたら、それぞれの案が適切なものであるかどうか、データやエビデンスと照らし合わせて検討しましょう。
まず、意思決定やその後のビジネスに関連するデータやエビデンスを参照します。自社の売上と競合他社の売上をそれぞれ参照し、解決策が事実に即しているものであるのか評価します。また、テスト販売など何かしら実証実験したことがあるならば、この結果もエビデンスとして参照しなければなりません。
例えば、議論の結果「カラーラインナップが3色しかないことが問題でありこれを解決する」という案が導かれたとします。この時、競合他社の売上データなどを参照し「A社は10色あり非常に多くの売上を得ている。B社は3色しかないが当社より売上がある。色の数だけが本当に問題なのか」などと評価するのです。この例の場合、データやエビデンスと照らし合わせることで「実は色の数ではなく赤色が含まれているかどうかが重要だと考えられる」などと、本質的な部分が見つけられるようになります。
5. 複数の選択肢の中から適切なものを選ぶ
それぞれの案に対する検討を十分に行った後は、問題の解決や目標の達成に向けて、最も適切であると考えられる案を選択しましょう。
これまでに収集した情報や、それぞれの案が持っているメリットやデメリットを整理すれば、適切な判断を下せるようになっているはずです。判断を下す際の注意すべき点として、相対比較によって挙げられた2つの側面に優劣を付ける場合、数の多寡や多数決で決めてはいけません。例え少数の意見であっても、意思決定に重要な影響があると判断できる場合には、客観性や公平性などの複数の視点から判断を行うべきでしょう。
また、適切な選択を行う際には、決定木や決定マトリクスを用いるのも有効な手段です。それぞれの手法を用いれば、明確な基準で判断を行えるため、スピーディかつ納得できる選択が可能となります。
6. 実際に行動に移す
数ある解決策の中から適切な意思決定を行ったなら、いよいよ行動に移りましょう。
決定した解決策に向けて、実行できる具体的なプロジェクト計画を策定していきます。プロジェクトをいくつかのタスクに落とし込み、タスクごとの役割を関係者1人1人に割り当てて、プロジェクトを実行していきましょう。
役割とタスクは表などに書き込んで視覚的に分かりやすくすると、誰がどの仕事を行っているのか一目で分かるので、スムーズにプロジェクトが進行していきます。
7. より良い意思決定ができないか見直す
プロジェクトの完了、あるいは一定の期間が経過した後に、行った意思決定が適切であったかどうか見直しましょう。意思決定プロセスで明確にした問題が解決したか、目標が達成できたかを見直し、今後に活かしていかなければなりません。達成できた場合、成功した理由を洗い出しておきましょう。達成できていなかったとしても、同じ失敗を繰り返してしまわないように、何が問題であったのかを振り返っておくのが大切です。
意思決定プロセスのサイクルを繰り返していけば、意思決定にいたるスピードや精度が向上していくでしょう。
意思決定のプロセスをよくする5つのポイント
意思決定のプロセスを改善するために、次の5つのポイントを意識するとよいでしょう。
- 問題を明確にする
- 分析手法を吟味する
- 関係者の責任と役割を明確にする
- 過去の決定に固執しない
- 外部データを活用する
問題を明確にする
ディスカッションで解決策を考えるよりも前に、まずは問題や目標を明確にするところから始めましょう。意思決定プロセスのステップで解説したように、問題や目標が明確になっていないと、立案される解決策の方向性もぶれてしまいます。
逆に問題や目標を絞りすぎてしまっても、提案される解決策の質が低下してしまいます。問題を明確にすると同時に、立案される解決策が絞られすぎないようにすることが大切です。特定の提案に誘導するのではなく、複数の解決策が出るように促せば、意思決定の質が向上していきます。
分析手法を吟味する
データに基づいた意思決定を下すためには、収集したデータを分析する必要があります。ただ、分析手法は数多くあり、どれを選択するかで結果が異なる可能性があります。そのため、状況に最適な手法を吟味して、それを適用することが重要です。
分析手法を吟味するためには、複数の手法を持っておくことが求められます。例えば、データ分析には「アソシエーション分析」「クラスター分析」「因子分析」などの手法があります。これらの手法について特徴を理解し、それを加味して分析することが求められます。
関係者の責任と役割を明確にする
意思決定においては、関係者のそれぞれが持つ役割と責任を明確にしましょう。日本人は、自分自身で責任を取りたがらない傾向があるため、責任の所在が明確でなければ他人任せになってしまう可能性があります。
例えば、意思決定プロセスでは必要な情報の収集から開始しなければなりません。このとき、情報が不足していると意思決定に悪影響を及ぼす可能性があります。収集の担当者は、十分な情報を提供することが役割であり、それを果たせないときにどのような責任を負うのか明確にしておくべきです。
過去の決定に固執しない
意思決定プロセスを繰り返すことで、それぞれのプロセスがブラッシュアップされ、効率化できるメリットがあります。ただ、これは同時に「前例主義」を生み出す原因ともなるため注意が必要です。これでは、意思決定にバイアスがかかってしまい、適切な判断が下せないリスクがあります。
意思決定で悩んだ際、過去の決定を参考にすることは決して悪い方法ではありません。ただ、過去の決定を踏まえるだけで最終的な判断を下していては、意思決定プロセスの意味が薄れてきます。過去を参考にしつつも、最新の情報を踏まえて決定することが重要です。
外部データを活用する
意思決定のプロセスには「情報収集」のステップがあり、この情報には社内で収集できる「内部データ」と外部の機関やWebサイトなどから手に入れる「外部データ」があります。これらのうち、客観的なデータである、外部データを活用することが重要です。
例えば、社内で売上のデータを収集しても「増えた」「減った」という数値の動きしか判断できません。しかし、これに気象データという外部データを組み合わせると「平均気温が平年より高いときに増えた」などと、増えた理由を客観的に評価できる可能性があります。
データドリブンな意思決定の重要性
データドリブンな意思決定が重要となった背景には、以下が考えられます。
情報の増加
現代は情報が爆発的に増加しているため、人間の感覚だけでは正確に状況を把握できません。その状態で意思決定しても、誤った方向へと進むことになるでしょう。例えば、今朝新しいニュース記事を読んだことによって、昨日までとは考え方が大きく変わるかもしれません。大量の情報を人間が客観的に捉えることは難しく、新しい情報やインパクトの強い情報に依存して、意思決定してしまうリスクがあります。
しかし、データドリブンなアプローチとすれば、このような問題は解決が可能です。大量の情報を効果的に解析して、むしろ意思決定に活用できるようになります。
ビジネス変化の高速化
ビジネスの変化が高速化したことで、今まで以上にデータドリブンな意思決定が重要になっています。顧客から選ばれるためには、世の中のニーズを客観的に評価することが重要であり、この評価には情報収集やその活用が大きな鍵を握るのです。
特に、リアルタイムな情報収集とそれによる意思決定ができれば、ビジネスでは優位性を確保できると考えられます。変化が激しい時代において「乗り遅れる」ということは避けなければなりません。常に理想的なポジションを確保するためには、顧客のニーズ・これからのトレンドなどをキャッチすることが必要です。
まとめ
ビジネスにおける意思決定は、データドリブンにやることが大切です。データに基づかない意思決定モデルもありますが、今の時代、データを最大限に活用することが求められます。活用できるデータには「内部データ」と「外部データ」の選択肢があり、これら両方を活用すべきです。これにより、主観だけではなく客観的な面も取り入れた分析ができるようになります。
また、外部データの活用は意思決定プロセスだけではなく、今後DXを展開するという観点でも重要な役割を担います。特に誰でも手にすることのできるオープンデータやWebデータは活用しやすい外部データであるため、この機会に活用できるような体制を整えておいたほうが良いでしょう。
もし、これからWebデータを収集し外部データを活用したいと考えるならば、Web上の情報を自動で大量に収集できるスクレイピングと呼ばれる手法が有効的です。PigDataはWebスクレイピングのプロであるため、収集したいデータがある際はぜひお問い合わせください。