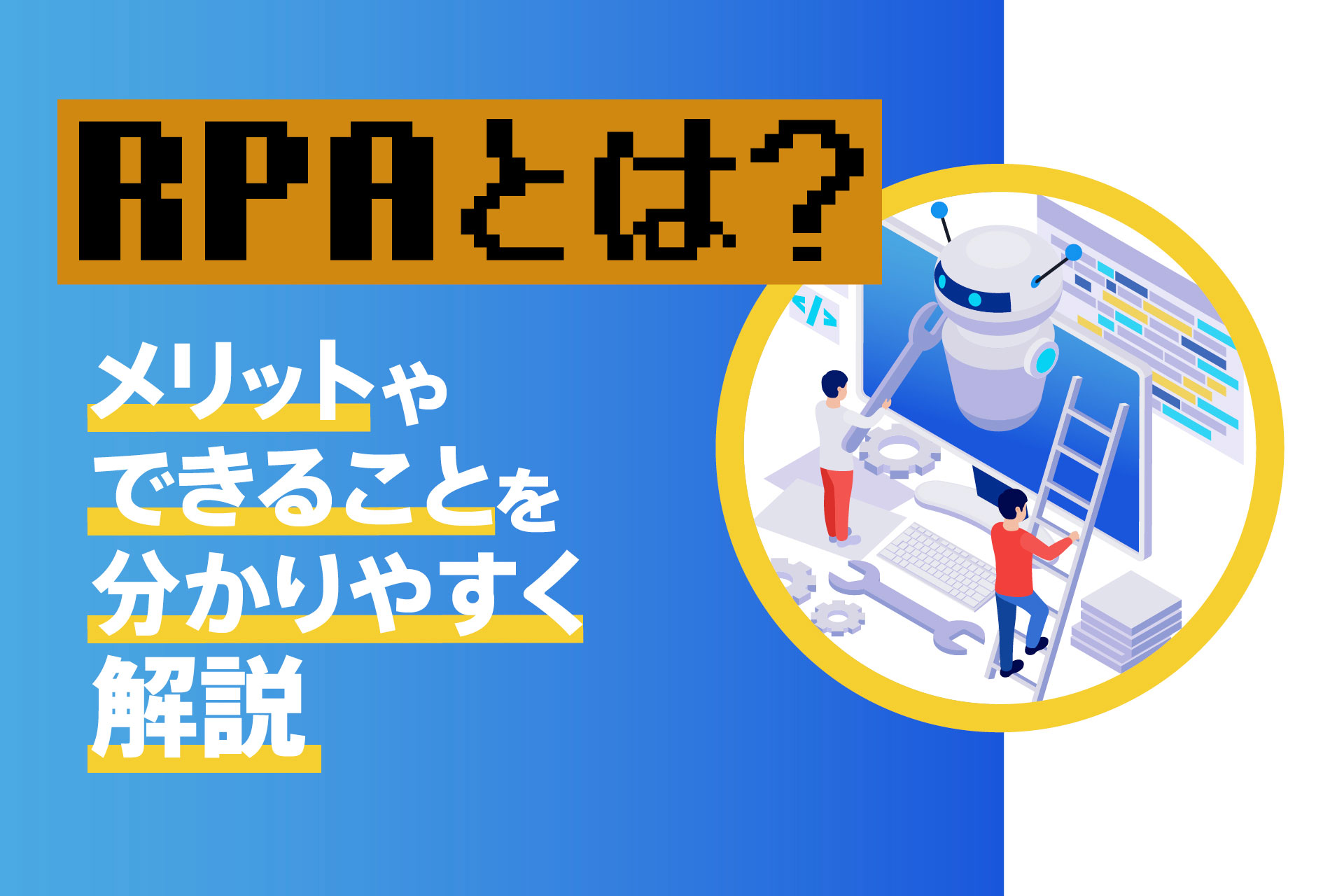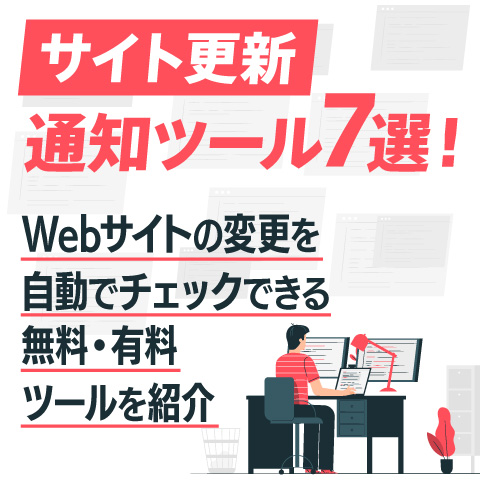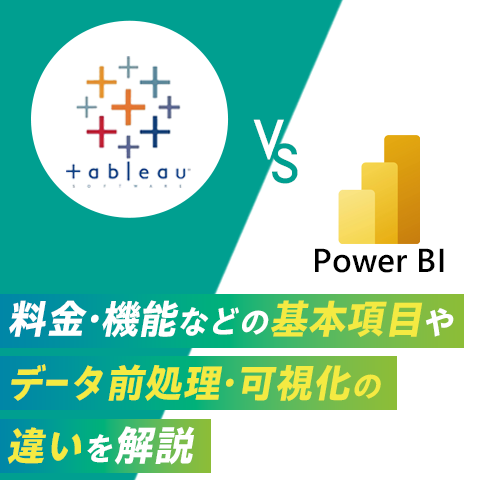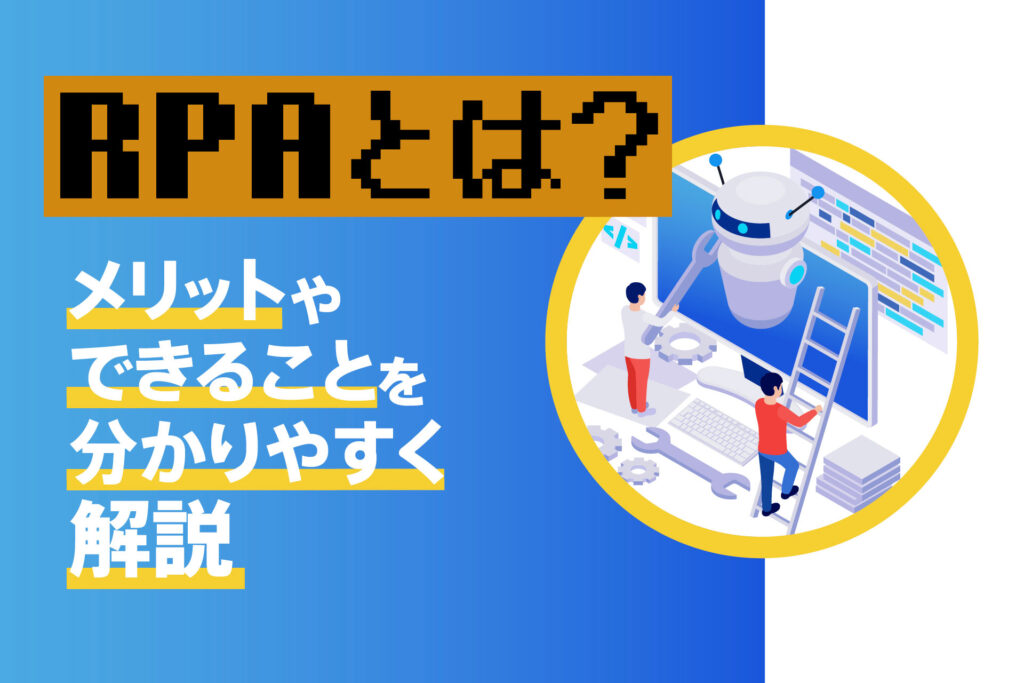
近年は業務を自動化するためにRPAが多用されるようになってきました。皆さんの現場でも、何かしらのロボットを利用していることがあるのではないでしょうか。ただ、RPAとは何か正確に理解しないまま利用している人もいるかもしれません。今回はRPAについて、わかりやすい解説を進めていきます。
RPAとは
RPAとは「Robotic Process Automation」の頭文字を取ったもので、直訳すると、ロボットを利用して自動的に処理をこなしてもらうことを指します。ここでのロボットとは、一般的にパソコンやサーバーなどに構築された「人間の代わりに作業してくれるソフトウェア」のことです。ソフトウェアに操作を指示することで、人間の代わりにパソコンを操作してもらうとイメージすれば良いでしょう。
基本的には人間の操作を再現するツールであるため、どのようなアプリケーションでも操作できることが特徴です。一部、対応できないことはありますが、マウス操作やキーボード操作であれば、概ねRPAで再現できます。
RPAが注目される背景
RPAが注目される背景は、IT人材の不足などが挙げられます。近年は多くのシステムが導入されていますが、これらに対応できる人は限られています。そのため、RPAという自動的に動いてくれるロボットを活用して、人間の負荷を減らしています。
人間の負荷を削減できれば、システムに関わらないクリエイティブな業務などに注力することが可能です。まだまだRPAでは対応できないこともあるため、余裕が生まれた人間がこの部分を処理していかなければなりません。
RPAとVBAの違い
RPAと似たものにVBAと呼ばれる技術があります。VBAはプログラミング言語の一種で、Windows環境のOfficeシリーズでの利用が基本です。事前にプログラミングしておくことによって、VBAに対応しているOfficeソフトの操作を自動化したり、データベースへ接続して情報を収集したりするなど、様々な作業に対応できます。
ただ、VBAはRPAと違い、サポートされている範囲内でしか動作できません。例えば、ExcelやAccessなどMicrosoft製品は操作できますが、Google ChromeなどWebブラウザは操作できないのです。そのため、用途が限られてしまう点に注意しなければなりません。
RPAとAIの違い
RPAとAIは同時に利用されることがあり、同じものと考える人がいますが実際には違ったものです。AIは人工知能であり自分で処理内容を考えるのに対し、RPAは人が事前に定義した処理を再現します。考えるツールか再現するツールかの違いと考えましょう。
なお、これらが混合されやすい理由は、どちらも「自動化」を必要とする場面で利用されることが多いからです。ただ、自分で考えてくれるか事前に定義するか、という点で大きな違いがあります。
RPAとスクレイピングの違い
スクレイピングは、Web上に公開されている情報を自動的に収集する技術を指します。RPAは、スクレイピングと同様にWeb上のデータ収集を自動化することが可能ですが、スクレイピング専用に作られているわけではないので、RPAツールによっては得意不得意があります。Webサイトからデータを収集したく、「どのような条件下でも」という場合はRPAではなくプログラミングを設計しスクレイピングを実装したほうが確実でしょう。
RPAの種類
RPAには大きく分けてデスクトップ型とサーバー型の2種類があります。
デスクトップ型
デスクトップ型は、RPAを個々のパソコンにインストールして利用する方法です。例えば、RPAの利用者10人がそれぞれパソコンを保有しているならば、10台のパソコンにRPAをインストールして利用します。自分のパソコンにインストールしているため、基本的には自分のパソコン内で実現できる操作しか自動化できません。また、RPAを起動している間は他の操作ができなくなるため、その点には注意が必要です。
サーバー型
サーバー型は、RPA向けにサーバーを用意して、その中にRPAを構築する方法です。サーバーとしてRPAを準備することで、基幹システムなど他のサーバーへアクセスしたり、同時に100体以上のロボットを起動したりできます。同時に大量のロボットを動作させられるため、社内で数多くのRPAを起動したい場合などにおすすめです。ただ、大規模な活用を想定したRPAであるため、初期コストが高くなったり導入時に複雑な設定が必要となったりします。
RPAでできること
RPAでできることは多くあるため、今回は例として5つを紹介します。
Web上のデータ収集
RPAを活用することで、Web上のデータを自動的に収集できます。上記でも触れた、スクレイピングと似たものであり、本来は人間がコピペなどを繰り返して収集すべき情報を機械的に集めることが可能です。例えば、ECサイトで特定のキーワードについて検索し、商品の価格を自動的に取得するなどの作業が考えられます。
ただ、RPAは事前に作業を定義しておく必要があるため、Webページが複雑で思うように情報収集できない可能性があります。また、スクレイピングの実装には法律が関わってくるため、RPAでWebデータを収集する際にもその知識が必要となります。
レポートの作成
定期的なレポートの作成を自動化できます。例えば、特定のシステムに期間を入力してレポートとしてデータを出力する作業を自動化できるのです。RPAがレポートそのものを作成するのではなく、レポートに必要なデータの一部を集めることの自動化をすることでその後の分析が楽にすすめられるもの、とイメージすれば良いでしょう。
データの転記
様々なデータの転記作業にRPAが役立ちます。例えば、取引先から送付された請求書の内容を読み取って、会計システムに入力する作業の自動化が可能です。単純な作業であり人間が対応する必要はないため、RPAに処理させることが増えています。
なお、データを連携する際は「AI-OCR」と呼ばれる、文章の読み取りツールを組み合わせることがあります。同時に導入することが多いですが、それぞれ異なった役割の別のツールであるため、そこの理解は重要です。
見積もりや請求書などの発行
事前に基づいたルールに従って、見積もりや請求書などを自動的に発行することが可能です。例えば、問い合わせフォームから見積もりの依頼が届いたことを検知し、対象となる製品の情報をデータベースから検索、見積もりのドラフトを作成することを自動化できます。今までは人間が内容を確認し計算していましたが、その部分はRPAに置き換えられるのです。結果、人間は最終的な内容のチェックと送付だけすれば良くなります。
メール配信
決まった時間にRPAを起動することで、メール配信に利用することも考えられます。例えば、毎朝RPAを利用して、作業の遅延が発生しないようにリマインドメールを送付します。メールを送信するツールと組み合わせることで、本文の動的な生成から宛先の設定、メールの送付までを自動化できます。RPAはスケジュール機能を持つ製品が多く、決まった時間に起動する要望にも応えてくれるでしょう。
RPA導入のメリット
RPA導入のメリットを挙げると4つ考えられます。
作業効率の向上
RPAによって業務を自動化すると、作業効率の向上が期待できます。特に、Webサイトでいくつもの画面遷移が生じたり、複数のソフトウェアを行き来したりする作業は、画面やソフトウェアの切り替えで時間がかかりやすいですが、RPAに処理してもらうと高速化が可能です。人間には難しいスピードでもRPAなら処理できるため、単純に処理速度で業務効率を向上させられます。基本的には自動化によって人間の手が空くことがメリットですが、人間には難しい処理速度も魅力的です。
人的ミスの低減
事前に定められたルールに沿って処理してくれるため、人的ミスが発生する可能性が下がります。人間が作業していると、どうしても何かしらのミスが発生しがちですが、RPAならばそのような状況にはなりません。ミスが減ると手戻りも減り、上記で触れた作業効率の向上にもつながります。
リソースの最適化
一部の業務をロボットに任せることで、リソースの最適化が可能です。今まで業務量が多いために、大量の人材を配置していた業務でも、RPAの導入で人員を一気に削減できるかもしれません。ある業務について削減できれば、手の空いた人員を別の業務に割り当てできます。また、場合によっては担当者の削減による人件費の低減も実現できるでしょう。
残業時間の削減
RPAによって作業効率が高まり人的ミスが減少すれば、残業時間の削減につながります。経理のように、業務量が多く残業が発生しがちな部門でも、RPAを導入すれば大きく改善できるでしょう。近年は働き方改革が重視されているため、RPAによって残業時間の削減ができれば、改革の実現に近づきます。
RPA導入のステップ
RPAを導入したいと考えるならば、以下のステップで進めていきましょう。
業務フローの洗い出し
最初に、RPAで自動化したいと考える業務フローについて洗い出します。自動化するためには、RPAに全ての作業を指示する必要があるため、業務フローの洗い出しができなければ自動化に向けた作業ができません。また、業務フローに抜け漏れがあると、RPAに作業を一任しようとした際、問題が生じると考えられます。全体のスタート地点となるため、時間がかかっても丁寧に対応しましょう。
適切なツールの選定とテスト
業務フローの洗い出しが終われば、適切なツールを選定して、自動化できるかどうかのテストを進めていきます。基本的にはRPAを中心に自動化していきますが、場合によっては別のツールも必要です。業務フローを洗い出しする際に、どのような機能を持つツールが必要なのかも検討しておくとスムーズでしょう。
ツールの選定まで完了すれば、業務フローの一部だけを実装して自動化できるかテストします。最初から全てを自動化すると、テストで問題が生じた際に大きな無駄が生じかねません。テストできる最低限の範囲に絞って自動化することを心掛けます。
効果測定と課題解決
テストが開始できる状態になれば、実際に動かして効果を測定したり課題を解決したりします。例えば、RPAの起動によって、1回あたりどれだけ作業時間を短縮できたか記録するのです。効果測定をできるだけ定量化することで、効果があったかどうか評価しやすくなります。また、RPAを導入してみると思わぬ課題が見つかることがあるため、これらを解決してさらに評価を続けていきます。
本稼働
RPAの課題を解決し相応の効果があると判断されたならば、本稼働へと進めていきます。複数の業務についてRPAを導入して、業務の効率化を目指していきましょう。ただ、本稼働においても一気に導入すると現場の負荷が高まる可能性があるため、段階的に導入し稼働させることが重要です。
RPA導入のポイント
RPAには多くの製品があるため、これらを導入したり比較したりする際のポイントを4つ解説します。
最適なRPAを見つける
RPAは製品によって機能が異なるため、最適なものを見つけ出すことが重要です。自分たちがどのような機能を求め、検証している製品はそれをカバーしているのかどうか評価しましょう。「業務を自動化する」という観点では大差ありませんが、詳細な部分は製品によって異なります。完璧に合致する製品が見つからない場合もあるため、RPAに求めることは優先順位をつけておくと良いでしょう。
例えば、デスクトップ型とサーバー型の2種類があるため、どちらのRPAにするか選択が必要です。個々のパソコンで利用することを想定するならば、デスクトップ型で良いでしょう。逆に、サーバーを立てて全てのRPAを一元管理したいならば、サーバー型を導入する必要があります。ただ、サーバー型は運用が難しくコストも高くなりがちであるため、導入を検討する際は運用できるかも考えなければなりません。もし、最適なRPAがどれなのか悩む場合は導入サポートを行っている企業に相談するのもよいでしょう。
費用対効果を評価する
RPAには高価な製品もあり、費用対効果を評価することが重要です。仮に業務効率が向上しても、莫大なコストが発生しているならばメリットが薄れてしまいます。コストだけで評価すると、RPAではなく人間が対応した方が良い場合もあるでしょう。RPAの導入はコストだけで評価すべきではありませんが、導入数が増えると負担が高まる部分であるため、常に費用対効果は意識すべきです。
運用体制を整える
RPAを社内へ導入する際は、運用体制を整えることが重要です。例えば、社内ITでライセンスなどを管理して、無駄なく社内へと展開できるようにします。また、何かしらの質問が生じた際は、サポートできる体制があると理想的です。
また、運用体制の一環として、ベンダーのサポートを受けられるようにしておくとなお良いでしょう。RPAによっては、法人向けのサポートプランなどが用意されていて、質問に答えてもらうことが可能です。思うように動作しないこともあるため、そのような状況に備え、サポートプランの活用が可能なベンダーの選定も視野に入れておきます。
スモールスタートを心がける
RPA導入のステップでも触れたように、できるだけ小さな規模で始めるスモールスタートを心がけましょう。最初から多くの業務を自動化してしまうと、問題が生じた際に手戻りが大きくなります。また、現場がRPAの導入になれる時間も必要であるため、スモールスタートでテストや評価を進め、問題がなければ段階的に範囲を広げていくべきです。
おススメのRPA
おススメのRPAはいくつもありますが、それらの中から3つピックアップして紹介します。
UiPath
UiPathは、世界中で利用されているRPAの中でも非常に有名な製品です。数多くの機能が搭載されていて、画面を操作しながら幅広い業務を自動化できます。また、パラメーターが数多く設定されていることから、複雑な操作の自動化も可能です。また、非常に有名な製品であることからSAPなど世界中で利用されている基幹システムを自動化するモジュールが最初から組み込まれています。
ただ、海外の製品であるため、情報収集には英語が求められる点に注意しておきましょう。ユーザーサポートのコミュニティが存在しますが、こちらも英語のやり取りが中心であるため、場合によっては情報収集しづらいかもしれません。
WinActor
WinActorは、NTTグループが開発する国産のRPAです。日本で開発されているRPAの中では最も利用されている製品であり、日本語のサポートも充実しています。機能開発が続けられていて、直感的な操作で多くの業務を自動化できることが特徴で、特定の業務について最初から自動化のフローが用意されている点も魅力です。
日本の製品らしくサポートが充実していることが特徴で、契約しておくことで何かしらトラブルがあった際に質問できます。RPAの設定は、専門的な考え方が必要になる場合もあるため、その部分を支援してくれることは日本の製品らしさです。
RoboTANGO
RoboTANGOは、月額契約で利用できる日本製のRPAです。簡単にロボットを作成することを意識していて、最低限の操作で業務を自動化できます。最低限の操作で済ませるために、自動化できる範囲にはやや限界がありますが、一般的な利用であれば申し分はないでしょう。サポートサービスが用意されているため、自動化してみたいことがあるなら相談することでアドバイスを受けられます。
また、RPAの中でもロボットの操作が安定していることが特徴です。処理が重いRPAを導入すると、思うように動いてくれない場合がありますが、RoboTANGOはそのような心配があまりありません。
RPAの今後
RPAはこれからも多くの企業で利用されると考えられます。業務の自動化に役立つものであるため、積極的に導入されていくでしょう。特に人材不足を解消するという観点から、RPAは非常に魅力的です。
また、近年はAIとRPAの組み合わせが増加しています。基本的に、RPAは事前に定義した内容を自動化するものですが、AIを組み合わせることで「判断」を下せるようになるのです。例えば、請求書のフォーマットを事前に定義しなくとも情報を読み取り、RPAで自動的に処理できます。また、状況に応じて分岐が必要な処理にも対応できます。AIとの組み合わせによって、さらに複雑な業務の改善にも役立てられるようになるでしょう。
他にも、業務改善を実現する「プロセスマイニング」にもRPAは役立つと考えられます。改善できる業務を見つけ出しても、適切なツールがなければこれを実現できません。その点で、RPAは幅広い業務の自動化に対応しやすく、プロセスマイニングとの相性が良いのです。
まとめ
RPAは業務の自動化に役立つツールであり、事前に定義できる業務ならば簡単に置き換えられます。ただ、言い換えると人間の判断が必要な部分など、単純作業ではなく定義が難しい部分はRPAにも置き換えられません。また、Web上のデータを収集する作業である「スクレイピング」なども、法律的な観点からRPAでの自動化には危険が伴います。
また、RPAによるスクレイピングで情報を収集しようとしても、Webサイトが複雑な構成になっている場合、実装が難しい場合があります。しかし、スクレイピング代行サービスであれば、安全かつ確実にスクレイピングによるWebデータ収集が可能です。もし、RPAを活用してWebの情報を収集する仕組みを作りたいと考えている場合、自分たちで実装するのではなくPigDataのスクレイピング代行サービスをご検討ください。