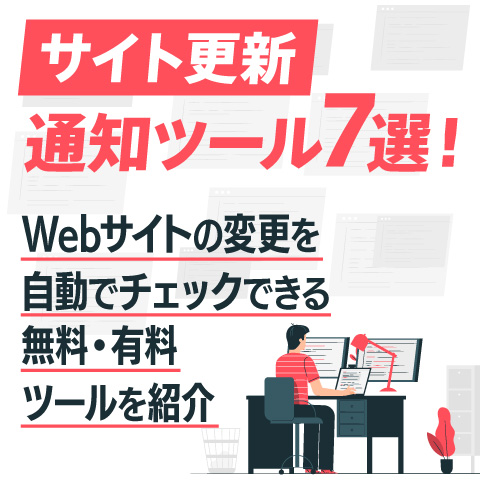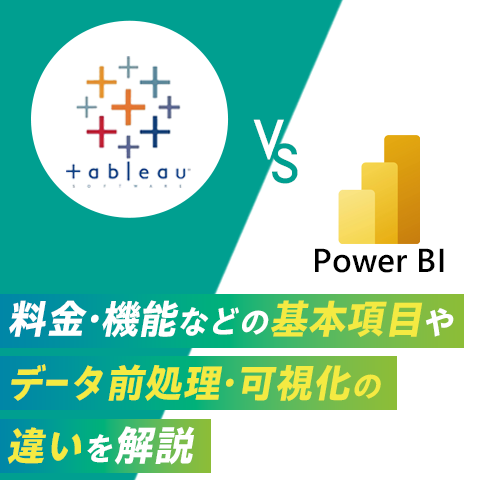ビジネスの現場では「PDCAサイクル」というキーワードが一斉を風靡し、皆さんも取り入れた経験があるのではないでしょうか。しかし、現在はPDCAが古いといわれるようになり、世の中の変化が感じられる状況です。今回は、より効率的なマネジメントを行うヒントとして、PDCAが古いといわれる理由や、PDCAに代わるOODAなど新しい手法をご紹介します。
PDCAとは
PDCAサイクルは、問題解決や品質管理など幅広い場面で使用される、反復的なプロセスの改善手法です。具体的には、以下4つのフェーズから成り立ちます。
- Plan(計画): 目標を設定し、それを達成するための計画を立てます。この段階では、問題を特定し、その原因を分析し、解決策を考案します。
- Do(実行): 計画に基づいて実際に行動します。計画を忠実に実行することが重要です。
- Check(評価): 実行した結果を評価し、計画した目標に対してどの程度達成できたかを分析します。計画と実際の結果を比較し、差異を明らかにすることが重要です。
- Act(改善): Checkの段階で得られた知見を元に、次のサイクルの計画に反映させ、プロセスを改善します。
このように、改善すべき部分を次回の計画に反映させることで、組織やプロジェクトが常に改善できるという仕組みです。また、品質管理や業務改善が主ですが、プロジェクト管理などビジネスにおいて幅広い分野で利用される傾向にあります。
一度のサイクルですぐ結果を出せるわけではないため、中長期的な改善活動に適しています。
PDCAが古いといわれる理由
PDCAが古いといわれる理由は3つあります。
計画から改善までに時間がかかる
PDCAは、計画を立ててから実際に行動し、その結果を踏まえて改善していきます。行動した結果を丁寧に評価するため、着実に成果を上げやすいですが、すぐに効果を得ることは不可能です。目に見えた結果をすぐに求められる環境では、PDCAは適していません。
現在は多くのビジネスにおいて「スピード感」が重要になっています。素早く行動して、素早く結果を出さなければなりません。そのため、中長期的な観点での成長を目的とする、PDCAは時代遅れの手法になってきました。
新しいアイデアが生まれにくい
目標を達成するため、問題点を明確にしつつ改善を繰り返すため、地道に状況を改善できます。ただ、常に前回の結果を踏まえるため「前例主義」となり、新しいアイデアが生まれにくい点がデメリットとして挙げられます。
目標達成のため、現在のやり方を改善するだけではなく、全く新しいやり方が必要な時もあります。しかし、PDCAではそのような発想に至りにくく、古いフレームワークだと指摘されるようになってきました。
負担だけがかかることになりがち
PDCAは、多くの情報を集めて分析、反映することが求められるため現場に負担のかかる作業です。使いこなせると効果を発揮しますが、現場の頑張りがあってこその結果と表現できるでしょう。
しかし、現場が忙しいとPDCAの意味を見失い「サイクルを回す」ということだけにフォーカスしがちです。結果、大した効果もなく負担だけがかかることになってしまい、嫌厭されるようになっています。
OODAとは
OODAとはアメリカで誕生した、ビジネスや学校教育現場などで用いられるメソッドです。近年、PDCAとは異なる考え方であるとして注目を集めており、日本を始め世界のビジネスシーンで広まりつつあります。
PDCAと比べて状況の即応性に優れているため、変化の早い昨今の市場で、チャンスを掴むために重要な手法であるといえるでしょう。イギリスの国際政治学者であるコリン・グレイらによって、あらゆる分野に適用できる一般理論と評価されているメソッドです。
OODAは「ウーダ」と読み、
- Observe(観察)
- Orient(状況判断)
- Decide(意思決定)
- Act(実行)
の頭文字を取った造語です。
目標に至るまでの要素を4つに分割し、4つの過程を繰り返していくことによって、正しい意思決定に繋げていきます。何度もサイクルを素早く繰り返していくことによって、数々の施策にスピード感をもって挑戦することが可能になるのです。
PDCAとの違い
PDCAとOODAは起源が異なり、それが起因して適用される環境が異なっています。今でこそ、PDCAは多くのビジネスで利用されるようになっていますが、本来の用途で考えるとOODAのほうが、より汎用的です。アプローチが柔軟であるため、多くのビジネスに適用させて利用できます。
また、OODAはPDCAよりも変化の速い環境で、迅速な対応を実現することを意識したものです。対して、PDCAはより予測可能な状況での段階的な改善に適しているという違いもあります。
OODAの意味
具体的に、OODAではどのような行動が必要となるのか、その意味合いを解説します。
Observe(観察)
Observeステップではまず、市場や顧客、競合などの対象の観察・調査を行います。現場の担当者自身が観察を行い、生のデータを収集するステップです。現在のビジネス環境では急激な変化が伴いがちなので、つい先日までは需要があったものが、急に別のものに取って代わるというのは珍しくありません。
変化にいち早く気付くには、現場の担当者自身が観察して、生のデータを収集することが大切です。観察・調査を行う上で、過去の経験や従来の常識に囚われないようにすることが重要です。思い込みや予断を排して、目の前の状況をありのまま受け入れることで、的確な状況判断を行えるようになります。
また、生のデータを収集・観察する際にはWebデータなど「外部データ」を活用することが大切です。社内で有する「内部データ」だけではなく、Webデータなど社外のデータも活用することで、より定量的かつ客観的に状況を把握できるようになります。
加えて、ここで収集したデータや観察した結果は、Orientステップに大きく影響します。そのため、優良なデータをできるだけ多く収集しておくことがポイントです。
Orient(状況判断/方針決定)
OrientステップではObserveで収集した情報を分析して、どのような状況となっているのかを把握し、行動の方向性を決めていきます。自身が培ってきた経験やこれまでの傾向から状況を正しく判断し、行動すべき順序や成果に繋がる手段を考え、実行すべき施策の仮説を立てていくステップです。
例えば、30代男性向けに販売した商品の販売状況が芳しくないためデータを収集し調査したところ、ターゲットとしていた30代男性ではなく40代男性に購入されていたことが判明したとします。相場よりも価格の高く、高級感がある商品のため、より収入が安定した40代男性から支持を集めていたのです。そのため、自社としては30代男性向けの商品であったものの、実態としては40代男性向けの商品であったと判断し、40代向けのプロモーションをしていく方針を決定します。これは一例ですが、データを基にした仮説を立てていきながら、どのような方向に舵を取っていくのか決めていきます。
Decide(意思決定)
Decideステップでは立てた仮説を基に、どのような行動を取っていくのか、具体的な方針や計画を決めていきます。
例えば、上記のように40代男性から支持が高い状況ならば、30代男性ではなく40代男性へとアプローチする方針へのシフトを決定します。今までと同じことを続けていても状況は改善しないため、具体的にどのように変更するかを決定しなければなりません。
もし複数の仮説があった場合には、目的を達成するために最適な仮説を選択し、施策を提案します。注意点としては、PDCAのように何回も繰り返して最適解を得ることを前提にする、あるいはコストを無駄にしないように入念にといった考え方をしないことです。OODAループは刻一刻と変わる環境に対して即応で成果を出す手法であるため、最善と思える行動を即座に取って最大限の効果を出すという思考で取り組みましょう。
なお、意思決定にはプロセスがあり、それを踏まえることが大切です。以下の記事もご参考にしてください。
Action(行動/改善)
Actステップでは今までのステップで決めてきたことを実行に移しながら、次回ループのObserveも同時に行います。計画に従って実行に移れば、結果とともに変化が生じるので、どのような変化が起きたのか観察して次のループに移ります。
例えば、40代男性へのアプローチ方法として広告を活用すると決定した場合、広告のデザインや媒体を40代男性へ訴求しやすいものへと変化させます。SNSでも購買層が近いものへ広告を出したり、収入が高い人向けの雑誌に広告を依頼したりするのです、そして、これらのアプローチが購買につながっているかを継続的に監視して、今までとは異なることが観察されれば、OODAで改めて現状の状況判断や意思決定を進めていきます。
OODAのメリット
OODAのメリットは以下4つです。
意思決定が迅速化される
OODAは、既存の計画にとらわれることなく、現在の状況を踏まえた臨機応変な対応ができるようにするものです。PDCAのように入念に計画を踏まえる必要がなくなり、「計画⇒承認」といったプロセスがないため、現場の判断でより迅速な意思決定ができます。これはPDCAで計画を立てている場合よりも、鮮度の高い情報に基づいた意思決定であるため、意思決定の精度もより高いものになることがメリットです。
また、計画の立案を必要とせず迅速に意思決定できるため、素早く結果が出るようになることもメリットといえます。例えば、トラブルが発生してから状況の観測、方針の決定や対策までをスムーズに進めることが可能です。急を要する際に、意思決定から結果を得るまでが短時間のOODAが特に役立ちます。
個人が裁量を持ち自発的に行動できる
個々が観察し、行動することが求められるフレームワークです。そのため、今までのように「上司が計画を決定するまで待機する」という動き方ではなく、個人が自発的に行動できるようになります。また、個々に裁量を持たせることで、今まで以上に柔軟な発想で活躍できるようになるでしょう。
自発的に行動し、それが評価されるようになれば、個々が成長を感じたり責任感を持ったりできるようになります。スピーディーに行動できるようになる以外にも、チームや組織、会社として全体的に成長することが可能です。
環境変化に対応しやすい
現場が観察し状況判断できる体制を整えることで、現場が置かれている環境の変化に対応しやすくなります。PDCAでは、計画を立てて実行するまで時間を要することがあり、その間に現場の環境が改めて変化してしまうかもしれません。しかし、OODAはPDCAよりも素早く結果を出せるため、環境が変化する前のその時の状況に順応できます。
例えば、現場で「顧客達が求めるものが変化している」と感じても、PDCAでは行動までに時間が必要です。結果、環境の変化に乗り遅れてしまい、ビジネスチャンスを逃すかもしれません。しかし、OODAならば意思決定が素早いため、環境の変化にも順応しやすく、ビジネスチャンスも逃しにくいのです。
OODAのデメリット
OODAにはデメリットもあり、以下4つです。
失敗するリスクが高い
OODAは観察した結果を踏まえて意思決定し、行動へと移すクイックさを重視したフレームワークです。そのため、観察の結果、つまり「所見」が誤っていたとしても修正されることなく前へと進んでしまいます。結果、仮説の段階で大きく誤り、その後の行動も失敗してしまうリスクが高い点はデメリットです。
対して、PDCAでは計画を立てる際に過去の失敗事例や計画の妥当性を十分に評価します。状況だけではなく、多角的な情報から総合的に判断を下すのです。そのため、比較すると失敗を回避しやすい体制が整っています。しかし、OODAはこのような評価プロセスがなく、誤りに気づきにくいことが大きなリスクなのです。
特定のメンバーに依存しやすい
個人単位でOODAを繰り返すようになることで、個人主義の現場が生まれてしまう可能性があります。結果、チーム内の一部メンバーの能力に依存する環境が生じるかもしれません。つまり、チームに所属しているメンバーに能力差がある場合、OODAの結果に差が出る可能性があります。OODAの意味で紹介した事例のように「40代男性へとアプローチする」と決定しても、実際の行動は担当者に依存するのです。そのため、能力によっては適切なアプローチができず、OODAを活かせなくなりかねません。逆に、能力が高いと十分なアプローチによって、良い結果を残すでしょう。
結果を出せる人と出せない人がいる場合、どうしても結果を出せる人に業務が偏りがちです。特定のメンバーに依存すると、負荷がかかったり抜けた場合にOODAが成り立たなくなったりするため、その点は注意すべきです。
統制を取りづらくなる
個人がOODAループを用いて判断を下すことで、統制を取りづらくなるリスクがあります。OODAループを個人で実施させることは良い方針ではありますが、その運用については注意が必要です。
特に、組織やチームとして方針が決まっている場合、個人がOODAループを繰り返すことで、それから逸脱するかもしれません。統制を意識するならば、ルールの元に運用させる必要があります。
定型業務には当てはめづらい
OODAループは「Observe」から開始されるため「このような現象が発生している」という事実の認識から開始されます。言い換えると、何かしら特定の事象が発生していなければ、このようなループを開始することができません。
そのため、定型業務のような毎回、大きな変化のない業務には当てはめづらいことが問題点です。「このような問題を解決したい」という目的ありきの業務改善には、別のプロセスを当てはめましょう。
他の業務改善手法
OODAやPDCA以外にも業務改善の手法はあるため、それらについても知識を持っておきましょう。
ECRS(イクルス)
ECRS(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)は、業務プロセスを改善するための考え方です。非効率な業務を特定し、改善することを目的としています。
主なメリットは、プロセスの効率化とコスト削減です。まず、不要なステップを排除することで作業を効率化し、人的な負担の軽減や時間の節約を実現します。また、関連するタスクを組み合わせることで、同じ作業を繰り返さないようにすることでも、効率化が図れる理由です。
ただ、デメリットとして、既存のプロセスが浸透してしまうと変更を受け入れられないことがあります。単純化・効率化されているため、新しいプロセスに反対意見が出がちです。
使用例としては、繰り返しが多い業務やエラーが発生しやすい業務が考えられます。大量の書類を淡々と処理するなど、小さなムダが大きなロスに繋がる場面で活躍するフレームワークです。
KPT
KPT(Keep, Problem, Try)は、プロジェクトや業務のレビューと改善に使用されるフレームワークです。この方法は、チームの活動を評価し、将来の改善点を見出すことを目的とします。
まずメリットとして、KPTはKeepでチームの成果やその要因を明確にするため、モチベーションを高めることが可能です。また、Problemで問題点も特定するため、次回に備えた準備にも取り組めます。また、最終的にはTryでProblemに対する新しいアプローチを起案することで、さらなる改善活動にもチャレンジできるのです。
ただ、デメリットとして、KPTはメンバーが互いに正確なフィードバックをしなければなりません。誰かを気遣い、問題点などを指摘しないと成り立たないのです。日本人はハッキリとした指摘を苦手とするため、やや順応しにくい手法かもしれません。
ロジックツリー
ロジックツリーは、問題解決や意思決定プロセスを構造化するために有効な手法です。複雑な問題を分解し、根本原因を特定することで、業務改善に役立ちます。
まず、メリットは問題を明確かつ体系的に理解できるようになることです。大きな問題を小さな要素に分割することで、それぞれの要素を詳細に分析したり理解したりできます。また、各要素がどのように連動しているかを直感的に把握することも可能です。
なお、デメリットとして、ロジックツリーの作成と利用に時間がかかることが挙げられます。特に、業務が複雑な場合にはツリーの作成に時間を要し、そこで無駄が生じるかもしれません。
まとめ
PDCAは従来から使われている業務改善手法ではありますが、素早い意思決定には向いていない手法です。そのため、時代の流れを汲んだ「OODA」が新たな意思決定するための手法として用いられるようになってきました。これからOODAを取り入れるにあたって重要なことは、「Observe」で多くのデータを収集することです。これにより「Orient」で正しい判断を下す材料を選定でき「Decide」につなげられます。
収集すべきデータは状況によって異なりますが、市場調査や競合調査では外部データの中でも「Webデータ」が有効的です。Webデータはスクレイピングと呼ばれるシステムで収集する方法が効率的であるため、こちらをおすすめします。もし、スクレイピングを導入してみたい際は、ぜひPigDataへご相談ください。