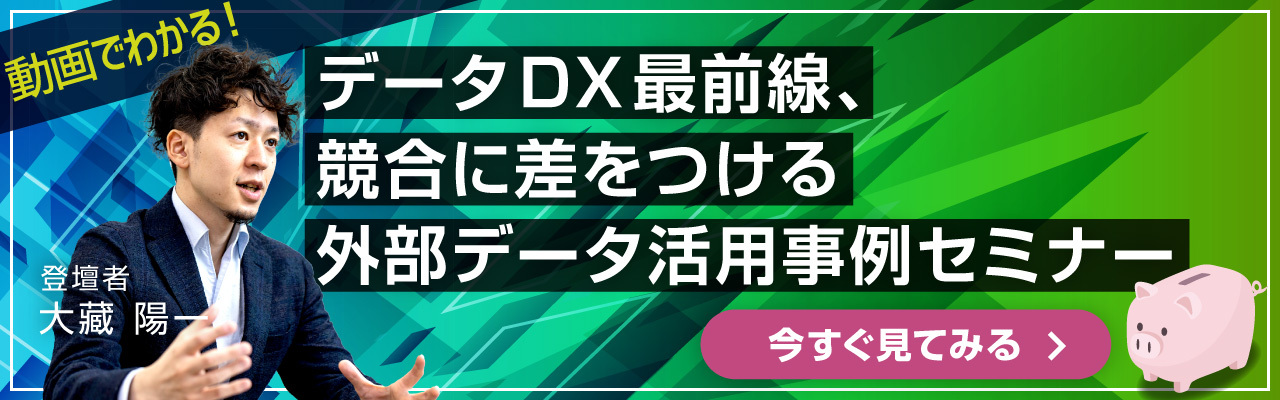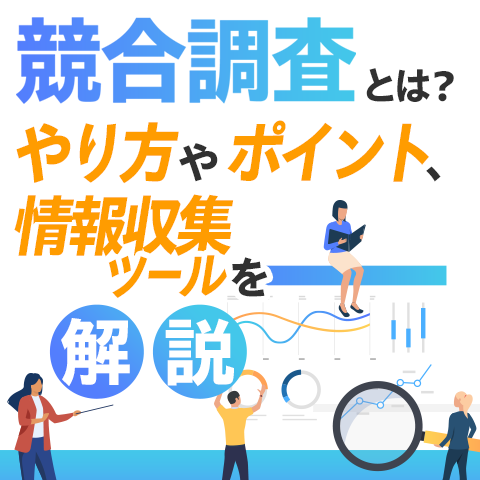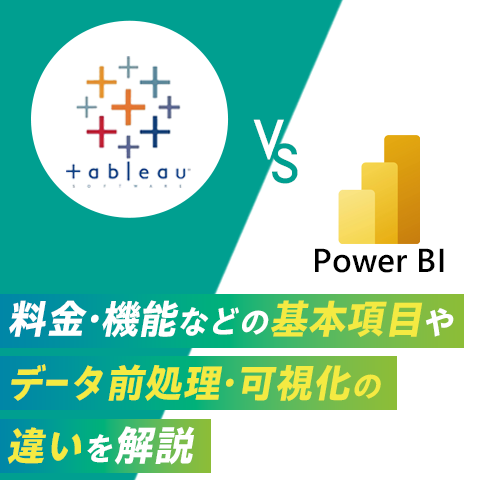企業活動においては、データ活用が重要な時代だと考えられています。数字など実績に基づいた活動が重要視され、今までのように「担当者や経営者の経験や勘だけで判断する」という状況は少なくなってきました。
しかし、データ活用が必要な理由や活用できるデータの種類のイメージが持てない人がいるでしょう。今回はデータ活用のポイントや活用事例とあわせて、これらを解説します。
データ活用が必要な理由
データ活用が必要な理由は経営上の目標を決定したり、新製品や新サービスの開発を属人的ではなく再現性のあり、データという確固たる根拠に基づいた方法ですすめるためです。総じて、企業収益を高めるために、データ活用が重視されていると考えましょう。
今までこれらの行為は、データではなく経営者や担当者の考えにだけに基づいていました。そのため、偏った考え方があると、失敗してしまうリスクがあったのです。現在でも、経営者などが最終判断を下しますが、データに基づいたエビデンスを示すことで、より正確な判断を下せるようになっています。
また、世界的に「ビッグデータ」の活用が重視されるようになりました。これは大量のデータから傾向などを見出して、製品開発やサービスの向上などに活かすものです。幅広い業界でビッグデータに基づいた事業判断が浸透してきているため、データを活用できていないと、他社に見劣りしてしまう状況になりました。
企業が活用できるデータの種類
企業が活用できるデータの種類は、大きく分けて「内部データ」と「外部データ」の2種類です。これらにも複数の選択肢があるため、どのようなデータがあるのか紹介します。
内部データ:社内の業務連絡
社内のメールや情報共有ツールなどのデータは、内部データとして活用できます。業務の内容や顧客先の情報など、活用できる情報が数多く含まれるでしょう。日頃からやり取りしている内容が、意外にもデータ活用に流用できます。ただ、これらのやり取りはデータ活用を想定したものではありません。そのため、データ活用するためには、加工が必要となります。データソースにはなりますが、活用にあたっては準備が求められると理解しましょう。
内部データ:販売など業務データ
販売活動など各種業務データは、積極的に活用できます。これを内部データとして認知している人が多いのではないでしょうか。システムなどに登録されている業務データは、非常に有用なデータソースになります。
また、これらのデータは最初から何かしらのルールに沿って登録されているはずです。そのため、その内容をスムーズに活用できることが魅力といえます。例えば、POSに登録された顧客データや販売データ、ECサイトでの販売記録や卸先との取引結果などです。これらは、所定のルールに沿って登録されているため、データの粒度が揃っており活用しやすくなっています。
内部データ:IoT機器から収集したデータ
IoT機器を導入しているならば、データを収集していることがあるでしょう。これらのデータも、何かしら活用できるかもしれません。例えば、ICカードの利用履歴から行動、エアコンの稼働状況と室温などから利用環境、スマホのGPSから位置などのデータを把握できます。IoTのために機器を導入する方法もあれば、ICカードの利用履歴のように、既存のデータを流用することも可能です。
どのようなデータが出力できるかは、導入している機器で変化します。収集できる範囲内での、データ活用を考えるようにしましょう。
外部データ:オープンデータ
オープンデータは、企業や公的機関などが、独自に公開しているデータを指します。調査や統計などの結果が公開されていて、日本全体など社外のデータであることが特徴です。代表的な外部データであると考えましょう。
また、官公庁等の公的機関が提供しているデータは、基本的に無料で利用できます。外部データの収集には、時間とお金がかかるケースがありますが、これらを活用すればコストを抑えることが可能です。さらに、データの信憑性が高いなどのメリットもあります。もちろん、公的機関以外にも多くのオープンデータが存在している状況です。活かせるデータを見つけ出し、活用することを考えましょう。
外部データ:Webデータ
Web上に掲載されている「Webデータ」を活用することが可能です。この外部データもオープンデータ同様に誰でも無料で閲覧可能となっていることが多いです。日頃から知らず知らずのうちに、Webデータを活用しているケースもあるでしょう。Webサイトに掲載されている情報を参考にする人は多いはずです。
これらのデータを大量に集めることで、非常に有用なデータソースとなります。少量では偏ったデータになってしまいますが、大量ならば統計的なデータが収集できるのです。自分たちで集める必要があり、活用までに準備が発生する外部データですが、これからは積極的に活かしたい内容だと理解してください。
データ活用のポイント
データ活用にあたっては、いくつものポイントが存在します。特に理解しておいてもらいたいポイントは、以下のとおりです。
必要なデータを見極める
データ活用にあたっては、どのようなデータが必要となるのか見極めましょう。不必要なデータを収集すると、時間を無駄にしてしまう可能性が高まります。具体的に、どのようなデータが必要になるのかは、状況によって異なります。例えば、売上数を増やしたいのであれば、流通させる商品についての情報が必要になるかもしれません。また、価格についての情報も必要となるでしょう。
これは一例ですが、必要なデータの見極めは非常に重要です。データ収集を始める前に、必要なデータは何か、データ活用の目的から選択できるようにしましょう。
データの分析・解析に力を入れる
データの分析や解析にも力を入れるようにすることが大切です。データを収集するだけでは、経営に活かせないケースが大半だと考えましょう。収集したデータを分析・解析することによって、必要な経営に必要な「資料」となるのです。ただ、分析や解析の手法は多数あるため、それらの中から適切なものを選択することが求められます。データ活用の目的に沿った結果を出せる分析手法を選びましょう。
外部データを活用する
内部データだけではなく、外部データの活用が重要です。上記で解説した、オープンデータやWebデータなどの活用が該当します。
現在普及しているデータ活用は、内部データの活用が中心です。例えば、社内の営業活動で蓄積されたデータを分析して、商品開発に活かします。「ビッグデータの活用」という観点では、これも間違った施策ではありません。ただ、内部データだけでは「自社に関連する顧客」の情報しか反映できません。つまり、分析対象のデータに偏りが生じてしまいます。これでは、市場を正確に反映できているといえません。外部データを活用しないと、分析の母体が偏ったものになり得られる結果も偏るリスクがあるため、外部データの組み合わせも重要なのです。
データが必要なときにすぐ活用できる仕組みを整える
業務でデータが必要になった時に、必要なデータが入手できる仕組みを整えておく必要があります。いざデータを業務で使おうと思っても、必要なデータが手に入るまで時間がかかるとなれば、使わなくてもよいと考えてしまう人が出てきてしまうでしょう。データ活用が面倒であるという雰囲気ができてしまうと、組織内でデータ活用が活発になりません。データ活用を促進させるには、必要なデータをすぐ取り出せる仕組みを整える必要があるのです。データを活用できる仕組みの1例として、データプラットフォームが挙げられます。データプラットフォームとはデータの集積から加工、分析まで一貫して行えるようにする機能の集合体です。データプラットフォームを導入できれば、データの分析をしたい時にすぐに作業に取り掛かれるほか、会社内で横断したデータ分析が可能となります。
しかし、データプラットフォームを導入するには専門的な知識やノウハウが必要となるので、自社に人材がいなければコンサルティング会社などに依頼する必要があるでしょう。
データを活用できる体制を整える
長期的にデータ活用に取り組んでいくために、データ活用人材を確保・育成し、適切に評価できる体制を用意する必要があります。データ活用は一朝一夕で終わらず長期間にわたるので、その場しのぎで人材を雇うのではなく、データを扱う専門の人材として常に会社に在籍させることが大切です。専門の人材を配置するということは、データ活用に対する会社の本気度の表れでもあるので、社内の意思統一やモチベーションの向上にも繋がるでしょう。専門のチームを結成すれば、データ活用を推進する取り組みに専念できるので、途中離脱の防止も可能です。
もし、データ活用の人材育成が難しい場合はアウトソーシングやBPOを活用することもひとつの手段です。難しいデータ収集やデータ分析を外部に任せることで、得られる結果からの施策を内部でじっくり検討することができます。
企業のデータ活用事例
企業がデータを活用した事例にはどのようなものがあるのか、具体例を紹介します。
スシロー
スシローはすべてのお皿にICタグを取り付けているため、どのお皿がどのように移動したかトレースできるようになっています。例えば、レーンに乗せられてからの時間や何時頃に顧客がレーンから取ったかなどを把握できるのです。
また、このようなデータを社内に蓄積し、ビッグデータとして解析しています。例えば、どのシーズンにどのような商品がよく売れているのかなどです。このようなデータの分析によって「いつ頃どのような新製品を出せば良いか」という需要の予測がしやすくなっています。
ローソン
ローソンはポイントカードの組み合わせで、商品の販売履歴を追跡しています。例えば、リピーターの多い商品とそうではない商品を洗い出し、商品の入れ替えに役立てているのです。中長期的にデータを集めることで「通年売れるわけではないが特定のシーズンに売れる商品」なども調査しています。
また、このようなデータと世の中のトレンドという外部データを組み合わせることで、新製品も開発されている状況です。社内で保有する技術をトレンドに活かすことで、効率よく売れそうな製品開発を実現しています。
オークランド
アメリカのカリフォルニア州にあるオークランドは「犯罪都市」と言われるほど犯罪が多発しています。そのため、観光客など現地に詳しくない人が犯罪に巻き込まれないため、データが活用されていることが特徴です。
オークランドでは、実際に起きた犯罪をデータとして蓄積し、分析しています。例えば、犯罪が起きやすい時間帯や場所、犯罪の種類などの傾向を洗い出しているのです。
デンソー
自動車部品メーカーのデンソーは、世界にある130程度の工場を共通のプラットフォームに接続しています。そのため、これらの情報を一元管理することが可能であり、またデータの分析なども容易であることが特徴です。
また、これらの生産に関するデータと各地の需要などを組み合わせ、生産計画を立てています。データを組み合わせることで、臨機応変に生産できるようになり、利益の向上などにも繋がっているのです。
松江市(島根県)
松江市の観光文化課は、マーケティング活動を効率化するために、観光に関するデータを活用しています。特に、市内向けの観光マップアプリの「松江歩き NAVI」やそれぞれの観光施設から収集できる内部データを分析していることが特徴です。
また、データの収集や分析にあたってはAIを活用し、表記ゆれなど分析に支障をきたす要素を可能な限り排除しています。結果、男女別・年齢別の行動パターンなどをより正確に把握できるようになり、マーケティング活動が効率化されました。
ヤクルト
飲料メーカーのヤクルトは、商品の販売データと外部データを組み合わせて、売上内容の詳細な把握に努めています。日頃からの購買データはもちろん、検索エンジンの結果や広告の反応など、大量のデータを蓄積していることが特徴です。
ただ、ヤクルトは一般的な内部のデータにとどまらず、外部データと売上の関係性を分析しています。例えば、気象データと組み合わせることで、最高気温や天気の悪さが売上に影響していないかを評価しているのです。内部の要素だけではなく、外的な要因も含めて分析に力を入れている事例です。
滋賀県日野町
滋賀県日野町では、渋滞を解消するためにデータを活用しています。町内で慢性的な渋滞が発生していましたが、データ活用により減少するようになりました。
この事例の場合、内部データではなく通信キャリアなどが収集した外部データを活用しています。例えば、人流データにより、どの程度の人がどの時間帯にどこへ集中するかを分析しました。町内でこれらの情報を収集することは難しいため、外部データを内部データのように分析し、問題の解決につなげています。
野村證券
証券会社として有名な野村證券は、外部データの活用に力を入れています。特に、TwitterなどSNSの内容を収集したり分析したりして、景気状況を把握していることが特徴です。証券会社などは「景況感指数」などを発表しているため、これらの算出に利用されています。
大量のデータを分析する必要があるため、AIと組み合わせたデータ活用の事例であることもポイントです。SNSは分析を前提にデータが発信されておらず、大量のノイズが含まれます。これをAIで処理して、効率よく活用できるようになっているのです。
医療業界
医療業界では、全体的にデータ分析やデータ活用が進み、事例も増えてきています。例えば、診療や治療、治験などのデータを活用して、新たな治療法や医薬品の開発が進められているのです。また、発症を早期に予想したり検知したりして、身体への負担を最小限に抑える取り組みもあります。
これらは「ビックデータ」を活用するケースが大半です。特定の医療機関が持つ情報ではなく、多数の医療機関や論文、日本や海外など医療業界全体を指します。内部データと外部データの組み合わせと捉えても良いでしょう。内部データだけでは信頼性のあるデータにはならないため、外部データも組み合わせて母数を増やし、医療に役立てています。
ビビッドガーデン
オンラインマルシェを展開するビビッドガーデンは、データ活用によってマーケティングを成功させています。販売する商品の見立てはもちろん、人気商品を見つけ出すためにもデータを活用している状況です。
データ活用の背景には、農家が収入の予測を立てづらいことがあります。販売できる量や収穫量が未知数であると、投資などにお金を利用できません。これを解決手段として、データ活用が推進された事例です。
データ活用における注意点
データ活用にあたっては、いくつもの注意点があります。これらについて理解して、データ分析をさらに使いこなせるようになりましょう。
複数の分析結果を活用する
データ分析の手法は数多くあり、採用するものによって結果が異なる場合があります。そのため、データ活用にあたっては1つの結果だけを信頼し過ぎないように注意しましょう。分析結果も評価しなければ、誤った方向に進んでしまう可能性があります。
特に、データの品質が悪かったり手法が適切でなかったりすると、データ活用に失敗する可能性が高まります。可能であれば、複数の手法を試すなどして、データ分析の結果が信頼できるか評価するようにしてみましょう。
データの取扱い
社内でデータ活用を推進すると、多くの従業員が様々なデータを閲覧するようになります。分析前のデータ、分析後の結果どちらについても、適切な取り扱いを心がけましょう。注意しておかなければ、情報漏洩など大きなトラブルに発展しかねません。例えば、顧客情報の分析にあたっては、個人情報を含むデータを取り扱うでしょう。そのようなデータに触れる従業員を管轄し、不正に利用しないよう注意しなければなりません。個人情報などが漏洩すると、社会的な信用力の失墜などを招いてしまいます。
そのため、データ活用においては、データを適切に利用するための「データガバナンス」の整備が理想的です。
まとめ
データ活用にあたっては、内部データを軸に外部データを組み合わせることが重要です。ただ、データは意図的に収集する必要があるため、必要となるデータを見極めて収集することからスタートしましょう。データの品質が悪いと、データ活用に失敗してしまう可能性があります。
また、内部データだけでは偏ってしまう可能性があるため、外部データの組み合わせが重要です。複数の観点からデータを分析することで、より効果的な活用ができます。外部データを活用しないと、データ活用の意味が薄れると表現しても過言ではないでしょう。
また、今後外部データを活用する企業が増えてくると予想されます。そのような時代において、自社だけ外部データを活用していないと、データ活用の結果が劣ってしまうのは言うまでもありません。他社に引けを取らないという点でも、外部データの活用が必須になっています。