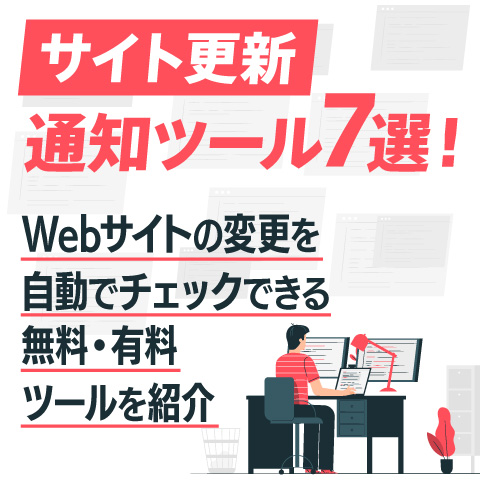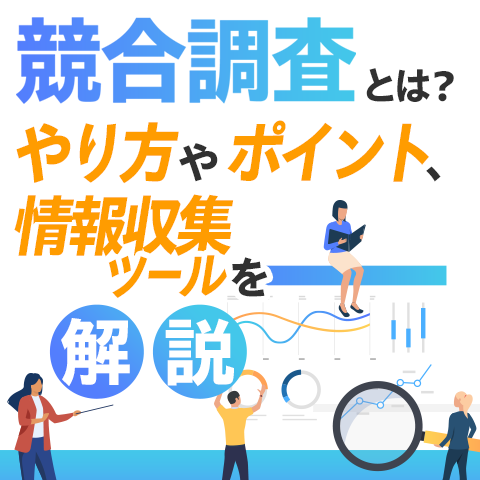データのサイロ化とは、縦割りの組織構造や複数システムの利用などにより、データ統合が行われていない状態のことです。データのサイロ化が起きれば、意思決定スピードの遅れや手間・コストの発生、顧客満足度の低下などにつながります。本記事では、データのサイロ化に関する概要や解決するメリットとそのステップ、その他データ活用における課題と解決策について詳しく解説します。データのサイロ化について知りたい方、データの有効活用を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
データのサイロ化とは

データのサイロ化とは、ある組織やシステムで収集したデータが共有・連携されておらず、他のシステムと分断された状態のことです。そもそも、サイロとは飼料・農産物などを個別に貯蔵しておく容器や倉庫のことを指します。データのサイロ化は、部門やシステムごとにデータが分断されている状態が個別タンクでの飼料保存に似ていることから名づけられました。
データのサイロ化が発生する原因
データのサイロ化が発生する主な原因は、以下の4つです。
- 縦割りの組織構造
- 複数システムの利用
- 利用システム・ツールの設計
- アナログデータの存在
順に解説します。
縦割りの組織構造
組織の構造が縦割りであれば、データのサイロ化が起きる原因になります。独立採算制などを導入して、組織の専門性や業績意識の向上を図ることは、組織戦略として有効です。
ただ、縦割りの組織を築くとコミュニケーション不足や独自業務・データ管理方法の確立につながります。ノウハウやデータの共有がなされず、結果データのサイロ化につながるでしょう。
複数システムの利用
多数のシステム利用も、データのサイロ化を引き起こす原因です。近年は、便利なシステムが複数開発・提供されており、業務改善や企業競争力の向上に役立っています。
ただ、基本的にシステムごとにデータのフォーマットや形式が異なり、データの統合が困難です。最近は、部署や業務ごとに複数のシステムを活用するケースも少なくありません。複数のシステムを導入・利用すれば、データの形式や保管場所が分散して、データのサイロ化につながります。
利用システム・ツールの設計
データのサイロ化は、利用システム・ツールの設計における問題で発生するケースもあります。複数のシステムを活用していても、データ連携や一元化する仕組みが整備されていれば問題ありません。
ただ、多くの企業では一つの課題を解決する目的でシステム・ツールを導入するケースがあり、導入後データ連携の方法を検討しています。最初からデータ連携ありきでシステム選定しなければ、導入後に連携が難しかったり、手間がかかったりすることに気付く場合もあるでしょう。
アナログデータの存在
アナログデータの存在は、連携を阻害してデータのサイロ化を引き起こします。手書きの情報などが存在する場合、連携させるために一度デジタルデータへの変換が必要です。
現在はDXが推進されており、多くのデータがデジタル化されていますが中にはアナログデータ中心の企業もあるでしょう。また、過去の膨大なアナログデータを活用するためにどうすれば良いか、悩みを抱える企業も存在します。
データのサイロ化により発生する悪影響
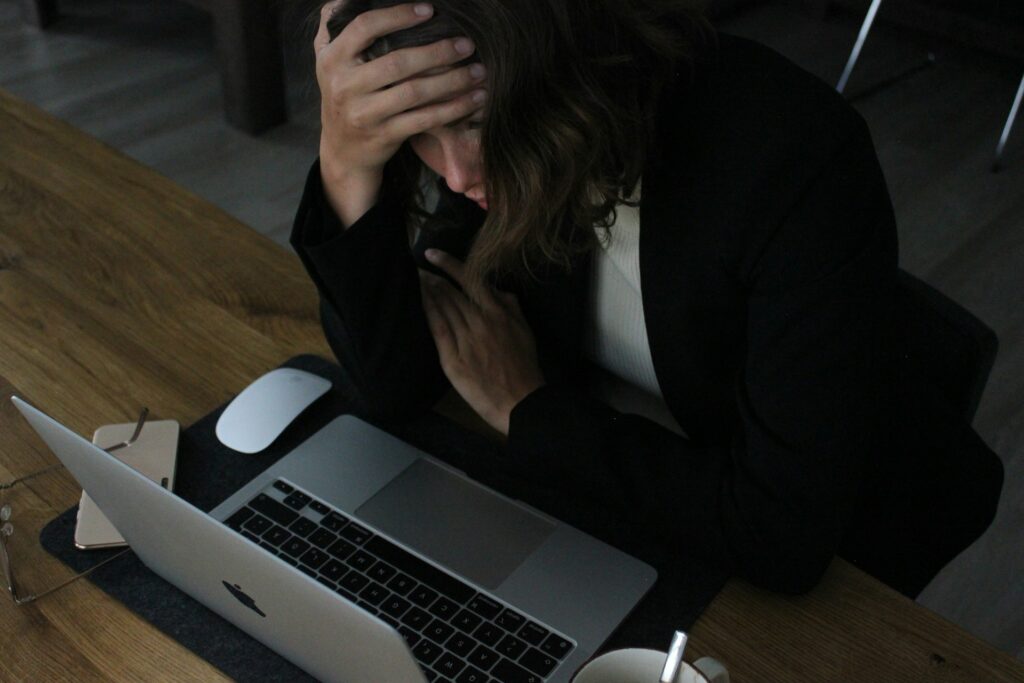
続いて、データのサイロ化により発生する悪影響を紹介します。
データ活用が阻害される
データのサイロ化における問題の一つは、データ活用が阻害されることです。業務効率化などに役立つAIやIoTなどの最新テクノロジーは、データを活用することで効果を発揮します。とくに、AIは大量のデータ学習で作業や業務処理の精度を向上させる仕組みが取られています。有効なソリューションの活用には、統合された大量のデータが必要です。
意思決定スピードと正確性が低下する
データのサイロ化が起これば、意思決定スピードと正確性の低下を招く恐れもあります。企業内の情報がさまざまなシステムに点在している場合、データに基づく判断が困難です。各システムを個別に確認すれば、その分多くの手間と時間がかかるでしょう。しかし、全ての情報を把握せずに意思決定を行った場合、間違った判断をするリスクがあります。
手間が発生し作業効率が低下する
データのサイロ化は、手間を発生させるとともに作業効率の低下を招きます。データが統合されていなければ、活用するにあたり手動で集約しなければなりません。また、人がデータ転記を行った場合、ヒューマンエラーが発生するリスクがあります。入力データが重複して無駄な業務が発生しているケースもあるでしょう。
コストが発生する
コストの発生も、データのサイロ化による悪影響です。例えば、データの統合作業や情報共有を目的とした会議により、人件費が増加します。また、部署や業務ごとにシステムを導入すれば、運用・管理負担の増加や無駄なライセンス費用の発生につながるでしょう。
顧客満足度が下がる
顧客満足度の低下も、データのサイロ化の悪影響です。近年は、カスタマーエクスペリエンス(CX)やカスタマーエンゲージメント(CE)などの考え方が注目されており、顧客ごとにパーソナライズした体験・価値の提供が重要です。
各顧客に合わせてアプローチ方法や紹介する商品・サービスを変えなければ、ユーザーの不満につながるでしょう。また、データの適正な分析ができない場合、既存商品・サービスの効果的なアップデートが困難です。
データのサイロ化を解決するメリット

続いて、データのサイロ化を解決するメリットについて解説します。
データの価値向上と利用の促進
データのサイロ化を解決することにより、データの価値向上と利用の促進が可能です。データを統合すれば、さまざまな分析ができるようになるでしょう。結果の正確性や活用方法の幅も広がります。
スピーディーで適切な経営判断の実現
スピーディーで適切な経営判断の実現も、データのサイロ化解消におけるメリットです。データが一元化されていれば、さまざまなシステムを確認することなく、一目で正確な状況を掴めるでしょう。また、データを総合的に加味した経営判断を行うことで、適切な施策を検討・選択できる可能性が高まります。
業務効率化と生産性の向上
データのサイロ化解消は、業務効率化と生産性の向上にもつながります。重複した情報の入力を避け、必要な情報へのスムーズなアクセスを実現可能です。情報入力などのルーティンワークが減少すれば、従業員は本来行うべき売上の向上やコスト削減に効果を発揮するコア業務に、多くの時間を割けるでしょう。
顧客満足度と売上の向上
データのサイロ化を解消すれば、顧客満足度と売上向上も期待できます。多彩なデータの統合と分析は、正しい顧客ニーズの理解につながるでしょう。顧客ごとに適切な対応が可能になります。
また、既存商品・サービスをブラッシュアップするヒントも得られます。市場の動向やニーズの分析は、新たなビジネスを構築する手助けとなるでしょう。長期的な顧客との関係を築くだけでなく、新たな顧客獲得により売上向上が見込めます。
データのサイロ化を解決するステップ

続いて、データのサイロ化を解決するステップについて解説します。
1.組織別データの棚卸しと統合対象の検討
まずは、各部門・部署など組織別データの棚卸しを行います。具体的には、保有するデータの種類や量、使用・管理方法などの調査を行います。棚卸しが終わった後に、データを統合した方が良いか、する場合はどのデータを対象とするかを検討しましょう。
2.データの統合
データを収集・保管するシステムが異なれば、形式もデータごとにバラツキがあるでしょう。そこで、データの標準化やクレンジング、マージなどを実施してデータの形式を揃え統合を行います。データの統合には専門的な知識やスキルが求められるため、IT部門や専門家と相談しながら進めると良いでしょう。
3.データ保管場所の用意やルール化
次に、データの保管場所を用意します。クラウドストレージやデータウェアハウスなどの利用がおすすめです。データウェアハウス(DWH)とは、企業内のさまざまなシステムやデータソースから収集された大量のデータを統合・蓄積するデータベースのことです。高いデータ処理速度とアクセス性能が特徴で、データ分析や報告を行う目的で、多数の企業が利用しています。
なお、データウェアハウスの詳細は以下をご覧ください。
また、併せて保管場所や保管する際のルールなどを決定することにより、データのアクセス性やセキュリティが向上します。
4.適切なアクセス権限の設定
最後に、データへの適切なアクセス権限を設定します。サイバー攻撃で高度なアクセス権を持つアカウントが乗っ取られれば、さまざまなデータにアクセスされてしまい被害が拡大するでしょう。情報漏洩などのリスクを減らすには、必要最低限のアクセス権限設定が重要です。また、定期的にアクセス権限の見直しを行い、設定し直しましょう。
サイロ化以外のデータ活用における悩み・困りごととその解決策

最後に、サイロ化以外のデータ活用における悩み・困りごととその解決策について解説します。
企業内の協力体制が整わない
データの適切な活用には、企業全体でデータの収集が必要です。ただ、中には企業内の協力体制が整わない会社もあるでしょう。一部の部署や担当者が頑張りデータの収集を行っても、他が実施せず必要なデータがそろわなければ有効活用は困難です。
社内の協力体制を築くには、経営層の理解と推進が求められます。データ活用には多くの手間とコストがかかり、短期的な施策ではなく長期的に実施することが重要です。まずは、経営層が理解して従業員に協力を呼びかけるとともに、リーダーシップの発揮が求められます。また、プロジェクトなどを組成してデータ活用の旗振り役を任命するのも良いでしょう。
データ活用に関する専門人材を採用できない
データ活用には、専門的な知識やスキルを有する人材が必要です。ただ、近年はDX・データ活用の需要が増加する一方で、専門的なノウハウを備えた人材の供給が追いついていません。専門人材の市場価値が高まるとともに、人件費も高額になっており、自社での採用が難しいケースがあるでしょう。
そこで、外部パートナーの活用も有効です。自社での採用・育成には多くの手間と時間、コストがかかりますが、外部パートナーであれば、必要な場面のみ依頼できスピードやコストパフォーマンスが高まるでしょう。
収集したデータの精度が低い
収集したデータの精度が低ければ、間違った分析結果が導き出されてしまいます。具体的には、データが不正確、古い、不完全などの質が低いデータ利用はリスクがあります。データは大きく社内と社外データの2つに分けられ、効果的な活用には両方必要です。とくに、正確な社外データを自社のみで収集するのは簡単ではありません。
自社で難しい場合は、外部パートナーやツールを上手く利用すると良いでしょう。近年は、簡単に情報収集できるツールも多数存在します。コストはかかる一方で、正確性の向上や手間の抑制につながります。PigDataでは、Web上のデータ収集をサポートしており、ご希望する形式への成形も可能です。また、データ活用のお悩みを解決するコンサルティングから実際の活用まで全面的にサポートしています。
なお、効果的な活用につながるデータの種類に関する詳細は以下をご覧ください。
実施事項が多すぎて対応しきれない
データ活用と一言でいっても、実施事項が多く対応しきれないケースもあるでしょう。具体的には、データの収集や整理・成形、分析などを行う必要があります。また、データ分析の手法も多数あり、活用方法に応じて適切な方法で行わなければなりません。
そのため、まずはデータ活用の目的を明確にしましょう。目的が明確にならなければ、収集するデータや分析手法が定まらず無駄な作業が発生します。
なお、データ分析の進め方や分析手法の詳細は以下をご覧ください。
まとめ

データのサイロ化とは、ある組織やシステムで収集したデータが共有・連携されておらず、他のシステムと分断された状態のことです。サイロ化が起こればデータ活用が阻害され、意思決定スピードの遅れや手間・コストの発生、顧客満足度の低下など多くの悪影響が発生します。
データのサイロ化を解決するにはデータ収集・連携・分析基盤の構築が重要です。ただ、社内の現状が不明瞭、他部署との連携が難しい、データ活用できる環境が整っていないなどの課題・悩みを抱える企業も多いでしょう。
そのような場合には、PigDataにお任せください。データ戦略立案からデータの収集・貯蓄・分析・活用までお客様の状況に合わせて解決策をご提案いたします。
まずは無料相談から!一緒にデータ活用の課題を解決しましょう!