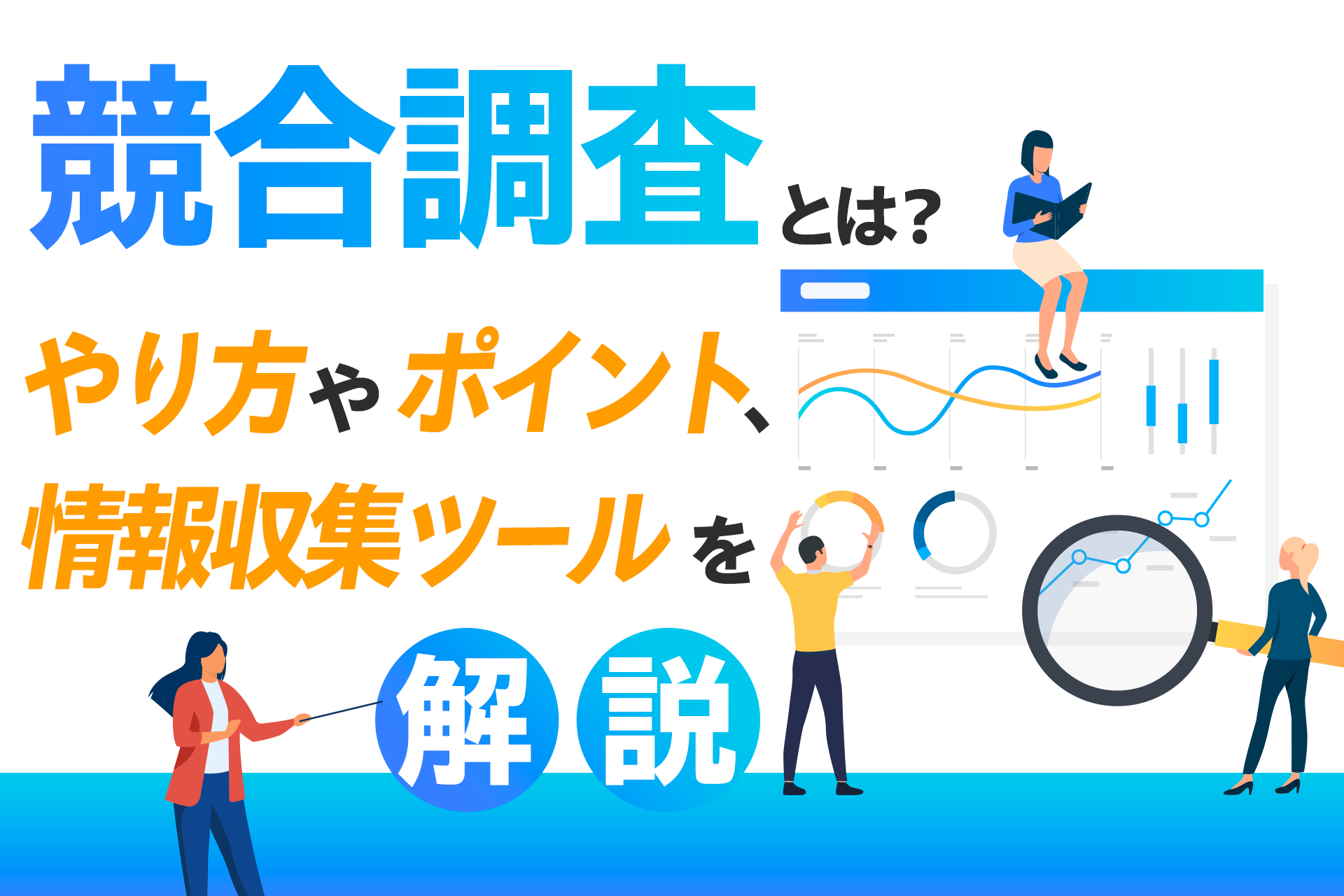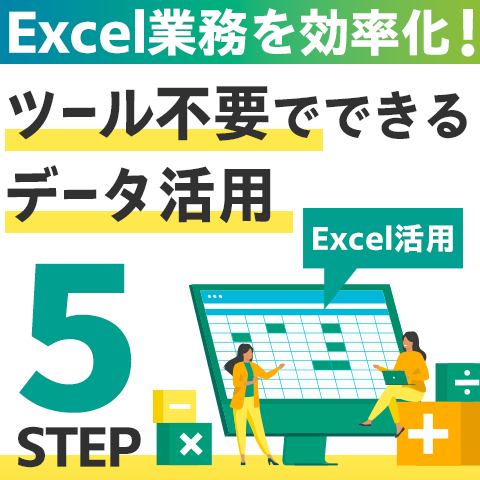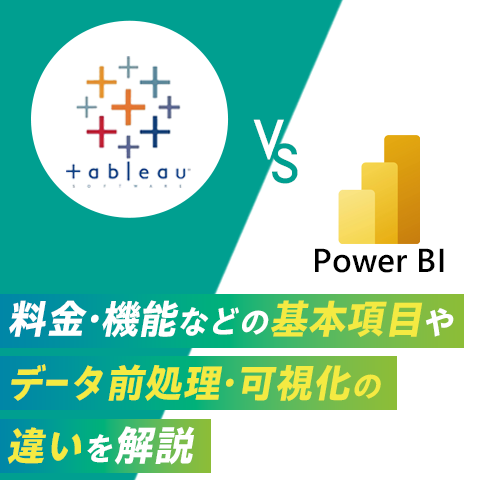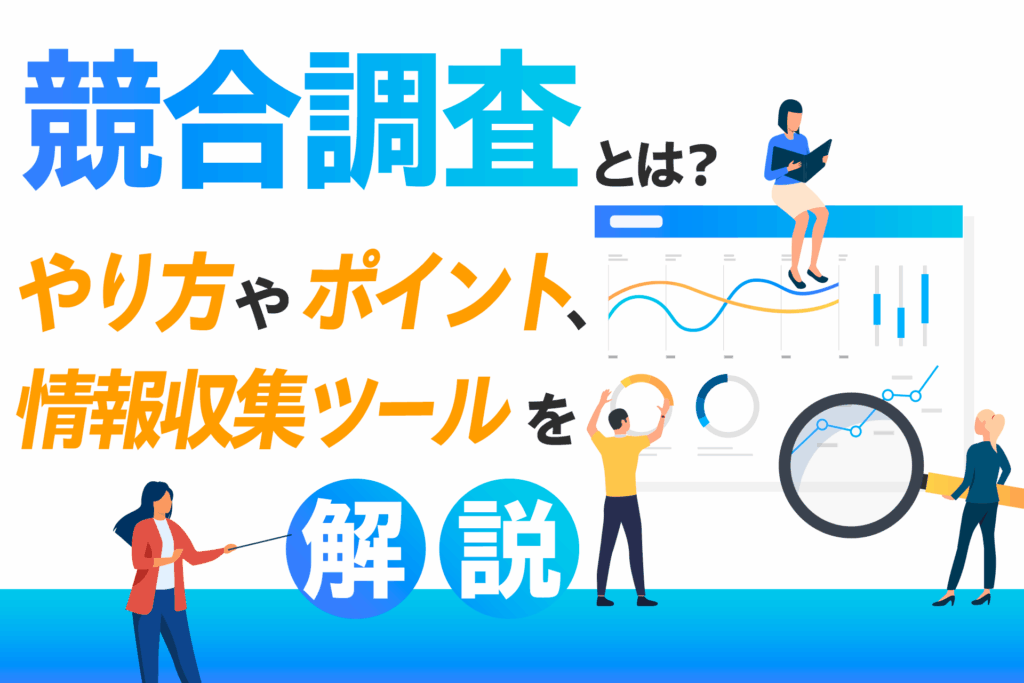
マーケティング担当者や企画担当者にとって、競合他社の動向を把握することは重要です。いわゆる競合調査によって、市場の動きを捉え、自社の立ち位置を明確にすることが求められます。商品やサービスの価格設定や付加価値の検討、リリース時期など数多くの戦略が求められます。これらの戦略は、事業成長のカギを握る要素です。
ただ、競合調査についてやり方が分からず、漠然と実施している人が多いのではないでしょうか。今回は、競合調査を効率よく進めるために、やり方や押さえておきたいポイント、効率化するツールなどを解説します。
競合調査とは
競合調査とは、自社と同じ市場で活動する他社の製品・サービス、価格、販売戦略、強み・弱みなどを分析する活動です。また、分析結果を踏まえて、自社の戦略に活かすことも含まれます。市場の動向やトレンドを把握し、自社の差別化ポイントや改善点を明確にすることが大きな目的です。既存の商品やサービスに対して調査するイメージを持たれますが、新商品開発やマーケティング戦略の立案にも役立ちます。
競合調査を行うメリット
競合調査を実施するメリットを解説します。
相対的に自社の強み・弱みを把握できる
競合調査のメリットの一つは、自社の強みや弱みを客観的に把握できることです。自社だけを見ていても、市場での立ち位置は見えてきません。競合調査を行い、他社と比較することで、自社の優位性や改善点が浮き彫りになります。
商品やサービスを他社と差別化できる
競合の商品やサービスを把握することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。競合が提供していない価値を打ち出すことで、市場での独自性や優位性を築くことが可能です。特に競争の激しい市場では、他社との差別化は重要な戦略となります。
競合他社の存在を認知できる
競合調査を通じて、これまで認識していなかった競合企業の存在を把握できる点も大きなメリットです。とくに中小規模の企業や新興企業は見落とされがちですが、これらを把握することで、自社の競争環境や市場での立ち位置をより正確に理解できます。
競合調査のやり方
具体的に、競合調査をどのように進めていくか、そのやり方を解説します。
競合調査の目的を明確にする
まず最初に行うべきは、「何のために競合調査を行うのか」を明確にすることです。目的が不明確なままだと、調査すべき内容の判断ができず、方向性がぶれてしまいます。また、調査結果をどのようにビジネスへ活用するかも、事前に検討しておくことが重要です。目的と活用方法をセットで考えることで、調査結果を事業へ効果的に反映しやすくなります。具体例を挙げると以下のとおりです。
- 競合調査の目的 :売上高を5%伸ばすために、競合他社の製品情報を網羅する
- ビジネスへの活用方法:送料無料やポイント還元率などの付加価値施策の見直しに活かす
さらに、競合調査では「仮説を立てて検証する」視点も重要です。たとえば、「送料無料の商品は売れやすい」という仮説を立て、それが実際のデータと合致するかどうかを検証します。仮説が正しければ施策に活かし、誤っていれば新たな視点で仮説を立て直す、といったサイクルを繰り返すことが調査の精度を高めます。
競合の企業や製品を選定する
競合調査は、対象を正しく選定することから始まります。やみくもに調査を始めるのではなく、実際に競合となりうる企業や製品を事前に洗い出すことが必要です。
たとえば、自社が「平均単価5,000円のアクセサリーを販売する通販サイト」を運営している場合、以下のように競合性を判断します。
- A社:単価の平均 3,000円
- B社:単価の平均 20,000円
- C社:単価の平均 6,000円
この場合、A社とC社は価格帯やターゲットが近いため、直接的な競合と見なせます。一方で、B社は単価が大きく異なり、顧客層も異なると想定されるため、、競合性は低いといえます。
このように、「本当に競合になり得るのか」という視点で対象を絞り込むことが、調査の精度を高めるポイントです。誤った競合選定は、的外れな施策や判断ミスにつながるリスクがあります。
選定した企業や製品の情報収集を行う
競合企業や競合製品を選定できたならば、具体的に情報収集を進めましょう。情報の収集元はいくつもあり、たとえば、以下が考えられます。
- コーポレートサイト(ビジネスモデル)
- サービスサイト(製品・サービス)
- SNS
- 採用サイト(人事戦略)
- ニュースサイト(ニュースリリース等)
競合調査では情報の鮮度が重要です。できるだけ頻繁に更新されている情報源を利用すると良いでしょう。たとえば、コーポレートサイトよりも、SNSで頻繁に情報を発信する企業があるかもしれません。できるだけ新しい情報が手に入る情報源を用いて、必要な内容を集めましょう。
収集した情報の分析と可視化を行う
競合調査によって集めたデータは、分析と可視化によってはじめて実際の戦略に活かせます。たとえば「どの会社がどんな商品に力を入れているのか」「どの価格帯が多いのか」といった情報を整理し比較することで、自社の立ち位置や改善点が明確になります。さらに、価格帯や促進施策をマッピングするなどして業界内のポジションを図で見せれば、営業・企画・経営層それぞれが迅速に次のアクションを判断しやすくなります。
ただし、こうした分析や可視化には、複数の情報源からのデータを集めて整理し、目的に合った形でまとめる手間がかかります。グラフや図をつくる際も、ツールの選定や設計に一定の知識が必要です。
PigDataでは、「データをどう使うか分からない」というお悩みに対して、情報の整理から分析・見える化までを一貫してサポートしています。属人化しがちな調査・分析業務を仕組み化し、チーム全体で活用できるデータ基盤の構築を支援します。データの扱いに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
バラバラなデータをまとめて分析に繋げるなら ⇒データ統合&自動化システム構築サービス
見やすく伝わるグラフ・ダッシュボード作成なら⇒Tableau構築支援サービス
分析結果から戦略・施策へ活かす
分析結果から得た知見をもとに、戦略や施策へ活かしていきましょう。分析の目的は、単なる情報整理ではなく明確な意思決定に繋げることです。分析結果が設定した目標に対して十分な答えを出しているかを評価します。もし、事前に仮説を立てているならば、その内容が正しいかを検証する作業も必要です。仮説が外れている場合は、新たな視点で戦略を見直す必要があります。
競合分析では、特定の企業だけでなく複数の競合に対してもバランス良く情報が集まっているか確認しましょう。偏りがある場合は、別の分析対象について情報を収集したり改めて分析したりする作業が必要です。
必要な情報が揃ったならば、具体的な戦略や施策に落とし込みます。たとえば、売上の増加を期待して「価格や割引率の見直し」「ポイントや送料無料などの付加価値の提供」などです。重要なのは、得られた知見をどのように戦略や施策に変えるかです。分析は手段であり、目的は成果に繋げることを意識しましょう。
競合調査のポイント
競合調査を実施する際は、以下のポイントを意識するようにしましょう。
- 常に競合の最新情報をチェックする
- 調査結果の活用方針を明らかにする
- フレームワークを効果的に活用する
- 情報の入手経路を複数設ける
常に競合の最新情報をチェックする
情報を収集する際は、常に最新の情報であるかを確認しましょう。古い情報を収集しても、現在との乖離が大きく役に立たないケースがあります。たとえば、ECサイトの運営で1週間や2週間前の製品価格を収集しても、直近の価格設定には反映しづらいでしょう。現在、競合がどの程度の価格を設定しているかを知り、それを踏まえて自社の価格を決定すべきです。「現在、競合他社がどの程度の価格で、どのようなサービスを提供しているのか」を確認できる情報を収集、チェックするようにします。
調査結果の活用方針を明らかにする
調査結果の活用目的を明確にしておくことがポイントです。たとえば、「ポイント還元率を競合他社と比較したうえで決定したい」などと定めておきましょう。明確な調査目的があると、どのデータを中心に収集し、どのような観点から分析すればよいかも明確にできます。
フレームワークを効果的に活用する
むやみに調査を行うのではなく、適切なフレームワークを活用しましょう。これにより、収集した情報から必要な要素を抽出しやすくなります。活用の目的を明確にし、それに沿ったデータとフレームワークを活用しましょう。
情報の入手経路を複数設ける
情報の入手経路は複数設けるようにしましょう。複数設けることで、最新情報を収集しやすくなり、データの偏りを防ぐことができます。例えば、以下のような経路が考えられます。
- 競合企業の公式Webサイト
- プレスリリースやニュース記事
- 業界団体・業界誌のレポート
- SNSや口コミサイトでのユーザーの声
- 店頭調査やオンラインショップの価格比較
- 有料の市場調査データやコンサルティングレポート
競合の最新情報を効率よくチェックする方法
競合の最新情報を収集する際は効率化が重要です。少ない負担でチェックする方法を紹介します。
Webスクレイピング
Webスクレイピングは、Webサイトのデータを機械的に収集する技術です。システムが指定したURLへアクセスし、必要なデータだけを自動的に取得します。コンピューターがデータを収集するため、人間よりも効率よく、大量の情報を収集できることが特徴です。
ただし、Webスクレイピングには専門的な知識を習得しなければなりません。そのため、専門的な知識を持ち合わせていない場合は、スクレイピング代行サービスを利用するのもよいでしょう。
PigDataでは、ご要望に合わせてデータを収集するWebスクレイピング代行サービスを提供しています。また、収集したデータを分析、可視化、活用まで幅広いサポートも行っています。競合調査に向けて大量データの収集や分析が必要となる場合は、ぜひご相談ください。
TOWA
競合の情報が変化したことを素早く察知したい場合は、Web監視ツールの「TOWA」がおすすめです。事前に監視したいURLを登録しておくことで、そのWebサイトに変更があった際に関係者へ通知できます。たとえば、商品の価格を監視しておけば、キャンペーンや値下げなどが発生した際に即座に察知することが可能です。
Web監視ツールは複数存在しますが、TOWAでは最大で25,000件のURLを登録できます。競合が多数存在していても、すべてを網羅しながら効率的に競合調査を実施できるのです。
Googleアラートの活用
簡単に競合調査を実施したいならば、Googleアラートの活用がおすすめです。事前に調査したいキーワードを設定しておくと、それに該当するWebページやニュース記事が公開された際に通知してくれます。例えば、競合他社が自社と同様のサービスや商品を展開したことなどを素早く把握できるようになるでしょう。
無料で利用できるツールではありますが、通知したい情報の設定には限りがあります。競合の大枠を調査する場合には向いていますが、詳細まで調査する場合は向いていません。競合調査の第一歩として捉えると良いでしょう。
IR情報・プレスリリースの自動通知設定
IR情報やプレスリリースを自動的に通知してもらう方法もおすすめです。企業によっては、最新情報をSNSなどで公開している場合があるため、これを自動通知で受け取れるようにします。たとえば、Xのアカウントをフォローしておき、新しいポストがあった際にスマートフォンアプリで受け取るなどです。
ただ、すべての企業が頻繁に情報を発信しているとは限りません。また、SNSアカウントを持たない企業やIR情報の発信頻度が少ない場合もあります。そのため、自動通知だけに頼らず、必要に応じて自ら情報取集を行うことも大切です。
競合調査で使えるフレームワーク
競合調査では、収集した情報を効率的に分析するため、目的に応じたフレームワークを利用します。
3C分析
3C分析は「Customer(市場・顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3要素から成るフレームワークです。競合調査では特にCompetitorの視点を重視し、自社と競合の違いや強み・弱みを明確化します。顧客ニーズや市場動向と照らし合わせることで、自社が取るべき戦略の方向性を把握できるのです。
SWOT分析
SWOT分析は、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4要素に分けて対象企業を分析する手法です。競合の戦略や市場での立ち位置を理解し、自社が活用できる機会や警戒すべきリスクの特定に役立ちます。内部環境と外部環境の両面から比較できる点もポイントです。
ポジショニングマップ
ポジショニングマップは、縦軸と横軸に異なる評価基準(例:価格×品質)を設定し、競合と自社の立ち位置を視覚的に整理する手法です。市場内での差別化ポイントや競合の集中度、空白市場(ブルーオーシャン)を発見する際に活用されます。直感的に理解しやすいことも特徴的です。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の活動を製造や販売など「主活動」と調達や人事など「支援活動」に分解して分析する手法です。どの部分が競争優位を生み出しているかを明らかにします。競合が持つ強みの源泉や効率的なビジネスモデルの構造を理解するのに適していることが特徴です。競合の強みを踏まえて、自社が何を改善すべきかの洗い出しに利用されます。
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析は、業界の競争環境を「既存競合」「新規参入」「代替品」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」の5つの視点から分析する手法です。競合の脅威だけでなく、業界そのものの魅力度や競争の激しさを評価できます。中長期的な戦略立案に有効な分析手法です。
まとめ
競合調査を実施する際は、目的を明確にして活用方法を定め、最適な情報を収集することが重要です。さらに、情報を収集するだけでなく、最適な分析方法を用いて活用することも欠かせません。また、競合調査は一度きりで終えるものではなく、市場の変化に合わせて継続的に競合の動向を把握し続ける必要があります。
しかし、継続的にデータを収集・分析する作業は、社内で大きな負担となりがちです。そのため、競合調査を継続的に実施したい場合は、データDX支援企業「PigDate」にご相談ください。社内や社外のデータ活用にむけて、データの収集・分析・可視化を支援し、競合調査全体をサポートいたします。