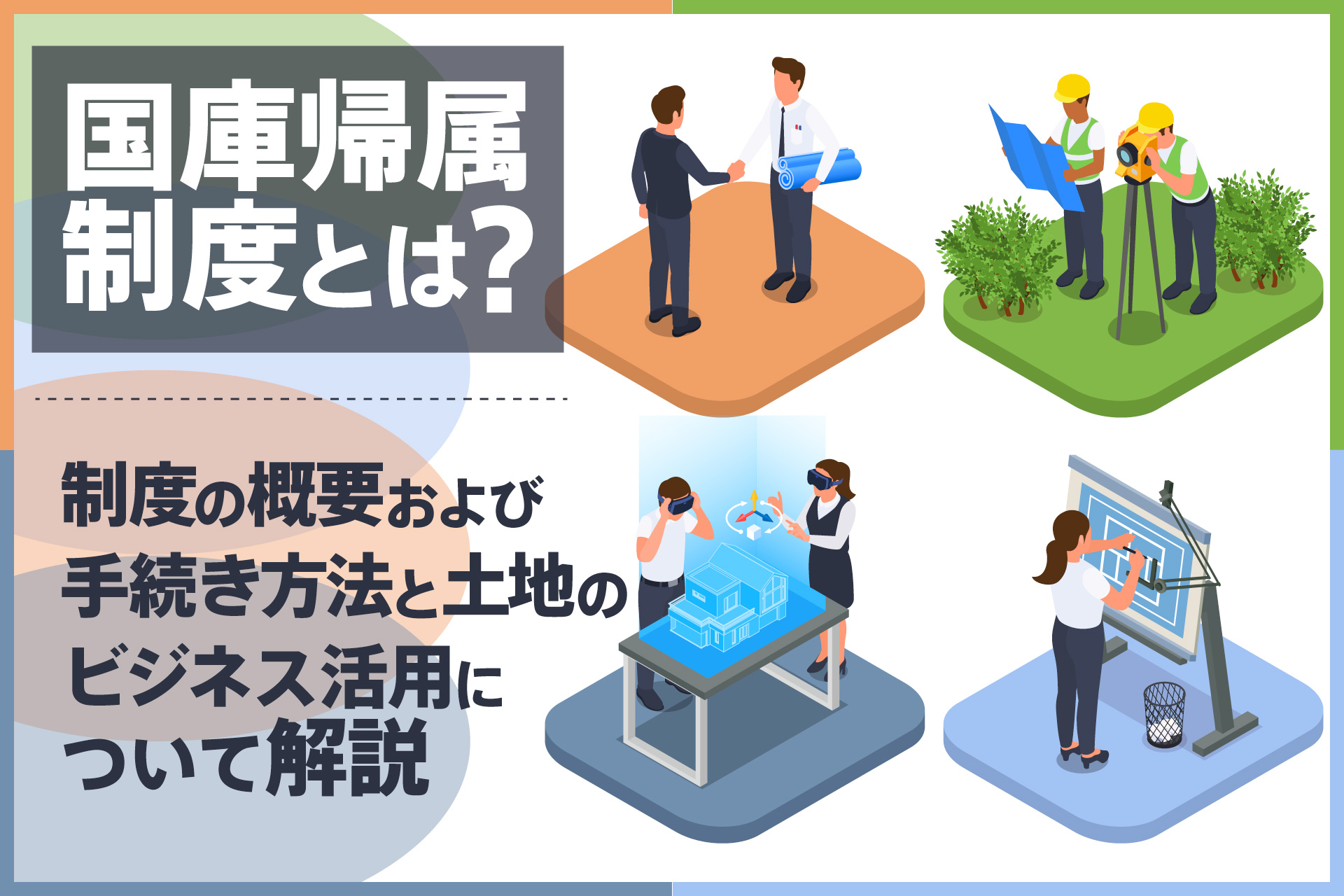この記事では国庫帰属制度の概要、手続き方法について詳しく解説します。
また、国庫帰属制度の説明とあわせて、土地をビジネスに活用するための方法についても紹介します。
「国庫帰属制度の内容がよくわからない」
「土地を所有しているが国庫帰属制度の条件に該当しないので、何か有効な活用方法が知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。
国庫帰属制度とは
国庫帰属制度とは、正式名『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』といい、その名の通り相続した土地の所有権を国に渡すことを指します。
法律上、遺産を相続する際には、すべて放棄するか・すべて相続するかの二択しかなく、例えば預貯金だけを相続し、土地は相続しないという方法を取ることはできません。
土地を所有するというのは、かなりコストがかかります。税金の対象となり、手入れ等も必要なため資金面でも工数面で負担を背負うことになります。
国にとっても、土地が相続された時に必要な手続きが行われず、所有者不明の土地が生まれてしまうことでデメリットを被ります。また、国や自治体が土地を活用したいと考える場合、所有者を調べる必要があります。その情報が管理できていないというのは、計画に大きな支障を及ぼすことになります。
国庫帰属制度が普及することで、個人は土地を所有する際に発生する様々なコストを削減することができ、国も土地を有効活用する際に所有者確認の過程をせず活用をすすめられるようになります。
不動産業界へのインパクト
国庫帰属制度が不動産業界に与えるインパクトはどういったものが予想されるでしょうか。
結論、現時点ではそこまでの影響はないと考えます。
理由としては以下の2点です。
- 承認の際の条件が厳しいこと
- 申請に費用がかかること
名城大学の村上広一氏は論文によると、土地の所有権の放棄を希望する世帯の中で、条件を満たすのは4.51%程度だと推計しています。(参照:名城大学「相続土地国庫帰属法の問題点と見直しの方向性」)
制度の内容が見直され、個人にとってより活用し易い内容になると、不動産業界にとっては顧客の獲得競争にさらされる可能性はあります。ただ、現時点では条件のハードルや一定の費用がかかることから、大きな脅威にはなり得ないのではないかと予想されます。
国庫帰属制度のメリット
国庫帰属制度には以下3点のメリットがあります。
- 引き取り手を探す手間の削減
- 国が管理するという安心感
- 管理コストからの解放
順に詳しく解説します。
引き取り手を探す手間の削減
土地は捨てることができません。つまり『売る』か『渡す』しかないのです。
土地は所有しているだけで資金面・工数面でコストが発生してしまうので、引き取り手を探すのはそう簡単ではありません。
しかし国庫帰属制度では、長い期間引き取り手が見つからなかった土地であっても、国庫帰属制度に定められた条件さえクリアできれば無条件で国に渡すことができます。
国が管理するという安心感
引き取り手が国であることは元々の土地所有者にとっては安心材料になります。
例えば、相続した親の土地を手放すために、なんとか引き取り手を探して譲ったとします。その引き取り手が適切な管理を行わなかった場合、周辺住民の迷惑になるケースが予想されます。
一方で、国に土地を渡すのであれば、その後の管理も国が行うため安心して任せることができます。
管理コストからの解放
土地の所有権を手放すことで、資金面・工数面のコストから解放されます。
土地を所有している際に発生する主な資金面のコストは以下の通りです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 水道代、電気代など
またこれらに加えて手入れを行う必要があり、それを業者に委託する際には別途その費用もかかります。
しかし、国庫帰属制度を用いて土地の所有権を国に渡すことで、これらの管理コストから解放されます。
有効活用できず、ただ資金面・工数面でコストが負担となっていた土地を手放すことができるのは大きなメリットになります。
国庫帰属制度の条件
国庫帰属制度によって国がすべての土地を引き取ってくれるわけではありません。申請し承認を得るには条件をクリアする必要があります。
条件をクリアした後の流れとしては以下の通りです。
- 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
- 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
- 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
- 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(引用:法務省_相続土地国庫帰属制度の概要)
申請できる人の条件
申請できる人の条件は以下の通りです。
- 相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人
- 相続により土地の共有持分を取得した共有者全員が申請を行う場合
また、本制度は令和5年4月27日からスタートしていますが、それ以前に相続した土地も対象となります。
引き取り手が見つからず、やむなく土地を所有している場合は国庫帰属制度の活用を検討しましょう。
国庫への帰属が認められる土地の条件
国庫帰属制度に該当するのは、以下に当てはまらない土地です。
- 建物がある
- 担保権などの様々な権利が設定されている
- 通路・道路が含まれている
- 汚染されている
- 一定の勾配・高さがある
- 有体物がある
- 管理・処分にあたり隣接する土地の所有者との訴訟が必要な場合
- 管理・処分に過分の費用や労力を有する
いずれかにあてはまるものがあると、国庫帰属制度の条件には満たないため、国の承認はおりません。
例えば実家の一軒家が建ってる土地を相続した場合、『建物がある』という条件に該当してしまうため、更地にする必要があり、取り壊しには当然費用がかかってしまいます。
もし『取り壊す費用』を用意できない場合は、国庫帰属制度を利用することができません。
手放したいが国庫帰属が認められない場合は、他に土地を手放す方法を考える、もしくは活用する方法を検討する必要があります。
国庫帰属の申請先や手続き方法
申請先は土地がある都道府県の法務局・地方法務局になります。支局や出張所では申請の受付を行っていないので要注意です。
また手続きについては、以下の流れに沿って行われます。
| 対応事項 | 詳細 | 備考 |
| 承認申請・手数料の支払い | 承認申請書を『法務局の窓口に提出』もしくは『法務局に郵送で提出』土地一筆あたり14,000円を申請時に収入印紙にて納付 | 【必要書類】承認申請書土地の位置・範囲を示す図面申請する土地と隣接する土地の境界を示す画像・写真土地の形状を明確にする画像・写真印鑑証明書 |
| 書面調査 | 法務局担当官による提出書類の確認・調査 | |
| 実地調査 | 法務局担当官による実地調査 | |
| 承認 | 法務大臣・管轄法務局長によって承認 | |
| 負担金の納付 | 負担金を納付10年分の費用額を考慮した算定式により示される金額が対象 | 負担金額の通知を受け取った日から30日以内に納付30日を過ぎると承認が無効になる |
| 国庫帰属 | 申請した土地の国庫帰属が決定 |
(参照:法務省_相続土地国庫帰属制度の概要)
国庫帰属の費用や負担金
申請時に土地一筆あたり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。
また、申請が承認された後に負担金を納付しなければなりません。この負担金とは、土地の種類に応じて10年分に相当する標準的な管理費用をベースに算出されます。
| 種類 | イメージ | 内容 |
| 宅地 | 面積に関わらず20万円*市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については面積に応じて計算例:500㎡の宅地の場合、1,454,000円 | |
| 田、畑 | 面積に関わらず20万円*市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業等の施行区域内の農地については面積に応じて計算例:3,000㎡の田、畑の場合、2,518,000円 | |
| 森林 | 面接に応じ算定例:8,000㎡の場合、351,000円 | |
| その他原野など | 面積に関わらず20万円 |
負担金は国に引き渡す土地の種類や広さによって異なります。上記を参考にどのくらいの費用になるのか事前に試算しておきましょう。
ビジネスへの活用方法
所有している土地が国庫帰属制度の条件を満たさなかった場合でも、活用方法によっては収益を生むビジネスになる可能性もあります。
代表的な3つの活用方法について解説します。
土地の貸し出し
ビジネス活用方法の1つ目は、所有している土地を貸し出して収益を得る土地の貸し出しです。
例えば、マンションやアパートを建てたいと考えている人に対し土地を貸し出すことで『地代』を得ることができます。この場合、土地の所有者と建物の所有者はそれぞれ別となり、老朽化対策のための修繕費などは建物の所有者が負担するため、土地の所有者は維持費を気にする必要はありません。
一方で、借地借家法により借地人の土地を借りる権利が強く守られているため、一度土地を貸し出しすると契約を解除することは難しくなります。もし建物の所有者が近隣とトラブルを起こした際、土地を貸している側にも一定の責任があるため問題に巻き込まれてしまう可能性があります。
貸し出す相手をしっかり見極めることが重要です。
建物の貸し出し
ビジネス活用方法の2つ目は、所有している土地に建物を建てて他人に貸し出すことで収益を得る建物の貸し出しです。マンションやアパートを自身の名義で建て、入居者からの家賃を収益とするビジネスモデルになります。
実際に建物を建てる費用がかかるため初期投資にまとまったお金が必要で、建物を維持するための費用も発生するのが注意点です。
ただ、家賃収入は地代や駐車場のような他のビジネスと比較すると高額なため、入居者が見込めるようであれば高い収益を上げられる可能性があります。
暫定的な利用
ビジネス活用方法の3つ目は、建物を所有しない、建物を建設しない、もしくは期間限定の用途で他人に土地を貸し出す暫定利用です。具体例としては駐車場や物置場所などが挙げられます。これらは借地借家法の適用外となるため、借地人の権利が強く守られるようなことはありません。
つまり、契約の解除を簡単に行うことが可能です。
ただ地代よりも低い収益となることがほとんどですので、土地活用方法がまだ定まっていない際の暫定利用としての活用がおすすめの手段になります。
まとめ
この記事では国庫帰属制度と土地のビジネス活用について紹介しました。
条件の良い土地であればビジネス活用によって収益となるため引き取り手を探す難易度は易化します。そのような中で国庫帰属制度は、条件が良くないために引き取り手を探すのが困難な土地に対しての活用が考えられます。
また、2024年には相続土地の申請義務化が施行されるため、今後土地を相続する世代はその活用が推進されると予想されます。
国庫帰属制度を含む制度の見直しにより、土地を国に引き渡すのか、所有しビジネスとして有効活用するのか、不動産界隈はまさに変革の過渡期にあるのです。
土地を所有している場合は様々な制度や今後の不動産動向をチェックしてみましょう。