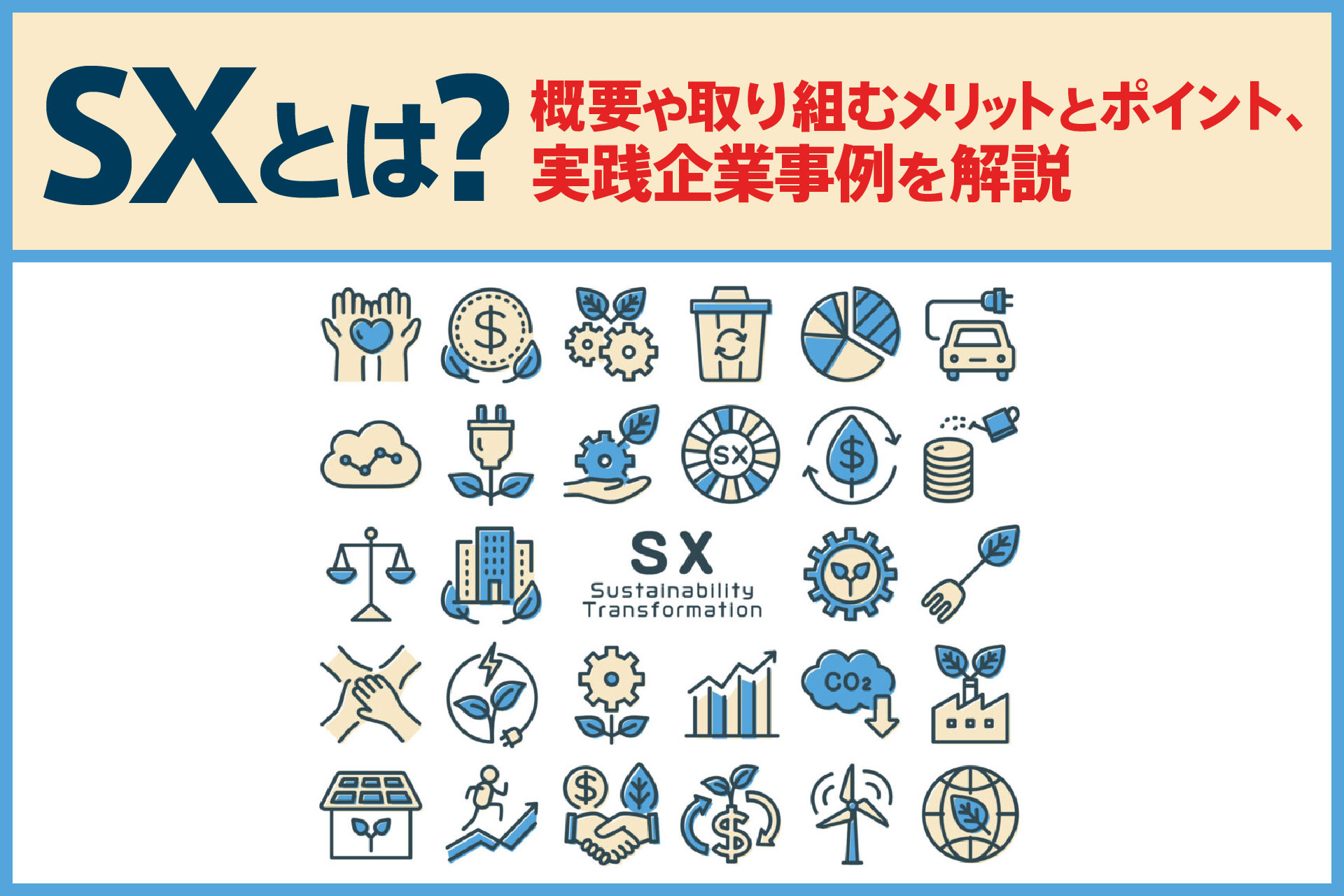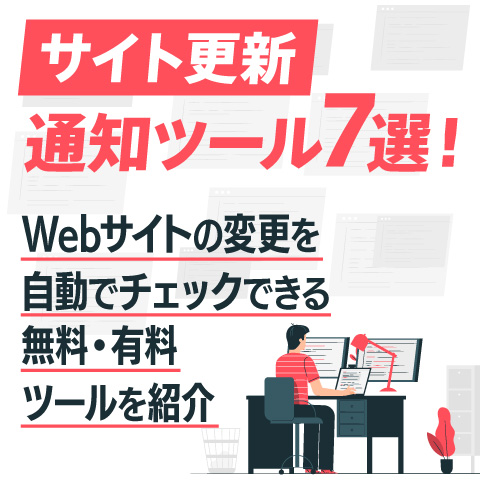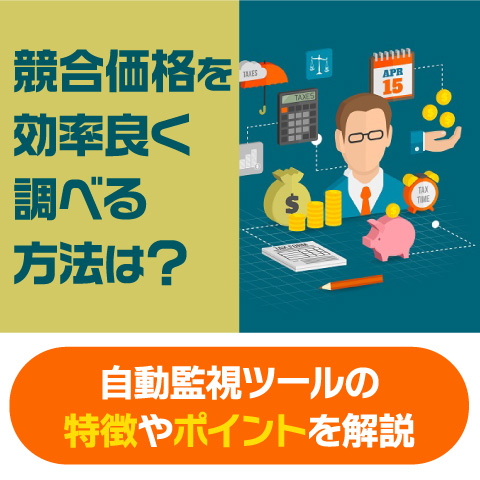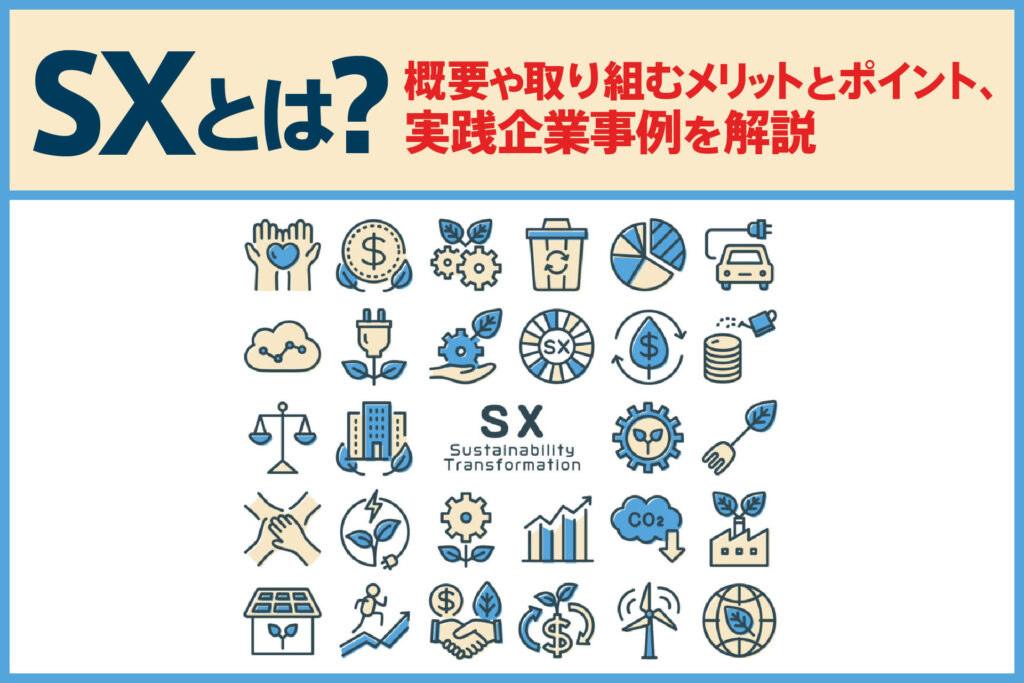
近年注目を集めているキーワードとしてSXが挙げられます。取り組む企業が増え、SX銘柄2024が発表されたため、耳にしたことがある人もいるでしょう。SXとは、社会の持続可能性実現へ取り組むとともに、企業の稼ぐ力を高めることで、GXやSDGsとも密接に関係しています。
今回は、SXの概要や注目を浴びている背景、取り組むメリットについて解説します。また、SXに取り組むステップや具体的な企業の事例も紹介します。
目次
SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは

SXとは、社会の持続可能性をサポートする取り組みと、企業が継続的に成長する活動を併せた経営や活動のことです。正式名称は、Sustainability Transformation(サステナビリティ・トランスフォーメーション)です。SXは、2020年に経済産業省が設置した「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」で提唱されました。
サステナビリティにおける2つの観点
SX実現には、企業と社会の持続可能性(サステナビリティ)を同化させる必要があります。サステナビリティとは、将来にわたり現在の社会機能を継続するためのシステムや考え方のことです。
企業の持続可能性(サステナビリティ)
企業のサステナビリティとは、企業の稼ぐ力における持続性のことです。企業の継続的な活動や成長・発展には、人材の雇用や設備への投資などが必要で、それらにはコストがかかります。
稼ぐ力が弱ければ、企業成長へ向けた投資の原資を確保できず、ライバル企業の成長により自社の競争力が低下する可能性もあります。企業は以下の取り組みにより、競争優位性や稼ぐ力の維持・向上が重要です。
- 中・長期の視点で、企業価値を向上させる取り組みを行う
- 将来性を踏まえ、取り組む事業を見直す
- 自社の強みを明確にし、技術革新や新たな価値の創造に取り組む
社会の持続可能性(サステナビリティ)
社会のサステナビリティとは、将来的な社会の姿を構築し、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)などで社会を持続させることです。企業には、社会のサステナビリティ実現における貢献が求められています。
また、近年は以下の想定外な出来事が起こり、不確実性の高い社会になっています。
- 新型コロナウイルス感染症の流行(パンデミック)
- ロシアとウクライナの戦争
- 第4次産業革命やDXの進展による、産業構造の変化
- 気候変動
- 災害
企業の成長には、不確実性が高い現代でも将来的な社会の姿を具体的に描き、そこから逆算して、成長に必要な戦略や方向性を決めることが大切です。
SX・DX・GXの違い
SXと混同されがちな言葉として、DX・GXが挙げられます。それぞれ概要は以下の通りで、SXとは意味が異なります。
- DX:デジタルトランスフォーメーションの略で、AIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや業務プロセス、企業文化を変革することです。
- GX:グリーントランスフォーメーションの略で、温室効果ガスの排出削減に取り組むとともに、経済や社会を変革することです。
SXは社会と企業のサステナビリティ実現を意味するのに対し、DXはデジタル技術を活用した企業の革新を意味します。GXは環境問題の中でも温室効果ガスの削減に重点を置いており、さらに広範囲を対象としたSXとは異なります。
ただし、SXとDX、SXとGXが無関係なわけではありません。SXの実現には、デジタル技術を活用するDXにより企業を変革し、稼ぐ力の向上が求められます。また、SXには環境問題も含まれており、SXの実現にはGXが欠かせません。
SXが注目を浴びている背景

SXへの注目は年々高まっています。富士通株式会社が2023年11月から12月にかけて、15ヵ国・11業種の経営者層600名を対象に行ったアンケート調査の結果は以下の通りです。
- 「サステナビリティはビジネスの最優先事項である」と回答した経営者層の割合:70%(前回調査より13ポイントアップ)
- 「12ヵ月前よりもサステナビリティ経営の重要度は増していると感じる」と回答した経営者層の割合:53%
- サステナビリティへの取り組みが「進んでいる」と回答し経営者層の割合:61%
また、経済産業省はSXに取り組み、企業価値の向上を実現している先進的企業を選定した「SX銘柄2024」を発表しました。企業経営者はもちろん、多くの投資家もSXに注目しています。
SDGs(持続可能な開発目標)の観点
SXはSDGsの実現に関連するため、SDGsの観点から注目されています。
SDGs(エスディージーズ)とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標のことです。「Sustainable Development Goals(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ)」の略称で、17のゴール・169のターゲットから構成されています。ゴールとして設定されている項目として、例えば以下が挙げられます。
- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
- 働きがいも経済成長も
- 産業と技術革新の基盤を作ろう
- 住み続けられるまちづくりを
- つくる責任、つかう責任
- 気候変動に具体的な対策を
社会のサステナビリティが含まれるSXの実現は、SDGsのゴール・ターゲットの達成につながります。
ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点
2006年に国連が発表した投資判断の基準である「ESG(環境・社会・ガバナンス)」からもSXが注目されています。国連は、発表した国連責任投資原則の中で、以下の頭文字を組み合わせたESGを新たな投資基準として紹介しました。
- E:環境(Environment)
- S:社会(Social)
- G:ガバナンス(Governance)
国連の発表により、企業の長期的な成長には、持続可能で豊かな社会の実現を目指す「ESG」の観点が必要だとする考えが広がりました。SXには社会のサステナビリティが含まれており、ESGの考え方と合致します。
人財資本経営の観点
政府や経済団体は、人財資本経営の観点からもSXを推進しています。
人財資本経営とは企業や組織で働く人を、お金・設備などと同様に資本の一つとして捉え、人材の価値を最大限に引き出し、中長期的な企業価値を高めることです。従業員の教育や働き方改革は、能力・生産性の向上につながり、企業の競争力を高めます。企業の持続的な発展には、人材の成長も重要な要因です。
SXの推進に必要なダイナミック・ケイパビリティ
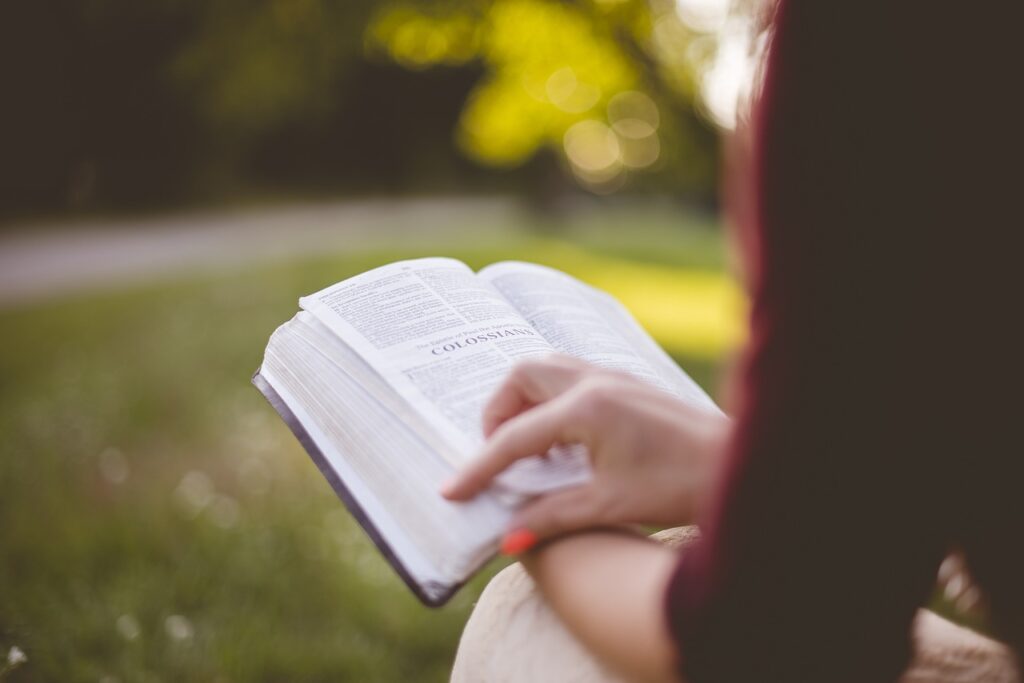
SXの推進には、企業変革や対応力を表すダイナミック・ケイパビリティが欠かせません。不確実性が高く、将来予測がしづらい現代で企業が成長するには、外部環境の変化に対応しつつ、企業価値の向上に向け変革の継続が重要です。
ここからは、ダイナミック・ケイパビリティの概要と強化する方法について解説します。
ダイナミック・ケイパビリティとは
ダイナミック・ケイパビリティとは、環境変化への対応を目的に企業が自己改革を行う能力のことで、以下3つの要素で構成されています。
- 感知力:脅威や危機を感知・推測する能力
- 捕捉力:機会を捉えて、保有する資産や知識・技術を再構成し、競争力を獲得する能力
- 変容力:創造した競争力を持続的なものにするために、組織全体を刷新し、変容する能力
ダイナミック・ケイパビリティを強化する方法
感知力・捕捉力・変容力で構成されるダイナミック・ケイパビリティの強化には、積極的なDXの推進が重要です。DXの推進が外部環境の感知能力を高めるとともに、限りある資源の活用や組織の変革につながるからです。
デジタルツールを活用すれば、迅速かつ正確なデータ収集と分析が可能となり、感知力・捕捉力が大幅に向上します。また、業務プロセスや組織風土の変革に役立つDXにより、変容力も向上しダイナミック・ケイパビリティの強化が可能です。
例えば、サステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」を活用すれば、サステナビリティに関する最新情報を自動でチェックします。リストから必要な情報を選択したり、国内や海外サイトのURLも登録でき、自社に必要な情報をカスタマイズできます。
サステナモニターの活用によって、サイト更新部分の抜け漏れ防止や必要なサイトだけを見ることにより、情報収取業務の効率化につながります。また、感知力や捕捉力を高められることで、ダイナミックケイパビリティの強化を実現します。
SXに取り組むメリット

SXに取り組めば、以下3つのメリットを得られます。
- 企業イメージが向上する
- ESG投資家・株主からの評価が上がる
- 中・長期的な稼ぐ力が強化される
ここからは、上記それぞれのメリットについて解説します。
企業イメージが向上する
SXに取り組むことで、社会課題や環境問題の解決に取り組む企業として、イメージが向上します。
急速に進む地球温暖化により異常気象が発生し、環境問題に対する意識が高まっています。また、ビジネスを通して社会課題の解決に取り組むソーシャルベンチャーも増加し、社会起業家(ソーシャルアントレプレナー)を志す人も少なくありません。
企業がサステナブルな取り組みをしているか否かを、購入・利用するサービスや商品を選ぶ際の判断材料にしている消費者も増えています。とくに、1980年代前半から1990年代半ばごろに生まれたミレニアル世代は、サステナブルな取り組みを重視する傾向が強いといわれています。
SXに取り組むことで、企業イメージ向上と新たなビジネスチャンス獲得が期待できるでしょう。
ESG投資家・株主からの評価が上がる
SXが注目を浴びている背景で解説した通り、国連から新たな投資の判断基準として、ESGが紹介されました。SXの推進はESGを満たすことになるため、ESG投資家・株主からの評価が上がります。
また、近年は投資判断をする際に、財務情報だけでなく人的資本のデータを確認する投資家が増えています。「企業は人でできている」といわれることもあるように、企業の競争力を左右するのは働く人の質です。
欧州では上場企業に対して、人的資本の情報開示が義務づけられています。日本でも2023年3月期から、大手企業4,000社に有価証券報告書への人材投資額や社員満足度など、人的資本情報の記載を求めています。SXの実現に必要な人財資本経営も投資家・株主からの評価を向上させる要因です。
中・長期的な稼ぐ力が強化される
企業の持続可能性が含まれるSXの取り組みは、企業の中長期的な稼ぐ力の強化につながります。不確実性が高い昨今であっても、稼ぐ力を強化すれば増資などによりリスクに備えられます。継続的な成長投資も可能となるため、競合他社への優位性も高まるでしょう。
SXに向けた取り組みのステップ

SXに向けた取り組みを行う際のステップは以下の通りです。
1. サステナビリティを踏まえた目指す姿の明確化
まず、サステナビリティを踏まえた自社の目指す姿を明確にします。SXと関係があるSDGsでは、17のゴール・169のターゲットが設定されているように、社会のサステナブル実現における課題は複数あり、全ての問題に取り組むことは困難です。
自社は何を重点に取り組むか範囲を絞るためにも、目指す姿を明確にする必要があります。明確化された目指す姿は、社会の課題に対して企業と社員一人ひとりが取るべき行動の判断軸・判断の拠り所となります。
2. 長期価値の創造を実現するための戦略構築
続いて、目指す姿と現在のギャップを埋め、長期的な価値創造を実現するための長期戦略を描きます。現在の自社における事業状況やポジショニングの分析、競争優位と強みを把握します。また、長期的なリスク・機会となり得る外的・内的要因も分析し、それをもとに長期ビジョンを構築しましょう。
必要であれば、長期ビジョンにもとづき既存のビジネスモデル変革も検討します。事業ポートフォリオ戦略や革新を行うための組織戦略、人材戦略など、長期ビジョンを実現するための、短中期の取り組み決定も大切です。
3. 推進に向けたKPI・ガバナンスの設定とブラッシュアップ
戦略を決定したら成果やKPIに落とし込み、実行するとともに定期的に進捗をチェックし改善を続けるPDCAサイクルを続けることが重要です。KPIとは、Key Performance Indicator(キーパフォーマンスインジケーター)の略で、定点観測を目的にゴールを達成するためのプロセスを定量的に定めた指標です。
成果やKPIなどの指標がなければ、戦略を実行できているかや、ゴールに向かっているかなどの判断ができません。また、長期戦略などの策定や実行、検証を通じ長期的・持続的に企業価値を高める仕組み・機能であるガバナンスを設定し、そのブラッシュアップも効果的です。
SXに取り組む際のポイント
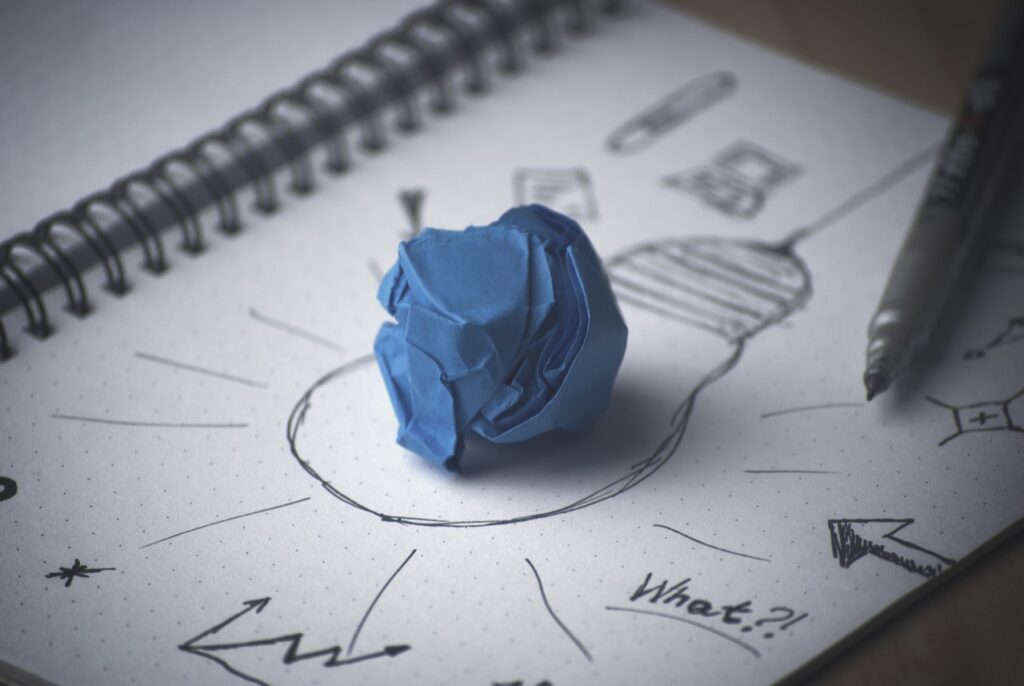
DXを推進して稼ぐ力の持続化・強化を図る
SXへの取り組みにおいて重要なのは、稼ぐ力の持続化と強化であり、そのためにDXへの取り組みも欠かせません。DXとSXは相乗効果を生み出すため、両方取り組むことが企業存続への鍵となります。
日本は総人口・労働人口が減少しており、人手不足が課題となっています。それを補うためデジタルツールを活用することで、人が行う業務の自動化や負担の軽減につながり、業務効率化・事業の変革といったDXの実現が可能です。一人ひとりの生産性向上やコストの削減にもつながり、企業全体における稼ぐ力の向上が期待できるでしょう。
また、近年はユーザーの消費動向やニーズが多様化・複雑化し、変化のスピードも早い傾向にあります。デジタルツールの活用等によってDXを推進することで、消費者のニーズを的確に捉えられる他、サービス改善や創造にも活用可能です。その結果、稼ぐ力の持続性と強化につながりSXの実現が期待できます。
社会のサステナビリティを経営に取り込む
SXへの取り組みには、企業のみならず、社会のサステナビリティを経営に取り組む必要があります。フードロスの削減に取り組む企業や、人・環境に配慮した洋服だけを集めた専門店など、社会のサステナビリティを解決するビジネス展開を行う企業も多く存在します。
また、地球温暖化に対する注目が高まっているため、脱炭素経営に取り組む企業も少なくありません。脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営を行い、エネルギーや炭素の排出を可能な限りゼロにする取り組みのことです。
SXを実践している企業事例

SXを通じて持続的に成長原資を稼ぎ、企業価値を向上している企業も多く存在します。ここからは、いくつかの企業事例について詳しく解説します。
トヨタ
サステナビリティ基本方針や個別方針を定めているトヨタは「社会・地球の持続可能な発展への貢献」に取り組んでいます。具体的には「2035年までに工場でのカーボンニュートラル」「2050年までに工場CO₂排出量ゼロ」に挑戦しており、低CO₂生産技術の開発・導入を行いました。また、稼働しないときのロスを最小化する改善や、再生可能エネルギーの導入など、さまざまな取り組みを推進しています。
JAL
JALでは、以下4つの重点領域を定め、さまざまな活動を行っています。
- 環境:豊かな地球を次世代に引き継ぐために
- 人:誰もが安全・安心でいきいきと輝ける社会の構築
- 地域社会:社会インフラとして地域社会の発展に貢献
- ガバナンス:透明性の高い経営の実践
JALグループは、中期経営計画でESG戦略を最上位に位置づけ、ESGやCO₂に対する取り組みが役員報酬に影響を与えるガバナンス体制を構築しています。また、省燃費な飛行機などへ投資を行い、環境に優しい飛行機の利用を推進しています。
味の素
味の素では「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」を目的として、2030年までに10億人の健康寿命を延ばし、環境負荷の50%削減を目標にしています。2001年から脱フロン化の取り組みを開始し、2021年3月には冷凍食品業界で初めて、国内自社工場の全てを脱フロン化しました。また、2021年4月から取締役会の下部機構として「サステナビリティ諮問会議」を、経営会議の下部機構として「サステナビリティ委員会」を設置し、SXを推進しています。
まとめ

社会の持続可能性をサポートする取り組みと、企業が継続的に成長する活動を併せた経営や活動であるSXに取り組めば、以下のメリットを得られます。
- 企業イメージが向上する
- ESG投資家・株主からの評価が上がる
- 中・長期的な稼ぐ力が強化される
SXの推進には、感知力・捕捉力・変容力で構成され、企業変革や対応力を表すダイナミック・ケイパビリティが欠かせません。ダイナミック・ケイパビリティの強化にはDXの推進が重要であり、DX促進がSXにもつながります。デジタルツールを活用すれば、迅速かつ正確なデータ収集と分析が可能となり、ダイナミック・ケイパビリティの感知力・捕捉力が大幅に向上します。
弊社が提供するサステナモニターなら、サステナビリティに関する情報をリストから選択するだけで、変更点があれば関係者にその変更点を通知できます。例えば、自社が取り組むべき環境に関する情報や、事業の脅威とリスクに影響を与える情報を関係者に通知可能です。また、日本のみならず海外のサイトからも情報収集が可能であるため、自社に必要な情報の収集をカスタマイズでき、抜け漏れなく情報の収集ができます。