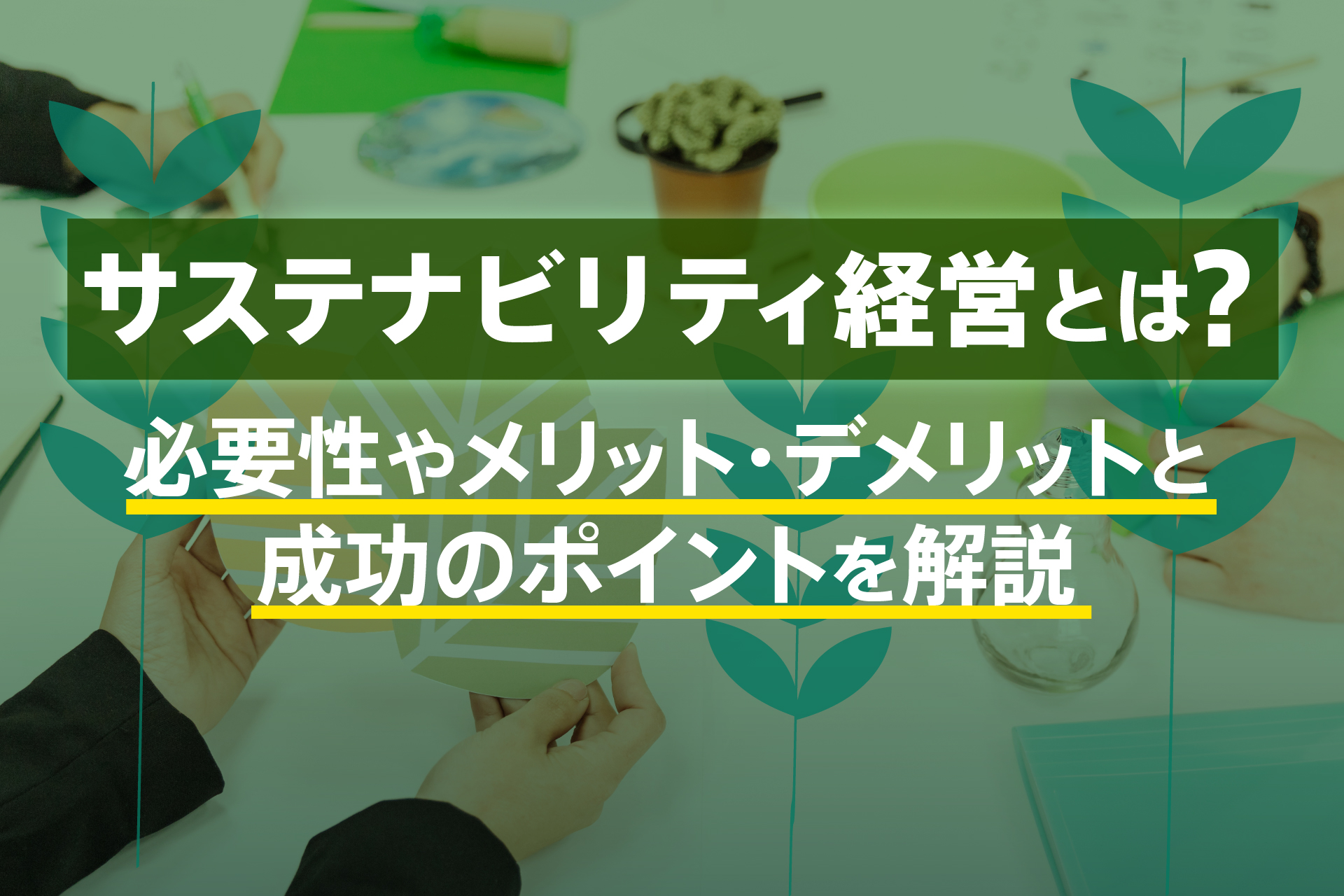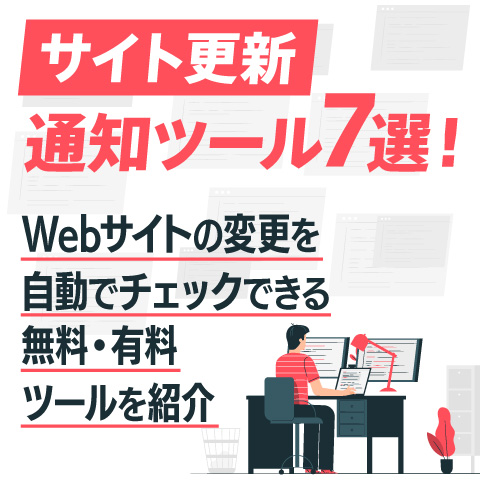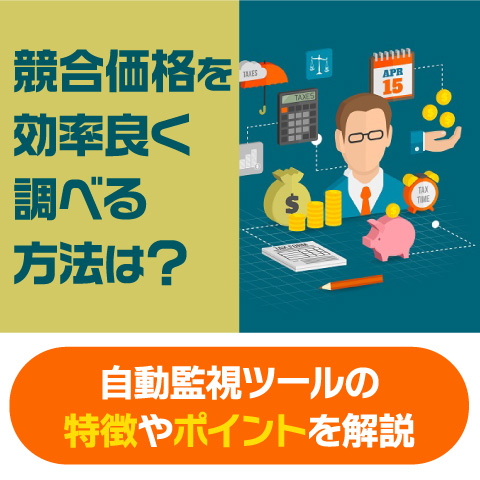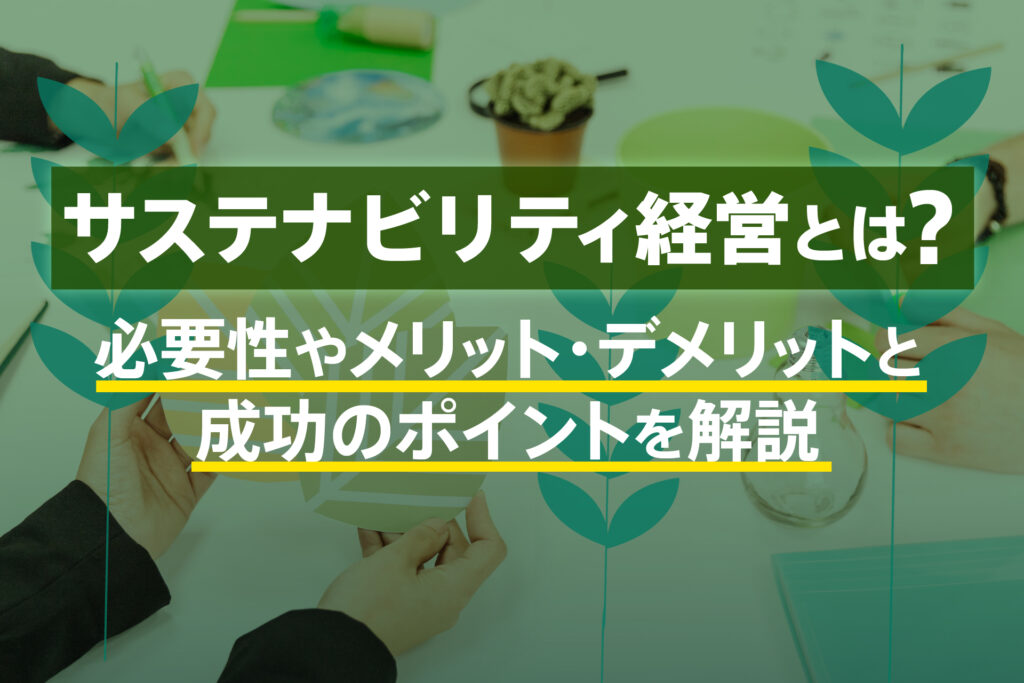
近年、企業経営において「サステナビリティ」というキーワードが注目されています。環境問題の深刻化や社会的課題への対応が求められる中、多くの企業が持続可能な成長を目指した経営手法として「サステナビリティ経営」を導入し始めています。
本記事では、サステナビリティ経営の基本的な概念、ESGやCSRとの違い、実施するメリットや課題をわかりやすく解説します。これから取り組みを検討している方や、より深く理解を深めたい経営上層部、企業のCSR担当者やESG担当者に向けた実践的な情報をお届けします。
目次
サステナビリティ経営とは
サステナビリティ経営とは、環境・社会・経済と3つの観点をそれぞれ考慮し、持続可能な成長を目指す経営の手法です。企業活動が自然環境や社会全体に与える影響を踏まえ、短期的に利益を求めるだけでなく、長期的に企業価値を生み出すことを目指しています。
例えば、サステナブル経営には環境負荷の低減、社会的責任の遂行、ガバナンスの確立などが挙げられます。これらに取り組むなど、企業が環境保護や社会貢献を続けることによって、ステークホルダーとの関係強化、持続可能な社会の実現を目指すのです。
サステナビリティ経営の概要と必要とされる背景
サステナビリティ経営が注目される背景には、環境問題や社会の不平等、経済の不安定さなどに起因する懸念が挙げられます。地球温暖化など、課題が次々と増えている状況で、企業には環境負荷を軽減しつつ新しい価値を生み出すことが求められているのです。また、消費者や投資家が環境へ配慮する意識を持つようになり、企業に対してこれを求めていることも背景にあります。
サステナビリティ経営と他の経営戦略との違い
サステナビリティ経営は、企業が環境・社会・経済をバランスよく考慮し、持続可能な成長を目指す経営戦略です。例えば、以下のような取り組みが考えられます。
- 再生可能エネルギーの導入
- サプライチェーン全体での環境負荷削減
- 地域社会との協力による事業展開
サステナビリティ経営とESG経営との違い
ESG経営は「環境(E)」「社会(S)」「ガバナンス(G)」の観点から、投資家や関係者が企業の価値を評価するものです。経営戦略ではなく、非財務的要因として、売上や利益以外の観点を重視した考え方といえます。
サステナビリティ経営は社会的な影響を鑑みたものであり、ESG経営は投資家向けにリスク管理や透明性を示すという、目的が異なる活動なのです。ただ、両者は補完しあう関係性であり、併用することでより信頼性の高い経営に繋げられます。
サステナビリティ経営とCSRとの違い
サステナビリティ経営とは違い、CSR(企業の社会的責任)は、法令遵守や社会貢献活動を通じて、企業が社会的責任を果たすことです。サステナビリティ経営は、企業全体で継続的に取り組みますが、CSRは主に本業外の活動や短期的な社会的貢献であるという違いがあります。
サステナビリティ経営を行う必要性
サステナビリティ経営は、持続可能な社会を築くために必要な取り組みであると考えられています。
これまでの経済活動による環境問題の深刻化
これまでの経済活動は、化石燃料の大量消費や森林破壊、大量生産・大量消費などにより、環境へ大きな負担をかけてきました。例えば、二酸化炭素(CO₂)排出量は、1992年から2010年の間に世界で36%増加し、これが地球温暖化の原因の一つとなっています。また、森林面積は1990年以降、世界で約3億ヘクタールほど減少したと推定され、光合成によるCO2の減少を阻害する原因となりました。
このような状況は、地球全体の生態系に悪影響を与え、将来的に人間の生活や地球の存続を難しくしています。この深刻な問題をサステナビリティ経営によって、状況を打破しなければなりません。
サステナビリティ経営による環境負荷の軽減
サステナビリティ経営を実践することで、企業は環境負荷を大幅に軽減できます。具体的には、エネルギー効率の高い設備を導入や再生可能エネルギーを積極的に活用、資源の循環利用の取り組み推進、さらには廃棄物削減といった施策が挙げられます。これらの取り組みにより、企業は持続可能な社会の実現に貢献できます。
さらに、こうした活動は、環境負荷の軽減するだけでなく、顧客や関係者に対し「環境に配慮している企業」としてのポジティブな印象を与えることが可能です。その結果、企業のブランド価値を向上させるとともに、信頼性の向上や新たなビジネス機会の創出を通じて、利益増加にも繋がります。
サステナビリティ経営のメリット
サステナビリティ経営に取り組むメリットを解説します。
顧客や取引先との関係強化
サステナビリティ経営に取り組むことで、顧客や取引先に対して環境や社会に配慮する企業であることをアピールできます。特に、現在は環境や社会に対する意識が社会的な評価を左右する時代です。そのため、積極的な取り組みは顧客からも取引先からも信頼され、関係の強化に繋がります。長期的な関係を築きやすくなるほか、新たな取引を生み出すこともあり得るはずです。
社会的な信用力の獲得
環境に配慮した経営や社会貢献を続けることで、社会的信用力を高められることがメリットです。また、このような取り組みが社外へ公開されることで企業としてのイメージが向上し、さらに社会的な信用力を獲得できることも考えられます。社会的な信用力は、安定的な企業運営を実現するために重要な要素です。競争力の向上にもつながる部分であり、サステナビリティ経営の大きなメリットといえます。
労働環境の改善や従業員の満足度アップ
従業員の健康や安全を確保する取り組みを導入することで、労働環境の改善や従業員の満足度アップが期待できます。例えば、業務負荷を分散させ、従業員の残業時間を短縮できれば、従業員のモチベーションアップを実現できます。さらにその結果、生産性の向上も期待できるでしょう。
また、中長期的に見ると、満足度の高い職場環境は従業員の定着や質の高い人材の確保にも貢献します。これにより、今まで以上に利益が高まるなど、さらなる労働環境の改善にも繋がります。
生産性の向上とコスト削減
サステナビリティ経営を実践する際は、省エネルギーや資源の効率的な活用などを意識する必要があります。結果、生産性を高めつつコスト削減を実現できることがメリットです。
例えば、エネルギー効率の高い設備や新しい業務フローを採用することで、コストの削減と環境負荷の軽減を同時に実現できます。また、廃棄物の削減やリサイクルの推進により、資材コストを節約することにもつながります。
サステナビリティ経営のデメリット
サステナビリティ経営に取り組むデメリットも解説します。
業務内容が変化することによるコスト増加
サステナビリティ経営を導入するためには、業務内容の見直しや新たな設備の導入が必要になる場合があります。これにより初期投資や運用コストが増加することはデメリットとなります。例えば、エネルギー効率の高い機械の導入やサプライチェーン全体の見直しには大きなコストが発生します。また、業務フローの再設計や従業員の教育といった取り組みも追加コストを生むため、短期的には企業に負担がかかるでしょう。
販売機会の損失
サステナビリティ経営を採用することで、短期的には販売機会を損失する可能性もあります。例えば、環境へ配慮した製品に注力するために、従来の主力製品から撤退する場合や、コスト増加に伴う製品やサービスの値上げが顧客離れを招くことがあります。また、サプライチェーンを見直した結果、取引先との関係が悪化するリスクも考えられます。
ただし、これらのデメリットは中長期的に克服可能であり、サステナビリティ経営がもたらすメリット(ブランド価値向上や新たな顧客層の獲得など)を享受できる可能性があります。
サステナビリティ経営を成功させる方法
サステナビリティ経営を成功させる方法について解説します。
現状の洗い出しと課題の特定
最初に現状を把握し、課題を特定することが重要です。現状を無視して方針を立てても、効果的な成果を得ることは難しいでしょう。課題を明確化し、その解決に向けた具体的な方針を策定する必要があります。
現状分析では、可能な限り客観的な根拠に基づくアプローチを意識しましょう。例えば、社内データを活用して、温室効果ガスの排出量が多い業務を特定します。経営者や現場の直感に頼らず、十分なエビデンスに基づく判断が求められます。
社内体制の確立とリスク管理
サステナビリティ経営は短時間で完了するものではなく、中長期的に取り組む必要があります。そのため、継続可能な体制を構築しましょう。例えば、経営者をトップに据え、その配下にサステナビリティ専任の担当者を配置した「サステナビリティ推進室」を設置します。規模に応じた専任人材の確保が安定した運営を支える鍵となります。
さらに、リスク管理も継続的に行うことも重要です。例えば、定期的に環境負荷を測定し、法的基準を超えた場合には迅速に対処します。リスクヘッジを意識した体制づくりは、サステナビリティ経営を成功させるための基本です。
目標を設定しての事業運営
サステナビリティ経営を成功させるためには、明確な目標を設定しておきましょう。短期的な目標と長期的なビジョンを組み合わせ、具体的で数値化可能な指標を設定するのが効果的です。例えば、温室効果ガスの排出量削減や再生可能エネルギーへの移行を目標に掲げます。
目標を設定する際には、SDGsやパリ協定など国際的な基準を参考にしましょう。これにより、目標の妥当性が市場から評価されやすくなります。
定期的な評価と情報開示
定期的な評価と透明性の高い情報開示は、関係者から信頼をえるために重要です。進捗状況を把握し、課題があれば明確化して対応を検討します。内部監査や外部の第三者評価を活用することも良いでしょう。
また、サステナビリティレポートやWebサイトを通じて進捗を公開することで、関係者との信頼関係を構築できます。情報開示を積極的に行うことで、企業の取り組みを広く認知させる効果も期待できます。
サステナビリティ経営ツールを活用する
サステナビリティ経営の成功に、ツールを活用することもおすすめです。業務を正確かつ効率的に進められる体制を整えることで、よりスムーズに取り組むことができます。
サステナビリティ経営では、国内外の環境法規や法令に基づいた対応が求められます。しかし、対象となる法規や法令は莫大であり、手作業で最新情報を収集することは現実的ではありません。また、法規や法令は変化し続けるため、継続的な情報収集が必要です。
サステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」であれば、国内外の環境法規や法令などの情報を自動で収集し、最新情報を通知します。これにより対応漏れを防ぎ、安定したサステナビリティ経営を行うことができます。
サステナビリティ経営の企業事例
具体的にサステナビリティ経営を実現している企業とその内容を紹介します。
キリンホールディングス株式会社
キリンホールディングス株式会社は、自社の成長を第一に掲げており、環境問題や社会的責任への対応が十分ではありませんでした。そこで、2012年の経営方針からCSV(Creating Shared Value)」を経営の中心に据え、社会的な課題の解決と企業価値の向上を同時に目指すサステナビリティ経営に転換しています。現在は、メディアなどでも取り上げられるほど環境負荷の低減に力を入れており、ブランド価値や消費者からの信頼を獲得できているのです。公式サイトでは今後の取り組みも示されていて、中長期的な成長に期待できます。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、意外にも自動車業界内での環境対策が遅れ、グローバル市場での競争力低下が懸念されました。そこで「トヨタ環境チャレンジ2050」を策定し、CO₂排出ゼロや水使用の最小化など、環境を意識したサステナビリティ経営を採用しています。
また、製造や企業活動における負荷を減らすだけではなく、ハイブリッド車や電気自動車の開発にも力を入れました。その結果、販売している自動車の内容とサステナビリティ経営の両面から、企業イメージの向上を実現しています。
ヤンマーホールディングス株式会社
ヤンマーホールディングス株式会社は、環境負荷の高い製品やサービスが多く、持続可能な社会への配慮が不足していました。そのため、2050年に向けて「YANMAR GREEN CHALLENGE」を掲げ、環境負荷の低減や再生可能エネルギーの活用を推進する経営方針に切り替えています。負荷を軽減する例として、環境に配慮した製品を増加させるなどしている状況です。今後も技術革新に力を入れ、環境に配慮した製品の導入を続けると発表しています。
株式会社クボタ
株式会社クボタは環境への配慮するための方針が存在せず、投資家などからの信頼を勝ち取りづらい状況でした。これを打破するために「K-ESG経営」を導入し、環境・社会・ガバナンスの視点から経営する方針に転換しています。例えば、環境負荷の低減や社会貢献活動を強化することで、市場からの評価を高めているのです。持続的な取り組みが表明されているため、今後はよりサステナビリティを意識した企業となるでしょう。
株式会社ユニクロ
株式会社ユニクロは、衣服の販売に力を入れているものの、リサイクルやリユースなど環境への配慮が進められていませんでした。そこで「THE POWER OF CLOTHING」と呼ばれるサステナビリティ経営を取り入れ、プラネット(地球環境)」「ソサエティ(地域社会)」「ピープル(個性)」の3本柱で推進しています。加えて、全商品のリサイクル・リユースを目指す「RE.UNIQLO」を推進し、将来的なサステナビリティにも力を入れるようになりました。
まとめ
サステナビリティ経営は短期的なトレンドではなく、将来に向けた中長期的な戦略です。そのため、企業として生き残っていくためにも、可能な限り早くサステナビリティ経営を導入するように心がけましょう。サステナビリティ経営を実現することで、顧客先との関係強化や社会的な信用力の獲得、労働環境の改善や利益アップなど多くの効果が期待できます。
しかし、サステナビリティ経営を実現するためには、関連する法令などを細かくチェックして、その内容に沿うことが求められます。ただ、これらの情報を人手で収集し続けることは現実的ではありません。そこで、サステナモニターを活用して必要な情報を効率的に収集しましょう。