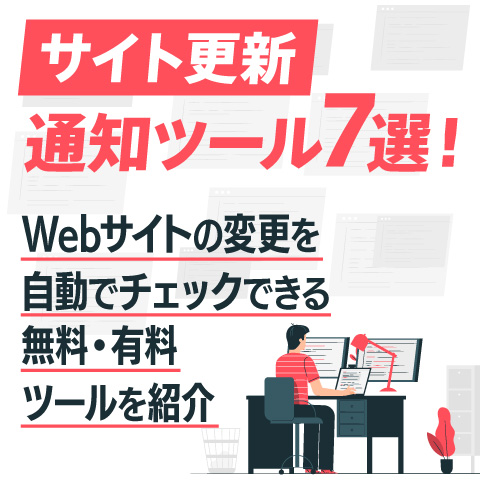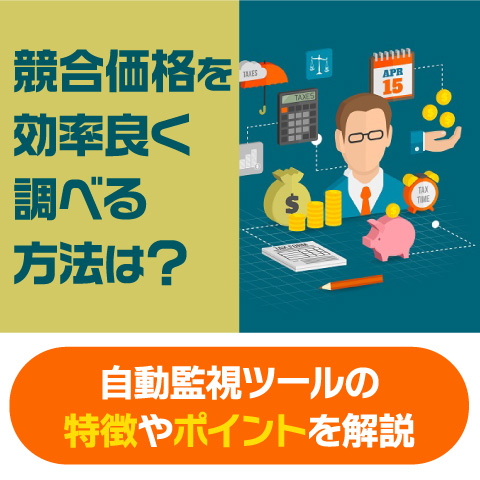近年は、新しくGX人材と呼ばれるキーワードが注目されています。まだまだ浸透していませんが、GXと呼ばれる取り組みが広がりつつあり、これを推進するための人材も求められているのです。皆さんもこれからGXに取り組もうとGX人材について調べているのではないでしょうか。ただGX人材といわれても、そもそもGXがどのようなものであり、そしてどのような人材を集めれば良いのかイメージできないことが多いでしょう。今回はGXの基本的な部分から、具体的に求められる要素や職種などを解説します。
GX人材とは
GX人材とは、GX(グリーントランスフォーメーション)を推進する上で、非常に重要な役割を果たす人物です。明確な定義はありませんが、持続可能な社会や企業の実現に向けて、環境負荷の低減や資源の効率的な活用など、環境と経済の両立を目指すプロジェクトなどをリードします。例えば、再生可能エネルギーやカーボンニュートラルなどの環境技術について知識を有し、これらに関するプロジェクトを推進するのです。
また、GXはデジタル化と密接に結びついているため、デジタル技術を活用することもあるでしょう。他にも環境に関連する法規制や政策はいくつもあるため、これらを理解して目標に従い、企業活動を推進するなどの役割も担います。環境に関することはもちろん、デジタル面も含めて幅広く対応する人物がGX人材なのです。
そもそもGXとは
GX(グリーントランスフォーメーション)とは持続可能な社会の実現を目指し、経済成長と環境保護を両立させるための取り組みです。主に脱炭素化や再生可能エネルギーの推進、資源の循環利用などを進めます。その結果、温室効果ガスの排出を削減したり、環境負荷の軽減を目指したりすることが目的です。
また、GXは日本のみならず、世界中の企業や政府で「環境と経済を同時に発展させる重要な戦略」として注目されています。現状、広く浸透しているとは言い難い状況ですが、将来を見据えた中長期的な発展のために、社会や経済の仕組みを持続可能なものに変革する取り組みと考えましょう。
今GXが注目されている理由
GXが注目されている理由は以下の2点に集約されます。
脱炭素の推進が加速
気候変動対策の一環として、温室効果ガスを削減するための取り組みが世界中で加速しています。多くの国や企業でカーボンニュートラルを意識し、これを実現するための手段であるGXが注目されるようになりました。環境負荷の低減と経済成長の両立を図る戦略であるため、GXを軸として、様々な考え方が展開されているのです。GXの取り組みは多岐に渡り、再生可能エネルギーの利用やエネルギーの効率的な利用などが考えられます。多くの企業が脱炭素化に向けて取り組みやすい活動であることも、注目される理由となっているのです。
世界的に投資の対象
サステナビリティやESG投資がグローバルな投資のトレンドであることも理由として考えられます。これまでは、企業の成長や財務的な側面だけが評価されていましたが、現在はGXへの取り組みや環境への配慮が評価対象の一つとなっています。
投資家が同じような業績で事業を展開している企業同士を比較する場合に、GXに取り組んでいるかどうかが、投資の決め手になるかもしれません。投資家は環境へ配慮した企業を持続可能な企業であると考えており、リスクが低いため、GXが注目されているのです。
企業がGXに取り組むメリット
企業がGXに取り組むことには多くのメリットがあります。そのため、企業はGX人材を確保して、以下で解説するメリットを享受できるようにすべきです。
競争力の強化
企業がGXに取り組むことで、持続可能なビジネスモデルを構築しやすくなり、競争力を強化できることはメリットです。例えば、エネルギー負荷の改善や再生可能エネルギーの導入によって環境負荷が軽減すると、継続的にビジネスを展開しやすくなります。また、GXに取り組んでいることを対外的にアピールできれば消費者や投資家からの評価が高まります。評価が高まることで商品の売り上げが増えたり、取引先が増加したりするなど、事業基盤の安定化も期待できます。これも競争力の強化につながるため、副次的なメリットも期待できるのです。
コストの削減
積極的にGXに取り組むことでコスト削減が期待できます。エネルギーの使用量を削減や、資源効率の向上により、日々の業務に必要なエネルギー関連コストを削減できます。例えば、省エネ技術や再生可能エネルギーを採用した設備を導入することで、オフィスの光熱費を削減につながります。短期的には導入コストが発生しますが、中長期的には光熱費削減などの効果が期待できます。
また、廃棄物の削減や資源の再利用を進めることで、産業廃棄物を処理する費用を削減できます。特に、製造業では廃棄が少ない製造技術を開発することで、原材料コストの削減にも貢献できるでしょう。コスト削減はさまざまな観点から経営効率の向上や継続的な成長に寄与します。
公的予算の確保
企業がGXを推進することで、国の補助金や税制優遇措置など公的支援を受けられる可能性があります。これにより、企業成長に必要な資金調達がしやすくなるというメリットがあります。経済産業省は、2025年度にGX補助金を提供する予定であると発表しています。現在は概算請求中で今後変更される可能性はありますが、公的支援を活用できる見込みです。この支援により、新技術の導入や設備投資に伴う初期負担を軽減できるでしょう。
日本政府はGX推進のため、補助金や税制優遇制度を積極的に提供・計画しています。今後もこのような支援制度は増加すると考えられるため、積極的なGXの取り組みが大切です。
GX人材に求められる要素
GX人材には、どのような要素が求められるのか紹介します。
GXへの興味・情報のキャッチアップ
GXを積極的に推進する必要があるため、最新情報のキャッチアップ能力が必要です。組織内のGXを中心となって牽引していくには、GXへの興味関心があり、積極的な情報収集ができる能力が必要でしょう。例えば、GXの取り組み事例は「GXリーグ」と呼ばれる企業団体が公開しています。この「GXリーグ」は経済産業省が主導していることから、公的な機関からも多くの情報が公開されます。
これらの最新情報を抜け漏れなくキャッチアップし続けて、自社に必要なものを取捨選択する能力が求められます。
関係者とのコミュニケーション力
多くの関係者と関わるポジションであるため、スムーズに意思疎通を図れるコミュニケーション能力が必要です。対面での会話や電話対応、重要な情報をメールやチャットでまとめること、資料を提供できることも求められています。
また、コミュニケーションを取るために、必要な知識を有していることも重要です。例えば、製造業の場合は、原材料の購入や輸送、工場内での製品や製造、そして供給先による製品の使用といった流れが考えられます。GXは全体に関わりうることであるため、GX人材は一連の幅広い業務について知識を持つ必要があるのです。その内容を踏まえて、コミュニケーションを取れることが望ましいと考えましょう。
GXプロジェクトのマネジメント力
GXのマネジメントは、戦略的な環境目標の設定からリソースの最適化を意識したプロジェクト進行を成功させる能力が求められます。上記で触れた複数のステークホルダーとのコミュニケーションはもちろん、環境技術や再生可能エネルギーなどの専門知識、リスク管理やコスト管理などにも対応できなければなりません。
また、環境に与える負荷を定期的に計測し、状況に応じて柔軟に計画を修正できるスキルも必要です。加えて、各種法令や規制を理解しながらプロジェクトを進める必要があり、急な法改正などに対応できる臨機応変なマネジメント力も重視されます。
GX人材の具体的な職種
サステナビリティ推進担当者・コンサルタント
企業の環境目標を設定し、達成することを支援するポジションです。例えば、カーボンニュートラルや再生可能エネルギー導入に向けた戦略を立案することが挙げられます。また、ESGレポートを作成と公開、従業員教育を担当するなど、持続可能な経営の実現に向けてサポートする役割もあります。
また、これらの活動を推進するためには、法規制を理解したりステークホルダーとの関係性を保ったりすることも重要です。純粋にサステナビリティを推進するだけではなく、それに付随する作業全般に対応すると考えましょう。
建物の建設におけるZEH・ZEBの担当者
ZEH(net Zero Energy Building)やZEB(net Zero Energy House)の設計や施工に関わるポジションです。建築士の資格を持つ人と協力し、環境に配慮した建物の設計や建築をサポートします。例えば、省エネ技術や再生可能エネルギーを最大限に活用し、エネルギー消費を可能な限り抑える建物を提案します。
また、提案に関連して建材の選定や施工管理エネルギー効率の最適化など、具体的な作業プロセスを決定する場合があります。また、日本ではZEH・ZEBの建築に関連して補助金などが提供されているため、これらの情報をキャッチアップして適用していくなども担当することもあるでしょう。
プラスチックなど資源の再生事業の営業
リサイクル事業に関連する営業職で、その中でも廃プラスチックやその他資源の再利用を提案するポジションです。営業職は企業との契約交渉をすることが多くありますが、その前段階として、環境に配慮した持続可能なビジネスモデルの提案も担当します。例えば、サプライチェーン全体でリサイクルプロセスを検討し、導入することで企業の環境負荷に繋がるなどです。また、コスト削減に繋がる新技術などを提案するなどの役割も兼ねています。
GX人材が仕事をするうえでのポイント
GX人材が仕事をする上で重要なポイントは3つあります。
戦略的な思考を持つ
GXを推進するためには、短期的な目標だけではなく、長期的な視点を持つことが重要です。そのため、GX人材は企業の中長期的なビジョンと環境目標の両方を理解して、それを踏まえた戦略を策定しなければなりません。
また、戦略を策定する際は、市場の動向や最新技術の活用に関する法規制の変化なども踏まえることが重要です。戦略である以上、時にはリスクを背負うことも必要であり、経営層とのやり取りなども求められます。
ステークホルダーと積極的に連携する
GXを推進する際は、社内のみならずさまざまなステークホルダーと協力しなければなりません。例えば、内部では経営者やエンジニア、各従業員と連携が必要です。また、外部ではサプライヤーや顧客、企業周辺の地域などとのコミュニケーションが求められます。GXの推進は、幅広い視点で利害関係者の理解を得られるように連携を進めなければなりません。そのため、企業の窓口として積極的に行動していかなければなりません。
上記の例であれば、内部のエンジニアと頻繁にコミュニケーションを取り、GX活動について理解してもらったり、進捗を確認したりすることが重要です。また、地域社会に対して情報を積極的に発信し、活動を知ってもらうことも大切です。
法令をチェックする
GXに関連する法規制や規則などはいくつも存在しています。そのため、これらの情報を積極的に収集することが求められます。国や地域ごとに法規制には違いがあるため、そのような違いを含め、幅広く情報を収集することが重要です。情報源は多岐にわたり、これらは不定期に改正される可能性があるため、常に最新の情報をキャッチアップする作業が必要です。頻繁に法令をチェックし、状況を監視することで、自社に影響を及ぼす変更に速やかに対応することがポイントです。
ただし、いつ変化するか分からない法令を常に監視し続けることは大変で、現実的ではないでしょう。弊社が提供するサステナモニターなら、リストからGXに関する情報を選択するだけで最新情報をお知らせします。日本国内のURLはもちろん海外サイトのURLも登録されているため、幅広い情報収集に役立ちます。トレンドや法規制、競合他社の取り組みなどを監視し、自社の活動に反映させましょう。
まとめ
企業として環境関連の取り組むには、GX人材を増やしていくことが重要です。十分な知識を持つ担当者を確保することで、効率的に意味のある取り組みを進められるようになります。可能な限りGX専門の人材を確保することが望ましいでしょう。GX人材を確保しておくことで、市場で競争力を高めたり、業務コストを削減したりできます。
また、積極的にGXの取り組みができれば、補助金や助成金など公的な予算を活用しやすいこともポイントです。GXへの関心が強く情報収集に積極的で、関係者とのコミュニケーションやプロジェクトマネジメントに強い人材を割り当てましょう。
GXに取り組む際は、関連する法令をチェックすることが大切です。最新の法令に則って取り組みを進めなければ、評価されないだけではなく、問題を引き起こすことになりかねません。弊社のサステナモニターであれば、リストに登録されているURLを常に監視し、変更を検知したらすぐに通知されます。最新の規則に則ったGXを推進するために、ぜひご活用ください。