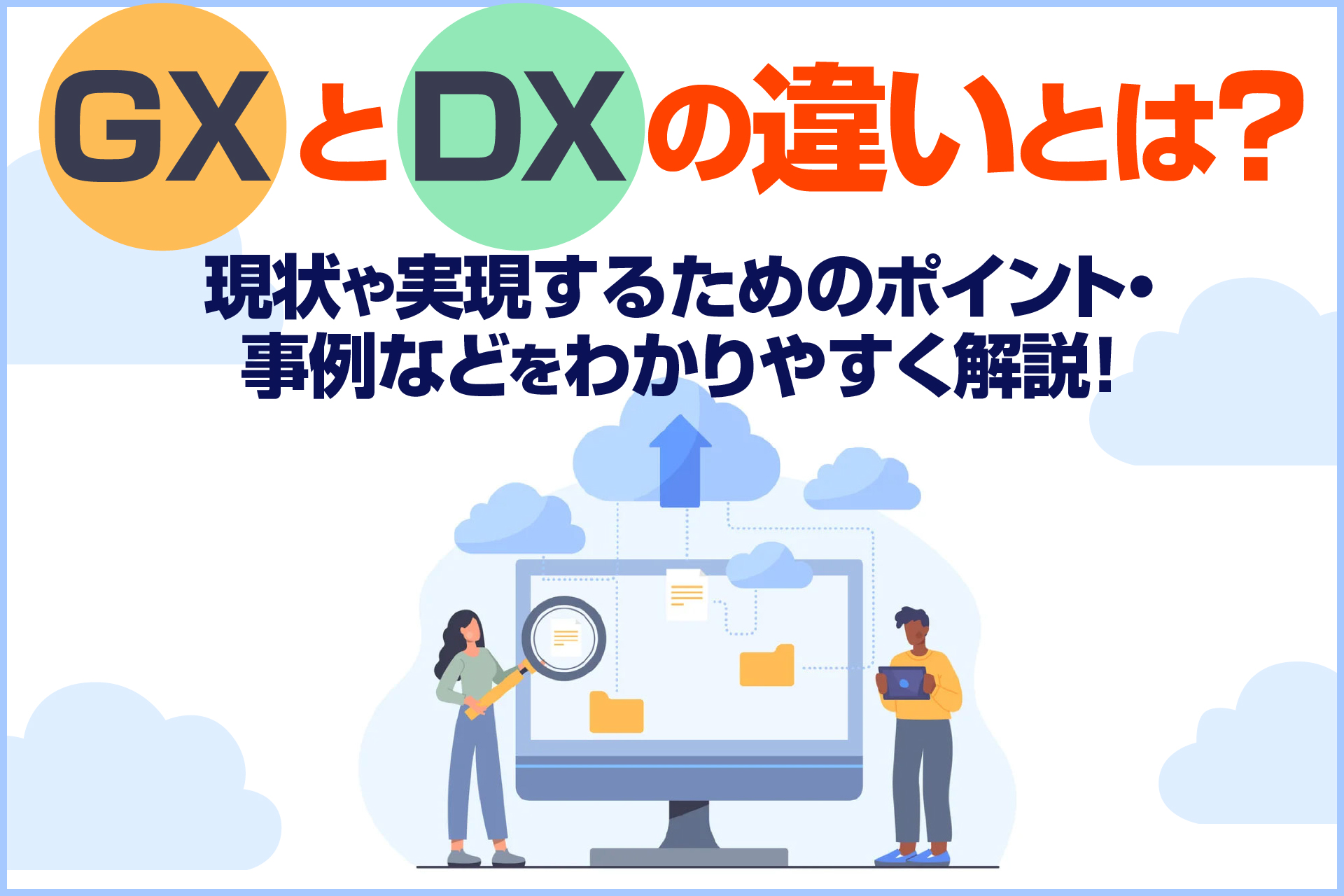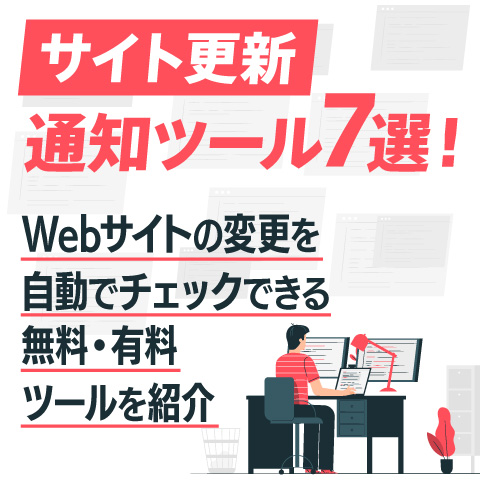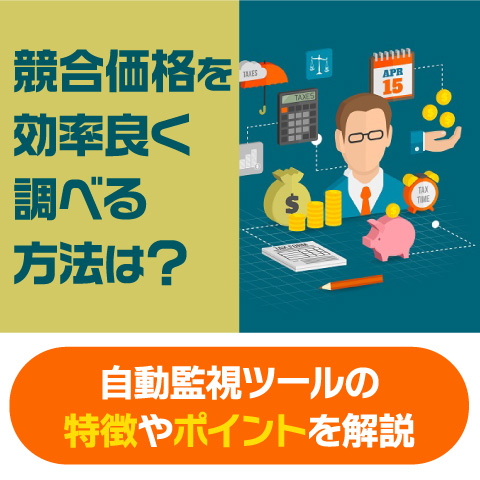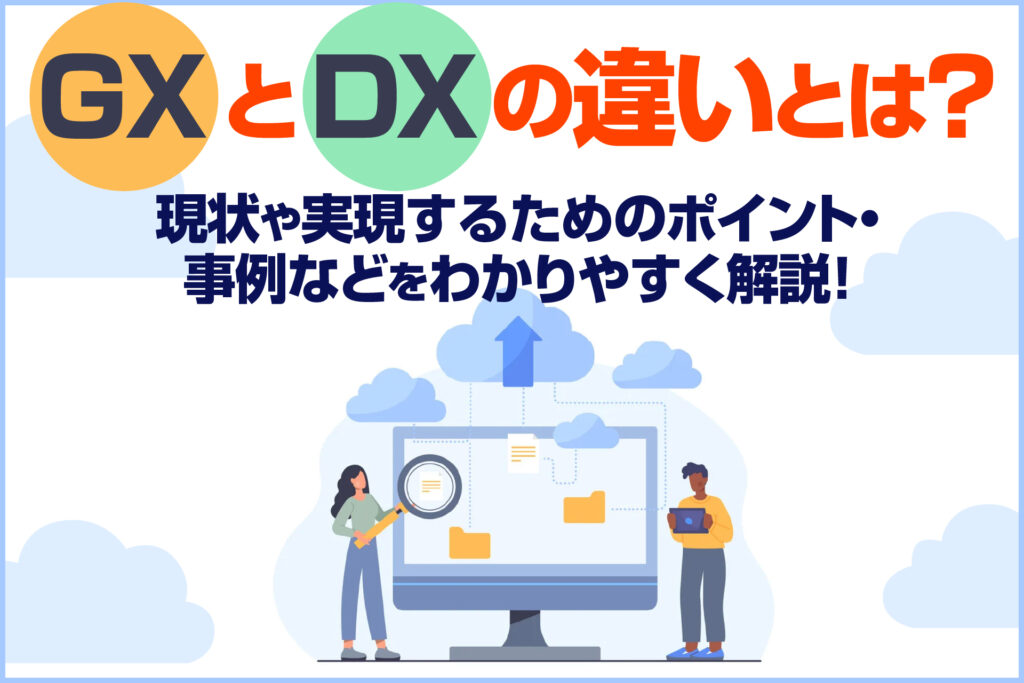
グリーントランスフォーメーションの略称である「GX」とデジタルトランスフォーメーションの「DX」の違いが気になっている方もいるでしょう。
GXは環境保護と経済の成長を目指す取り組みですが、DXはデジタルの技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを刷新することを指します。一見、相反するような2つの言葉ですが、GXを行うためにはDXの推進を図る必要があるため、どちらも把握しておくことが重要です。
この記事では、DXとGXの違いをはじめ、これら2つが重要視される背景や得られるメリットなどをわかりやすく解説します。
GXとは

GXとはグリーントランスフォーメーションの略で、温室効果ガスの排出削減に取り組みつつ、経済や社会の変革を実現させることです。温室効果ガスを発生させる化石燃料に代わるエネルギー源として、太陽光発電や風力発電・水力発電などの再生可能エネルギーが注目されています。
GXが重要視される理由
GXが重要視される理由として、以下の3つが挙げられます。
- 地球温暖化の深刻化
- 2050年カーボンニュートラル宣言
- ESG投資の拡大
地球温暖化は気温の上昇だけではなく、海面の上昇や洪水・干ばつなどの自然災害を増加させる一因となっています。石油や石炭などの化石燃料が地球温暖化の最大の原因である温室効果ガスを発生させることから、削減する取り組みが加速しています。
また、2020年に政府が発表した2050年カーボンニュートラル宣言も、GXが重要視されるようになった理由の1つです。2050年カーボンニュートラル宣言とは、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする取り組みのことです。
人為的に発生した二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを、植林や森林管理などにより差し引きゼロの状態にすることを目指しています。現在では、120以上の国がカーボンニュートラルの目標に向かって取り組んでいます。
GXが重要視されるようになった理由の3つ目として、ESG投資の拡大が挙げられます。ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字をつなげた言葉です。
環境や社会に配慮して事業展開を行っている企業に投資しようという動きがESG投資です。2006年に国連で機関投資家の投資原則にESGの視点が取り入れられたのがきっかけとなり、ESG投資が世界的に広まりつつあります。
このように、地球温暖化やカーボンニュートラル宣言、ESG投資により、GXが重要視されるようになりました。
GXの取り組みの現状
国内では「GX実現に向けた基本方針」をはじめ、グリーン成長戦略・第6次エネルギー基本計画・GXリーグの設立など、さまざまな施策が行われています。温室効果ガスの約6割を占める二酸化炭素の排出量は、以下の画像の通り年々減少傾向にありますが、取り組みは活発とは言えないのが現状です。
の実現に向けた課題と対応」-1024x608.png)
(引用:資源エネルギー庁「GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた課題と対応」)
日本ではGX促進のための施策が多く出されていますが、具体的な取り組み例が言及されていないことが足かせとなっています。今後、GXへの取り組みを加速するためには、海外の動きを把握しておくことが重要です。
GXに取り組むメリット
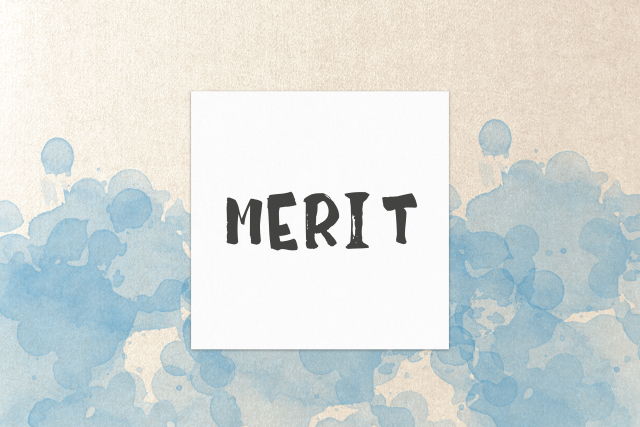
GXに取り組むメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 企業のイメージアップ
- エネルギーコストの削減
- 公的な予算の増加
社会的に環境問題への注目が高まっているため、GXに取り組むことで企業のイメージアップに繋がります。好感度や信頼度がアップし、企業のブランディングにも役立つでしょう。さらに、GXに取り組んでいる企業として認知度がアップすると、投資対象が拡大したり、優秀な人材を確保できたりする可能性が高まります。
また、GXへ取り組むことにより、エネルギーコストの削減が見込めます。代表的な取り組みであるクールビズやウォームビズなどの省エネ対策を実行するだけでもエネルギーの消費量を減らせます。
さらに、クリーンエネルギーである太陽光発電や風力発電・水力発電に移行することで、燃料費の削減が見込めます。クリーンエネルギーに移行する費用が懸念材料として挙げられますが、資源エネルギー庁によると、今後コストが下がる見込みです。
GXに取り組むメリットとして、公的な予算の増加も挙げられます。GXへの取り組みに活用できる補助金は、以下の通りです。(2024年7月現在)
- 事業再構築補助金のグリーン成長枠
- ものづくり補助金のグリーン枠
- 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 など
GXに取り組むことで、以下の補助金や助成金の交付が期待でき、導入費用の負担軽減に役立ちます。
また、これらの公的な予算は今後要件が緩和され、受給しやすくなる見込みです。
DXとは

DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を活用し、企業として新たなビジネスモデルを確立する取り組みを指します。業務のデジタル化だけではなく、業務全体を見直し新しいビジネスモデルを創出するのが特徴です。
DXが重要視される理由
DXが重要視される理由として、以下の3つが挙げられます。
- 2025年の崖
- デジタル化の加速
- IT関連の人材不足
2025年の崖は、日本の企業が世界的なデジタル化に乗り遅れることで、2025年以降に最大12兆円の経済損失が発生すると言われている問題のことです。経済産業省が発表したDXレポート内にて使用された言葉がきっかけで注目を集めました。導入から長い月日が経過しているシステムやソフトウェアを使用している企業が多いため、国が総力を挙げてデジタル化を推し進めています。
また、ここ数年で消費者の行動がWEB中心となっているのもDXが重要視される理由の1つです。企業は顧客のニーズを理解し、それに対応する製品やサービスの提供が求められています。日本国内ではIT関連の人材が不足しているため、外部のツールやサービスを活用する必要が高まっています。
DXに取り組むメリット

DXに取り組むメリットは、以下の5つです。
- IT関連のコスト削減
- IT関連の人材不足の解消
- 経済損失のリスク低減
- 既存システムの刷新を促す
- IT関連のリスクの低減
DXの推進により、製造や販売、在庫管理などのさまざまな業務を自動化することで、企業の業務効率化や経費削減につながります。その結果、人材不足の解消や経済損失を低減させることが可能となります。また、DXの推進は、従来使用しているシステムを新しいものに変えるきっかけにもなるでしょう。
経済産業省が発表した「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」によると、既存システムの老朽化がDX推進の妨げになっているケースが圧倒的に多いことが明らかになっています。
具体的には、データが整備されておらず活用しづらい、運用者が不足しセキュリティのリスクが高まる、などのさまざまな問題が起こっています。
DXを進めることで、老朽化が顕著に見られる既存システムを多用した体制を変え、セキュリティ面でも安心できる最新システムを活用した効率的な仕事環境を整えることが可能になります。
GXとDXの関係性
GXとDXはそれぞれ目的が異なりますが、相関性があるのが特徴です。GXの代表的な取り組みであるクールビズやウォームビズなどの省エネ対策を実現するためには、業務の効率化を図る必要があります。業務を効率化するためには、デジタル技術の活用によるビジネスの革新、つまりDXが不可欠です。このように、GXを行うためにはDXの推進を図る必要があります。
GXとDXの取り組み事例

ここからは、GXとDXの具体的な取り組み事例を2つずつ例に挙げて紹介します。
GXの取り組み:トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社では地球環境の問題に対して、クルマの持つマイナス要因を限りなくゼロに近づける以下の取り組みがなされています。
- 風力・バイオマス・水力の100%再生可能エネルギーを利用して二酸化炭素の排出量を削減する
- ハイブリッド技術を次世代車の技術に活かして、二酸化炭素の排出量を削減する
- 工場での水素利用技術の開発を進める
- 田原工場に風力発電設備を設置する
ブラジル工場では2015年から、風力・バイオマス・水力の100%再生可能エネルギーにて電力を賄っています。また、メキシコ新工場では、2019年に生産時の車1台あたりの二酸化炭素排出量を約40%以上削減することに成功しました。日本でも水素利用技術の開発や風力発電設備の設置など、再生可能エネルギーの活用に向けた取り組みが行われています。
GXの取り組み:NTTグループ
NTTグループでは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー中心の産業構造へと転換するために、以下の取り組みがなされています。
- 温室効果ガスの排出量を可視化するプラットフォームの開発
- パートナー会社と協力して太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電所を開発
温室効果ガス排出量のプラットフォームの開発においては、2027年度までにサプライヤーを含む企業1,000社への導入を目指しています。また、再生エネルギーについては、開発中の発電所も含めて、2030年には再生エネルギー発電量26.9億kWhを達成する見込みです。
DXの取り組み:トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社ではDX促進のために、以下の取り組みがなされています。
- デジタル関連の人材の育成プログラムの実施
- アプリやデータを活用したデジタル技術の活用による働き方変革
デジタルに関する人材育成のために開発された開発者養成プログラム「デジタル イノベーション ガレージ(DIG)」により、これまでに100名を超える人材育成に成功しました。
また、育成した人材によるアプリ開発の成果として、重量計で測定した数値を直接帳票に入力できるシステムの導入に成功。これまでの課題であった誤入力や転記ミスを防げるようになり、業務効率化を実現しました。
DXの取り組み:キユーピー株式会社
キユーピー株式会社では、DX促進のために、以下の取り組みがなされています。
- シミュレーション技術による生産の最適化
- 品質検査にAIを活用して、検査精度および速度の向上
- 食品安全システムのデータを活用した食品ロスの削減
- お客様の好みや気分に合ったドレッシングが診断できる、AI(人工知能)を活用した新コンテンツ「myドレッシング診断」の開発
- 高度な専門性を持ったデジタル関連の人材の育成
業務効率化はもちろん、お客様へのサービス提供・人材育成など、さまざまな観点からDX促進に取り組んでいるのがキユーピー株式会社の取り組みの特徴です。
GXの取り組みを実現するためのポイント

最後に、GXの取り組みを実現するためのポイントを3つ紹介します。
GX実現に向けた基本方針を参考にする
GXを実現するためには、令和5年2月に発表された「GX実現に向けた基本方針」を参考にするのがおすすめです。「GX 実現に向けた基本方針」では、以下の5項目をはじめ、産業・事業別にどのようにDXに取り組むべきかが記載されています。
- 徹底した省エネルギーの推進
- 製造業の構造転換
- 再生可能エネルギーの主力電源化
- 原子力の活用
- 水素・アンモニアの導入促進
また、GXを実現するためには、自社がどれほど温室効果ガスを排出しているか把握しておくことが重要です。現在の排出量を把握し、どのように削減していくか、再生エネルギーへの転換が可能かどうかなどを検討し、目標を設定しましょう。
DX推進の体制を整える
GXを実現するためにはDX推進も同時に行う必要があるため、DXを推進のための基盤作りも重要です。「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、デジタル関係のインフラが必要であると明言されています。
以下のポイントを押さえて、DX化を推し進めましょう。
- DXのビジョンを明確にする
- 自社内で有力な人材を育成する
- デジタルツールを積極的に活用する
- データを活用する
また、DX化はコストがかかるため、経営陣と密に連携できるよう、体制を構築する必要もあります。
GX推進法や国際ルールなどの情報を収集する
GX実現のためには、GXに関わる法律や国際ルールについて情報収集を行うことも大切です。2023年5月に国会で成立した「GX推進法」は、日本のエネルギー政策の今後の方向性を定めたもので、企業が今後、GXの取り組みを実現するにあたって知っておくべき法律といえます。
例えば、GX推進法にて決定された「成長志向型カーボンプライシング」は、企業ごとの二酸化炭素の排出量に応じて税金や負担金が徴収されるというものです。
この仕組みについて理解を深めることで、二酸化炭素の排出量を抑えることが、企業の経費節約につながることが理解できます。さらに、企業への直接的なメリットを知ることで、二酸化炭素の排出量をおさえる行動につながります。
結果的に、GX推進法への理解は、企業のGXの実現につながっていくと言えるでしょう。
これらの法律やルールは随時変更する可能性があります。特に、環境問題に関わる規則は世界の状況によって新しいものもでてくるでしょう。そのような変化を見逃さないためには常に関連するWebサイトを監視し、新しい情報を収集していく必要があります。常にWebサイトをチェックすることは人手では難しいことも多いため、ツールなどでデジタル化し、この業務をDXの対象にすることも大切です。

まとめ

GXとはグリーントランスフォーメーションの略で、温室効果ガスの排出削減に取り組みつつ、経済や社会の変革を実現させることです。温室効果ガスを発生させる化石燃料に代わるエネルギー源として、太陽光発電や風力発電・水力発電などの再生可能エネルギーが注目されています。
GXを実現するためには、DX推進の体制を整えたり、GX推進法や国際ルールなどを把握したりしておく必要があります。
サステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」は、国内だけではなく海外サイトの環境やESG関連の最新情報を常に把握できます。GXについての法律やルールをチェックするのはもちろん、他にもWebサイトチェックの業務がある場合には業務効率化を促進させる1つの方法として「サステナモニター」を活用してみてください。