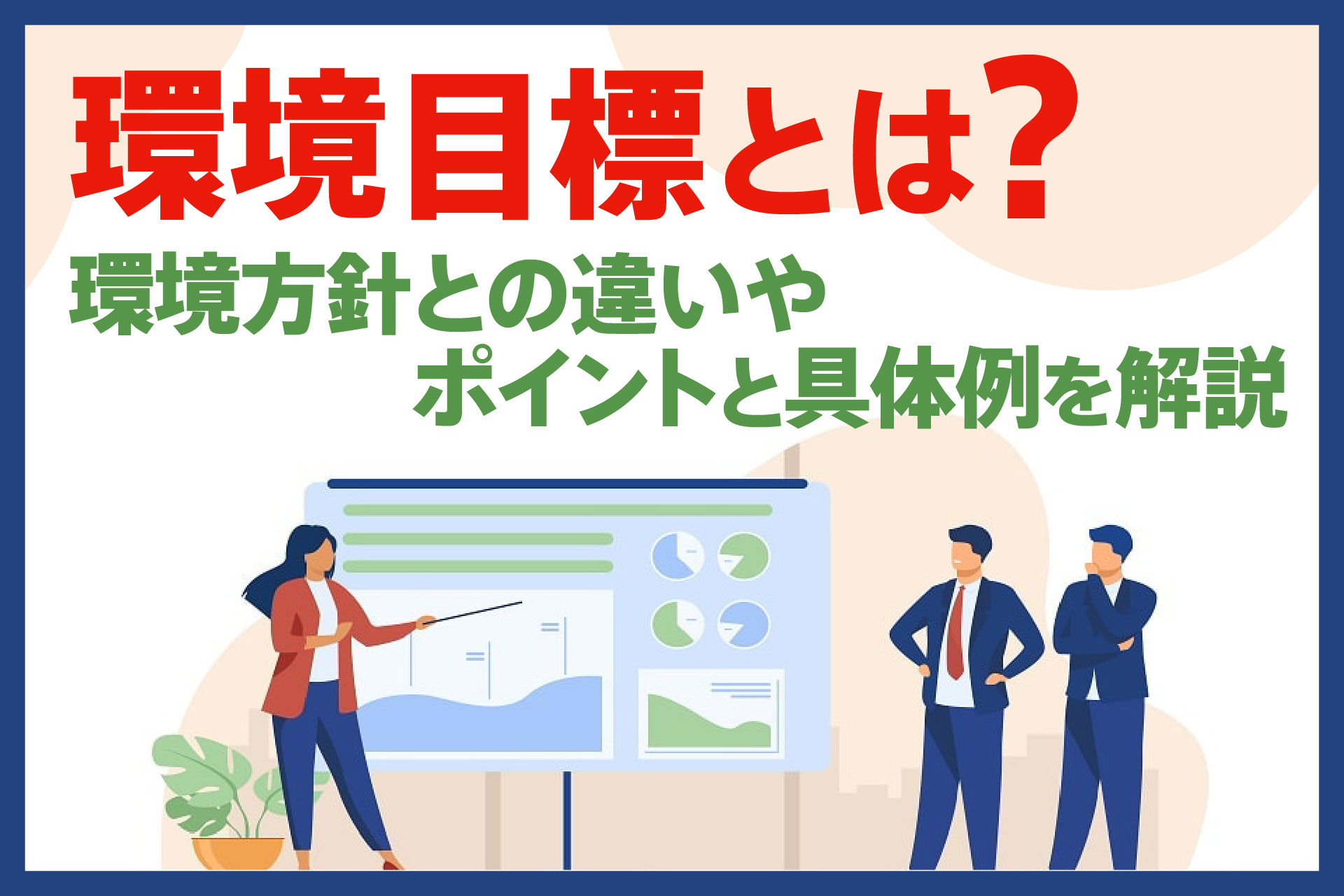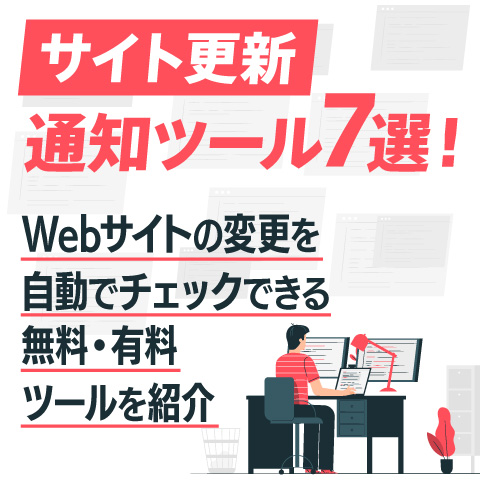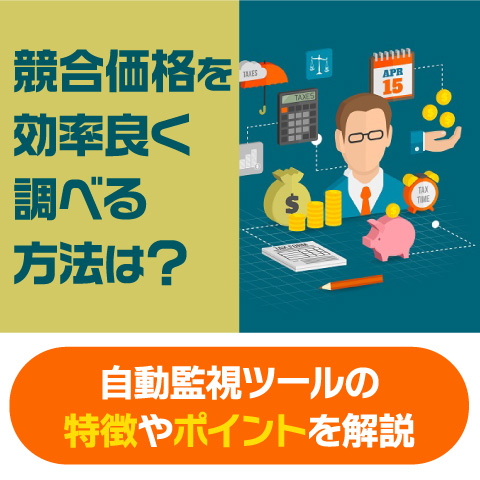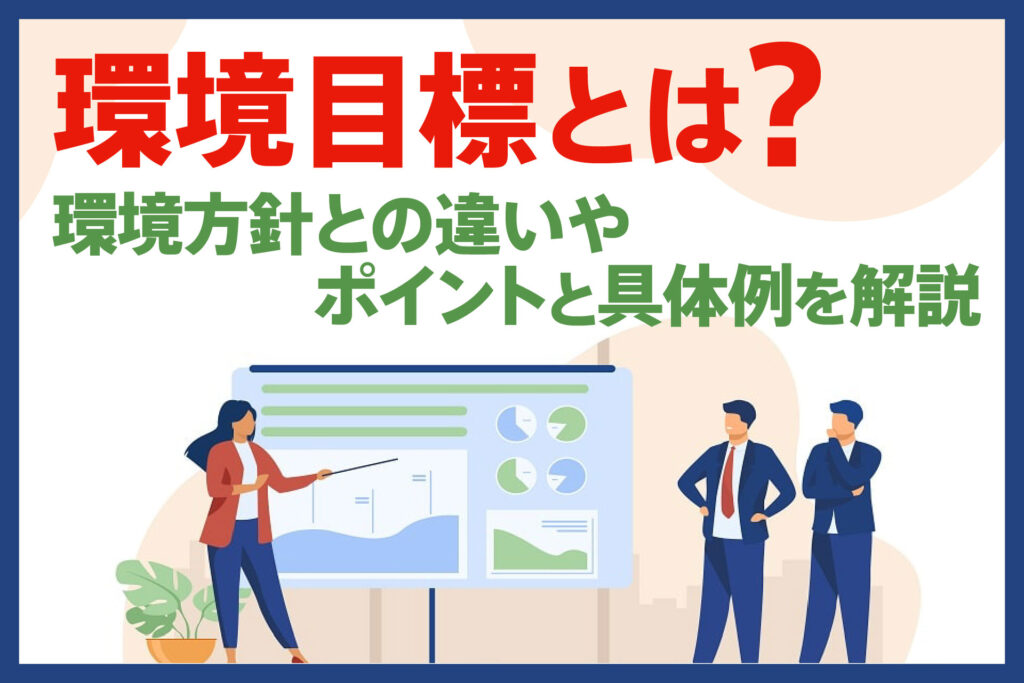
世界的に事業者は環境への影響を意識することが求められています。自社のことだけを考えて発展するのではなく、環境に配慮して持続可能な発展が必要とされているのです。そして、このような発展を実現するために環境目標と呼ばれるものを設定する企業が増えてきています。
企業のサステナビリティ担当者やESG担当者の中には、目標を設定する作業を割り当てられたが「実際は詳しく理解できていない」という方もいるのではないでしょうか。今回は、環境目標を決めたい方に向けて基礎から決め方、具体例まで解説します。
環境目標とは
環境目標とは、企業や組織が持続可能な発展を目指すために、環境保護や改善に向けて設定する具体的な指標や目標です。設定内容は多岐にわたり、例えば以下の観点から目標は設定されます。
- 地球温暖化の抑止
- 大気や水質の改善
- 廃棄物の削減
- 生物多様性の保護
環境面の課題は数多くあるため、それに対応するための環境目標もさまざま考えられるのです。
環境目標は、企業が自らの環境影響を評価し、改善するための計画や行動を検討する際に利用されます。また、設定した目標の達成状況を関係者や社会全体に示すことで、企業としての責任を証明することが可能です。着実に目標を達成すれば、信頼性や評価を高めることに繋がります。
そのため、客観的に評価しやすいように具体的な数値や期限を設定します。そして、定期的に進捗を評価・公開することで、持続可能な発展に向けた取り組みを続けていると証明し続けるのです。
環境方針と環境目標
環境方針と環境目標は、企業や組織が持続可能な発展に向けて取り組む際の重要な指針となるものです。ただ、それぞれには役割の違いがあります。
まず、環境方針は「企業や組織が環境保護に対してどのような姿勢を持っているか」「具体的にどのような取り組みを進めていくか」を明文化したものです。企業の使命や価値観、行動指針や法令遵守を明文化しておくことで、これが企業の全体的な環境戦略の基盤となり、社内外に対して環境問題に取り組む企業であることを示すのです。
対して、環境目標は、環境方針に基づいて、具体的かつ定量的な内容で設定される個別の目標を指します。具体的な行動計画であり、環境目標を達成することで、環境方針も達成できるようになっています。そのため、期限が設定された行動内容を定義し、それらの進捗を主に数値で評価できるようにするのが大切です。
環境マネジメントシステム(EMS)とは
環境マネジメントシステム(EMS)とは、企業や組織が環境保護を推進し、環境影響を管理するためのフレームワークです。それぞれの企業が環境方針や環境目標を立てる際には、環境マネジメントシステムを踏まえるようにします。例えば、環境方針や環境目標を立てる際の数値目標を参考にしたり、方針を決定するまでのプロセスを整えたりする際に環境マネジメントシステムに沿ったものとするのです。
なお、環境マネジメントシステムに関連が深いものとして「ISO 14001」が挙げられます。これは、環境マネジメントシステムに関する国際的な標準規格で、多くの企業がこれに基づいて環境管理を進めるのです。環境マネジメントシステムを導入する際は、世界的な規格を踏まえることを心がけましょう。
環境目標を設定する際のポイント
環境目標を設定する際に意識したいポイントについて解説します。
現行業務による環境への影響を確認し、正しく評価する
環境目標を設定する際は、最初に自社の業務が環境にどのような影響を与えているかを正しく把握することが重要です。例えば、以下の観点からデータを集めて評価します。
- エネルギーの消費
- 温室効果ガスの排出
- 廃棄物の生産量
- 水資源の使用量
具体的なデータを収集し、感覚ではなく正しく評価することが重要です。正確な現状分析を実施することで、どの分野で改善が必要であるかを把握できます。また、どのように環境への影響を軽減できるかを数値で理解できるため、効果的な目標設定につなげることも可能です。
定量的な数値目標を設定する
達成度合いを適切に評価できるように、定量的な数値目標を設定することがポイントです。例えば、「エネルギー消費を5年間で20%削減する」「温室効果ガス排出量を2030年までに50%削減する」といった具体的な数値と期限を明示します。
また、このような数値目標を設定する際には、最新の国際基準を把握しておくことが重要です。例えば、日本では環境省が「大気汚染に係る環境目標値設定状況」との基準を出しています。これを踏まえて設定することで、より説得力のある数値目標となるのです。
しかし、環境に関する情報や基準は国内外に数多くあり、それらを細かくチェックする作業は大きな負担です。加えて「いつ変化するのか」「どの部分が変わったのか」を人力だけで確認することは難しいでしょう。そのため、国際イニシアティブの最新情報や海外法令のチェックは、ツールを活用して自動化するのがおすすめです。

自社にメリットがある目標を意識する
単純に数値目標を設定するのではなく、達成することで、自社にメリットがある値を設定すべきです。例えば、エネルギー効率の改善や廃棄物の削減などは、環境負荷を軽減するだけでなく、そのやり方によってはコスト削減や廃棄物を処理する手間がなくなることによる業務効率の向上に繋げることも可能です。これは、自社の業務効率を上げることで環境目標を達成できる可能性がある、ともいえるでしょう。つまり、DXのような業務改善も環境目標を設定する際、同時に検討することが効果的と考えられます。
また、持続可能な取り組みを継続的に進めることで、企業のブランド価値や顧客、関係者からの信頼性を高めることも期待できます。環境保護に貢献するというメリットだけではなく、経営的にもメリットがある目標を意識しましょう。
部門や部署ごとに適した目標とする
企業全体だけでなく、各部門や部署ごとに適した目標を設定することがポイントです。それぞれの部門は、異なる業務内容や環境影響を持つため、それらを考慮しなければなりません。例えば、生産部門ではエネルギー消費の削減、物流部門では排出ガスの削減、オフィス部門では紙の使用量削減などと設定します。部門ごとの特性を踏まえた目標設定とすることで、全社的な環境改善を効率化できるのです。
現実的な目標を立てる
達成可能な現実的な目標であることが重要です。極端に高い目標を設定してしまうと、達成が困難になってしまいます。結果、従業員の士気が低下したり目標が達成できないことによる、信頼の失墜につながりかねません。そのため、自社のリソースや技術などを踏まえて、実現可能な範囲で目標を設定することがポイントです。
また、段階的な目標を設定し、達成度を定期的にモニタリングしましょう。もし、達成が難しかったり余裕があったりするならば、必要に応じて目標の見直しを実施することも重要です。
環境方針・環境目標の具体例
環境方針や環境目的の具体例を挙げていきます。
環境方針の例
製造業とIT業界を例として、どのような着眼点で方針を立てれば良いか紹介します。
製造業
| 持続可能な資源利用 | 製品のライフサイクル全体を通じて、持続可能な資源の利用を推進します。再生可能エネルギーの使用を増加させ、廃棄物の削減とリサイクルの促進に努めます。 |
| 温室効果ガスの削減 | 温室効果ガスの排出を削減するための具体的な目標を設定し、これを達成するための技術革新と効率的な生産プロセスの導入を推進します。 |
| 法令遵守 | 全ての環境関連法令を遵守し、環境リスクを最小限に抑えるための継続的な改善活動を実施します。 |
| 意識向上 | 社員全員が環境保護の重要性を理解し、環境へ配慮できるよう、定期的な教育を実施します。 |
IT業界
| エネルギー効率の向上 | データセンターおよびオフィスのエネルギー効率を向上させるため、最新技術の導入や最適な運用を実現します。 |
| 電子廃棄物の管理 | 電子機器のライフサイクルを管理し、不要な電子機器のリサイクルと再利用を促進します。 |
| 持続可能な製品開発 | 環境に配慮した製品の設計と開発を推進し、製品のエネルギー消費と環境影響を最小限に抑えます。 |
環境目標の例
製造業、IT業界、小売業を例として、具体的な数値をどのように設定すれば良いか紹介します。なお、ここでの数値は一例です。
製造業の場合
| 温室効果ガス排出量の削減 | 2030年までに、温室効果ガス排出量を2010年比で50%削減する。 |
| 再生可能エネルギーの使用 | 2025年までに、全工場でのエネルギー使用のうち30%を再生可能エネルギーに転換する。 |
| 廃棄物のリサイクル率向上 | 2025年までに、製造過程で発生する廃棄物のリサイクル率を80%以上に高める。 |
IT業界の場合
| データセンターのエネルギー効率 | 2025年までに、データセンターのPUE(電力使用効率)を1.2以下にする。 |
| 電子廃棄物のリサイクル | 2028年までに、全社の電子廃棄物リサイクル率を90%以上に引き上げる。 |
| カーボンニュートラル達成 | 2030年までに、全社的にカーボンニュートラルを達成する。 |
小売業の場合
| プラスチック使用の削減 | 2025年までに、使い捨てプラスチック包装の使用を50%削減する。 |
| 持続可能な製品の販売拡大 | 2026年までに、全商品のうち30%を持続可能な素材から製造された製品にする。 |
| 廃棄食品の削減 | 2023年までに、廃棄食品の量を2018年比で25%削減する。 |
まとめ
環境目標を設定する際には、自社のことだけを考えるのではなく、関連する法規制を遵守することが重要です。また、環境マネジメントシステムの継続的な改善を意識して実行することを方針に含めなければなりません。状況に応じて最善の行動を取れるようにすることが大切です。
このように最善の目標を立てるためには、関連する法令やアセスメント、環境に関する国際イニシアティブのチェックが求められます。ただ、これらの情報をチェックする作業は担当者の負担となりやすいため、自動化できるツールの活用がおすすめです。このチェック業務を効率化することでも、環境目標を達成するためのDXのひとつになる可能性があります。
弊社が提供するサステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」は、国内外の環境やESGに関連した情報を自動で収集し、関係者に通知します。ツールを活用しながら効率的に情報収集をして、自社に合った環境目標を設定しましょう。