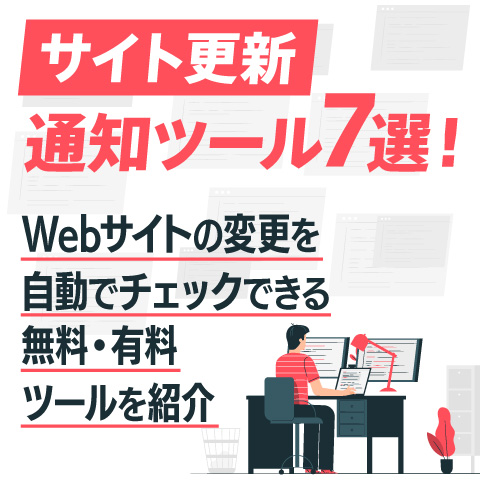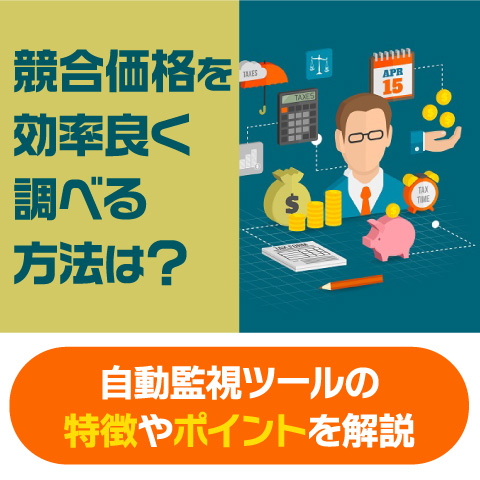ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品サービスのライフサイクル全体における環境負荷を評価するための考え方です。近年は環境に与える影響が重視されているため、ライフサイクルアセスメントによって評価することが求められています。また、評価の結果から課題を明確にして、改善することもしなければなりません。
しかし、ライフサイクルアセスメントが求められる分野で勤務していても、その内容を理解できていない人は多いでしょう。自動車業界の担当者などライフサイクルアセスメントが重要な人はもちろん、ライフサイクルアセスメントの基礎知識を習得したい人も含めて、概要から事例などを学んでいきましょう。
目次
️ライフサイクルアセスメント(LCA)とは
ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品やサービスの製造から廃棄までの全過程における環境負荷を定量的に評価する手法です。例えば、資源の採取、製品の製造や流通、顧客による使用と廃棄など、すべての過程で関わるエネルギー消費や排出物を評価します。これにより、環境への影響を一括で把握できるため、負荷のかかる作業の見直しや、更なる改善点を洗い出したりできます。特に、製品設計や製造プロセスの段階でLCAを活用することで、持続可能な製品開発や効率的な資源利用が可能です。
日本では、特に日本自動車工業会がライフサイクルアセスメントを推進していることが特徴です。自動車業界は環境負荷が大きいとのイメージを持たれがちであるため、積極的に環境への影響を下げようとしています。また、京都議定書により日本はカーボンニュートラルを目指す必要があるため、これの達成を目指すためにも、ライフサイクルアセスメントを推進している状況です。
️ライフサイクルアセスメント(LCA)の背景
ライフサイクルアセスメントは、1970年代に製品やサービスの全ライフサイクルを通じて環境影響を評価する手法として始まりました。1980年代から1990年代にかけて国際標準化が進み、ISO14040シリーズとして規格化されています。現在、多くの産業で採用されている概念で、自動車業界では特に重要な役割を果たしています。
例えば、自動車メーカーは製造から廃棄までのカーボンフットプリントを評価し、環境負荷の低減に努めています。国際連合ヨーロッパ経済委員会(UNECE)は、2025年に新しい自動車向けLCA標準を導入する予定で、これにより業界全体での取り組みが加速すると想定されています。自動車業界は、環境へ与える負荷が大きいため、持続可能性の高いビジネスが求められているのです。
️ライフサイクルアセスメント(LCA)の特徴
ライフサイクルアセスメントの特徴は、包括性にあると考えられます。アセスメントに際しては、製品の原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの各段階を対象とし、その個別の工程ごと、もしくは総合的に評価します。これにより、単一の工程だけでなく、製品ライフサイクル全体を通じて環境影響を明確に把握できるのです。
さらに、LCAは環境負荷を定量的に評価するため、具体的な数値でエネルギー消費や排出物を示せます。定量的に示せることで、異なる製品やプロセス間での環境影響の比較が可能となり、標準化された手法を用いることで信頼性の高い結果を得ることも可能です。
️ライフサイクルアセスメント(LCA)を取り組むメリット
ライフサイクルアセスメント(LCA)に取り組むメリットは多岐にわたり、例えば以下が考えられます。
- 包括的な環境負荷の把握により改善点を見つけ出しやすい
- 製品の設計段階から環境負荷を低減するための具体的な改善策を講じれる
- 法規制へ適合し条件の厳しい市場でも競争力を高められる
- 製品の環境影響に関するデータを透明かつ信頼性の高い内容でステークホルダーへ提供できる
- 資源の効率的な利用や廃棄物の削減により製造コストを削減できる
️ライフサイクルアセスメント(LCA)のコツ
ライフサイクルアセスメントを実施するにはいくつかのコツがあります。
️ライフサイクル全体の見直し
手作業の自動化は、ライフサイクルアセスメントにおけるプロセスの効率化において重要です。手動で実施するとミスが発生しやすく、時間のかかる作業を自動化すれば、正確かつ短時間で完了させられるようになります。
例えば、担当者がWebサイトを閲覧して情報をチェックする作業は、時間がかかり無駄を生みやすいと考えられます。また、情報の見落としによって問題が生じてしまうかもしれません。そのため、Webサイトの情報確認はツールを利用して自動化することが望ましいのです。
弊社のサステナモニターを利用すれば、環境やESGに関するWebサイト(URL)の変更を自動的に検知して関係者へと通知できます。サイトチェックの時間を最小限に抑えられるため、作業工程を改善し、二酸化炭素の排出量を抑えるなど、ライフサイクルアセスメントの実施に役立つでしょう。

️対応の優先度を決定
ライフサイクルアセスメントにおいては、全ての環境影響を均等に扱うべきではありません。影響の大きい部分や改善の余地が大きい部分に焦点を当てることが重要です。
対応の優先度を決定する際は、環境負荷が高いプロセスやライフサイクル段階を特定することが求められます。そして、大きな効果を得られるように、影響が大きい部分に改善に向けたリソースを集中させます。そうすることで、限られたリソースでも、迅速かつ効率的に環境改善できるでしょう。
️評価にはプロの意見を含める
各アセスメントには、専門家の意見を含めることが重要です。評価には算出ルールがあるものの、仮定する条件などによって大きく結果が変化します。そのため、環境影響の分析や評価方法に関する深い知識を専門家の意見を含めるべきです。これにより、評価の信頼性や妥当性を高められます。特に、評価の過程で用いるデータや仮定の適正性は結果を大きく左右するため、プロの意見を取り入れるべきです。
ライフサイクルアセスメント(LCA)の社会動向
ライフサイクルアセスメントは社会的にどのような動向であるか日本と海外について解説します。
日本の動向
日本では、ライフサイクルアセスメントが企業や研究機関で広く取り組まれています。また、取り組みについての情報発信も積極的であり、2024年には第19回日本LCA学会研究発表会が開催され、非常に多くの研究成果や実践事例が共有されました。参加数は年々増加していて、民間企業での取り組み事例の発表も増えています。学会での発表数の増加は、それだけ日本でライフサイクルアセスメントが注目されていることを意味するでしょう。
海外の動向
海外では、LCAの導入が進んでおり、特に欧州と北米で活発に実施されています。例えば、EUではエコラベルや製品環境フットプリント(PEF)を通じてLCAの標準化を推進しています。また、企業が製品のライフサイクル全体で環境影響を評価することを求めています。北米では、米国環境保護庁がLCAツールやデータベースの開発をサポートし、ガイドラインも提供しています。
他にも、国際標準化機構(ISO)はLCAの国際標準であるISO 14040シリーズを提供中です。これにより、各国での統一的なLCA実施を推奨しています。
️ライフサイクルアセスメント(LCA)とSCOPE3の違い
ライフサイクルアセスメントとSCOPE3の違いは主に評価範囲です。
まず、ライフサイクルアセスメントは、製品やサービスのライフサイクル全体(資源採取、製造、使用、廃棄)を通じて環境影響を評価する手法です。対して、SCOPE3は「事業者の活動に関連する他社の温室効果ガス(GHG)排出量を評価する手法」を指しています。例えば、原材料の調達やそれらの輸送で排出される部分や製品の使用で排出される環境影響に関わる部分です。ただ、そもそもSCOPE3はISOに基づいたライフサイクルアセスメントが成立しているからこそ正確に測定できるものです。単独で実施できるものではないため、ライフサイクルアセスメントにSCOPE3が内包されていると理解しても間違いではありません。
なお、SCOPEは事業活動における温室効果ガスの排出量を評価するものであり、SCOPE3以外に事業者が自ら排出する「SCOPE1」と他社から供給されたエネルギーの使用に伴う間接的な排出である「SCOPE2」、そして事業活動における他社の排出である「SCOPE3」が設けられています。SCOPE1・SCOPE2・SCOPE3の合計をサプライチェーン排出量と呼んでいます。
️ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施方法
ライフサイクルアセスメントを実施する方法は、大きく4つのステップに分解できます。
️目的と調査範囲の決定
ライフサイクルアセスメントは、評価の目的と調査範囲を明確にすることから始まります。例えば、目的として「環境負荷の特定」「製品設計の改善」「規制遵守」などと定めるのです。
また、調査範囲の決定では、対象とする製品やサービス、ライフサイクルのどの段階を評価するかを決定します。加えて、使用するデータや評価方法を決定しておきましょう。この段階で明確に定義できるかどうかが、後続の分析や結果の解釈の精度と信頼性を左右します。
インベントリ分析(LCI)
インベントリ分析をするにはまず、ライフサイクル全体にわたる資源使用量や排出物のデータを収集します。具体的には、原材料の採取、製造、使用、廃棄に至るまでの各工程でのエネルギー消費や排出ガス量を詳細に把握するのです。このデータ収集は評価の基礎となるため、正確で網羅的な情報を収集しなければなりません。データは、既存のデータベースを活用することもあれば、現地で実際に調査や測定、企業へ提供情報を依頼するなどが考えられます。
インベントリ分析では収集したデータを「入力」「出力」に分類して、定量的に評価します。例としてペットボトル飲料を考えると以下のとおりです。
| 出力 | 入力 |
| ペットボトル飲料 600mL | ポリエチレンテレフタレート 30g 水 500g砂糖 5g ビタミン 3g 包装材 2g 電力 0.02kw ※値は正確なものではありません。 |
これらの入力や出力からどの程度の環境負荷が発生しているかを算出します。算出の際は実際に測定することもありますが、原材料によっては測定に出向くことが非常に難しかったり測定できる環境でなかったりすることもあります。そのため、工業会などが発表している「排出原単位」を利用して計算したり、業界団体が提供しているデータベースを利用したりすることが大半です。ただ、参照するものによって環境負荷の評価が異なるため、最終的に得られるライフサイクルアセスメントの結果も変化します。
影響評価(インパクトアセスメント)
影響評価では、インベントリ分析で収集したデータを基に、環境への影響を定量化します。例えば、温室効果ガスの排出がどれだけの気候変動を引き起こすか、廃棄物がどれだけ生態系に影響を与えるかを数値で評価するのです。一般的には、環境負荷カテゴリごとに影響を分析し、ライフサイクル全体の環境影響を明確にします。評価手法には、ISO規格に基づくさまざまなモデルを採用することが大半です。
例えば、特定のモデルを利用して「地球温暖化」というインパクトカテゴリーを評価するとします。この場合、CO2やメタン、フロンなど複数の温室効果ガスが影響を及ぼすはずです。そのため、それぞれの影響の度合いについて、IPCCで採用されている地球温暖化係数を利用してCO2換算重量と呼ばれる単位に換算し、その値を集計します。
解釈
最後に、解釈では影響評価の結果を分析し、環境負荷の軽減に向けた行動を起こすためにはどのような観点で行動すべきかという結論を導き出します。評価結果を踏まえて改善策を提案し、環境負荷を低減するための具体的なアクションを決定する工程です。また、場合によっては結果の妥当性や信頼性を検証し、問題点があるならば影響評価のやり直しなどを指示します。解釈の過程で具体的な行動案が決定するため、実際の環境改善に結びつく重要な過程と考えるべきです。
ライフサイクルアセスメント(LCA)の事例
ライフサイクルアセスメントの具体的な事例を紹介します。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、乗用車とその部品に対してライフサイクルアセスメントを実施しています。結果は製品カタログに掲載され、一般に公表されています。近年は、電気自動車のバッテリー製造におけるCO2排出量を削減するため、再生可能エネルギーを100%使用した電池セル製造を目指しています。
本田技研工業株式会社
ホンダは2002年に「Honda LCAシステム」を構築し、生産・購買・販売・オフィス・輸送などの各部門で低炭素化に向けた活動を展開しています。このシステムは、CO2排出低減だけでなく、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」の達成を目指す重要なツールです。ライフサイクルアセスメントのみならず、多角的に環境への影響を最小限に抑える取り組みを続けています。
キリンホールディングス
キリンは1996年からライフサイクルアセスメントを導入し、ビール製造のGHG排出量を評価しています。また、1999年からは環境負荷の少ない容器の開発にライフサイクルアセスメントを活用し、2004年にはエータルク缶と呼ばれるものを開発・採用しました。
最新の環境報告書では、生物資源や水資源などの項目でリスクと機会を定量的に評価していることも挙げられています。また、製品ライフサイクルの早期段階で容器原材料の選定を実施して、環境負荷の軽減も実現しています。
日立製作所
日立製作所は、家電製品のライフサイクル全体での環境負荷を評価するためにライフサイクルアセスメントを導入しています。特に、冷蔵庫や洗濯機の製造プロセスでのエネルギー消費と廃棄物の削減に焦点を当て、環境負荷の低減を実現している企業です。上記に限らず多くの製品の改善点をライフサイクルアセスメントで特定し、持続可能な製品開発を推進しています。
パナソニック
パナソニックは、電池や電気機器の製造においてライフサイクルアセスメントを実施しています。特にリチウムイオンバッテリーの製造過程でのエネルギー消費と排出物を評価していることが特徴です。また、定期的な評価を踏まえて、再生可能エネルギーの使用を増やすことによる環境負荷の低減を目指しています。
資生堂
資生堂は、化粧品のライフサイクル全体での環境負荷を評価するためにライフサイクルアセスメントを採用しています。主に温室効果ガスに着目していて、製品のパッケージングなどで環境負荷を最小限に抑える物質や製造方法を選定していることが特徴です。また、これらの取り組みは「第20回LCA日本フォーラム表彰 奨励賞」を受賞するなど、化粧品メーカーの先端を進む取り組みとしても評価されています。
まとめ
日本では、日本自動車工業会がライフサイクルアセスメントを通してカーボンニュートラルの達成を目指しています。トヨタが実績を公開しているとおり、カーボンニュートラルに近い自動車を販売しているかどうかは非常に世の中の関心を集める部分だからです。EUでも売れ行きの良い車種はライフサイクルアセスメントが公開されるなどしています。
ライフサイクルアセスメントは環境への影響を評価する作業ですが「解釈」においては、問題点を解決しなければなりません。この過程で作業プロセスを見直すことで、環境保護や製品の改善に繋がるからです。また、業務を効率化することが求められるならば、DXを推進し労働環境を変えるキッカケにもなるでしょう。