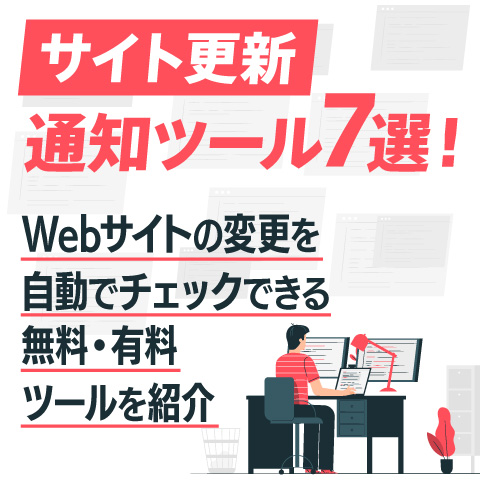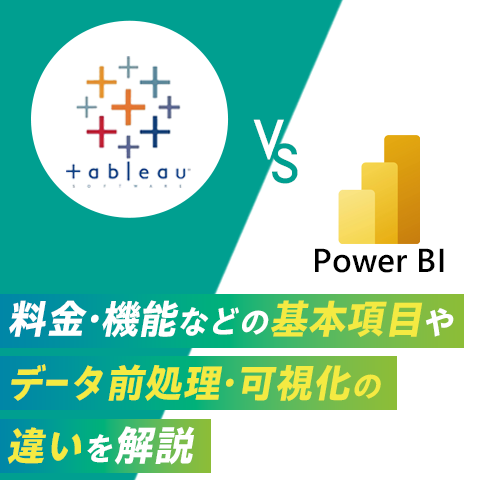社内に存在する大量のデータを活かす方法として「情報共有ツール」の活用が挙げられます。いくつものツールがあり、これらを適切に運用することで業務効率を高められるのです。導入によりどのようなメリット・デメリットがあり、どのツールを導入すれば良いのか具体例を紹介します。
情報共有ツールを活用するメリット
情報共有ツールを導入する際は、以下をメリットとして感じられるかどうかを重視しましょう。
情報を素早く共有できる
専用のツールを活用することで、情報を素早く共有できます。Excelやメールなど、その都度、手動のデータで連携する場合と比較すると、その差は歴然です。
また、情報共有ツールにはさまざまなものがあり、複数導入しておくこともできます。このような状況下であれば、必要に応じて使い分けすることで、より素早く情報を伝えられるでしょう。
履歴として残せる
情報共有ツールでやり取りすれば、基本的には履歴が残ります。後から参照することで、やり取りの証拠になったり無駄を省けたりすることがメリットです。
また、ツールによっては検索機能が用意されていて、履歴を簡単に検索できます。大量の情報からでも簡単に見つけられるため、時間の短縮にも役立つはずです。
公開範囲を制御できる
どの情報を誰に公開するのか、簡単に制御が可能です。権限設定などができるようになっていて、特定の人にだけ情報を表示するなどできます。一定期間だけ情報を共有するなどの制御も可能です。
紙媒体などで共有すると、このような制御が難しくなります。意図しない人に資料を参照される可能性は十分あるでしょう。しかし、ツールでシステム化すればこのような問題は最小限に抑えられます。
情報共有ツールを活用するデメリット
情報共有ツールの活用は、デメリットやリスクがあるため、そこも理解すべきです。
情報共有ツールの停止
ツールを導入すればするほど、利便性が高まるため、活用を前提とした業務フローが構築されます。そのため、どうしても依存性が高くなってしまい、ツールが障害などで停止した場合のインパクトが甚大になりかねません。
特に、コミュニケーションやファイル共有のツールが停止してしまうと、業務自体が停止する可能性があります。障害を見越して、業務フローを構築することは難しいため、ここはデメリットやリスクであると認識しておきましょう。
インターフェースなどに制約がある
基本的に情報共有ツールは、既に開発されているものを導入します。いくつものベンダーがツールを開発しているため、内容を評価して適切なものを導入する流れです。一部の製品を除いて、ユーザーインターフェースなどは既に開発されているものを利用します。
そのため、情報共有ツールの利便性には、制約が生じてしまいます。例えば、ボタンの配置場所を変更するなどは、難しいと考えておきましょう。また、ベンダー側のバージョンアップによってインターフェースが変更されると、強制的にその影響を受けてしまいます。
情報共有ツール導入のポイント
情報共有ツールとはどのようなものであり、どんなメリットとデメリットがあるのか解説しました。ここから、導入前に知っておきたいポイントについても解説しています。
ツールの操作感
実際にトライアル等でツールを利用してみて、操作感を確認しておきましょう。各社がさまざまな方針でユーザーインターフェースを作成しているため、操作しやすいものを選択すべきです。操作感の悪いツールを導入しても、社内で定着せず無駄になりかねません。
また、操作感を評価する際は、利用する部門の代表者を集めることが重要です。IT部門だけではなく、実際に利用するユーザー全体の意見を入れて、最終的な判断を下しましょう。
ツールのコスト
利用人数を踏まえて、どの程度のコストになるかが重要です。あまりにコストがかかりすぎると、コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。
情報共有ツールによって、利用者1人ずつ課金されるものとまとめて課金されるものがあります。例えば、1人500円のツールと10人まで5,000円のツールがあります。10人利用する場合はどちらも同じコストですが、10人未満の場合は後者の料金プランだと高くなってしまうのです。このような細かなところまで正確に算出しましょう。
搭載されている機能
ツールに必要な機能が揃っているかどうかが重要です。情報共有ツールを導入しても、機能が不足していては意味がありません。
機能を評価するためには、事前に求める機能を決定しておくことが重要です。情報共有ツールには多くの機能があるため、良いものを求めると際限がなくなってしまいます。料金との兼ね合いも考慮する必要があるため、最低限必要な機能は事前に定めておきましょう。
おすすめ情報共有ツール
おすすめ情報共有ツールは多数あるため、これらをグルーピングして紹介します。
チャット系ツール
Chatwork
Chatworkは、日本で幅広く導入されている情報共有ツールです。大手企業でも多数導入されていて、高いセキュリティが注目されています。
基本的にはチャットツールですが、ビデオ音声通話に切り替えたり、タスクやファイルの管理も可能です。外部のツールとも連携できるようになっていて、効率よく情報共有ができます。
また、有料版であればユーザー管理ができるなど、ビジネス利用にも影響がありません。グループチャットの利用も可能であり、ビジネスに応じた運用ができます。
MicrosoftTeams
Windowsを利用しているならば、MicrosoftTeamsがおすすめです。基本的には標準で利用できるため、パソコンを導入するだけで利用を開始できます。世界的に利用されていることから、海外とのコミュニケーションにも役立つものです。
基本的にはチャット利用ですが、ボタンをクリックするだけで音声通話やビデオ通話に切り替えられます。また、Microsoftが提供するSharePointなどのサービスとも連携でき、多角的に情報共有が可能です。
Slack
社内SNSとして、特に知られているのがSlackです。パソコンやスマホから使いやすく、有名なアプリケーションであることから、多くの外部ツールと連携できます。
情報の記録に力を入れていて、検索や「ピン留め」機能が充実しています。これらを駆使することで、多くの情報を効率よく活用でき、過去のやりとりも無駄にしない仕組みです。
しかも、標準で十分なストレージが割り当てられます。有料プランに切り替えると、さらに多くなりますが、無料版でも十分に活用できるはずです。
Discord
Discordは、チャットと通話と両方に対応しているツールです。最初は、ビジネスツールではなくゲームなどのコミュニケーションツールとして利用されていましたが、現在はビジネス利用も増えています。
無料で利用できることから、小規模な企業でコストを抑えたい場合に役立つでしょう。有料版に切り替えなくとも、幅広い機能が利用できることが魅力です。
また、画面共有に力を入れていて、同時に複数の画面を共有できます。他の情報共有ツールは、誰か一人の画面に制限されることが多いため、メリットとして感じる部分です。
LINE WORKS
LINE WORKSは、個人で利用するLINEのビジネス版です。基本的な使い方は、個人で利用するものと大差ないため、操作方法で悩む可能性は低いでしょう。
他の情報共有ツールとは異なり、LINE WORKSはカレンダーやストレージなどのサービスが充実しています。そのため、外部のサービスと連携するのではなく、内部で完結することが特徴です。
ChatCo!
ChatCo!は、社内のコミュニケーションを活性化するために開発されたツールです。チャット機能を活用して、社内でコミュニケーションを取れるようになって、中小企業での利用を想定しています。
一般的なコミュニケーションはもちろん、時刻を指定して投稿させる機能もあります。人事情報など、公開するタイミングを指定したい場合は、このような機能が魅力的です。
他にも、議事録の作成を支援する機能やスタンプ機能など、他社ではあまり見られない機能が提供されています。幅広いサービスに魅力を感じるならば、ぜひ検討してみましょう。
Oneder Talk
Oneder Talkは、社内と社外のコミュニケーションを円滑にし、情報を共有するためのツールです。電話帳や050電話の通話に関する機能と、ビジネスチャットがそれぞれ兼ね備えられています。また、名刺をスキャンする機能など、円滑に利用するための機能が備わっていることも特徴です。
また、気軽に導入できるような仕組みとなっていて、スマートフォンにアプリを導入すればすぐに利用できます。準備が必要になると、情報共有ツールを活用する妨げになりますが、Oneder Talkはそのような心配がありません。
ポータルサイト・wiki系ツール
NotePM
NotePMは、文章を作成してWeb上で共有する社内Wikiのサービスです。高機能なエディタが用意されていて、テンプレートを組み合わせることで、効率よく必要な情報をまとめられます。
また、Webサイト上で情報を登録するだけではなく、WordやExcel、PDFなどのファイルをアップロード可能です。ファイル内の検索にも対応しているため、情報の一元管理を実現できます。
さらに、日本語だけではなく英語にも対応しているツールです。海外の拠点も含めて、同じツールを利用できることは魅力でしょう。
DocBase
DocBaseは、ドキュメント管理を低価格で実現できる情報共有ツールです。文章をMarkdown記法で入力すると、その内容に沿って装飾されます。幅広く利用されている記法ではありませんが、効率よく文章を装飾できるため、非常に便利なものです。
本来は、文法を理解しておく必要がありますが、DocBaseならばボタンだけでデザインできます。装飾を施したい時にボタンを押すと、Markdown記法で記載してくれる仕組みです。そのため、Markdown記法であることは、あまり意識する必要のない情報の共有ツールといえます。
なお、Markdown記法で記載しておくと、別の環境でも同じ構造でデータを共有・表示できるなどのメリットがあります。
esa.io
esa.ioも、Markdown記法で文章を記述して管理できる、情報共有ツールです。入力サポート機能は充実していないため、エンジニアが多いなど、日頃からMarkdown記法を利用してる環境におすすめします。自分自身でMarkdown記法の文章を書けないと、情報共有ツールとしては使いづらいでしょう。
また、esa.ioは文章の管理を階層で管理するという特徴があります。これはエンジニアに馴染みのある考え方であるため、そういう観点でもエンジニアやそれに関連する部門に適した、文章形式での情報共有ツールだと考えましょう。
Qast
Qastは、Q&Aを投稿しておくことによって、ナレッジを集約できる社内Wikiサービスです。簡単なメモの投稿も可能となっていて、気軽に情報共有できるツールに仕上げられています。ユーザーインターフェースもシンプルなもので、直感的に情報を共有できることも魅力です。
手軽な情報共有に特化しているため、複雑な使い方はできません。ただ、投稿した内容の検索機能や権限設定に対応しているため、情報共有ツールとして最低限の機能は備わっています。また、外部サービスとの連携も可能であるため、応用的な使い方も可能です。
monday.com
monday.comは、チームの業務をすべて一元管理できる情報管理ツールです。幅広い情報を共有することによって、チーム内の誰がどこで何をしているのか簡単に把握できます。
例えば、monday.comでは参画しているプロジェクトや顧客の情報など、各担当者の情報を確認可能です。また、会社全体でナレッジを共有したりヘルプデスクのサービスを運用したりもできます。総合的な情報共有ツールとして、非常に役立つことが特徴です。
単体でも十分な機能ですが、外部サービスとの連携には対応しています。ストレージ系のサービスと対応しているため、これらと組み合わせることで、大量のデータもスムーズに管理することが可能です。
aipo
aipoは、情報共有を簡単にするために、ユーザーインターフェースに力を入れた情報共有ツールです。直感的に使いやすいデザインとなっていて、複雑な情報共有ツールが定着しなかった環境でも導入できるでしょう。
シンプルでありながら、幅広い機能が用意されていることが特徴です。例えば、スケジュールを共有できる機能やチャット機能、申請のワークフローまで一元管理できます。情報共有ツールの範疇を超えて、多くの機能が用意されていることが魅力的です。
なお、プランによって提供される機能が異なる仕組みです。最初はスモールスタートし、利用者数の増加に伴って機能を増やすような使い方もできます。
toaster team
toaster teamは、社内の情報共有を強化して、人や組織を育てるためのツールです。社内wikiとしての機能を有していて、情報共有することによって、長く役立つナレッジベースを作成できるようになっています。
特に、文章での作成だけではなく、動画マニュアルを作成できることが特徴です。動画の加工は、一般的に専用のソフトを用いて行われます。しかし、toaster teamならばPCやスマートフォンに専用アプリを導入するだけで、動画マニュアルや作業手順書などの作成が可能です。単純な情報の共有だけではなく、動画を用いて「より伝わりやすい情報共有」を実現したい企業におすすめです。
Async*
Async*は、社内に存在する動画を蓄積して、資産として共有するためのツールです。例えばWeb会議の動画を蓄積することが可能で、この内容を必要な人へと共有できます。会議などに参加していない人にも、動画コンテンツで情報共有が可能です。
一般的に、文章の資料と動画コンテンツでは、情報量が大きく異なります。閲覧に時間は要しますが、動画コンテンツの方が情報量が多いのです。そのため、動画で情報共有するということも、選択肢として考えておいた方が良いでしょう。
監視系ツール
TOWA
TOWAは、Webサイトの情報を監視して、変化があれば通知してくれる情報共有ツールです。競合他社や顧客の情報を監視し、変化を共有することによって、ビジネスにいち早く活かすことができます。
また、情報の監視だけではなくタスクカード機能やグループ通知機能でチーム内での情報共有・タスク管理が可能です。これらと組み合わせることで、通知された情報を誰がどのように活用、処理するのかまでを簡単に管理できます。
また、カスタマイズにも対応していて、既存システムとの連携が可能です。すでに情報共有の仕組みが完成しているならば、それにTOWAを組み合わせることで、今まで同じ流れで監視した情報も共有できるようになります。
Octoparse
Octoparseは、クラウドでリアルタイムにWeb上の情報を監視、共有できるツールです。事前に定めておいた条件に沿って情報をCSVやExcelなどのフォーマットで出力してくれます。これらの情報を社内で共有すれば、外部のデータに基づいたビジネスができる流れです。
ただ、TOWAとは異なり、データを収集することに重きをおいたツールです。そのため、情報共有の機能については残念ながら限界があります。出力した、共有用のデータを他ツールと組み合わせて共有することで効果を発揮します。
情報共有ツールを活用した事例
情報共有ツールを活用した事例を具体的に紹介します。
シチズン時計株式会社
日本の時計会社として有名なシチズン時計株式会社は、情報共有ツールを活用することで業務の効率化を実現しています。SKIPと呼ばれるツールの導入により「社内での情報共有・技術継承」を実現しました。情報共有だけではなく、技術継承にも活用できる工夫が特徴です。
また、部門がいくつもあり、それぞれの担当者が多いことから縦のつながりも横のつながりも不十分であることが課題でした。これを解消するために、日常的な会話から業務まで一気に処理できる方法として、情報共有ツールが活用されています。
東京地下鉄株式会社
東京地下鉄株式会社は、コミュニケーションのデジタル化を推進するために、早い段階からSkypeを導入していました。現在は、サービスの名称が変更されていますが、2015年の導入から引き続き、チャットツールを軸とした情報共有を実現しています。
このような情報共有ツールは「チャット」「通話」「会議」と複数の方法を簡単に使い分けできます。同じツールですが、必要に応じて使い分けできることで、より効率よく業務を推進できるようになりました。
大手企業営業部
この企業では、監視系ツールのTOWAを利用して補助金情報の収集を実現しました。営業部門は、クライアントへの提案に補助金の情報を交えることがありますが、補助金の情報は都度変化するため、最新の情報を確認する作業に時間を要します。そのため、自動的に補助金の変化を検知し、共有できるツールの導入により、この問題を解決しました。
まとめ
今の時代、ビジネスチャットツールなどを活用しながら、社内で情報共有することは非常に重要です。効率よく情報を共有できなければ、ビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。
情報共有のやり方はツールによって様々で、単なるチャットやスケジュールを共有するだけのものから、なにか特定の要因があって随時発生するタスクを共有できるものもあります。その要因は時期であったり、外部からの情報だったりすることが多く、特に「事業に関係する情報の変化」は常にその情報に敏感でなければなりません。これらの情報を共有することも企業・チームとしては大切です。
外部情報とうまく付き合い、それを共有することでビジネスを円滑にすすめることもできます。これが外部データの活用につながり、競合他社との差別化にもつながります。是非情報共有ツールをうまくつかいながら、外部データ活用もご検討ください。