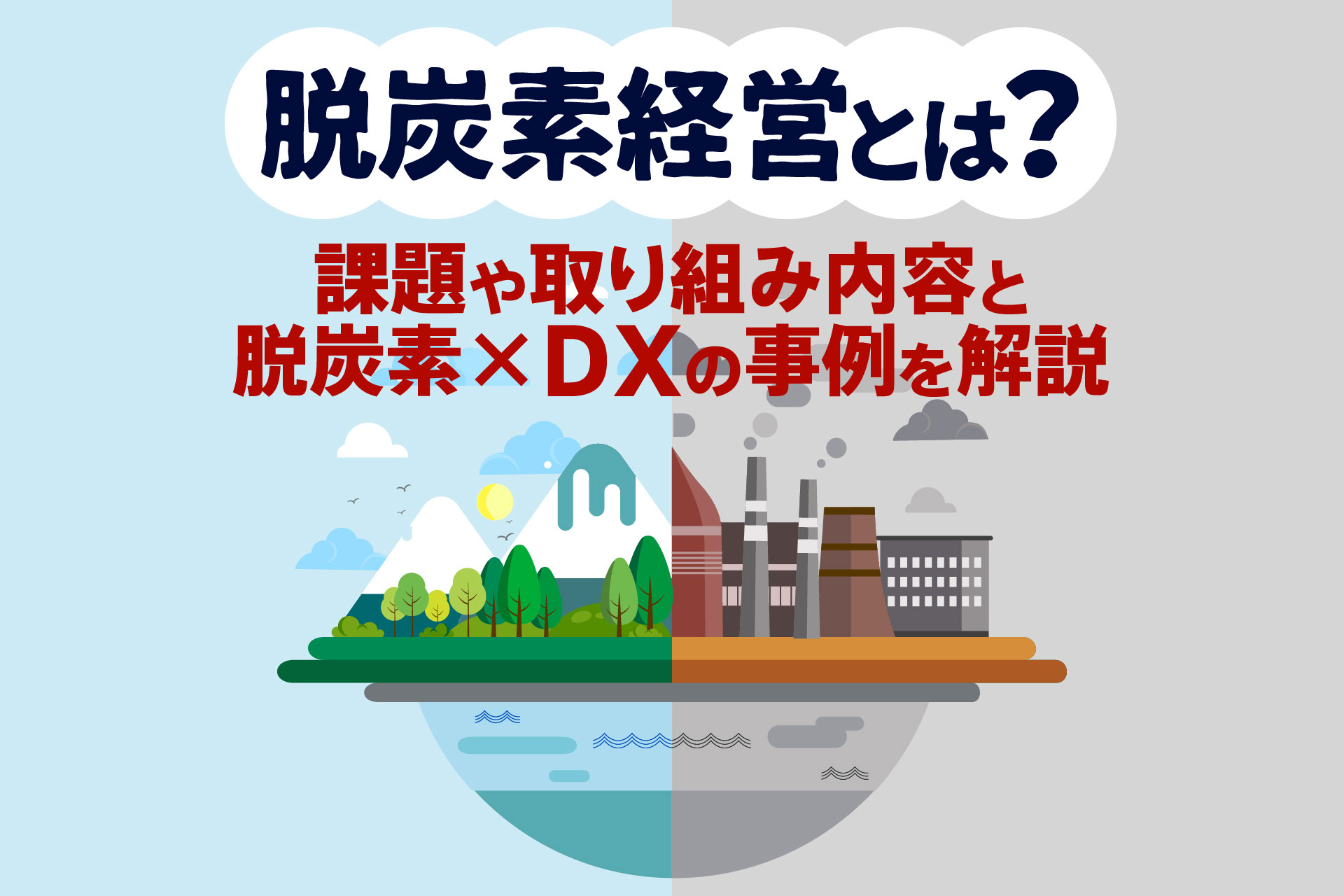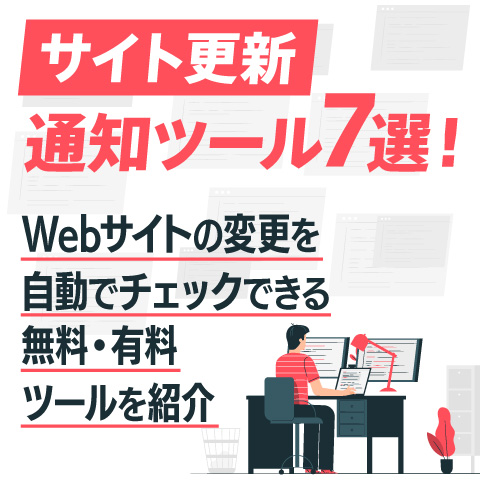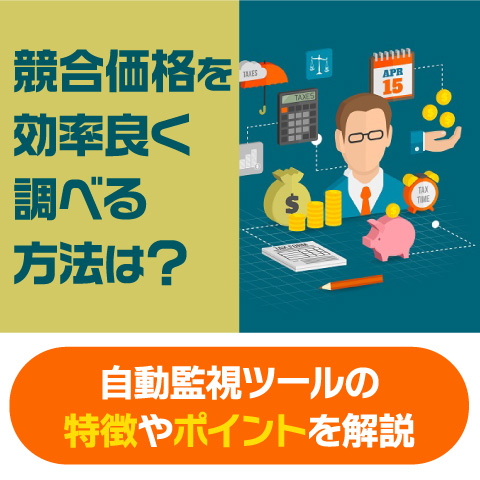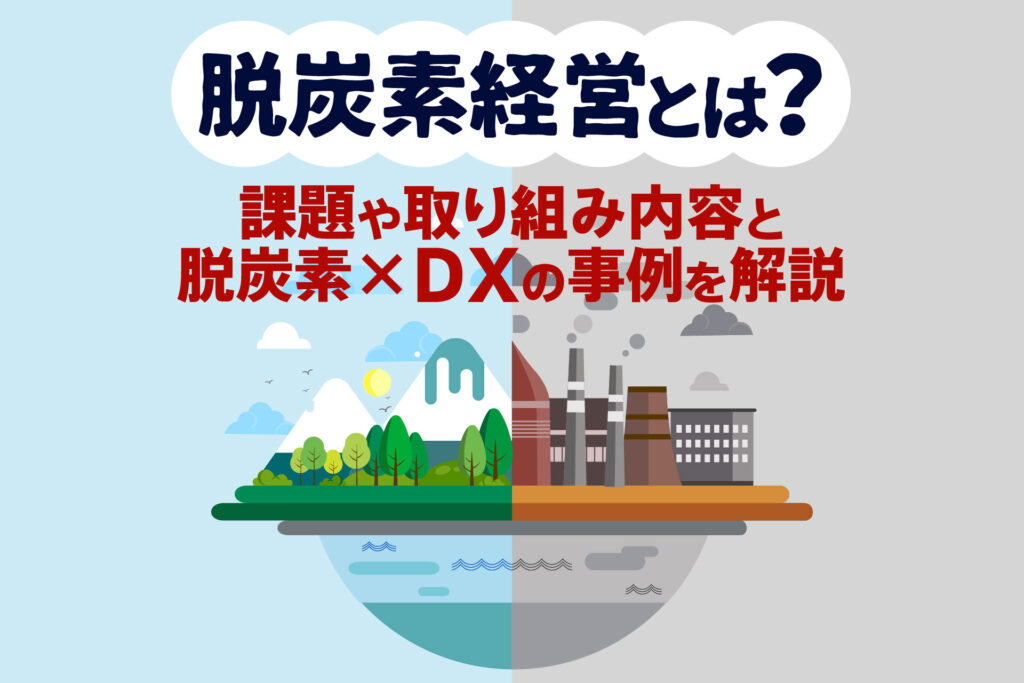
脱炭素経営は、企業活動におけるエネルギーや炭素の排出を可能な限りゼロにしようとする取り組みです。二酸化炭素などエネルギーの使用によって生じるものは、地球温暖化の原因になると判明しています。そのため、国際的に地球温暖化を防ぐための取り組みとして、脱炭素経営が進められるようになりました。近年は少しずつ普及している考え方ではありますが、具体的な取り組みは知られていない部分があります。ただ、脱炭素経営に取り組んでいるかどうかが、企業の評価を大きく左右しかねない状況です。
今回は日本のみならず、グローバル展開を目指している企業の方に向けて、世界的に見てなぜ脱炭素経営が求められているのかを解説します。また、脱炭素を実現するきっかけになり得るDX化についても解説します。
目次
脱炭素経営とは
環境省の定義によると、脱炭素経営とは「気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営」のことを指します。従来の気候変動対策は、企業がCSR活動の一環として実施するものでした。しかし、近年では気候変動対策が経営上の重要な課題だと捉えられるようになっています。そのため、経営戦略に盛り込むなど、全社を挙げて取り組む企業が増えてきました。
そもそも日本では2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロとする目標を掲げています。大手企業を中心に、この目標の達成に向けて行動していて、脱炭素経営はこの一環であると理解してよいでしょう。今までのように企業努力として、気候変動対策を盛り込むのではなく、企業の義務として取り組むようになってきました。
脱炭素経営を行うようになった背景と課題
脱炭素経営が求められる背景には、二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素などの温室効果ガスが、地球の気温を上昇させていることがあります。いわゆる地球温暖化と呼ばれるものであり、気温が上昇し、ハリケーンや豪雨、干ばつなど極端な気象事象が発生しやすくなりました。これらが経済活動に影響することも考えられ、今まで以上に懸念されるようになったのです。
しかも、温暖化は自然と起きるわけではなく、主に産業活動やエネルギー生産における二酸化炭素の排出が大きな影響を与えています。それを踏まえ、温暖化を回避するための手法として、脱炭素経営による持続可能な経済活動の実現が必要とされるようになりました。
脱炭素経営への取り組み
脱炭素経営に向けた取り組みは、大きく分けて3つの柱があります。それぞれについて、詳細と具体的な取り組み事例を解説します。
TCFDの取り組み
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) は、気候関連の財務情報の開示を促進するために設立された国際的なイニシアティブです。企業が気候変動リスクとそれが企業に与える可能性を開示し、それを投資家やステークホルダーなどが評価できるようにすることを推奨しています。主に以下の観点から示すことが求められています。
- 気候変動のリスクと企業に与える可能性を明確にする
- 気候変動が事業や戦略、財務計画に与える影響を示す
- リスクを把握してどのように対処する予定かを提示する
TCFRの取り組み事例を挙げると、アルミニウム加工の株式会社UACJでは、地球温暖化を防ぐために自然エネルギーを導入することで、エネルギーコストが上昇すると予想しています。また、エネルギーの変化により生産力の低下や原材料費の高騰などが発生すると予想しているのです。そして、これらの事象が財務にどのような影響を与えるかどうかも予想しています。また、シナリオは一つではなく、地球温暖化がどの程度進むかによって場合分けされていることも特徴です。これは一例ですが、TCFDではこれから地球温暖化がどのように進むかなどを仮定し、そのような状況でどのような事業活動を展開するかの方針をまずは決めます。その後、それぞれの企業が自ら地球温暖化が事業に与える影響を計算し、その結果として導かれた財務情報を一般に公開していくと捉えましょう。
SBTの取り組み
SBT (Science Based Targets) は、科学に基づいた温室効果ガスの削減目標を設定するためのイニシアティブです。そもそも2015年に締結されたパリ協定では「世界196の国が気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をする」という取り決めがあります。これを実現するために、科学的な観点からどの程度の温室効果ガス排出量に抑えれば良いかを算出したものです。
SBTに加盟する企業は、事前に定められた認定基準を満たすように、温室効果ガスの削減目標を設定して認定を依頼できます。その内容が認められれば、SBTから認定を受けられる仕組みであり、日本では2024年2月時点で920社以上がSBTに参加している状況です。
RE100の取り組み
RE100とは、企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブで、世界や日本の企業が参加しています。世界のエネルギーを再生可能エネルギーへと変化させることで、クリーン経済を生み出そうとする取り組みです。2050年までに再生可能エネルギーへの置き換えを目指す企業の集団を指すと考えましょう。
また、RE100と似たキーワードとしてEP100とEV100も存在します。EP100は事業のエネルギー効率を100%増しにする(つまり2倍にする)ことで、今までと同じ生産量を保ちつつ、脱炭素を目指すものです。また、EV100は自動車をすべて電気自動車に置き換えようとする取り組みを指します。EP100とEV100は知名度がやや低く取り組みしている企業も現時点では限られていますが、こちらも抑えておきましょう。
脱炭素経営を行うメリット
脱炭素経営を実施するメリットは以下のとおりです。
市場での競争力を高められる
脱炭素経営により市場での競争力を高めることが可能です。近年は、気候変動対策に取り組む企業が、消費者や投資家から評価されやすく、必然的に競争力が高まります。また、脱炭素経営を重視する消費者やESG投資の拡大により、環境に配慮した製品やサービスを提供することで、資金調達なども実現しやすいと考えられるのです。
将来的には規制が今まで以上に厳しくなると考えられます。それを見据え、早期に脱炭素化を進めることで、将来的なコストを低減できる点も競争力の向上に役立つでしょう。
企業イメージが向上する
脱炭素経営に積極的に取り組むことで「社会に貢献している企業」と認識してもらいやすくなるでしょう。これにより、消費者などからの信頼を獲得できると考えられます。そして、企業のイメージやブランド価値が向上することで、売上の増加や人材の確保にも繋げられるはずです。
近年はWebの発達によりプラスのイメージもマイナスのイメージも、簡単に拡散されます。そのような状況で、脱炭素経営に取り組むというプラスの要素を積極的に活用することが重要です。
エネルギーコストが低減する
再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の改善は、中長期的なエネルギーコストの削減につながります。例えば、初期投資は必要ですが、再生可能エネルギーを導入することでエネルギーコストが低減するでしょう。現状、暫定的にコストが高い部分はありますが、将来的には既存のエネルギーコストと逆転すると予想されます。
社員のモチベーションが高まる
脱炭素経営など環境保護などへ積極的に取り組む姿勢を示すと、モチベーションが高まる可能性があります。近年は環境問題に関心を持つ従業員も多く、企業としての取り組みが満足度などに影響しがちです。また、社内での環境活動やCSR活動などを開催すれば、社員同士がコミュニケーションを取るきっかけづくりとなるでしょう。チームワークが強化され、これもモチベーションが高まる理由となるのです。
脱炭素とDXの関係性
脱炭素はDXと関係性が深いものです。具体的にどのような関係性が見られるか解説します。
テクノロジーの発展にはエネルギー(炭素)が必須
一般的にテクノロジーの発展はエネルギー消費が必須条件として伴います。例えば、新しい技術やインフラの構築や運用には大量のエネルギーが必要です。そのため、ITを活用するためのデータセンターやクラウドサービスなど、情報通信分野ではエネルギー消費が急増していると考えられます。半導体製造や電子機器の生産自体もエネルギーを排出する行為であり、総じてエネルギーを消費しているでしょう。
これは一例ですが、テクノロジーの発展にはエネルギー(炭素)が必須であると考えられます。そのため、脱酸素に向けてエネルギー面の技術革新や炭素排出量を減らすための取り組みが必要なのです。
DXによる効率化で消費エネルギーを削減
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の業務プロセスやビジネスモデルをデジタル技術によって変革する活動です。この過程で自動化や効率化を進めることで、消費エネルギーの削減が期待できます。例えば、紙の業務をデジタル化することで、印刷物を用意するためのエネルギーの削減が可能です。業務を効率化できるだけではなく、消費エネルギーも減らせる取り組みといえます。
また、DXによってデータをリアルタイムに把握できれば、エネルギーを無駄に消費することを避けられるはずです。例えば、製造のトラブルをデータからいち早く検知することで、必要以上に不良品を製造する事態を避けられます。
総じて、DXは業務の効率化を実現しつつ消費エネルギーを削減できる手段といえるでしょう。積極的にデジタル化を進めることで、脱酸素経営を実現しやすくなるのです。
脱炭素につながる作業効率化のDX
脱炭素を進める方法はいくつもありますが、その中にDXにより業務を効率化するというものが挙げられます。
専用ツールによる業務時間の短縮
情報通知ツールのように手作業で実施しているものをDX化すると脱炭素経営に貢献できます。作業時間を大幅に短縮することで、排出してしまう二酸化炭素の量が少なくなります。業務を自動化する方法はいくつもありますが、Webサイトチェックによる情報収集のような手作業の場合は情報通知ツールの活用がおすすめです。専用のツールを活用することで、大幅な業務時間の短縮が可能になります。
弊社のサービスであるサステナビリティ情報通知ツール「サステナモニター」をご利用いただくと、環境やESGに関する最新情報のチェックを自動化で行えます。法令や加入している協会の情報など、国内外問わず登録したURLの内容のチェックが可能です。日々、情報収集に追われているならば、大きく業務を改善できるでしょう。

顧客データの自動分析による市場開拓
顧客について分析する作業は時間を要しやすく、人的リソースやコンピューターの活用という観点でエネルギーを消費します。しかし、顧客データをAIや機械学習技術で自動分析することで、市場開拓の作業の大幅な効率化が可能です。業務に取り掛かる時間を短縮することで、エネルギーの消費を最小限に抑え脱炭素につなげられます。
また、DXによりAIなどを導入し分析の正確性が高まれば、市場開拓におけるミスを軽減できます。分析ミスを繰り返すと、エネルギーを無駄に消費しますが、そのような状況も回避できるのです。
AIによる生産量の算出で製品を安定供給
AIを活用して適切な生産量を算出することで、製品の安定供給が可能です。例えば、過去のデータや市場の動向を踏まえて需要予測の正確性を高めることで、生産計画の最適化を実現できます。過剰生産や供給不足のリスクが軽減され、生産資源やエネルギーの無駄遣いを減らせるのです。
今までも生産量を予測して安定供給を目指す取り組みは続けられていました。しかし、人間が対応している限りはどうしても限界が生じてしまうのです。しかし、DXによりデータやAIを活用できる体制を整えれば、今までよりも良い状況を生み出せます。
脱炭素経営×DXの取り組み事例
脱炭素経営を実現するためにDXへ取り組みしている企業の事例を紹介します。
高砂熱学工業
高砂熱学工業はDXを促進し、建物からさまざまなデータを取得する取り組みを進めています。また、取得したデータを分析し「どのような形でエネルギーが消費されているか」を評価していることが特徴です。実際にエネルギーがどのように消費されるのかという状況を把握した上で、どの部分のエネルギー消費を抑えれば脱炭素に役立つ建物になるかを日々研究しています。例えば、建物の中で熱が籠もるというデータを発見したならば、その熱を空調に活かしたり発電したりする方法を考えるのです。
株式会社関電工
株式会社関電工では、DXによるデータ収集および活用を通じて、持続可能な社会に適した建築物の設計を目指しています。特に単体の建物だけでデータを収集しDXを推進するのではなく、街全体に対してDXを推進しようとしていることが特徴です。例えば、建物だけではなく、建物をつなぐ通路(道路)や建物間にある広場などのエネルギー状況をまとめて収集し、どのように分配すれば街全体で脱炭素を促進できるかなどを研究しています。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ株式会社は、自動車製造時の電気使用量を抑えることで、脱炭素経営を目指しています。最終的には、工場からの二酸化炭素排出量をゼロにするなど、自動車生産という大規模な施設を抱えながら非常に高い目標を掲げている事業です。
現状の代表的な取り組みとしては、工場で使用する電気の量を可能な限り減らすものを軸としています。例えば、製造に利用する機械を見直すことで最低限の電力に抑えるなどです。また、ソーラーパネルを利用した発電によって電気を生み出すなど、化石燃料に頼らない電力の創出によっても脱炭素経営を進めています。
キッコーマングループ
キッコーマングループでは、生産に利用する機器の更新やメンテナンスタイミングを見直すことで、脱炭素経営を実現しています。例えば、製造機器に関するデータを集めて分析し、必要最低限の部品交換やメンテナンス回数に抑えられるような取り組みを進めているのです。必要以上に部品を交換すると、部品製造や交換作業で無駄な炭素を排出してしまうため、これを削減しています。
また、商品の流通過程においてはシステムで効率の良いタイミングを計算し、トラックからの二酸化炭素排出を最小限に抑える方針を取り入れています。ガソリン車は温室効果ガスを排出してしまうため、これを抑止して脱炭素化を目指している企業です。
まとめ
地球温暖化が加速していることなどから、世界的に脱炭素経営が重視されています。どのような取り組みをしているかが企業の価値を採用するぐらいであり、大手企業を中心に中小企業でも進められている状況です。今後はさらに重要な要素になると予想され、DXによる業務の効率化などによって、二酸化炭素の排出を抑えなければなりません。
DXを進める方法はいくつもありますが、その中でもまずは手作業を自動化することをおすすめします。手作業の自動化はスモールスタートしやすいDXともいえるでしょう。例えば、Webサイトのチェックや法令チェック、加入している団体のお知らせをキャッチするようなチェック作業は自動化が可能です。弊社のサステナモニターならば、世界各国の環境やESGに関わる情報を自動で収集し関係者へ通知できます。例えば、既存の法令ツールでは見られない海外の情報や協会の情報を知ることができます。また、新しい脱炭素につながる情報や競合他社の実施状況なども知ることができ、今後脱炭素経営を進めていくうえでも役に立つツールとなるでしょう。