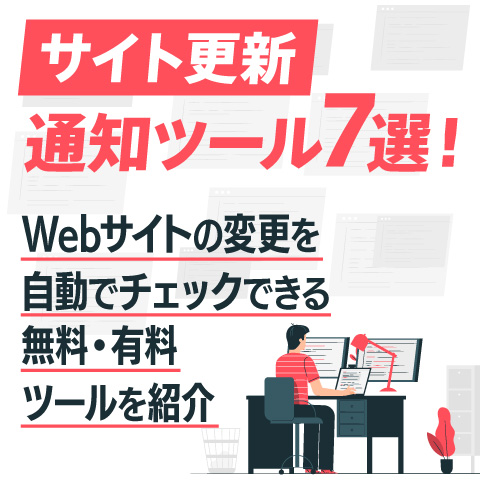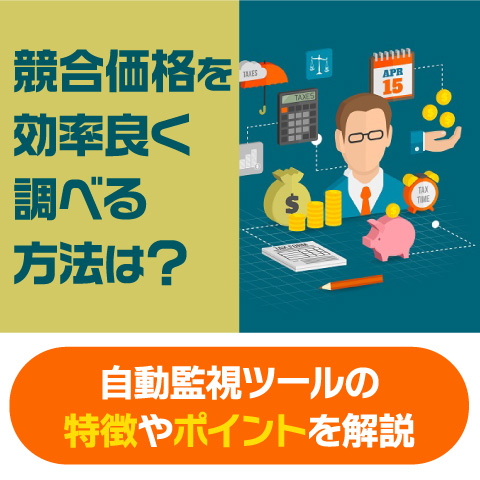近年は、カーボンニュートラルというキーワードを耳にすることが増えたのではないでしょうか。地球温暖化対策の一環として注目されている取り組みであり、日本はもちろん世界中で意識されています。
ただ、耳にする機会が増えたキーワードではあるものの、具体的に「カーボンニュートラルがどのようなものであるか」を理解できていない人は多いのではないでしょう。今回はカーボンニュートラルの概要から、世界に目を向けどのような取り組みが実施されているか、日本の企業は世界と足並みを揃えるためにどのようなことを意識しなければならないかを解説します。
カーボンニュートラルとは
最初にカーボンニュートラルとは、どのような取り組みを指すのかを解説します。
温室効果ガスの低減に関する取り組み
カーボンニュートラルとは、温室効果ガス(GHG)の排出を全体としてゼロにする取り組みを指します。「排出を全体としてゼロにする」とは、温室効果ガスの「排出量」から植林等による「吸収量」を差し引いて、合計をゼロにすることです。「実質ゼロ」や「ネットゼロ」と呼ばれることもあります。
なお「温室効果ガス=二酸化炭素(CO2)」とのイメージが強くありますが、実際には二酸化炭素だけではなく、メタンなどの気体も含みます。ただ、日本では8割以上の発電や経済活動などのエネルギー起源が二酸化炭素であるため、日本ではエネルギー分野で排出力をゼロにする取り組みが特に重要視されているのです。
2015年のパリ協定での決定事項
カーボンニュートラルは、2015年に開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)における「パリ協定」が根拠となっています。パリ協定は、京都議定書に代わる温室効果ガス排出削減等のための国際的な取り組みで、例えば以下の事項が定められました。
- 世界共通の長期目標として平均気温の情報上限を2℃に目標設定
- 同上について1.5℃に抑える努力を追求すること
- 主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること
- 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること
科学的な根拠を踏まえてこのような基準が定められ、先進国を中心に、これらの基準を満たすことが求められています。
「2050年カーボンニュートラル」の実現
カーボンニュートラルの実現は、2050年を一つの区切りとしていて、これを「2050年カーボンニュートラル」と呼ぶことがあります。日本並みならず、海外でも横並びでカーボンニュートラルが展開され、2030年や2050年をマイルストーンとしているのです。
ただ、日本における2050年カーボンニュートラルとは、2020年10月の総理所信表明において、脱炭素社会の実現を目指す宣言を実施したことを指すことがあります。日本における2050年と世界における2050年は少々意味合いが異なってくるため、そこは簡単にでも理解しておくとよいでしょう。
鍵を握る「脱炭素」「カーボンバジェット」「カーボンオフセット」
カーボンニュートラルと密接に関連するキーワードとして、「脱炭素」「カーボンバジェット」「カーボンオフセット」が挙げられます。それぞれの意味を正確に理解することが重要です。
脱炭素
「脱炭素」は、カーボンニュートラルとは異なり、二酸化炭素の排出量を完全になくしてしまう取り組みを指します。一方、カーボンニュートラルは、排出された二酸化炭素を吸収や相殺によって実質的にゼロにすることを目指しています。このように、「排出量を相殺する」か「排出量そのものを削減する」という観点で、両者には大きな違いがあります。
カーボンバジェット
「カーボンバジェット」は、地球温暖化による気温上昇を一定の範囲内に抑えるために、許容される二酸化炭素排出の上限を示す概念です。簡単に言えば、「二酸化炭素排出の残高」と考えることができます。
カーボンオフセット
「カーボンオフセット」は、日常生活や経済活動で避けられない二酸化炭素排出を踏まえ、排出量を可能な限り削減したうえで、残りの排出分を別の活動で埋め合わせる取り組みを指します。、具体例として、排出量に見合った植林事業への投資などが挙げられます。これにより、二酸化炭素吸収を促進し、排出量を補完します。
日本や海外でのカーボンニュートラルの取り組み
日本や海外では、広いカーボンニュートラルの取り組みが見られるため、日本、アメリカ、中国について解説します。
日本における取り組みと支援
日本では、環境省を中心にカーボンニュートラルの実現に向けた多様な取り組みが行われています。その一環として「脱炭素ポータル」と呼ばれる専用Webサイトが開設され、企業が必要とする具体的な知識や施策が紹介されています。また、カーボンニュートラル推進に役立つ助成金情報も提供されています。
例えば、ビルの建築や改築を検討する企業向けに、エネルギー効率を高めるための施策が提案されています。具体的には、遮熱性の高い壁や窓の回収が推進され、外気の影響を軽減することで冷暖房の使用量を削減し、温室効果ガスの排出量を減らす取り組みが挙げられます。
このような施策に関連する助成金も併せて紹介されています。
アメリカの目標と取り組み
アメリカでは、カーボンニュートラルの実現を重要な政策と位置づけ、多方面での取り組みを展開していますが、2024年11月の大統領選挙で再び当選したトランプ氏は、バイデン政権が進めてきた気候変動対策を大きく転換する方針を示しています。
具体的には、石油や天然ガスなどの化石燃料の生産を拡大し、国内エネルギー産業の活性化を重視しています。また、気候変動の国際枠組みである「パリ協定」から再度離脱する意向を表明しました。
さらに、ゼロエミッション車(EV)の普及に対する強制的な目標や補助金を撤廃し、従来型エンジン車の自由な市場競争を促す方針を明らかにしています。これにより、気候変動政策は州政府や企業などの自主的な取り組みに委ねられる可能性が高まっています。
トランプ政権は「エネルギー独立」を再び強調し、気候変動への対応よりも経済成長を優先する姿勢を取るとみられています。
中国の目標と取り組み
中国は、2030年までのカーボンピークアウト(排出量の最高値到達)と2060年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げています。この目標達成に向けて、多くの政策が導入されており、現在は2030年のピークアウトに向けた取り組みが進行中です。
具体的には、化石燃料中心の産業構造から再生可能エネルギーへの転換を推進し、2030年以降は段階的に排出量を削減する計画です。また、人口の多さを考慮し、住宅関連の政策にも注力しています。新規建築物には、建築資材の使用を最小限に抑え、廃棄物削減を考慮したカーボンニュートラル基準を適用しています。
カーボンニュートラルを取り組む方法
カーボンニュートラルに取り組むためには、3つの観点から理解が必要です。
カーボンニュートラルに関連する規則や法律について理解する
日本や海外でカーボンニュートラルを展開したいと考えているならば、関連する規則や法律について理解し情報を追うことが大切です。まずは必要な情報を収集し、その中で自分たちに関係がある内容の理解を深めていくことが求められます。
しかし、カーボンニュートラルに関連する規則や法律は多様なWebサイトなどに記載されているため、情報更新を常に手作業で追い続けることは難しいでしょう。そのため、情報収集にあたってはツールの活用も重要です。
例えば、弊社が提供する「サステナモニター」では、カーボンニュートラルに関連するサイトをリストから選択するだけで、最新情報を通知します。国内外のWebサイトを様々な目的に合わせて自由に監視できるため、幅広い情報の収集を一元化できます。グループ設定やキーワード設定により、必要な人に必要な情報を通知することも可能です。部署を超えても活用される情報通知ツールとしておすすめです。
実際の取り組み事例を参考にする
これからカーボンニュートラルに取り組みたいと考えているならば、実際にどのような取り組みがあるか。確認してみると良いでしょう。日本から海外へ進出している企業の事例はもちろん、進出を予定している国の現地でのような取り組み事例があるかも確認しておくことをおすすめします。それらの事例を完璧に真似することは難しいですが「どのような取り組みが求められているのか」や「どのような取り組みが受け入れられやすいのか」などを判断できるからです。
支援策など金銭的な負担を軽減する方法を知る
カーボンニュートラルの取り組みにあたっては、金銭的な負担も生じることも考えられます。そこで、負担を軽減するために、国が支援している補助金がないかチェックするとよいでしょう。例えば、日本では、中小企業を中心とした以下のカーボンニュートラル対策の支援が用意されています。
- 省エネ補助金
- 脱炭素ビルリノベ事業
- CEV補助金
- 省エネ設備投資利子補給金
- 環境・エネルギー対策資金
このように、補助金や助成金、融資の優遇などの支援を積極的に活用することで、金銭的な負担を大きく抑えられます。
上記は日本の支援ですが、アメリカでは「工業・食品セクター脱炭素化」としての支援が2024年3月に決定しました。このように、多くの国で様々な支援が用意されているため、海外に拠点がある場合は、現地でのカーボンニュートラルを目指す際には、情報収集が重要です。なお、情報収集にあたっては、政府機関が公表する情報などを素早く確認しなければなりません。条例などを利用して、最新情報を自動的に収集できるようにすればいいでしょう。
企業での取り組み事例
カーボンニュートラルの企業での具体的な取り組み事例を紹介します。
三菱重工グループ
三菱重工およびその関連会社は、『MISSION NET ZERO』と呼ばれる取り組みを進めています。世界的に見ても、製造業のリーダー企業であることから、積極的に二酸化炭素の排出量を減らし、2040年までにネットゼロにする目標を定めているのです。
例えば、製造過程における二酸化炭素の排出量を減らすだけではなく、二酸化炭素を回収したり、別の用途に活用する技術の開発などにも取り組んでいます。特に三菱重工では、製品などを輸送する部分にも多くの二酸化炭素が関連することに注目し、他の企業とは異なる観点から、カーボンニュートラル社会を実現しようとしていることが特徴です。
加えて、カーボンニュートラルに必要な事業や製品、技術などを保有していること等も注目しておきましょう。例えば、二酸化炭素を溜め込むプラントを保有して、必要なときに活用できるようにしています。事前に回収しておくことで、大気中の二酸化炭素を減らし温暖化の抑止に貢献しているのです。
セコムグループ
セコムグループでは、サプライチェーン全体で二酸化炭素の削減に取り組んでいます。2050年までに排出ゼロを目指し、2030年までには段階的な削減を宣言しているのです。具体的な取り組みとしては、社内で利用する設備を省エネ対象製品に置き換えたり、新しく建築する拠点は環境基準へ適合したものを建てるなどです。
また、セコム株式会社は海外にも拠点を持ち、海外でも日本と同様にカーボンニュートラルが進められています。例えば、オーストラリアでは車両を電気自動車に置き換えたり、オフィスの電力使用量を削減するために省エネ機器の導入を進めたりしているのです。日本での取り組みを海外にも横展開している企業の事例です。
三井不動産グループ
三井不動産グループは、地球温暖化を防止するために、2030年度までに40%の温室効果ガス削減を掲げています。特徴的な取り組みとして、新築や既存物件における環境性能の向上や、建築時の二酸化炭素排出量の削減が挙げられるでしょう。多くの不動産を手がける企業として技術力の向上など企業努力を重ね、カーボンニュートラルを推進していることが特徴です。また、グリーンエネルギーの活用なども進め、個人も企業もカーボンニュートラルへ貢献できるような環境を整えてくれています。
加えて、三井不動産グループは中国やアジア圏にも進出していて、このような技術を海外にも展開しています。日本と海外では基準が少し違いますが、それぞれの国で、カーボンニュートラルに適合した物件を提供しているのです。幅広い居住用物件やテナントビルなどを手がけるにあたって、それぞれの国や地域で二酸化炭素の排出量を抑えています。
三井住友フィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループは、2030年までに自社の温室効果ガス排出量をネットゼロにする目標を掲げています。他社が2050年までの目標を掲げていることと比較すると、速いスピードで説明しているといえるでしょう。
また、グローバルに投資している企業として、ポートフォリオ GHGでのネットゼロを進めています。これは簡単にまとめると、投資先の企業が温室効果ガスの削減に成功した場合、投資した企業の実績として扱っても良いものです。三井住友フィナンシャルグループは、世界中の電気や石油、石炭など、エネルギー関連の事業に多く投資しているため、これらにおいてもカーボンニュートラルを推進しています。
株式会社ブリヂストン
株式会社ブリヂストンは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、「サステナビリティビジネス構想」をすすめています。いくつもの観点から推進されていますが、エネルギー効率の改善や、再生可能エネルギーの導入、社内カーボンプライシングが中心です。
まず、生産拠点でのエネルギー効率の改善を積極的に進めていて、エネルギー消費量の削減や生産性の向上を進めています。例えば、エネルギー効率の良い設備に置き換えることによって、消費エネルギーを抑えながら今までと同じ生産能力を担保しているのです。また、省エネルギー設備や、太陽光発電装置などを積極的に導入し、全社的にカーボンニュートラルの実現に向かって進んでいます。
また、欧州や中国など世界中に拠点を持ち、これらにおいては再生可能エネルギーを積極的に導入しています。他にも、研究センターなど非生産拠点においても、再生可能エネルギーの導入を進め、製造の場ではなくともカーボンニュートラルを頭に入れていることが特徴です。
まとめ
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質的にゼロとする考え方です。日本国内だけでなく海外でも、2030年や2050年を目標に段階的に進められています。特に製造業は温室効果ガスの排出が多い分野であるため、カーボンニュートラルに向けた積極的な対応が期待されます。また、海外進出を目指す企業においては、現地の規制や方針に適合する対応が求められます。
現状、日本を含む多くの国々でカーボンニュートラル実現に向けた基本方針が策定されており、企業はこれに沿って経済活動を行う必要があります。
担当者がカーボンニュートラルを推進するためには、各国が提供する情報を正確に収集することが重要です。カーボンニュートラルの方針や理念に加え、推進に利用可能な補助金や助成金などの制度を把握することも欠かせません。ただし、これらの情報は頻繁に更新されるため、人力による情報収集には限界があります。そのため、効率的に情報を収集できるツールの導入が良いでしょう。
弊社が提供するサステナモニターなら、リストからカーボンニュートラルの取り組みに必要な情報を選択するだけで最新情報をお知らせします。日本のみならず海外のサイトも登録が可能であるため、リストにないサイトを登録し、自社独自の情報収集ツールとすることも可能です。カーボンニュートラルに関する情報をツールで漏れなく確認しましょう。