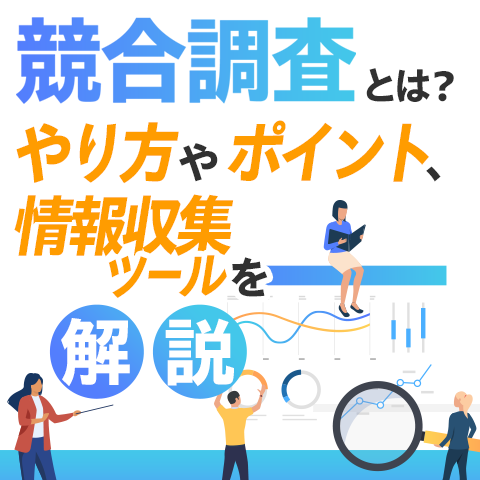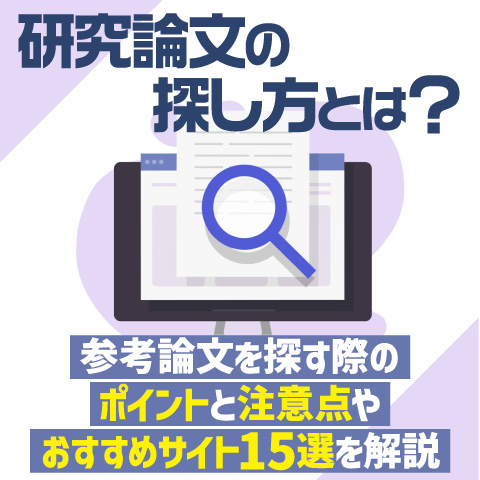論文を書く際には、さまざまなデータを収集しなければなりません。他の研究者が執筆した論文はもちろん、Webサイトに掲載されている情報や、ときにはアンケートやインタビューの実施も必要になることがあります。収集すべきデータは多岐にわたりますが、特に時間がかかりやすいのが、Web上にあるデータの収集です。
近年はインターネット上に膨大な情報が公開されているため、Web上のデータを手作業で収集することが困難になりつつあります。実際に、手作業での情報収集に限界を感じている人も多いでしょう。今回は、論文執筆のために効率よくデータを収集したい方に向けて、効果的なデータ収集の方法を解説します。
目次
論文作成のためにデータ収集する際によくある課題
論文作成ではデータ収集が必要です。このとき、よくある課題をピックアップしてみました。
欲しいデータが見つからない・分散している
論文のテーマに合致するデータがなかなか見つからない、または複数のサイトや機関に分散して存在しているという課題が多くあるでしょう。例えば、大学ごとに研究成果の掲載場所が異なっていたり、各教授が個別に公開しているケースもあります。これらを細かく調べてデータ収集しなければばりません。
さらに、Google Scholarや論文検索サイトを使っても、目的の情報にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。また、検索精度が十分であるとはいえず、引用文献などを何度も辿ってデータを探すことが求められます。
調査の対象が多くデータ収集に時間を取られる
特に横断的なテーマの研究では、調査対象が複数の分野・機関にまたがることが考えられます。この場合、調査対象が膨大となり、データ収集に多くの時間を取られてしまうのです。学会発表、プレプリント、大学の研究報告書など調査対象が増えると、相当な時間と労力が求められます。
また、時間を取られることは「論文作成のスケジュール全体に影響を与える」という課題にも繋がりかねません。データ収集に負荷がかかり、データや論文の質が下がるなど、二次的・三次的な問題を引き起こす可能性もあります。
提供されるデータの形式や品質がまばらである
収集したデータが一貫した形式で提供されていないことも、研究者を悩ませる大きな課題です。Web上には、CSV、PDF、HTML、画像ファイルなど、さまざまな形式で情報が存在していたり、表記方法や表記ゆれが異なっていることがあります。これらをまとめて使用するために、データ変換や整形の手間が生じるのです。
そのため、単にデータを集めるだけでは、品質の悪いデータになってしまうのです。このままでは分析や比較の際に障害となり、研究の精度が下がるという課題につながります。
論文のための3つのデータ収集方法
論文のためにデータ収集を効率化する方法の例を3つ紹介します。
| 方法 | メリット | デメリット |
| 自社スクリプトを作成 | 柔軟な制御ができ、繰り返し利用に強い | 開発スキルが必要で、保守・トラブル対応に時間がかかる |
| オープンデータを活用 | 法的に安全で、信頼性が高く、導入も容易 | 対象分野や必要項目が限られていて、欲しい情報が得られない場合がある |
| スクレイピング代行を利用 | 複数サイト・多言語にも対応可能見積書・納品書の発行に対応しており、研究費・補助金での利用も可能 | 仕様の整理や要件定義が必要 |
自社スクリプトを作成する(Pythonなど)
PythonやRなどのプログラミング言語を用いて、自分でスクリプトを作成する方法があります。いろいろな方法がWebで公開されているため、これらを参考にすることで開発できます。自分自身で作成するため、収集対象や出力形式を制御しやすくなります。
一方で、プログラミングの知識やHTML構造の理解が必須で、一定のスキルが無ければ実現できません。また、サイト構造の変化への対応やエラー処理など、継続的な維持・保守も求められます。「一度作成すれば終わり」というわけではなく、想像以上に負担が生じるかもしれません。
オープンデータを活用する
PubMed, arXiv, CrossRefなど、政府機関や学会、プレプリントサーバーが提供するオープンデータを活用する人は多いでしょう。CSV形式での提供やデータ取得のAPIが用意されているため、安心して信頼性の高いデータを収集できます。専門知識がなくても一定量のデータを容易に入手できるのです。
その反面、収集できるデータの種類が限られてしまうなど、いくつもの制約があります。また、細かいメタデータが省略されているなど、欲しい情報が得られないリスクもあるのです。
スクレイピング代行サービスを利用する
スクレイピング代行サービスは、技術や時間のない研究者でも、データを効率よく収集できる方法です。複数のWebサイトにまたがっていたり、多言語ページが混在していたりするような調査でも、柔軟に対応してもらえます。さらに、見積書・納品書の発行にも対応している業者が多く、研究費や補助金を活用して依頼できることもメリットです。
ただ、代行を依頼するには「どのサイトから、どのような情報を、どの形式で取得するか」といった仕様や要件を明確にする必要があります。
論文データ収集の効率化のカギは「スクレイピング」
論文データの収集を効率化するためには「スクレイピング」がカギを握ります。
スクレイピングとは?研究者が知っておくべき基礎知識
スクレイピングは、Webページの内容を解析し、特定の情報を抽出する技術です。例えば、論文のタイトルや著者、発行年、用紙名などをピンポイントで抽出できます。一般的には、PythonやRなどの言語を用いたスクリプトで、ページ内の構造をたどって必要なデータを取得するのです。
ただ、便利な仕組みである一方で、注意すべき点もあります。たとえば、一部のサイトでは利用規約によってスクレイピングが禁止されているのです。また、アクセスが集中するとWebページの応答が遅くなり、悪質な攻撃と見なされるリスクも挙げられます。他にも、ページ構造が変更されると、それまで正常に動作していたスクリプトが動かなくなるなどのトラブルも発生しやすいのです。
研究でスクレイピングを利用する際は、法的・倫理的に問題がないかを評価する必要があります。また、継続的に運用できる体制があるかどうかも考慮することがポイントです。
なぜ今、研究現場で注目されているのか
スクレイピングが研究者の間で注目されている背景には、研究環境の変化や技術の進歩が挙げられます。近年、プレプリントサーバーやオープンアクセス論文の増加により、学術情報がWeb上で公開される機会が増えました。これにより、従来の情報収集手段だけでなく、Web上の情報を幅広く収集する必要性が高まっているのです。
また、Pythonなどのプログラミング言語を扱える研究者が増えていることも、スクレイピングの普及を後押ししています。プログラミングができれば、手作業では実現できない量の情報を、迅速に収集できるようになるからです。
そのため、研究現場では、研究者自らがプログラミングを行い、気軽に情報を収集するスタイルが広がりつつあります。調査フェーズにおける新たな手段として、スクレイピングは今後ますます活用されていくでしょう。
研究機関でのスクレイピング活用事例
実際に、研究機関でスクレイピングを活用した事例を紹介します。
事例1:大学研究室による論文データの一括収集
大学研究室で利用する「Web辞書サービス」に掲載されているデータを、一括で取得して整理した事例があります。Web辞書サービスには膨大な用語が掲載され、これらを手作業で収集することは現実的ではありません。そこで、スクレイピングでデータを収集し、必要な形式へ加工、フォルダも要望にお応えする形で納品しました。
事例2:リサーチ会社による経済情報の自動収集
リサーチ会社では、大量の情報を収集し、その内容を研究、クライアントに提供するという活動を続けています。蓄積されたデータを活用することはもちろん、何十万件ものデータを新たに取得することもある状況です。この大量のデータ収集において、スクレイピング代行を活用いただいています。
スクレイピング代行を使うべき4つのケース
スクレイピングを実施する際は、自身で行うのではなく、代行サービスの利用がおすすめです。具体的に、どのようなケースで代行サービスに依頼すればよいのかを紹介します。
手作業でのデータ整理に時間を要している
手作業でのデータ整理に時間を要している場合には、スクレイピング代行サービスの活用が効果的です。代行サービスに依頼することで、繰り返し発生するコピー作業や、手動での転記作業を一気にアウトソーシングできます。特に、何十件・何百件もの論文情報を収集する場面では、代行を利用することで、膨大な時間を研究そのものに充てられるようになるでしょう。限られた研究時間を本来の分析や考察に集中させるために、非常に有効な手段です。
同じようなデータ収集が毎年・毎学期で発生している
同じようなデータ収集を繰り返している場合にも、スクレイピング代行サービスは非常に有効です。初回は取得対象やサイト構造に応じた設計・実装が必要ですが、一度仕組みを構築すれば、基本的には同様のデータ収集を効率的に行えるようになります。たとえば、論文のタイトルや学会発表一覧など、毎年似た構成の情報を繰り返し収集する場面におすすめです。毎年、毎学期でデータ収集の内容に大きな変化がないならば、特に効果を発揮します。
ただし、注意が必要なのは、スクレイピングは一度構築すれば終わりというものではないという点です。多くのWebサイトは定期的に構造が変更されるため、それに応じて仕組みの調整・再構築が必要になることがあります。また、データの正確性や安定性を保つためにも、運用後のメンテナンスは欠かせません。
そのため、スクレイピング代行サービスは「手間をゼロにするもの」ではなく、「設計と運用をプロに任せることで、効率と品質を高めるための手段」としてご活用いただくのが最適です。
データの形式がバラバラで困っている
研究に活用したいものの、データの形式がバラバラな場合にも、スクレイピング代行サービスは有効です。
Web上のデータはPDF、HTML、Excelなど形式がさまざまで、統一するのに手間がかかります。スクレイピング代行サービスなら、必要な情報を抽出し、CSVやExcelなど使いやすい形式に変換して提供可能です。これにより、収集後すぐに分析へ移れるようになります。
複数のデータを一覧化・比較したい
異なるサイトから同じ種類の情報を集めて一覧化・比較したい場合も、スクレイピング代行サービスが有効です。複数の出典からのデータを共通のフォーマットに整えてくれるため、比較しやすくなり、傾向分析などの作業がスムーズに進みます。
例えば、複数の大学の研究発表テーマをまとめたいときや、学会ごとの発表数を集計したいときなど、異なるWebサイトからそれぞれデータの収集が必要です。また、それらを加工することで、一覧化や比較ができます。本質的な部分に至る前に労力が必要ですが、代行サービスならばこの労力が掛かりません。
依頼時に知っておくべき3つのポイント
データ収集の依頼時に知っておくべきポイントをまとめると以下の通りです。
取得したい情報の“使い道”を明確にしておく
データを収集する際には、必ずその「使い道」を明確にしておきましょう。どのような用途でデータを使用するかによって、収集すべきデータの内容や粒度、そして形式に大きな違いが生じます。
たとえば、論文情報を集める場合でも、以下のように目的に応じた違いが考えられます。
- 論文のタイトルだけをテキスト形式で収集する
- 論文のタイトル、著者、公開年月日などをExcel形式でまとめる
- DOI(デジタルオブジェクト識別子)を収集し、公開日を加工してからExcelに整理する
このように、同じ「データ収集」といっても、その中身には大きな違いがあります。したがって、最初に用途を明確にし、目的に応じて過不足のない項目を、適切な形式で収集することが重要です。
利用規約や著作権など、法的観点が気になる場合は事前に確認をしておく
インターネット上に掲載されているデータには、それぞれに様々な権利が認められています。これらの権利を侵害して法的なトラブルが生じないようにしなければなりません。事前に、利用規約や各データの著作権を確認することが重要です。多くのWebサイトは、データに関連する権利について明記しているため、それを踏まえてデータ収集を依頼できるか判断しましょう。
なお、専門的な用語が含まれており、自分自身で正確に判断するのが難しいこともあります。このときは、スクレイピング代行サービスに改めて確認してもらうべきです。もし、リスクがあると判断された場合は、無理に進めず、別のデータソースを選定するようにしましょう。
成果物イメージを共有することで、要件がスムーズに固まる
スクレイピング代行でデータ収集を依頼する際は、初回の要件のすり合わせが必要です。その際に、成果物イメージを事前に用意しておくと、やり取りがスムーズになります。
たとえば、Excel形式での納品を希望する場合には、予めヘッダー項目や並び順を決めたサンプルを用意しておくのがおすすめです。収集してほしい内容やデータ形式も明記すれば、担当者が意図を正確に把握しやすくなります。
こうした準備により、「どの列に」「どの形式で」データが必要かが明確になり、要件が早く固まり、納品物の精度も高めることができます。
よくある質問(FAQ)
スクレイピングを外部へ依頼する際に、よくある質問をまとめています。
Q.自分でもPythonでスクレイピングできるのですが、外注するメリットはありますか?
PythonのBeautifulSoupやSeleniumなどを用いることで、個人でもある程度のスクレイピングは実装できます。ただ、実際にやってみると、本質的な部分では無いところに、時間を取られることが多くあります。例えば、以下のような問題がおきます。
- 複数ページにまたがるデータ取得が成功しない(ページネーション)
- JavaScriptで動的に表示される情報が取得できない
- 文字コードの処理やエンコーディング問題で文字化けする
- エラー処理・例外対応・サーバーへの負荷配慮ができない
- サイト構造変更時のメンテナンスが継続的に求められる
- メールによる送付やクラウド保存などデータの出力がうまくいかない
- セキュリティが厳しく個人での実装には限界を感じる
外注することで、これらの煩雑な作業から解放されます。結果、「自分にしかできない研究・分析」に集中できる環境が手に入るのです。
Q.費用はどのくらいかかりますか?研究費での対応は可能ですか?
金額は状況によって変化しますが、目安は下記です。
- 継続的なご依頼:1サイト5万円~+初期費用
- 単発でのご依頼:1サイト10万円~
なお、費用は、主に以下の要素で決まります。
- 対象サイト数(1つか複数か)
- ページ数や取得データ件数のボリューム
- 抽出項目数(例:タイトル+著者名+要旨など)
- データ整形・加工の有無(CSV形式、ダッシュボードなど)
また、これらの費用を研究費で賄うために、以下のような対応が可能です。
- 見積書・納品書・請求書の発行(大学の形式に準拠)
- 年度末予算のスピード対応
- 法人・研究機関向けの契約書対応
「研究費で使えるか不安…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
Q.すべてのWebサイトに対してスクレイピングできますか?違法ではありませんか?
すべてのWebサイトがスクレイピングに対応しているわけではありません。利用規約や技術的制限により、「スクレイピング禁止」と明記されている場合もあります。また、技術的に完璧なデータ収集が難しいことも考えられます。そのため事前に下記のような内容の確認が必要です。
- 対象サイトの利用規約やrobots.txtの内容
- 著作権・データ利用に関するリスク有無
- 技術的に取得可能か(動的表示やログイン有無など)
弊社では、上記について事前に確認しております。その後、法律上問題のない方法でのデータ取得提案をさせていただきますので、安心してご相談ください。
Q.納品されるデータはどんな形式ですか?
ご希望に応じて、CSV・Excel・JSON形式などで納品可能です。研究用途に応じて、以下のような対応でもご相談ください。
- CSVで整理されたデータ一覧(ヘッダー付き)
- Excelファイルで複数シートに分けたデータ構成
- 時系列やカテゴリ別に加工・整形したフォーマット
なお、毎月・毎週などの定期納品も可能です。他にも、「○○の列がほしい」「特定の条件でフィルタしたい」など、具体的な希望を伝えていただければ、最適な形でご提供します。
まとめ
論文を書く際にはデータ収集が必要です。ただ、手作業で対応するには限界があり、効率化を求めている人は多いでしょう。その場合、スクレイピング代行をおすすめします。
スクレイピング代行を活用すれば、事前に決めた要件に沿って、サービス事業者がデータを収集してくれます。データ収集を正確化・効率化できるため、「調査の質向上」「作業工数の削減」「論文の完成度UP」など多くの効果を生み出すのです。弊社はスクレイピング代行サービスを提供しているため、お気軽にご相談ください。