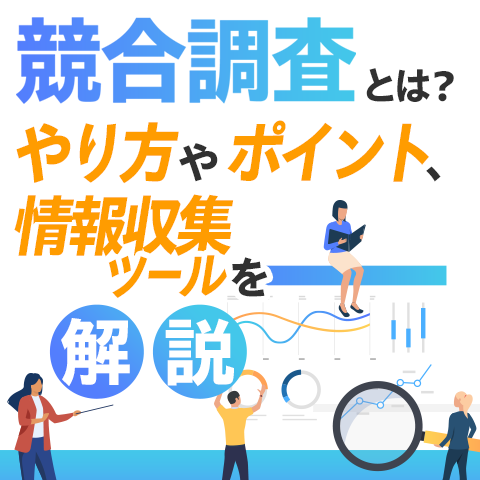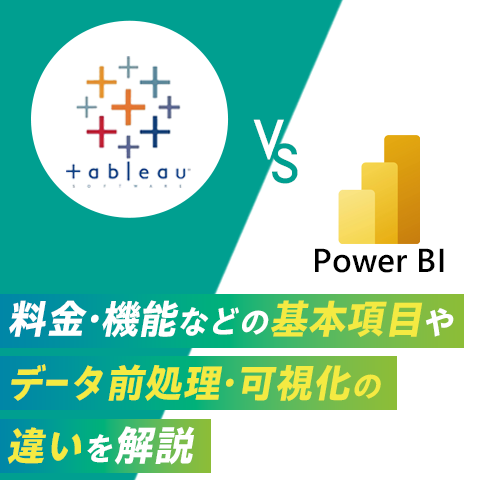自社の売上を伸ばすために、効果的なマーケティング戦略を立てたいと考えている方は多くいるのではないでしょうか。企業の目的を達成して売上を伸ばすためには、効果的なマーケティング戦略が欠かせません。市場のリーダーではないベンチャーや中小企業であっても、マーケティング戦略は必要不可欠であるといえるでしょう。しかし、いざマーケティング戦略を立てようとしても、どのように戦略を立てればよいかわからない方も多いことが事実です。
今回は、マーケティング戦略の概要や重要性、手順や活用できるフレームワークなどのポイントを詳しく解説します。また、事例やトレンドも紹介するため、マーケティング戦略の立案に活用してください。
目次
マーケティング戦略とは
マーケティング戦略とは「誰に」「どのような価値を」「どのように提供するのか」を決めて売れる仕組みを構築し、企業活動を効率的にする戦略です。
ピーター・ドラッガーによると、マーケティングは「顧客から始まるビジネス思考」と定義されています。「顧客から始まる」とは、顧客の視点に立って趣味や趣向を把握する、という意味です。その思考に基づいた販売戦略がマーケティング戦略といえるでしょう。また、ドラッガーはマーケティング戦略さえ徹底していれば、販売努力すら不要であるとまで断言しています。
もちろん製品やサービスによっては営業も必要となりますが、マーケティング戦略を徹底することでより一層成果をあげやすくなるでしょう。
マーケティング戦略の重要性
マーケティング戦略の重要性について解説します。
市場の変化へ対応
マーケティング戦略を立てる必要がある理由として、高度化・複雑化したビジネス市場に対応することが挙げられます。インターネットが普及して、情報を誰でも簡単に入手できるようになった現代では、これまでとは経済市場の状況が大きく異なっているのです。
一昔前のように、新聞やテレビといったマスメディアが情報発信の中心であった時代であれば、口コミなどが拡散されることは少なく、万人が評価してくれるような見た目や内容の商品がよく売れる傾向にありました。しかし、インターネットが普及し消費者が手軽に情報を集められる現代では、このような表面的に良い商品だけではうまくいきません。消費者が企業からの情報提供以外からの情報を入手できるようになり、万人向けの商品ではなく「特定の課題を解決してくれる商品」など、実際に使った人が高く評価した商品が売れる時代にシフトしたのです。競争力を身に付けるにはマーケティング戦略を立て、適切なアピールポイントを見つけたり、方法を選択したりして販売することが求められます。
顧客ニーズの理解
マーケティング戦略を検討しておくことで、顧客ニーズについての理解を深めやすくなります。マーケティング戦略の検討にあたっては、顧客のニーズや要求を正確に理解しなければならないため、これが結果としてプラスに働くのです。
現在は、顧客の行動が多様化し、それぞれの顧客がどのようなニーズを持っているのか判断が難しくなってきました。しかし、これを判断したり分析したりすることなくマーケティングしても、ターゲットに沿ったものとはならず、売上アップなどの効果につながらないのです。顧客に寄り添ったマーケティングを実施するために、マーケティング戦略の立案が求められます。
リソースの最適化
マーケティングには時間をかけるべきですが、実際にはアサインできる人数などに限りがあります。そのため、マーケティング戦略を立て、できるだけ効率的に効果を生み出せるようにしなければなりません。
例えば、マーケティング戦略には後ほど解説するとおり、多くのフレームワークが存在します。これらを活用することで、短時間で結論を出せたり、必要最低人数で分析を進められたりするのです。マーケティングのリソースを最適化することで、少ない人員でも大きな効果を生み出せます。
マーケティング戦略に欠かせないこと
マーケティング戦略に欠かせないことが6つあるため、それぞれについて解説します。
目標設定とKPI
マーケティングで成果を出すためには、目標やその具体的かつ中間目標であるKPIの設定が重要です。具体的な数字がない状態で、マーケティング戦略を評価しようとしても、効果があったのか判断できません。中間目標となるKPIを設定して、それを達成しているか定期的に評価することが重要です。
設定する数値は、業界や業種によって異なり、同業でも会社の規模などによって変化します。例えば、営業職では「商談数」「契約数」「契約率」などをKPIとして定められるでしょう。ただ、どのような数値を採用するかは、それぞれの状況などを踏まえて決定しなければなりません。
環境分析
マーケティング戦略を立てるにあたっては「マーケティング環境分析」が必要です。マーケティング環境を分析することで、企業を取り巻く社内外の経営状況を正しく把握できます。
環境分析には「内部分析」と「外部分析」の2つがあります。内部分析は、自社製品の売上など、企業内部について分析するものです。外部分析は、自社に関する情報以外を分析すると考えましょう。分析の対象が異なるため、環境分析といえども、分析に必要となる情報は活用するフレームワークには違いがあります。
市場分析
市場分析は、環境分析に含まれる部分ではありますが、自社が存在する「市場」について分析することです。一般的には「市場規模」と「市場動向」の2本立てで状況を評価します。
まず、市場規模とは業界全体の売上高を指し、競合他社などの情報も含めたものです。官公庁や業界団体が統計資料などを発表しているため、それらを参考にすると良いでしょう。また、公的な情報がない場合は、自社の情報に他社製品のシェアなどの情報を掛け合わせて、推測しなければなりません。
また、市場動向とは、簡単に説明すると市場が拡大しているか縮小しているかを示すものです。一般的には、市場が拡大していて、なおかつ競争が激化している方が望ましいと考えられます。これは売上などの数値だけではなく、世にいう「バズ」やトレンド、口コミなどの文字情報から把握できる場合もあります。
市場規模、市場動向のどちらにおいても、社内の情報だけでは思うように評価できない可能性があります。その場合は、公的機関が発行しているデータやニュースサイトなど外部の情報源を積極的に活用し、多くのデータから分析しなければなりません。
ターゲットオーディエンスの明確化
ターゲットオーディエンスとは、製品やサービスに興味を持つ可能性が高い人々のことです。マーケティング戦略の一環として、この人物像を定めることで、どのようにアピールしていけば良いかも具体的に考えられるようになります。
明確化にあたっては「属性」「ライフスタイル」「興味」「価値観」などを検討しなければなりません。それを踏まえて、対象として絞った顧客に的確に接触できるような戦略を立てることでマーケティングとして成功させることができます。
差別化
マーケティングでは、常に差別化を意識しなければなりません。自社の製品やサービスと競合他社の違いを生み出すことで、独自の顧客を獲得したり売上を高めたりできるのです。
なお、市場における差別化といえば「価格を下げる」と捉えられることが多くあります。しかし、実際には製品の質を高める方法やラインナップを増やす方法も考えられるのです。固定概念にとらわれず、多角的な観点から、差別化を意識しなければなりません。
オムニチャネル戦略
オムニチャネルとは、実店舗・ECサイト・アプリ・SNSなど、全ての販売経路がシームレスに繋がった状態です。現代のマーケティング戦略では、顧客体験(CX)を高めることを重視すべきであるため、すべてのチャネルで一貫した顧客体験を提供できるオムニチャネルの実現は欠かせません。
チャネル間を行き来させることで、顧客にさらなる支出を生み出すことができる可能性があります。例えば、ECサイトのクーポンを店頭でも利用できるようにすると、お店へ足を運ぶきっかけとなるのです。
マーケティング戦略に使えるフレームワーク
マーケティング戦略に使えるフレームワークはいくつもあるため、それらの中から8つをピックアップして解説します。
STP分析
STP分析はターゲットを選定して、顧客の利益を追求するマーケティング手法です。
STPとは、
- セグメンテーション(Segmentation)
- ターゲッティング(Targeting)
- ポジショニング(Positioning)
という3つの工程から頭文字を取ったものであり、順にステップを踏んで戦略を立てていきます。セグメンテーションでデータをもとに市場を細分化し、ターゲッティングで細分化した市場のうち、どこのニーズを狙うのかを決めていきましょう。
また、セグメンテーションとターゲッティングが整っていたとしても、ポジショニングで自社を有意な立ち位置に置けなければ意味がありません。顧客のニーズと自社の強みをバランスよく捉える必要があるので、慎重な判断が求められます。
3C分析
3C分析とは現状を3つの視点から分析する、マーケットインと呼ばれる分析手法の1つです。
3Cで提唱されている3つの視点は、
- 市場・顧客(Consumer)
- 競合(Competitor)
- 自社(Company)
で構成されています。
自社としての目線で分析を行うのではなく、第三者の視点から分析することが重要です。
自社にとって有利な情報のみを収集するのではなく、客観的な事実の収集に努めて、出そろった事実についてはマイナスとプラスの両面から分析するようにしましょう。
自社の強みや弱みなどを複数人で分析すれば、客観的な視点で分析を行えるほか、共通認識も図れる効果も見込めます。
SWOT分析
市場を分析した後は、セグメンテーションで市場を細分化し、どの顧客層に対してマーケティングを仕掛けるのか優先順位を決めましょう。
セグメンテーションによる市場を細分化する基準として、
- 自社の強み(Strength)
- 自社の弱み(Weakness)
- 市場での機会(Opportunity)
自社にとっての脅威(Threat)
となっており、まとめて表にしてクロス分析を行います。
例えば、
- 強みを活かして機会を掴むにはどうするか
- 弱みを補強して脅威を取り除くにはどうするか
といったように、今後のビジネスチャンスを考えていきます。
自社の内部環境と外的環境にあるプラスとマイナス要因を組み合わせ、戦略の方向性を見出すために用いられるフレームワークです。
PEST分析
PEST分析とは経営運営を立てるために、自社の外的環境について大局的な視点から分析を行っていくフレームワークです。
PEST分析で捉える視点は、
- 政治的要因(Politics)
- 経済的要因(Economics)
- 社会的要因(Society)
- 技術的要因(Technology)
の4つです。
それぞれの視点から自社を取り巻く外的環境を分析すれば、社会全体の動向を掴んで、自社のビジネスチャンスに繋がる機会や脅威が見えてくるでしょう。
発見した外的環境の機会や脅威を、SWOT分析などに活用するとより効果的な分析が可能です。外的環境をよりマクロに分析するので、業界で起きている事柄をもれなく捉えられる方法といえます。
4C/4P分析
4P分析とは企業がコントロールできる要素を組み合わせて成果を上げるフレームワークであるのに対し、4C分析は顧客視点から成果の向上を目指したフレームワークです。
4P分析で提案されている要素は、
- 製品(Product)
- 価格(Price)
- 流通(Place)
- プロモーション(Promotion)
の4つです。
それぞれの要素を組み合わせて、より効果的なマーケティング戦略を分析するフレームワークです。しかし、マーケティング理論が進化していく中で、4P分析を顧客視点から見つめなおす動きが生まれ、誕生したのが4C分析となります。
4C分析は、
- 顧客価値(Customer Value)
- 顧客にとってのコスト(Cost)
- 利便性(Convenience)
- 顧客とのコミュニケーション(Communication)
の4つの要素で構成されており、顧客視点での分析を重視しているのが特徴です。顧客のニーズをより深く捉えるため、効果的なマーケティング戦略を立てやすくなります。
AIDAモデル
AIDAモデルは、消費者の購買決定プロセスを説明するマーケティングの概念です。消費者が製品やサービスに対してどのように反応し、最終的に購入に至るかを理解するのに役立ちます。
このモデルは
- 注意(Attention)
- 関心(Interest)
- 欲求(Desire)
- 行動(Action)
から構成され、どのように消費者の注意を引き、関心を持って行動してもらえるかを重視しています。マーケティングコミュニケーション戦略を設計する際のガイドラインとして広く使用されており、広告やプロモーション活動の効果を最大限、引き出すために役立つでしょう。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、顧客の購入プロセスやサービス体験を視覚化するツールです。このマップは、顧客が商品やサービスに触れる瞬間から、購入後の体験に至るまでの全過程を示すものだと考えましょう。顧客の目線でビジネスのインタラクションを評価し、顧客がどのような体験を得られているかを把握するものです。
カスタマージャーニーマップは、
- タッチポイント
- 顧客の感情
- 顧客の行動
- 顧客の目的
- 改善すべきポイント
などがまとめられています。細かくマップ化することによって、顧客の体験をより深く理解できるため、顧客のニーズを満たすための行動を具体的に検討できるのです。また、顧客満足度の向上やロイヤルティの強化などにも活かせます。
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy(ブルー・オーシャン戦略)は、競争の激しい市場である「レッドオーシャン」から離れ、新しい市場である「ブルーオーシャン」を創造するものです。新しい市場を生み出そうとすること、既存の競争を無意味にするなどの効果があります。
ブルーオーシャン戦略では
- 新しい市場の追求や創造
- 既存の競争を回避
- 独自の価値を創造
- 顧客満足度の向上(価値の向上)
などを意識することが重要です。市場そのものを創造することになるため、その詳細を吟味しなければ、結果的に競合他社に飲み込まれることになりかねません。逆に、新しい市場を創造できれば、先駆者として市場での優位性を確保できます。
マーケティング戦略の成功事例
マーケティング戦略の成功事例を具体的に紹介します。
Sansan株式会社:ハイブリッドなマーケティング戦略
Sansan株式会社は、名刺管理ソフトウェアを中心に提供する企業です。マーケティング戦略の中でも、オンラインとオフラインのハイブリッドなマーケティング戦略を展開することで成功しています。
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、Sansan株式会社はオンラインでの情報交換を軸にサービスを展開していました。しかし、昨今はオフラインでのイベントも増えてきているため、早々にオンラインとオフラインの両方をターゲットとした戦略に切り替えています。マーケットの変化を瞬時に捉え、マーケティング戦略を細かく見直すことで、顧客の拡大や新サービスの創造などに成功しています。
株式会社SmartHR:社内のデータを活用した戦略の立案
株式会社SmartHRは、人事や労務に関するプロダクトやバックオフィスサービスなどを提供する企業です。設立から期間が経ち、多くの情報が社内に蓄積されていることから、データアナリストを活用した戦略の立案に力を入れ成功しています。
例えば、社内に蓄積された契約データを活用して「アップセル」「クロスセル」の対象やアプローチのタイミング、その内容などを決定しています。KPIの設定やデータ活用を実現しやすいような環境を整え、積極的にマーケティング戦略に活かしているのです。
また、データアナリストが分析した結果を踏まえ、マーケティングに関する予算の策定も実現しています。トップダウンで予算を決定するのではなく、データをもとに現場が算出し、その範囲内でマーケティングを展開していくことが特徴です。
スターバックス株式会社:ソーシャルメディアを軸としたマーケティング
スターバックス株式会社は、以前よりソーシャルメディアを軸としたマーケティング活動で成功しています。多くの企業がテレビやWebの広告を多く出稿している中、スターバックスではそのような活動がほとんど見受けられません。
主に、ソーシャルメディアを活用して新製品の情報を拡散し、それだけで十分な来客を確保できています。また、独自のスマートフォンアプリを開発し、プッシュ通知を利用した広告ページへの誘導なども多いことが特徴です。顧客へ直接的なマーケティングを実施するのではなく、顧客による情報の拡散などでもマーケティング活動をしていることが特徴といえます。
デジタルマーケティングの最新トレンド
デジタルマーケティングにはトレンドがあるため、最新の状況を紹介します。
SNSマーケティング
マーケティング戦略としてSNSを活用したものが増えています。自社がX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのアカウントを作成して情報発信することはもちろん、インフルエンサーに紹介を依頼することもあるでしょう。すべてまとめてSNSマーケティングと考えられます。
近年は、SNSを活用して「口コミ」を踏まえた情報を収集する人が増えています。企業側もSNSを積極的に活用することで、引用による口コミや「リポスト機能」などによる情報の拡散に期待しているのです。
動画の活用
情報量を増やすために、動画を活用したデジタルマーケティングが増えてきています。文字や画像よりも圧倒的に情報量が多いため、SNSマーケティングと組み合わせて利用されることもあるぐらいです。
例えば、新製品に関する情報をYouTubeやInstagramなどに投稿し、誰でも簡単に情報を得られるようにしています。昔はテレビCMなどが主流でしたが、現在はWeb媒体への投稿が主流と考えましょう。短い動画に情報を効率よく詰め込むことで、高いマーケティング効果を発揮しています。
AIの採用
マーケティングを最適化するために、AIを活用することがトレンドになっています。例えば、ペルソナの決定にAIを活用したり、文章の生成をAIに任せたりするのです。汎用的なAIも専門的なAIも増えているため、状況に応じて適切なものを選択できます。
ただ、AIの活用がトレンドではありますが、AIだけですべてが完結するわけではありません。人間が考えたり作業したりする部分は多く、作業の効率化を目的として採用されていると考えましょう。
まとめ
マーケティング戦略には環境分析や市場分析が重要であり、そのために多くのデータを分析しなければなりません。分析手法にはいくつもの選択肢があり、その内容に応じて適切なデータを用意することが大切です。マーケティング戦略のためのデータ分析をするには社内にある内部データはもちろん、外部データも活用することで、より正確かつ幅広い視点の分析を実施できます。
外部データの収集方法はさまざまあり、その中でもWebサイト上のデータを収集したり活用したいならば「スクレイピング」が有効的です。弊社PigDataはスクレイピング代行サービスを提供し、マーケティング戦略に必要なWeb上のデータを準備できるため、ぜひご相談ください。