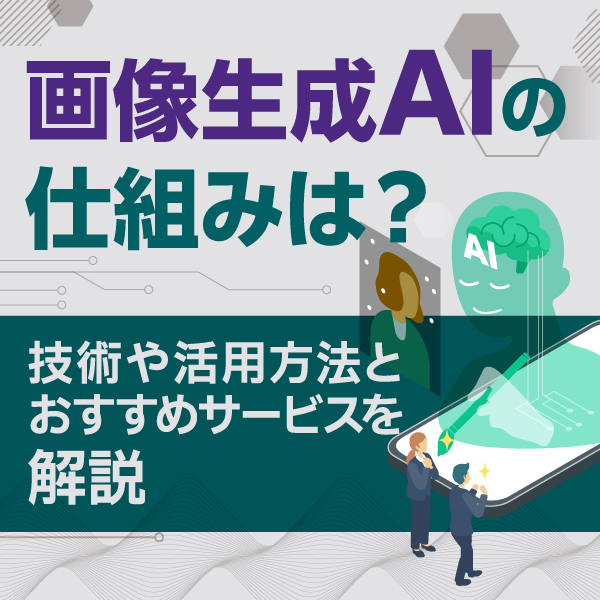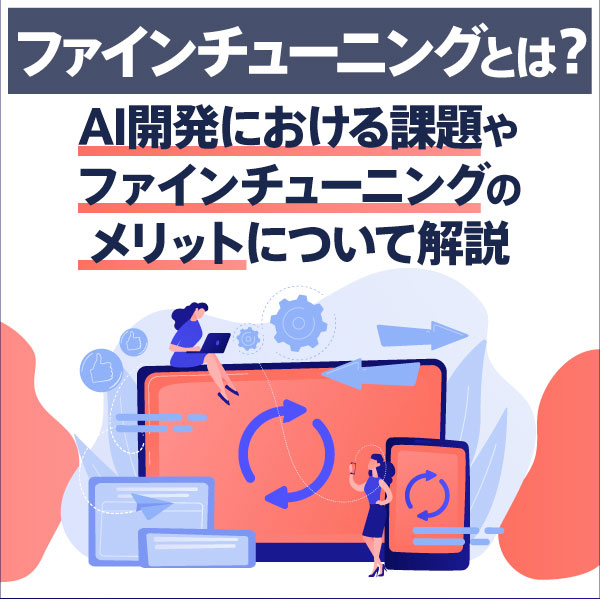人工知能が安定してきたことにより、画像生成AIが利用されるようになってきました。必要な画像についてのキーワードを入力すると、それを元にAIが画像を生成してくれる仕組みです。画像の加工ツールなどにも組み込まれるようになってきました。
ただ、生成AIは事前の学習を必要とすることから、著作権の問題が生じると考えられています。今回は、画像生成AIと著作権問題の解決策について解説します。
画像生成AIの背景と普及
画像生成AIとはどのような技術であり、なぜこれほどまでに利用が拡大し普及するようになったのか解説します。
生成系AIとは
生成系AIとは、ディープラーニングによって大規模な機械学習モデルを準備しておき、そこから新しいデータを生み出すものです。基本的には大量のデータを学習し、そのデータの特性やパターンを捉えてから、新しいデータを生成します。学習したデータの特性に基づき、オリジナルのデータやコンテンツを生成できるのです。結果、画像生成やテキスト生成、デザインやアートの構図を生み出したりできます。
AI技術の進歩と利用の拡大
コンピュータの能力が高まっていることもあり、AI技術は急速に進歩しています。今までは、計算能力の限界からAIの性能にも限界がありましたが、現在はスーパーコンピュータなど強力なコンピュータではなくとも処理できるようになりました。アルゴリズムの開発だけではなく、ハードウェアの進化も後押しして、AI技術は進歩しています。
また、AI技術が進歩して低コストで利用できるようになったことから、利用が急激に拡大しました。例えば、検索エンジンにAIが組み込まれたり、画像や文章を簡単にAIで生成できるようになったのです。現在もAIを導入する企業やサービスは増え、利用の拡大が続いています。
生成AIの能力とクリエーターとの関係
生成AIの能力は、クリエイターを完全に超えているわけではありません。これは、生成系AIが何かしら をアウトプットするためには、事前に学習が必要だからです。画像生成AIならば、クリエイターが作成したイラストやフォトグラファーが撮影した写真、その他数多くの画像データの学習が求められます。
学習データを必要とするという点で、生成系AIが人間を超えていることはないでしょう。ただ、近年はAIが生成したデータを利用して、AIが学習する仕組みが 研究されています。もし、これが完璧に実現してしまうと、クリエイターなしに生成AIが学習できてしまうのです。
著作権問題の現状
画像生成AIは、非常に魅力的なツールではありますが、著作権問題が生じています。どのような背景から問題が生じ、どのように著作権が侵害される可能性があるのか、理解しておきましょう。
生成AI画像の著作権侵害の懸念
AIが生成する画像は、著作権を侵害しているのではないかと懸念されている状況です。この背景には、生成系AIが学習に利用する画像データの著作権が関係しています。
上述したとおり、生成系AIは莫大なデータを学習し、その結果を踏まえて文章や画像を生成する仕組みです。画像生成AIにおいては、大量の画像を学習し、それを踏まえて画像を生成します。ただ、学習に利用される画像には著作権が認められていることが多く、これを利用して学習したり画像を生成したりすることは、著作権侵害ではないかと考えられているのです。
もちろん、学習に利用されているだけであり、AIがまったく同じ画像を生成するわけではありません。ただ、部分的に酷似した画像が生成されるなど、著作権を侵害してしまう可能性があります。特に、Webから大量のデータを収集してAIを学習させている場合には、この問題が大きくなりかねません。
クリエーターの権利が脅かされる可能性
著作権が認められている画像が学習に利用されることで、クリエーターの権利が脅かされる可能性があります。例えば、時間を掛けて構図を考えクライアントから費用を受け取るような画像の一部が、AIに無断で利用されてしまうからです。人間が同じことをすれば、それは「盗用」として判断されるでしょう。
ただ、一般的に画像生成AIは莫大な画像を学習しているため、ひとつの画像と酷似した画像が生成される可能性は低いと考えられます。数多くの画像から特徴を見つけ、それを踏まえて生成することが一般的です。そのため「画像生成AIが出力したこの画像が、私の作品を侵害している」とは主張できないかもしれません。あくまでも、理論的には権利が脅かされる可能性があると理解しましょう。
クリエーターの懸念と反応
クリエーターは画像生成や写真撮影などで生計を立てるため、画像生成AIには懸念を持つ人が多くいます。プロはどのような視点を持っているのか解説します。
イラストレーターや写真家といったプロフェッショナルの視点
AI生成画像について、イラストレーターや写真家などプロフェッショナルは、さまざまな視点を持っています。
例えば、公益社団法人日本写真家協会の意見によると、AI生成画像はイラストレーターや写真家などの著作物を利用した「二次的著作物」に該当するとしています。現行法では、二次的著作物には元の著作者の権利が認められるため、イラストレーターや写真家に著作権があると主張しているのです。
一般的に、二次的著作物が適切に運用されるならば、AI生成画像自体に問題は発生しません。例えば、著作者に対価を支払って二次的著作物を作成するならば、著作者は権利が守られ収入も得られます。つまり、二次的著作物が一概に悪いというわけではありません。しかし、AI生成画像においては、著作者が得るべきはずの対価を得られないことを問題視しています。また、著作者が知り得ないところで生成されることで、需要が傾いてしまうことも懸念しています。AI生成画像について一概に悪というのではなく、それによって著作者が得られるべき対価や権利が守られないことが問題なのです。
参考:「生成AI 画像についてその考え方の提言」
AI生成画像とオリジナル作品の類似性とその問題点
AI生成画像は、学習に利用したオリジナル作品との類似性が認められる場合があります。例えば、写真の構図が同じであったり、登場する キャラクターが酷似していたりするのです。人間の目には判断が難しくても、部分的には完全に一致することも考えられます。このように類似している画像の生成は、一般的に著作権侵害にあたる行為です。オリジナル作品の著作者が訴えれば、裁判となり損害賠償請求が認められるかもしれません。生成AIの活用は、著作権の観点で大きなリスクを抱えるのです。
ただ、文化庁の発表を参考にすると、生成する行為は著作権侵害ではなく、生成した画像を営利目的で利用すると著作権の侵害だとされています。オリジナル画像と酷似するという問題点はありますが、私的に楽しむのであれば、著作権の問題は発生しない状況です。
参考:「AIと著作権の関係等について」
解決策と今後の方向性
画像生成AIは、これから今まで以上に活用されると考えられます。それを踏まえ、著作権問題に対してこれからはどのような解決策が考えられるか、今後の方向性と併せて解説します。
著作権の制度的議論と更新
AI生成画像を活用するには、著作権の制度について議論してその内容を最新のものに改定する必要があります。現在の著作権は生成AIなどを前提としたものではないため、どうしても内容面でカバーしきれない部分があるのです。
この議論はすでに開始されていて、政府は2023年内にも対応の方針を示すとされています。例えば、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害になるのかが示されるのです。また、オリジナル作品とAI生成画像を見極めるための技術についても検討するとされています。
著作権の重要性は認識されていますが、制度の議論が開始される段階であり、それが法律などへと反映されるのは先になるでしょう。現在は問題点が認識され、国として対応が進められていると認識するようにしてください。
クリエーターの権利を保護するための推奨策
クリエーターの権利を保護するためには、いくつもの対策を取らなければなりません。具体的な案は、上記で触れた制度の検討において議論されると考えられます。この案では、以下のような保護策が採用されるでしょう。
- 生成AIへの学習に利用させない権利
- 生成AIが生み出した作品を二次的著作物として認める仕組みづくり
- 学習に使用したデータを示させる制度の確立
生成AIのように莫大なデータを学習しているサービスは、データソースを示すことが難しいと考えられます。そのため、二次的著作物としての権利を主張するよりも、学習に利用させないことを前提に考えるべきではないでしょうか。学習に利用されることで、生成AIが二次的著作物を生み出してしまうため、そもそもこれを防げるようにすれば一定の権利が保護されるのです。
アメリカでの対応とその取り組み
生成系AIによる著作権の侵害は世界的に問題視されていて、例えばアメリカでも議論や対策が進められています。
例えば、2023年7月には、アメリカのバイデン大統領がAI開発に携わる大手IT企業を中心に7社の幹部と意見交換会を開催しました。この場では、AIが生成したデータとそうではないデータを判断するために、何かしらのツールを開発することが合意されています。
また、2023年9月には、同じくバイデン大統領を中心としてAI規制の法整備について、超党派の特別会議が開催されました。会話の内容は細かく公開されていませんが、健全なAIの活用に向けて、検討が進められたと考えられます。
まとめ
これまでの内容を踏まえて、画像生成AIや著作権のこれからについて考察します。
生成AIとクリエーターの共存のためのバランスの取り方
生成系AIはこれからも活用が広がると考えられ、規制するのではなく、クリエーターとの共存を意識しなければなりません。クリエーターの権利を守りつつ、気軽にAIを利用できる環境が望ましいでしょう。
これを担保するためには、例えば生成AIの学習に利用できるデータの規制が求められます。Web上のデータを自由に利用できるのではなく、学習を許可しているデータだけから学習できるように法整備するのです。このような仕組みが整えば、クリエーターの権利や利益が守られます。
また、画像生成AIを開発したいと考えるならば、収集するデータを考慮するリテラシーが求められます。例えば、著作権を考慮せず画像を一括ダウンロードしてAIに学習させる行為は、著作権の観点から望ましくありません。著作権侵害の片棒を担ぐことは避けるべきなのです。
持続可能なクリエイティブな未来の構築
持続可能なクリエイティブな未来のため、生成AIの学習に利用するデータを考慮することが大切です。例えば、著作権を主張するデータから学習するのではなく、著作権フリーのデータから学習するようにします。こうすることで、クリエーターの権利を侵害することなく、生成AIの発展も続けられるのです。
ただ、著作権などを気にして人間が学習用のデータを収集することは現実的ではありません。そのため、特定のルールに沿ってデータを収集できる、スクレイピングの活用をおすすめします。スクレイピングを活用することで著作権フリーのWebサイトからデータを一括で収集し、それらに学習用のタグを割り当てたりできるのです。