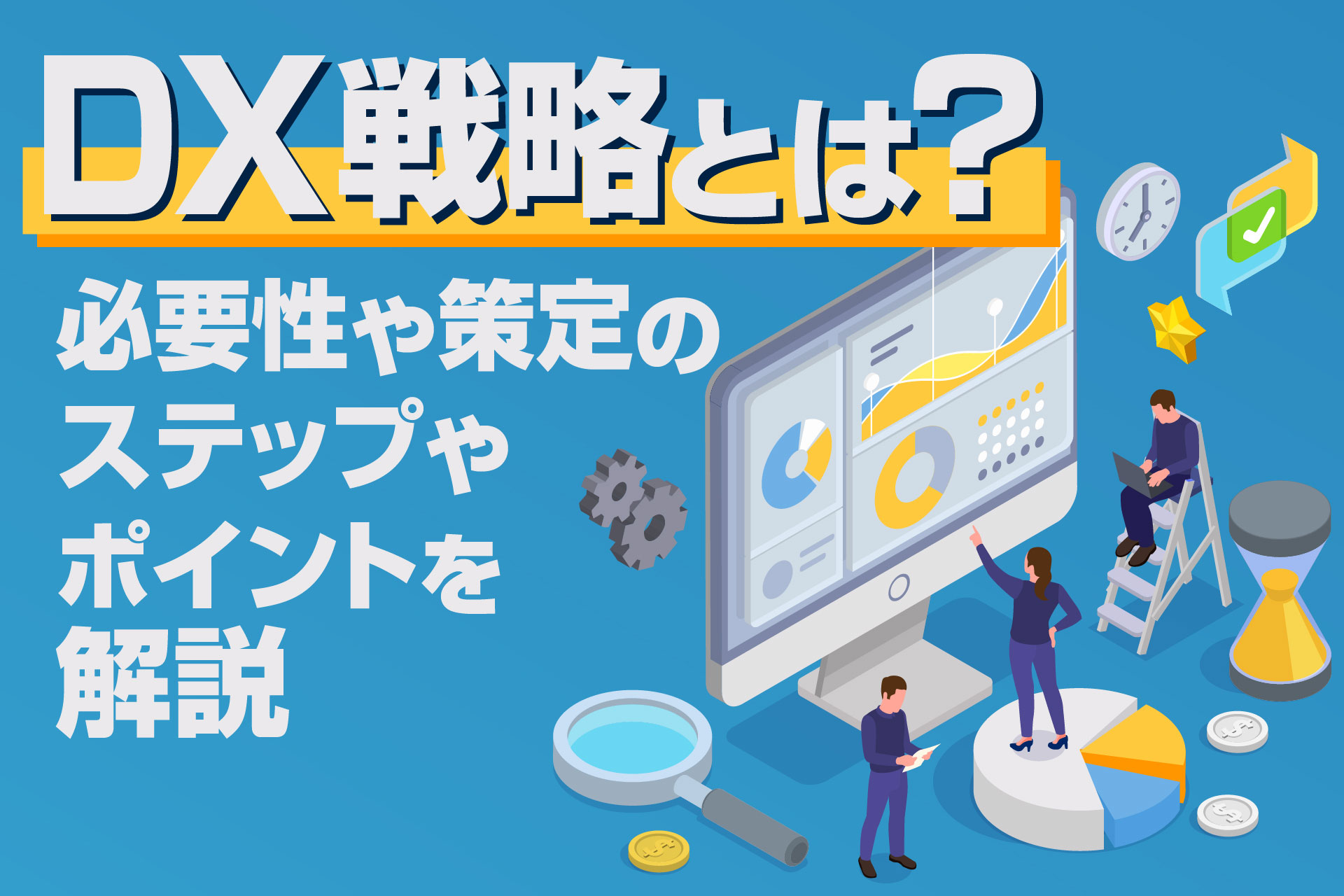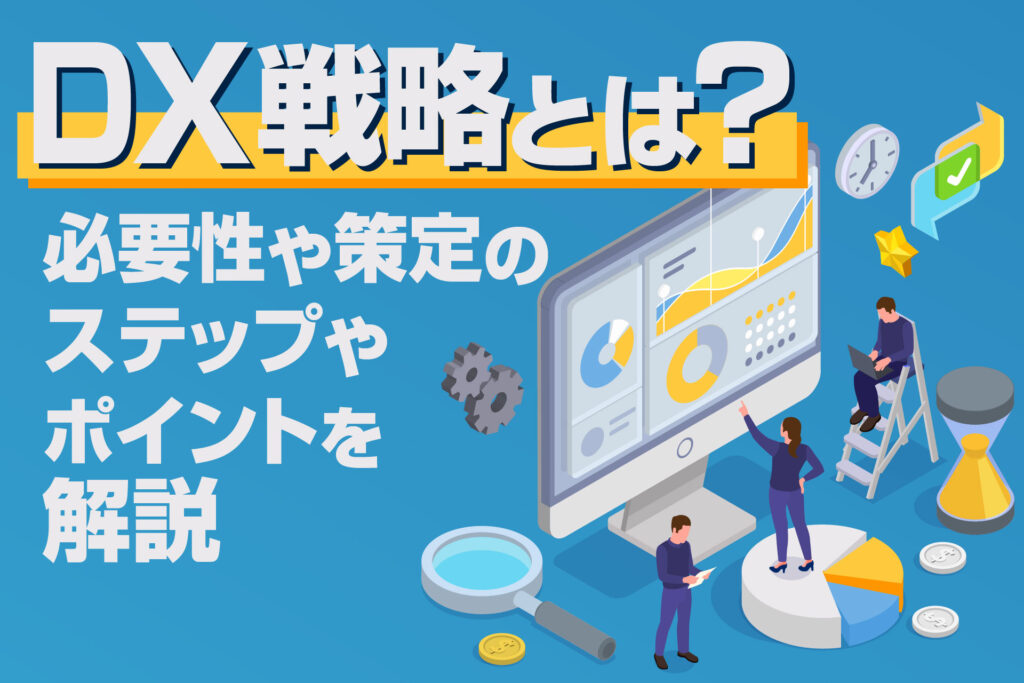
企業がDXを推進するためには、前段階としてDX戦略を立案することが重要です。しかし、DX推進室に配属された人やDX担当者でも、戦略の必要性やその内容について理解できていないことが多いでしょう。DX戦略がなければスムーズにDXは進められないため、今回は概要や必要性から策定のステップ、ポイントについて解説します。
DX戦略とは
DX戦略(デジタルトランスフォーメーション戦略)は、企業がデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデル、組織全体を変革するための計画です。DX戦略を策定しておくことで、市場の変化や顧客ニーズに柔軟に対応し、競争力を高められます。
なお、DXといえばデジタル化をイメージされがちですが、単にITツールを導入するだけではなく、企業文化の改革や従業員のスキル向上も含めたものです。これからDX戦略を立てる際は、この点も考慮しなければなりません。
DX戦略の必要性
DX戦略がなぜ必要であるかについて以下では3つの観点から解説します。
全社的に展開して理解を得る
DXは全社的に進めるものであるため、DX戦略を全社的に展開すれば、従業員の理解を得やすくなります。単なるITツールの導入ではなく、企業全体の業務プロセスやビジネスモデルを根本的に変革するため、それらを知ってもらうことに繋がるのです。それぞれの従業員が役割を全うするために、非常に重要な資料となります。
経営者がDXに対して正しい認識を持つ
全社的にDXを成功させるためには、経営者がDXの重要性とその具体的なメリットを正しく認識しなければなりません。これを認識するためのキッカケとしてDX戦略が必要なのです。策定に関わったり、担当者が策定したものを熟読することで、DXについての知識を深めていきます。DXはトップダウンで進めるべき活動であるため、経営者がDX戦略を通じて正しい認識を持たなければ、失敗に終わってしまうのです。
自社の目的を達成する
自社が見据える最終的な会社としての目的を達成するためにDX戦略が求められます。例えば「業務プロセスを見直して他社よりも素早くサービスを提供する」「データを分析して新しいビジネスモデルを見つけ出す」という目的を達成するために「RPAなど自動化を盛り込んだデジタル化を進める」「データ分析基盤の構築に力を入れる」などのDX戦略を立てるのです。
このような戦略を立てることで、会社全体で目標達成のために何をすべきであるかが見えてきます。例えば「現在の業務フローを洗い出し、自動化できる部分がないか調査する」「社内に点在しているデータの種類を洗い出して基盤構築に向けた下準備を進める」などです。また、それぞれのプロセスが完了したならば、次に何をすべきかも見えてきやすくなります。
DX戦略の策定のステップ
これからDX戦略を策定したいならば、以下のステップに沿って進めるようにしましょう。
具体的にDX後の業務や姿をイメージする
最初に、DXを実施してどのような結果を得たいかを具体的に想像する必要があります。新しい業務の進め方や組織全体の姿を思い浮かべなければなりません。例えば、請求書処理業務が課題ならば「AIとOCRを活用して自動化し、残業時間を半分以下に抑える」などと具体化しておきます。
このように新しい業務の姿を思い浮かべる際は、最新の情報を収集する作業が必要です。先程の例ならば「請求書処理にどのようなトレンドがあるか」や「同じ業界や業種の企業はどのような取り組みを採用しているか」などです。具体的な姿は自分自身で思いつけない場合があるため、実際の事例を参考にすることをおすすめします。
現状の姿と問題点を洗い出す
上記でイメージした内容を実現するために、現状の姿を把握して、問題点やギャップを洗い出していきましょう。現行のビジネスプロセスやITインフラ、組織構造など必要な情報を多角的に収集する必要があります。また、従業員からヒアリングするなど、定性的な情報を集めたほうが良いケースもあるでしょう。
現状の姿が明らかになれば、問題点は自ずと明らかになってくるはずです。例えば、ビジネスプロセスに無駄がある場合、根本的な業務変革や人員配置が必要かもしれません。問題点の洗い出しは、DX戦略を策定する基礎となる部分であるため、時間をかけて丁寧に掘り下げておきます。
経営層へ説明し理解を得る
担当者がDX戦略の策定に向けて現状と課題を資料にした後は、経営者にその内容を説明しなければなりません。全社的に推進する活動であるため、担当者が中心となるのではなく、経営者が中心になってもらえるように説明して合意を得ることが重要なのです。最終的にはトップダウンで様々な活動を進めていかなければなりません。
特に、担当者が考える現状の姿や問題点と経営層が考えるものには乖離があることも考えられます。そのような状況では、DX戦略を策定してもスムーズに進められないでしょう。現状を理解してもらうだけではなく、認識を一致させるための活動でもあるのです。
問題点を解決するための戦略を策定する
問題点についての認識が一致したならば、具体的にそれらを解決するためのDX戦略を立てます。問題点について説明した際に、解決策の方向性についても合意を取り、それに沿って進めるようにしましょう。例えば、コストを重視する方針を指示されたならば、それをDX戦略にも含めていきます。また、スピード感を持つように指示されたならば、素早く進められる計画を立てるのです。
具体的に戦略を立てることで、スムーズにDXを進められるようになります。必要に応じてDXを進めている途中でも修正できますが、十分に調査など準備に力を入れて、吟味した内容で仕上げることが大切です。
DX戦略策定のポイント
DX戦略の策定に当たっては、いくつものポイントがあります。それぞれを考慮することが重要であるため、どのようなポイントがあるのか、理解を深めていきましょう。
外部環境を調査する
最初に外部環境の調査に力を入れることが重要です。DXを推進する際は社内の情報収集に注力しがちですが、実際には外部環境の情報も収集して分析しなければなりません。
例えば、新型コロナウイルスの蔓延は大きな外部環境の変化であり、これに伴いリモートワークが採用されたりデリバリー業界が成長したことも大きな変化です。他にも、IT業界ではAIを利用するハードルが大きく下がったり、IoTが多用されるようになりました。これも外部環境の変化といえます。Webには世界中の最新情報が公開されているため、積極的な情報収集で外部環境を把握しておきましょう。
これらの外部環境について調査した結果、自社への影響が大きい要素はDX戦略に反映すべきです。例えば、世界的にAIが発達し導入が当たり前になるならば、自社もAIの導入を検討しなければ、周りに遅れを取ってしまう可能性があります。外部環境の変化をすべて踏まえることは不可能ですが、まずは調査および分析に着手すべきです。外部環境によって進めるべきDXの方向が左右されると考えられます。
フレームワークを活用して分析する
社内外の状況について分析する際は、フレームワークの活用が重要です。客観的や理論的ではない内容で分析するのではなく、フレームワークを利用して、理論的に分析することを心がけましょう。例えば、以下のフレームワークがDX戦略の策定に役立ちます。
- SWOT分析:戦略策定に必要な内部および外部の要因を明確にするためのフレームワーク
- PEST分析:外部環境を評価するフレームワーク
- バリューチェーン分析:企業の活動がどのように付加価値を生み出すかを分析するフレームワーク
- マッキンゼーの7Sフレームワーク:企業の内部調整とどの分野からデジタル化するかを評価するフレームワーク
顧客や関係者に与える影響を考慮する
社内だけではなく、顧客や関係者に与える影響も考えるべきです。DXといえば社内だけに注目しがちですが、幅広い視点から考えなければなりません。例えば、DXの一環で商品の申し込みについて、電話での申し込み受付を終了しオンライン受付だけに一本化するとしましょう。これによって、担当者の業務負荷は下がり、生産性が向上すると考えられます。
しかし、今まで電話で申し込みしていた利用者の利便性は下がってしまうと予想されます。場合によっては、購入を諦めてしまい、重要な顧客を失ってしまうかもしれません。これは極端な事例ですが、自社のことだけを考えてDXを進めると何かしら別の問題が生じてしまう可能性があります。可能な限り、顧客や関係者への影響を考慮して、DX戦略へと反映することがポイントです。
ビジネスモデルや社内風土も踏まえる
事前に自社のビジネスモデルや社内風土を評価して、それらも踏まえられるようにしておきましょう。DX戦略の策定は理想論で進める部分が多いですが、現実的に実現できるものでなければ意味を成しません。例えば、今まで対面で商品販売を続けていた企業が全面的にオンラインへと切り替えることは、ビジネスモデルが崩壊すると考えられます。
加えて、社内風土もある程度は考慮しておきましょう。デジタル化を進めても、社内に根付かなければ意味はありません。DXは業務フローの変革も含むため、最終的には受け入れてもらうしかありませんが、大きく反発が出そうな内容はできるだけ避けるべきです。
DX戦略が成功している事例
DX戦略が成功している事例を3つピックアップして紹介します。
中外製薬株式会社
中外製薬株式会社は、2021年に「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を発表し、デジタル技術を駆使してビジネスモデルの変革を目指しています。主にデジタル基盤の強化に力を入れ、バリューチェーンの効率化を目指しているのです。
実際、戦略に沿ってDXが進められ、工場のデジタル化、治験のデジタル化、デジタルマーケティングが広がっている状況です。特に新薬の開発は効率化されているため、DX戦略に沿った取り組みが成功していると言える事例です。
トラスコ中山株式会社
トラスコ中山株式会社は、製品のデジタル化と業務プロセスの効率化を目指して、DX戦略を策定しています。「デジタルプラットフォーム構築」に注力し、物流業務の自動化と効率化を図っていることが特徴です。例えば、倉庫内でのロボット導入や自動化システムの導入により、物流プロセスのスピードアップと精度向上を実現しています。
プロセスが効率化されたことで、顧客サービスの質が高まり、顧客満足度も高まっています。社内にも社外にもプラスの効果を与えている事例です。
清水建設株式会社
清水建設株式会社は、建設業界におけるDXの先駆者として、デジタル技術を積極的に活用しています。特に、プロジェクト管理の効率化と現場の生産性向上を目指した戦略が特徴です。具体的には、ドローンによる現場監視や3Dモデルを活用した設計・施工の高度化、リアルタイムでのデータ共有と分析などを次々と導入しています。
DX戦略を立てたら
DX戦略を立てることがゴールではなく、戦略に基づいて結果を出すことがゴールです。そのためゴールに向かって、以下の取り組みを進めていきましょう。
段階的なテクノロジーの導入
DX戦略を立てたならば、それに沿って各種テクノロジーを導入しなければなりません。ただ、導入にあたっては、段階的に進めることが重要です。一気に導入を進めてしまうと、何かしらの問題が起きた際、影響範囲が大きくなってしまいます。DX戦略は「最終的なゴール」を示していることが大半であるため、実際に進める際にはブレークダウンして少しづつ進めるようにしましょう。
例えば、勤怠管理についてDXを進めるケースを考えてみます。この場合、段階的に導入することを考えるならば、全社に導入するのではなく、総務部門のみ新しいシステムを導入するのです。そして実際にシステムを利用してみて、特に問題がないと判断されたならば、少しずつ導入する部門を広げていきます。DX化する業務と特に関係が深い部門にのみ導入し、その効果を評価してから、横展開することが重要です。
定期的なデータ分析と戦略への反映
DXの状況は定期的に評価して問題があれば修正していくことが重要です。これを実現するためには、定期的にデータを収集して定量的な視点で判断しなければなりません。例えば、DXによって残業時間の削減を目指しているならば、残業時間についてのデータを収集して、目標を達成しているか評価します。もし、達成していないならば、その理由を掘り下げて業務フローの修正やツールの改修などを検討しなければなりません。
もし、問題が発見され修正が必要になった場合は、DX戦略にその内容を反映すべきです。例えば、ツールを導入する流れで課題が顕在化したならば、DX戦略に記載されているフローを修正し、他の部門には影響を与えないようにしておきます。DX戦略は全体の基礎になるものですが、絶対的なものではなく、場合によっては修正した方が良いのです。
導入結果の評価やフィードバックの受け取り
DX戦略の内容を完遂したり残念ながら中座したりした際は、取り組み結果の評価が必要です。上記で解説した定期的な評価と同様に、可能な限り定量的な情報を利用して判断を下しましょう。文句のつけようがないぐらいに成功することもあれば、思うように目標を達成できなかったこともあるはずです。多くの場合、DXは一度きりの取り組みではないため、良かった点と悪かった点を洗い出しておきます。
他にも、定量的な評価ではなく、定性的な評価も収集しておきましょう。例えば、社内の従業員からDXの過程で導入したシステムが前のシステムと比べて良いものであるかどうか感覚的な内容を集めておくのです。もし、「前のシステムと比べてボタンの配置が悪くなった」「色合いが変化して間違いが増えた」など定性的な面で不満が多いならば、方向転換なども求められます。
まとめ
DXを進めるにはまず戦略を立てることが重要です。戦略を立てる際にはいくつものステップがありますが、どの段階でもデータ分析が求められます。内部を把握するための社内データの分析はもちろん、外部環境を把握するために外部データの収集や分析も必要です。両者を組み合わせることで、質の高いDX戦略を策定できます。また、DX戦略を立てた後、実際にDXを推進する際にもデータは必要です。
ただ、外部データは簡単に手に入らないため、業務委託で収集するか買取する方が効率的です。特に、Web上にあるデータはスクレイピングサービスを利用することで、素早く収集してもらえます。弊社PigDataはスクレイピング代行サービスを提供しているため、DX戦略の策定やDXの推進に外部データを活用したい際はぜひご相談ください。