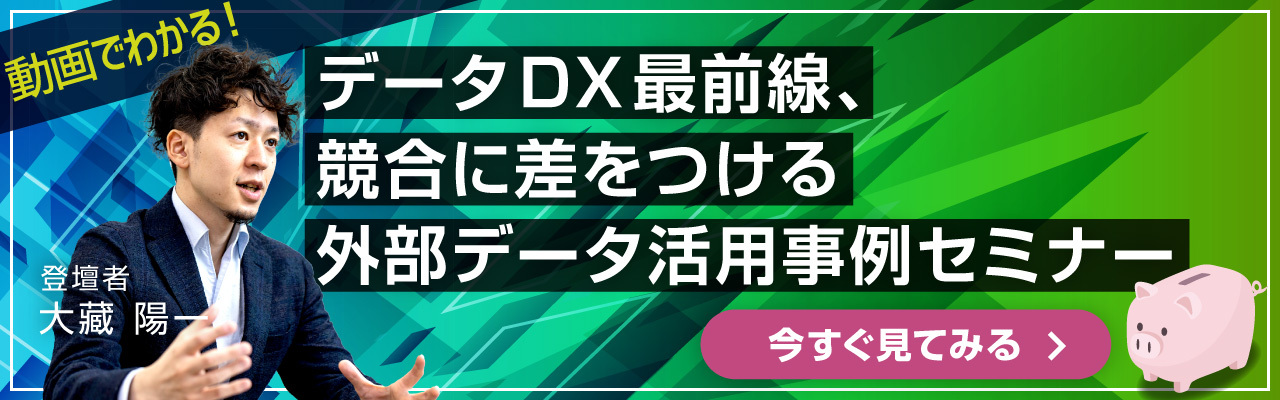世界的にDXの重要性が高まり、日本でも多くの企業が取り組むようになりました。皆さんの中にも、DXに興味を示している人が多いでしょう。しかし、DXとはどのような取り組みであり、なぜ必要となるか分からない方もいるでしょう。今回は、DXの概要や日本における状況、思うように日本でDXが進んでいない理由などを解説します。
DXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを革新することを指します。単なる業務のデジタル化だけではなく、ビジネスや業務そのものを革新させることが重要です。場合によっては、組織風土や文化などを根本的に改善することも含まれます。例えば、クラウドサービスの活用やビッグデータの解析によって、迅速な意思決定や効率的な業務の遂行を実現するなどです。
なお、これまでのIT化(デジタル化)とDXの違いは「業務の変革を通じて新しい価値を生み出すか」という部分です。IT化は業務を効率的に進めることに主眼をおいていますが、DXは効率化にとどまらず新しい価値を生み出すことに主眼をおいています。
DXの必要性
DXは、急速に変化する市場環境や顧客ニーズに迅速に対応するために必要とされています。従来通りのビジネスモデルや業務の進め方では市場で取り残されることがあり、これを防ぐためにDXが必要とされています。特に近年は「データドリブン経営」と呼ばれる、過去の実績や市場の情報など大量のデータに基づいた経営が重視されています。これを実現するために、DXによるデータ収集や活用の基盤、それらを活用できる業務フローが必須であると考えましょう。
実際、大手企業を中心に中小企業でもDXに積極的であるほど売上や利益が増加している状況です。つまり、DXは企業として長く生き残るために必須ともいえる取り組みになっています。
また、経済産業省が「2025年の崖」と表現したシステムの老朽化問題を解決する手法としてもDXが必要です。日本ではある程度のシステムが導入されていますが、5年から10年の期間が経過して、生産性に悪影響を与えるものが存在してしまっています。DXへの取り組みをキッカケに、これらのシステムを刷新することが求められるのです。
日本のDX推進状況
日本ではDXの重要性が強調されているものの、積極的に進められている状況ではありません。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX 白書 2023」によると、DXに取り組む日本企業は全体の70%程度です。2022年の調査では60%程度であったため、増加しているものの非常に多いとはいえません。また、全社的に取り組む企業は全体の55%程度にとどまり、企業の一部門だけでDXが進められているケースも見受けられます。これだけDXの重要性が叫ばれていても、日本では実際に行動ができていない企業が数多くあるのです。
なお、同じくDX白書2023を参考にすると、アメリカでDXを推進している企業は全体の80%程度です。日本でもDXが必要であると認識されるようにはなっていますが、世界的にみるとまだまだDXが遅れていると言えるでしょう。
DX推進のメリットとデメリット
DX(デジタルトランスフォーメーション)には多くのメリットがある一方で、導入にあたって注意すべきデメリットも存在します。次の項目では、DXの主な利点と課題について整理して解説します。
DX導入のメリット
業務の効率化・生産性向上
アナログ業務をデジタル化・自動化することで、業務プロセスが簡素化され、作業時間や人的リソースの削減につながります。これにより、社員がより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
データ活用による意思決定の高度化
業務や顧客から得られるデータを可視化・分析することで、属人的な判断に依存せず、科学的かつ戦略的な意思決定が可能になります。
顧客体験(CX)の向上
顧客の行動データやニーズをもとに、パーソナライズされたサービスやサポートの提供が可能になります。結果として、顧客満足度の向上やリピート率の改善が期待されます。
新たなビジネスモデルの創出
従来の枠を超えた新しい収益モデルやサービス提供の形が生まれることで、市場競争力の強化にもつながります。
DX導入のデメリット
初期投資と運用コストの負担
DXの推進には、システム導入や業務設計の見直しが必要となり、初期費用が発生します。また、継続的な運用や保守にもコストがかかる点は考慮すべきです。
DX人材の不足と育成の課題
社内にDXを担う人材がいない場合は、新たに採用するか育成する必要があります。これには時間と予算がかかるため、中長期的な計画が重要です。
社内の抵抗感や文化的障壁
ツールや業務フローの変更に対して、現場からの抵抗や混乱が起こるケースもあります。全社的な理解と段階的な導入が成功の鍵となります。
セキュリティやデータガバナンスのリスク
デジタル化が進むほど、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクも高まります。法令順守や情報管理体制の強化が欠かせません。
DX推進に必要なこと
DX推進の過程で必要となることを順番に解説します。
業務の洗い出しとデジタル化
最初に既存の業務を洗い出し、デジタル化の対象を決定しなければなりません。業務の詳細を把握して、デジタル化できるかどうかを評価していく作業です。また、デジタル化できる場合は単純に業務を電子化するのではなく、自動化や効率化を目指す「業務の変革」ができるかどうかも評価します。
例えば、紙を利用した出張申請について評価します。これをデジタルに置き換えることで、上司が外出中でもスマートフォンから承認できるようになります。これは単なるデジタル化にとどまらず、場所を問わずに業務がすすめられるという業務の変革、つまりDXといえます。
業務プロセスの根本的な改善
プロセスの根本的な改善は、DXの推進において重要なポイントです。DXは単なるデジタル化ではなく、変革が求められるため、ときには思い切った見直しも必要となります。
例えば、今まではFAXで送信してもらった注文書をメールで送信してもらうことも大きな変革となるでしょう。以下のような変革が考えられます。
- 変革前
FAXで注文書を受信⇒関係者へ紙を手渡す⇒担当者が手動でシステムに入力⇒担当者が在庫や納期を確認⇒納品
- 変革後
メールで注文書を受信⇒自動で受注システムに連携⇒自動でシステムに登録⇒担当者がシステムから通知を受け取り在庫や納期の確認⇒納品
このように手動の部分を減らし、デジタル化することは業務の根本的な変革といえます。この例は、FAXからメールへの切り替えにより、社外の取引先にも影響を与えてしまうものです。もちろん、取引先にも影響を与えるような変革は、影響範囲は常に評価し、慎重に進めることが重要です。しかし、このような業務プロセスの根本的な改善を実施することで、企業の競争力を高め、持続的な成長の実現に繋がるといえます。
社内外のデータ活用
社内外のデータ活用は、DXの成功に欠かせない要素です。データを収集・分析し、経営戦略や顧客サービスの改善に役立てます。例えば、顧客データを分析してパーソナライズされたマーケティングを実施したり、サプライチェーンデータを活用して在庫管理を最適化します。データ活用が成功すれば、企業がデータに基づいた意思決定を実現しやすくなります。その結果、データドリブンな経営につながり市場で優位性を獲得しやすくなるのです。
ただ、データを活用するためには「データ活用基盤」「データレイクやDWHなどのデータ蓄積ツール」「データ分析や可視化ツール」などの導入が必要です。
推進体制の構築
DXをするためには、推進体制を構築することが望ましいです。例えば、社内にDX推進室のような専門部署を設け、そこに配属された従業員を中心にDXを推進します。さらに、他の業務と兼任せず、DXの推進に専念できる環境に整えることでよりスムーズにDXを推進できるでしょう。
また、推進体制を整える際は経営層など重要なポジションの人材を含めることが重要です。DXを推進する過程では、企業全体に影響を与える決断が求められる可能性があります。その際に、迅速に決断を下せる体制が整っていなければ、DX推進が滞る原因となりかねません。
DX人材の育成や獲得
スムーズなDXの推進を目指すためには、DX人材の確保や育成が重要です。DX推進は専門的な知識が求められる取り組みであるため、それに対応できる人材を用意しましょう。可能であれば知識を要しているだけではなく、今までにDXの企画や推進など、DXプロジェクトの中核を担った経験を持つ人が望ましいです。
ただ、優秀な人材を外部から確保することは難しく、計画的に採用したり社内の人材を時間をかけて育成するケースが大半です。DXを進めるためには、スキルを持った人材の確保が非常に重要であるため、いつまでに、どのような人材が必要なのかを特に意識しておきましょう。
DX推進における課題
DX推進は重要な取り組みですが、現状として取り組めていない日本企業が約半数もいます。抱える課題について、代表的なものを挙げると以下のとおりです。
DXが進まない危機感の不足
社内のDXが進んでいないことに対しての危機感が不足しているケースが多く見られます。特に、経営者がDXに興味を示さず、推進しようとしていないことは大きな問題です。経営層が二の足を踏んでいる間に、DXを推進している競合他社に後れを取ってしまうことになりかねません。
危機感を持たない理由は多岐にわたりますが、例えばDX推進にはコストが生じることから「DXは予算を捻出できる大企業が行うものだ」などと考えているケースが挙げられます。確かに、コストを負担できないならばDXの推進は難しいこともあります。しかし、DXはその規模によってスモールスタートをすることも可能です。コストの問題を言い訳にし、推進できないことに対して危機感を感じないことは、大きな問題であると理解しましょう。
適切な人材の育成や確保の難易度
スムーズにDXを進めるためには、十分なスキルを持った人材の確保が重要です。しかし、上記でも解説したとおり人材の確保は難しく、人材不足がDX推進の大きな課題となっています。DXを推進しようとする気持ちはあっても、適切なスキルを持つ人材が見つからないことで、いつまでも具体的な行動に移せないのです。
外部から人材を確保するのではなく、内部で教育しようとする企業も見受けられます。その場合、DX人材は短時間で育つものではなく、短期的には人材不足に陥り、近々には課題を解決できないのです。
社内のITリテラシーの低さ
社内のITリテラシーが低いことはDX推進の障壁になりがちです。ITリテラシーが低い理由には、従来の業務プロセスが神谷手作業に依存していたことや、デジタルツールの導入が遅れていたことが考えられます。そのため、従業員がアプリケーションの基本的な使い方に慣れていない場合、DXを推進することにより、むしろ業務が滞ってしまう可能性があります。
近年はユーザーフレンドリーなツールが増えているものの、最低限のITリテラシーは依然として求められます。リテラシーの低い状況は簡単に解決できる問題ではなく、その改善には時間とお金がかかります。リテラシー向上がDXの成功を左右する要因となるため、社内での教育や研修が必要です。
DXの成功事例
DXの成功事例にはどのようなものがあるか具体的に紹介します。
味の素株式会社
味の素株式会社は、業務効率化と生産性向上の実現を軸としたDXを展開しています。特に、サプライチェーン全体のデジタル化を進め、リアルタイムでの在庫管理や需要予測を進めていることが特徴です。このDXにより、在庫とコストの削減を実現し、過不足の発生しない生産を実現しています。
また、社内の生産性を向上させるために、Web会議などコミュニケーションツールを積極的に導入しました。今では当たり前に活用されているツールですが、他社よりも早い積極的な導入により、部門間の連携強化や意思決定のスピードアップを実現しています。
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム株式会社は、DXを通じて製品開発と生産プロセスの効率化を実現しました。主に、IoT技術と収集したデータを活用する仕組みをDXの一環で導入し、生産ラインの自動化を進めています。また、センサーを活用した品質管理によって、素早いながらもエラー製品の少ないライン運営を実現しているのです。
また、ビッグデータ解析を導入し、消費者のニーズをリアルタイムで把握するデータ基盤も活用しています。これにより、新製品開発の効率を高めたり、顧客が求めているものをいち早くキャッチしたりできるようになりました。
株式会社IHI
株式会社IHIは、AIと機械学習を活用した予知保全システムをDXの一環で開発し、現在はこのノウハウを顧客向けにも提供しています。故障を事前に検知できる仕組みを導入することで、設備の故障予測やメンテナンスの効率化を実現しました。
また、3Dプリンタを用いた技術を採用して、製品の設計から製造までのプロセスを短縮していることも特徴です。昔から続く「匠の技」を3Dプリンタへ置き換えることを目標とし、人材の高齢化などによってスキルが失われることをDXで防ごうとしています。
株式会社クボタ
株式会社クボタは、農業分野におけるDXを推進し、スマート農業の実現に取り組んでいます。自社内で蓄積されたノウハウを「農機×ICT」という形で外部にも提供し、自社の関係者を巻き込んだDXを推進している状況です。例えば、ドローンやセンサーを活用した農作物の生育状況のモニタリングや、自動運転トラクターの導入した事業を展開しています。
株式会社ユニクロ
株式会社ユニクロは、DXを通じた顧客体験の向上を実現していることが特徴です。特に、オンラインとオフラインの統合を実現するために、顧客データを一元管理する仕組みを導入しました。これにより、顧客がオンライン・オフラインどちらで商品を購入しても統合されたデータベース上に記録され、パーソナライズされたサービスを提供できるようになったのです。
また、店舗でセルフレジを導入したり、倉庫で在庫管理の自動化を実現しました。顧客向けのDXだけではなく、社員にとっても大量の店舗を効率よく運営するためのDXも採用されています。
今後のDX
現在もDXは進められている過程ですが、今後はどのような変化を生み出すかも考えていきましょう。
DXを実施しない古い考えは淘汰される
大企業だけでなく中小企業でもDXが当たり前の時代になると、DXに消極的な古い考えは淘汰される可能性があります。例えば、業界標準の取引ツールの導入を渋っていると、取引先から敬遠されるかもしれません。特に、日本では大手企業の動向に従う傾向が強く、大手のDXに追随しない企業は競争力を失いかねません。
大手企業が推進するDXがデファクト・スタンダード(事実上の標準)となり、中小企業も同様のツールを導入しないければ業務が進まなくなるかもしれません。こうした変化に対応できない企業は市場から取り残され、古い考えは自然と淘汰されるでしょう。最終的にはDXが全国に広がり、日本で必須の取り組みとなる可能性があります。
データ分析がDXの鍵を握る
データ分析はDXを成功させる大きな鍵を握ります。例えば、社内で不良品が発生した理由をデータ化してみることで、どこに課題があるか分析できるでしょう。課題が明確になれば、DXでどのような仕組みを実現することで改善できるかを検討できるようになるのです。また、市場状況を頻繁に収集できるツールを導入し、データを分析しながら、生産計画を立てるなども考えられます。このように課題の原因がデータ分析によって可視化され、その解決方法もデータ分析から決定することができます。現在はデータドリブンな経営が求められているため、幅広い観点でデータを盛り込んだDXを心がけるべきです。
現在のDXは、依然としてツールによるデジタル化やデータ基盤の構築などが中心となっていますが、今後はこのようにデータ分析を中心とした推進が求められるでしょう。
DX人材育成が企業として当たり前に
これからの時代はDX人材の育成が当たり前になってくるでしょう。多くの企業でDXを推進する状況になるため、人材の奪い合いが生じてしまい、外部から優秀な人材を調達できなくなります。中長期的な発展を目指すためには、内部で人材を確保して継続的なDXに取り組んでもらう必要があります。
DX人材はプログラミングができる、といったITに関わる知識だけではなく、プロジェクトをしっかりと把握し、課題と解決法を見出せる力、つまり全体を見通す力が必要となってきます。そのため、DX人材の育成においては知識の詰め込みにならないよう注意しましょう。
まとめ
DXの推進においては、業務のデジタル化だけではなく、データ活用が非常に重要です。データに基づいてDXの戦略を立てることで、より効果的なDXを実現できます。また、データを活用する際には、内部データのみではなく外部データも掛け合わせていくことが必要です。
外部データにはいくつもの種類がありますが、中でもWebサイトのデータは誰でも収集可能な外部データです。スクレイピングと呼ばれる技術を利用した収集法を利用することで、自動的かつ効率的にDXに向けたデータを得られます。ただ、スクレイピングは知識や経験がないと法律に抵触することがあるため、個々での実施は避けたほうが良いでしょう。専門知識を持つ外部のサービスへ外注することをおすすめします。
また、PigDataではデータの収集から分析、可視化、活用まで一貫してサポートも行っています。データ活用でお困りの際は、ぜひご相談ください。