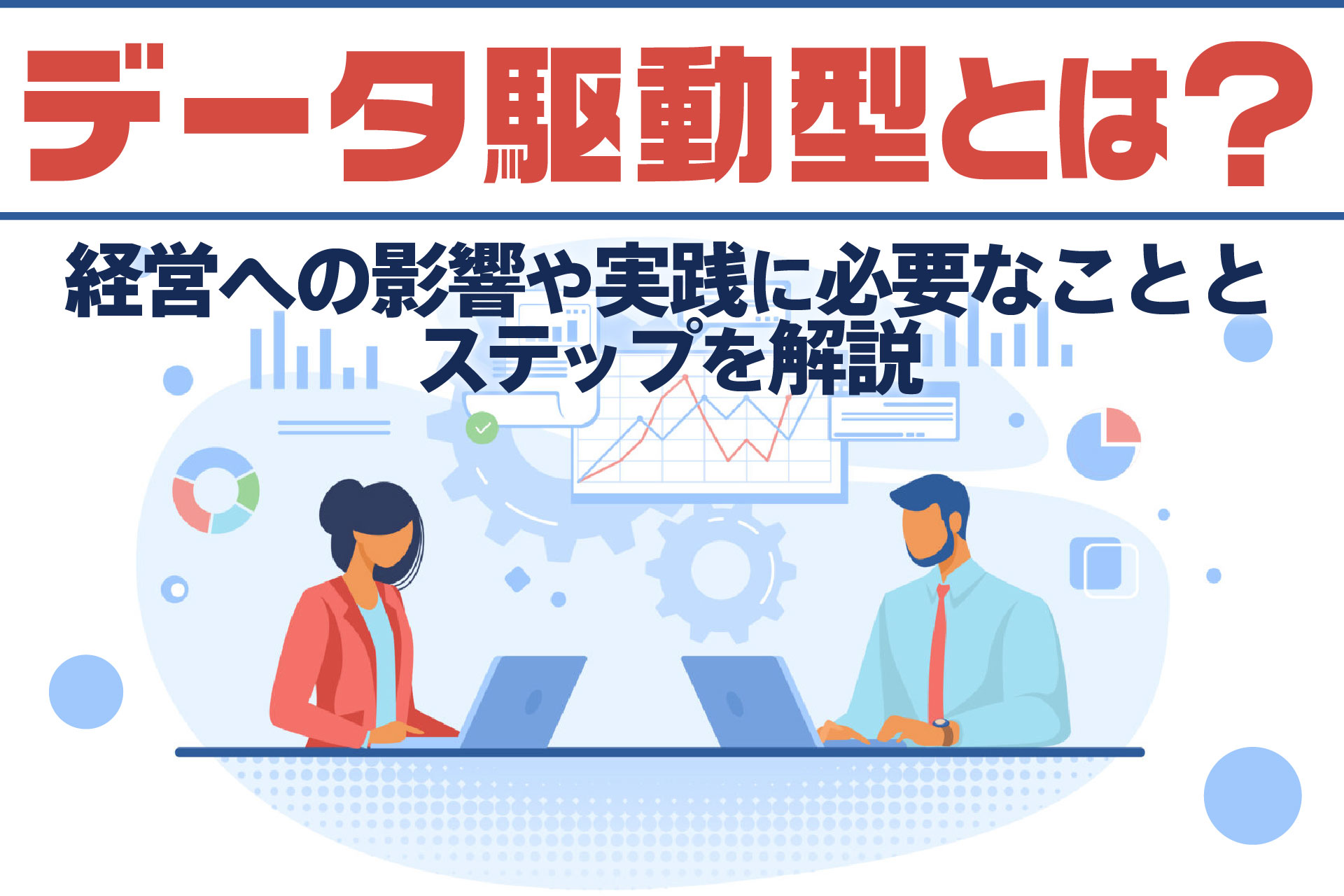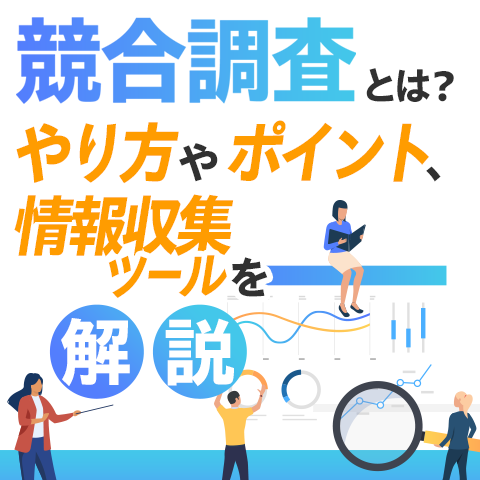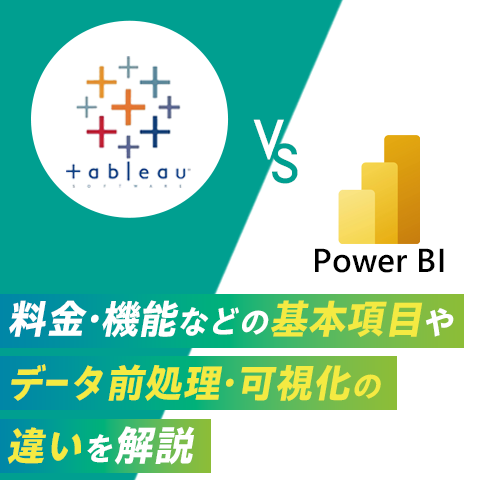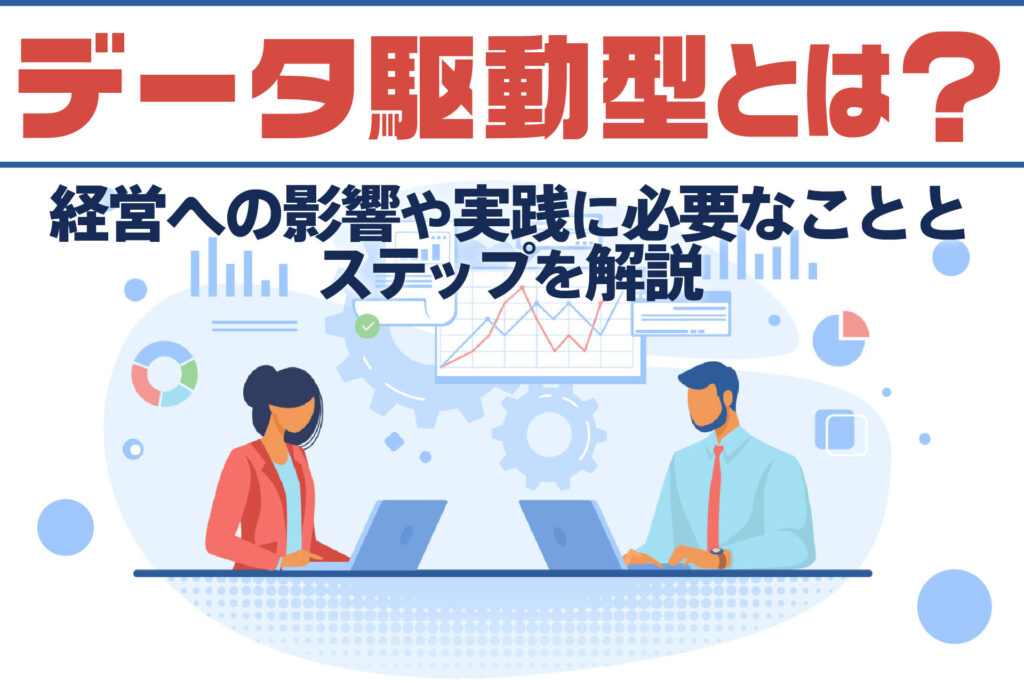
データの重要性が注目されている現在「データ駆動型」と呼ばれる考え方が広がっています。データドリブンとも表現されるものであり、データという根拠に基づいた判断を下すものです。DXが進められる過程で、データ駆動型というキーワードを耳にした人もいるでしょう。
ただ、実際にどのような考え方であるか理解できていない人も多いはずです。今回は、データ駆動型の基本知識からDXの関係性やメリット、実際の取組みについて解説します。
データ駆動型とは
データ駆動型とは、意思決定や行動をデータに基づいて実施するという概念です。経験や勘に頼った判断ではなく、データ分析や統計的手法を活用し、客観的な情報を基に判断します。ビジネスにおいては、売上データや顧客行動データを分析し、その結果をマーケティング戦略や商品開発に反映させることがデータ駆動型に該当するのです。データ駆動型を採用することで、今まで以上に精度の高い予測や業務効率化を可能にできます。
データ駆動型経営とは
データ駆動型経営とは、企業の意思決定時に、データを中心に据える経営手法を指します。経営に必要なデータを収集・分析し、その結果を基に戦略を立案したり実際に行動したりするのです。これにより、経営陣の経験や勘に頼った経営から脱却できます。
また、データに基づく予測や業務効率の評価などが実施されるため、効率的なリソース配分やリスク管理を実現できます。総じて、企業の競争力を高めるための経営手法であると考えられるのです。
データ駆動型とDXの関係
データ駆動型の概念は、DXの根底を支えると考えられます。つまり、これらは非常に関係性の高いものなのです。
DXで改善の対象としたい業務を洗い出すためには、データの分析が役立ちます。経営層や管理職が、感覚的にDXの対象業務を指定するのではなく、データから分析した結果を踏まえて決定するのです。科学的根拠に基づいたDX、つまりデータ駆動型のDXを推進することで、より効果が高くなると考えられます。
また、近年はDXの過程でAIを導入するケースが増えてきました。AIの用途は多岐にわたりますが、例えば大量のデータをAIを用いて分析し経営に役立つ資料を作成させるなどの使い方が可能です。人間の作業をAIに補助してもらうことで、データ駆動型をスムーズに進めることもできます。
データ駆動型のメリット
ビジネスにおいて、データ駆動型を採用することには、どのようなメリットがあるかについて解説します。
顧客ニーズや課題を明確にできる
社内に蓄積されている大量のデータを分析することで、顧客ニーズや課題を明確にできることがメリットです。蓄積されたデータの中には多くの知見が隠されています。これらを見つけ出し、判断の礎とすることによって、根拠に基づいた経営戦略を立てられるようになるのです。
例えば、商品の売れ行き状況とSNSの口コミデータと商品の売れ行きを組み合わせて分析することで、その商品が市場でどのように評価され、どのくらいニーズがあるか把握できます。その結果から新たな商品開発や商品改善につなげることができます。
顧客ニーズや課題は抽象的になりやすい部分ですが、データ駆動型にすることで、直感ではなくデータという客観的な根拠に基づいた判断を下せます。
収益アップを実現しやすくなる
データに基づいた根拠のある施策を立案できることで、収益アップを実現しやすくなります。今までのように担当者の直感や経験に依存せず、より安定した収益アップにつながるはずです。
例えば、生産計画を感覚に依存して作成するのではなく、過去の製造数やその販売実績などから算出するようにします。必要に応じて気候や市場の物価など、販売数に影響するデータも組み合わせることで、最も収益を期待できる生産数を算出できるのです。利益を最大化するための生産計画を立案できれば、無駄のない収益アップに大きく寄与してくれます。
なお、収益アップには2つの観点があり「売り上げの向上」「利益率の改善」です。どちらもデータ駆動型で実現できるものですが、異なるアプローチであることは理解しておきましょう。
情報の可視化と組み合わせて業務効率を高める
各種データの処理と可視化を組み合わせることによって、業務の効率化を実現できます。業務の問題点をデータから洗い出し、それを中心に解決していくことで、効果的な業務効率化が進むのです。例えば、商品の発注を受けてから実際に発送するまでの工程を「受付」「受付連絡」「担当者への指示」「在庫確認」「発送準備」「発送」と分割し、それぞれの作業に要する時間をグラフ化します。極端に時間を要している部分があるならば、その原因を分析し、改善できるような業務効率化を検討するのです。
データを分析しても、可視化していなければ問題に気付けない場合があります。業務効率の向上などに利用したいならば、直感的に読み取れる形式を意識しましょう。
意思決定に根拠を持ち精度が高まる
データを根拠とした意思決定にすることで、経験や勘に依存したものよりも精度が高まることがメリットです。今までのように、経験や勘に依存した判断と比較すると、失敗する可能性が下がると考えましょう。
人間の経験もある種のデータであり、経験を基にした判断というのもあながち間違ってはいませんが、そのデータは一般化することができず再利用ができません。それに対して、データ駆動型は一般化された多くのデータを数学など論理的な根拠に基づいて分析するため、客観的に根拠があるといえます。また、経験のように個人の感覚に依存してバイアスがかかることもありません。客観的な視点かつ論理的な根拠を持って意思決定できる点もメリットです。
新規事業の立案などに役立つ
様々なデータを組み合わせて分析することで、新しいビジネスを創出しやすくなります。これまで組み合わせていなかったデータを掛け合わせて分析することで、想定外の顧客ニーズが見つかる可能性があります。また、競合他社がサービスを展開していない分野であれば、いち早く参入することで、市場で大きなシェアを獲得できる可能性も考えられます。
新しいビジネスを創出する際は、これまでに試したことがないデータの組み合わせが必要になることもあります。しかし、データの組み合わせパターンを検討しても、過去の経験に基づいた偏りが生じ、新しいアイデアが生まれにくくなることが考えられます。
そのため、データ駆動型で新しいビジネスの創出を目指すならば、今までに試したことがないデータの組み合わせにチャレンジする意識が重要です。データの組み合わせパターンを機械的に試すなど、「このパターンは意味がないだろう」と無意識に排除せず、網羅的に挑戦する仕組み作りを検討してみましょう。
データ駆動型であるために必要なこと
データ駆動型の環境を実現するためにはいくつか必要なことがあります。
データ活用に向けた技術の導入
データを活用できる環境が整っていなければ、データ駆動型経営は実現できません。最初に必要な技術を導入して、データを活用できる環境を整えましょう。
例えば、データ活用の環境を一気に整える仕組みとして「データ活用基盤」と呼ばれるものがあります。NEC社の「NECデータ活用基盤」などの製品を利用することで、何も整っていない状態からでもデータ駆動型をスタートできるのです。
ただ、多くの場合はすでにシステムが導入されていて、それらにデータが格納されているでしょう。そのため、これらのデータを「Tableau」などの分析ツールに連携して、データ駆動型を実現することが多いはずです。
適切なデータ収集
データを軸とした考え方では、常にデータを収集することを心がけなければなりません。そのデータは、自分たちのビジネスに適切なものを意図的に収集することが重要です。社内にあるデータを収集して再利用することも求められますが、不足しているデータがあるならば、別の手段を用いて事前に集めておかなければなりません。
最低限必要なのは、社内にある「内部データ」を収集し、活用できるようにすることです。ただ、これだけでは不足することがあるため、公的機関が発表するデータやSNSなどWeb上にある「外部データ」も組み合わせます。複数のデータをかけ合わせることで、精度の高いデータ駆動型が実現されます。
経営層を軸とした意識改革
経営層を基軸として、データを活用した意思決定を下せるよう全社的な意識改革が必要です。もし、経営者や管理職がこれまで感覚で判断していたならば、それらをなくすよう変革を進める必要があります。例えば、経営目標を「今年はAさんから聞いたところ、主要商品の業界の動きが鈍くなりそうなので、別の業界に着手しよう」といった個人の感覚に依存して目標を立てるのではなく、「Aさんから主要商品の業界の動きが鈍くなると聞いたため、市場データを分析し、データに基づいた対策を立てよう」とすべきです。これは一例ですが、データ駆動型の仕組みを導入しても、それを利用する側の意識が伴わなければ意味がありません。
データ駆動型は社内全体で必要とされる考え方であるため、経営層を基軸としてトップダウンで展開することが望ましいでしょう。経営層から管理職、そして一般の従業員へと展開するようにします。
業務フローの根本的な改革
データを積極的に活用できるように、業務フローの根本的な見直しも必要です。データ駆動型に適した業務フローでないならば、根本的に見直すことを視野に入れましょう。例えば、製造の現場では業務フローを以下のように変更することが考えられます。
- 変更前:各工場の工場長が自分の経験や勘に基づいて生産計画を立てて、各ラインに指示する
- 変更後:製造部門が全ての工場の生産についてデータ駆動型で計画を立て、工場・各ラインへ展開する
この場合、それぞれの工場にデータ分析の仕組みを導入する選択肢もありますが、本社などで工場の生産量を一元管理する方が業務効率が良いでしょう。これにより、工場長が担っている仕事を奪うことになる可能性もありますが、工場長のような管理者には本社からの指令を作業者に的確に伝えるといった新たな役割が生まれるでしょう。
分析や活用に精通した人材の確保
一般的に、データ分析には専門的なスキルが必要とされます。ツールを活用することでサポートを受けられますが、全く知識がない状態ではデータ駆動型を実現できません。そのため、データ駆動型を牽引する立場となるデータ分析や活用に精通した人材を確保すべきです。いわゆる、データアナリストやデータサイエンティストと呼ばれるポジションを確保しなければなりません。
しかし、近年はデータ活用が注目されているため、このようなスキルを持つ人材の需要は高く、思うように見つかりません。また、ベンダーなどに支援を依頼しても、多くの案件を抱えていることから断られることがあります。そのため、データ駆動型を実現するためには、育成にせよ雇用にせよできるだけ早く人材の確保に向けて動き出すことが重要です。
データ駆動型実施のステップ
データ駆動型を実施するために、具体的にやるべき取り組みをステップで解説していきます。
活用目的の決定と現状の分析
最初に活用目的を明確にする必要があります。データ駆動型は幅広い状況で適応できる漠然とした考え方であるため、各企業が具体化していかなければなりません。
例えば、業績を向上させるために、データ駆動型の経営を目指すとします。ただ、これも漠然としているため「売上を増加させる」「事務作業に割く時間を削減する」などとさらに具体化していくのです。ここまで具体化できれば、データ駆動型で実現したい目的が明らかになります。
データ駆動型の活用目的を定めると同時に、現状について把握し、可能な範囲で分析しておきましょう。例えば、売上の増加を目指すならば、現状の売上高や利益率、主力商品など、経営で必要な情報を分析してまとめておきます。
データの収集
適切なデータが揃っていなければ、データ駆動型は実現できません。そのため活用目的に応じたデータを収集する作業が必要です。
例えば、製品のリピーターを増やしたいならば、商品の売上に関するデータや顧客に関するデータを準備します。また、前述のとおり社内に存在するデータだけではなく、Web上など外部に存在するデータも収集しましょう。競合他社の出す広告内容を収集し、分析することで競合他社の戦略を把握することができます。さらに自社製品と競合製品の特徴を相対的に分析することで、競合に勝つための広告戦略を立てることもできます。
このように、社内データだけではなく、外部のデータも多角的に収集し分析することが重要です。
データの分析
適切なデータの収集が完了したら、実際に分析を進めていきます。分析手法はいくつもあり、どのような結果を得たいか考え、選択しなければなりません。例えば、以下の手法が考えられます。
- 売上予測:時系列分析・回帰分析
- 顧客セグメンテーション:クラスタリング・RFM分析
- 需要予測:時系列予測・線形回帰
- 顧客離脱予測:生存分析・分類モデル
ここで重要となるのは、分析手法を誤ると、分析結果が役立たないものになってしまうことです。手法の選定には専門的な知識が求められるため、事前によく調査し、適切なものを選ばなければなりません。
データの可視化
一般的に分析結果は数字や文字の羅列になりがちです。この状態では直感的に理解しにくいため、可視化して直感的に読み取れるようにする作業が求められます。「Tableau」「PowerBI」「Google Charts」などのツールを用いて、グラフや表形式に変換しましょう。
なお、可視化においても「どのような形式を採用するか」が非常に重要です。例えば、円グラフと棒グラフでは直感的に伝えられる内容が異なります。そのため、適切な形式を選び、可視化することが重要です。
意思決定
分析担当者が結果を可視化したならば、それを基に意識決定者が判断を下さなければなりません。例えば「製品の売上を増加させるために、競合他社よりも広告の回数を増やし知名度の向上させる必要がある」という結果が提出されれば、その方針を採用するかを決定するのです。
なお、判断にあたっては実行に必要なコストなどの情報も必要です。上記の例であれば、広告の回数を増やすどれだけのコストが生じ、経営にどの程度のインパクトを与えるかが重要です。そのため、データ駆動型で意思決定を促す際は、意思決定者が必要とするコストなどの関連情報も併せて分析し、提供するとよいでしょう。
実行と結果の収集
方針が決まったならば、それを確実に実行に移さなければなりません。実行や結果が出るまでの期間は一概に断言できませんが、計画通りに進めることが大切です。定期的に進捗状況を確認するポイントを設け、計画通りに進められているかを確認することも重要です。もし、計画が遅れるようなことがあれば、その原因を特定し、適切なフォローアップを行う必要があります。
また、一通りの活動が完了した後は、その結果を収集する作業が求められます。例えば、売上の増加を目的としたデータ駆動型の活動であったならば、実際に売上が増加したかなどを確認します。そして、そのデータを収集し、収集結果を評価して、想定通りの効果があったかを分析します。この結果を次のデータ駆動型の取り組みに活かすことで、より効果的な活動が可能になります。
データ駆動型の成功事例
データ駆動型の成功事例について3社をピックアップして紹介します。
日清食品ホールディングス
日清食品ホールディングスは、全社データ基盤を導入し、データ駆動型の経営を成功させた企業です。データ活用専門の組織を準備し、経営の意思決定に活用されています。
例えば、サプライチェーンに関する情報を収集し、製造や配送におけるボトルネックの発見と解消を目指しています。自社の売上状況はもちろん、季節ごとに物流がどのように変化するかのデータや気候によってサプライチェーンに影響が出るかを評価したデータなど、いくつもの外部データを組み合わせていることが特徴です。
大企業ということもあり、まだまだこのような取り組みは社内でも限られています。しかし、経営層を軸にトップダウンでデータ駆動型を展開し、全社的なデータ活用を目指していることが特徴です。
日本調剤株式会社
日本調剤株式会社は、データ駆動型によって「患者中心の業務展開」を目指している企業です。従来は、調剤業務や監査業務が大きな負担となっていたため、データ駆動型によりこれを解消し、処方箋の内容をチェックしたり患者と会話したりする時間を増やしています。
具体例を挙げると、日本調剤株式会社では処方箋の内容を自動的に認識し、調剤ロボットが調剤業務を実施できる仕組みを整えています。社内の勤務データから、調剤に要する時間のコストを算出し、それ以上の価値を生み出すロボットを開発したのです。感覚的に「ロボットを導入しよう」と決定するのではなく、データ駆動型でピンポイントに調剤業務に特化したロボットを開発しています。
まとめ
DXを推進する際には、データ駆動型で進めることが重要です。実際のデータに基づいた方針を採用することで、より効果的な活動を実現できます。データ駆動型を行うには、利活用できる適切なデータの収集と分析が重要です。
データは社内に蓄積されているものを活用することはもちろん、外部で公開されているデータも組み合わせることで、より精度や信頼性の高い分析ができます。例えば、Webサイトに掲載されているデータを収集して活用することで、社内データの分析にさらなる根拠を加えたり、別の視点を得られるため、データ駆動型の質を高めることができます。
外部データのひとつであるWebデータを収集したいと考えるならば、スクレイピングと呼ばれる手法がおすすめです。スクレイピングを活用すると、自動でWebサイトの情報を収集し、データ活用に向けたデータ加工も同時に行えます。弊社PigDataはスクレイピングの代行サービスを提供していますので、ぜひご相談ください。