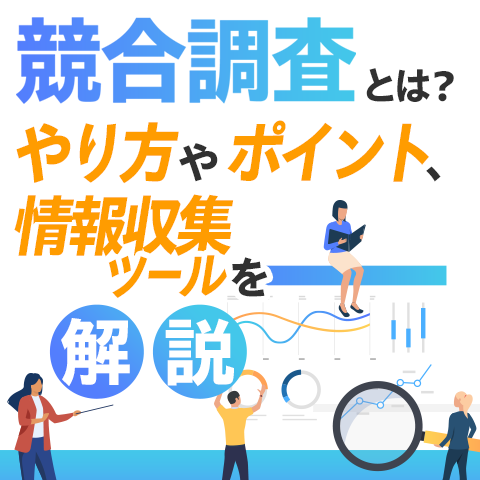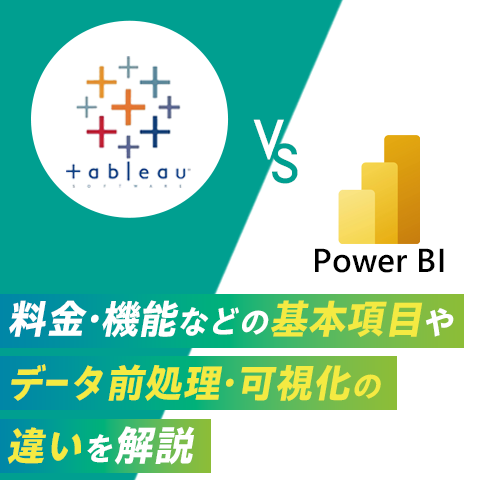DX推進室に配属され、DX推進を担う立場となった場合、データ活用や分析について理解が求められます。ただ、データの蓄積方法やその活用について理解できていない人は多いでしょう。類似する言葉が多いため、それらの違いを理解するのが難しいケースも見受けられます。今回は、データ活用に欠かせないデータウェアハウスの基礎知識や類語との違いなどについて解説します。
目次
DWH(データウェアハウス)とは
データウェアハウス(DWH)は、企業内のさまざまなシステムやデータソースから収集された大量のデータを統合・蓄積するためのデータベースです。主に分析や報告を目的として導入され、データを一元管理して、大量のデータを活用したサービスを提供します。多くの場合、データに基づいたビジネスインサイトの発見や意思決定のために導入されるものです。
また、一般的にデータウェアハウスは、高いデータ処理速度とアクセス性能を持つことが特徴です。大量のデータを素早く処理できるようになっているため、企業が長期間に渡って保存してきたデータも一瞬で処理したり分析したりできます。
DWHとデータベースの違い
データベースはデータの保存や編集など、データに関わるさまざまな機能を提供することを目的としています。データ分析に利用されることもありますが、日々の業務データやメディアサイトで公開されている記事の内容を保存することもあります。データベースは、システムやソフトウェアによって多様な用途で使用されるため、幅広いの機能が備わっています。
対してデータウェアハウスは、最初から保存形態が定義された状態で、データ分析に特化したデータのみが保存されています。一般的なデータベースのように幅広い用途は想定されていないのです。幅広い使い方ができるか、データ分析に特化しているかが大きな違いと考えましょう。
DWHとデータレイクの違い
データウェアハウスとデータレイクはどちらもデータ分析に向けて大量のデータを蓄積するツールです。ただ、保存できるデータの形式に違いがあります。
まず、データウェアハウスは、事前に定義された規則性のある「構造化データ」と呼ばれるものが保存の対象です。事前に決められた形式のデータを保存することによって、スムーズにこれらを活用できるように設計されています。対して、データレイクは規則性を持たない「非構造化データ」も保存の対象です。例えば、非構造化データと呼ばれる画像や動画、音声データ、さらに電子メールなども保存できます。
データレイクの方が幅広いデータを保存できますが、事前に形式が指定されていないため、分析の際に加工が必要という違いもあります。
DWHとデータマートの違い
データウェアハウスとデータマートは、どちらもデータ分析に適したツールです。しかし、分析対象の範囲に違いがあります。
データウェアハウスは解説したとおり、蓄積されたデータを幅広く活用できるものです。大量のデータを蓄積できるようになっているため、データ活用の方法も多種多様なのです。対して、データマートは最初から目的に沿って、最小限のデータだけを収集しています。例えば、社内向けに情報を発信するために、従業員情報から名前とメールアドレスだけを抜き出して保存するのです。
データウェアハウスが幅広いデータを扱うのに対し、データマートは一部のデータしか扱いません。その結果、分析に利用しようとしてもデータの種類が少なく、最低限の分析しかできないという違いを生み出してしまいます。
DWH(データウェアハウス)の機能
データウェアハウスが持つ主な機能について解説します。
サブジェクトごとに整理
データウェアハウスで管理されているデータは、サブジェクトごとに整理されていることが特徴です。サブジェクトとは、「顧客」や「商品」などといったデータのカテゴリを指します。一般的なデータベースは、システムやアプリケーションごとにデータを整理しますが、データウェアハウスはこのような分類方法で整理していることが大きな特徴です。
多くの場合、データウェアハウスは企業内のさまざまなシステムからデータを収集します。そのため、システムやアプリケーションごとにデータを分類してしまうと、同じ項目であったとしてもそれぞれ独立したデータとして格納されてしまい集約する意味をなしません。データを顧客や商品など利用しやすい分類ごとに整理しておくと、分析する際に活用しやすくなるため、データウェアハウスではこのような方針が採用されているのです。収集元のシステムやアプリケーションに関わらず、データが持つ内容ごとに整理されているため、純粋にデータの内容に注目した分析などが実施できます。
重複の排除とデータ統合
多くのデータソースからデータを統合すると同時に、重複データを排除する機能が実装されています。例えば、取引先の情報が複数のシステムに登録されている場合、それぞれが個別のデータとしてデータウェアハウスに連携されてしまうと、実際の取引先数よりも多く表示される可能性があります。このような状況で分析を行うと、現実と乖離した結果が出てしまうことがあります。データウェアハウスの効果を発揮するために、データの統合時に重複データを排除する仕組みになっています。
重複データの排除方法については、ユーザーが自由に設定できます。例えば「取引先の名称と住所が一致している場合に同じ内容であるとみなす」などと設定できます。また、「取引先」と「クライアント」の項目を同一のものとして扱い、重複データを排除することも可能です。
データを時系列に整列
データウェアハウスでは、過去から現在までのデータが時系列で整理されています。最新の情報だけを管理するわけではなく、データを連携し始めた初期から現在に至るまで、変化などを汲み取れるようになっています。時系列に整列されたデータを活用することで、過去から現在、さらに将来の予測に至るまで、データ分析を行いやすい点が、データウェアハウスの大きな魅力といえます。また、過去のデータを大量に保持しておくことで、当時どのような状況であったかをデータから再現できることも特徴です。
データの永続的な保管
データウェアハウスは、データを時系列で管理し、永続的に保存ができることが特徴です。一度、保存されたデータは、削除や上書きされず、そのまま保持されます。他のシステムやアプリケーションでは、容量や速度の問題でデータを削除することもありますが、データウェアハウスではそのような心配はありません。
データ分析において、過去のデータは非常に重要な要素です。そのため、不要と思われるデータもすべて保存しておくことが求められます。また、大量のデータを高速に読み取る仕組みも整っており、データを削除する必要は基本的にありません。ただし、契約しているデータウェアハウスのストレージ容量によっては、データ削除が必要になることもあるため、「無限にデータを保存できる」とは限らない点に注意しましょう。
DWH(データウェアハウス)の使い方
データウェアハウスの代表的な使い方を紹介します。
横断的な分析(総合評価)
様々なシステムからデータを集約し、横断的な分析が可能です。企業内の「会計システム」「顧客管理システム」「人事管理システム」などのデータは通常別々に保存されていますが、これらを統合することで、全社的な視点からの総合評価が実現します。例えば、顧客情報に従業員データや売上データを組み合わせることで、より包括的なマーケティング戦略や経営戦略を立案でき、部門間の連携を強化することができます。
このような横断的な分析は、組織全体のデータ活用力を高め、部門ごとのパフォーマンスの評価や改善に役立ちます。また、情報の一元化によって迅速な意思決定が可能となり、業務効率の向上にも寄与します。
時系列分析
大量のデータが時系列に沿って保存されているため、データウェアハウスでは時系列分析が可能です。日付や時刻に基づいてデータを分析し、特定のイベントが時間とともにどのように影響を与えているのかを把握できます。
例えば、特定の製品について小売価格と販売数の変化を時系列で分析することで、価格変動が売上にどのような影響を与えたのかを評価できます。さらに、景気の変動や季節要因などの外部データを組み合わせることで、より正確なインサイトを得ることができ、価格戦略やプロモーションの最適化に役立ちます。
このような時系列分析により、企業は過去のパターンから将来の動向を予測しやすくなり、意思決定の精度が向上や業務の効率化、売上の最大化が期待できるでしょう。また、異常値やトレンドの変化を早期に検知することで、リスクの軽減やチャンスの早期把握も実現できるでしょう。
予測分析(機械学習)
大量にデータを収集・蓄積することで、過去のデータから傾向やパターンを分析し、未来の動向を予測ができます。数理モデルや機械学習を活用し、売上予測や顧客行動の変化を高精度に予測できます。
例えば、過去の販売データをもとに商品の販売数を予測することで、適切な在庫管理やプロモーションのタイミングを見極めることが可能です。また、予測分析によりリスクやチャンスを事前に把握し、迅速な対応を取ることで、競合他社との差別化や市場での優位性を確保できます。正確な予測は、経営戦略の精度を高め、業務の最適化にもつながります。
DWH(データウェアハウス)の選び方
データウェアハウスには非常に多くの製品が登場しています。それらの中からどのように選べば良いのか理解しておきましょう。
提供形態
提供形態は、オンプレミスとクラウドがあります。
| オンプレミス | クラウド | |
| 導入方法 | サーバー準備が必要でインストールすることで利用できる | サーバー準備の必要がなく契約するだけで利用できる |
| コスト | 高い | 低い |
| 活用の制約 | 使い方に合わせてカスタマイズできる | 決められた機能しか利用できない |
オンプレミスは自分たちでサーバーを準備して、そこへデータウェアハウスをインストールする形式です。対してクラウドは、ベンダーが準備したサーバーなどにデータウェアハウスがインストールされていて、契約者は利用するだけの形式を指します。一般的に、オンプレミスの方が導入のハードルは高く、コストも高くなりがちです。ただ、自分たちに適したカスタマイズを施しやすいなどのメリットがあります。一方で、クラウドは導入のハードルは低いですが、決められた機能しか利用できないなどの制約が生じがちです。どのようにデータウェアハウスを活用していきたいかを考えて、選択することが重要です。
対応しているデータの種類
データウェアハウスが対応しているデータソースや形式を確認することが大切です。例えば、CSVやExcelファイルの取り込みに対応しているツールもあれば、HTMLファイルにも対応しているものもあります。現在使用しているサービスやツールのデータを活用したい場合は、それらと連携してデータを集約できるかどうかを確認しましょう。
自社で使用する可能性のあるファイル形式に対応したものをデータウェアハウスを選ぶことが望ましいです。予算に余裕がある場合は、より多くの形式に対応できるデータウェアハウスを選ぶことで、将来的な拡張性が高まります。データの多様性を考慮した選択がビジネスの成長につながるでしょう。
提供される機能の数
データウェアハウスには、提供される機能には違いがあります。例えば「マーケティング」や「製造」など、特定の分野に強い分析機能が搭載された製品があります。また、分析結果をExcelファイルに出力できるものもあれば、画面上でのみ表示されるものもあります。さらに、定期的に自動で分析を辞しするスケジューリング機能を持つものも登場しています。
一般的に、機能数が多いほど導入コストや運用コストが高くなります。また、機能数が多すぎると、社内のユーザーが使いこなせないリスクもあります。データをどのように活用したいかを考慮し、必要な機能数を適切に選択することが重要です。
ユーザインタフェースの使いやすさ
積極的にデータウェアハウスを使うためには、ユーザーインタフェースの使いやすさを重視しましょう。メニュー構成やボタンの配置が、必要なデータ活用に適しているかを評価します。最も使いたい機能が簡単に呼び出せないインタフェースでは、利便性が低くなり、導入しても使ってもらえないかもしれません。ユーザーインターフェースの使いやすさを評価する際は、実際のユーザーに協力してもらうことをおすすめします。一部の関係者だけで評価すると、実際に使うユーザーとの乖離が生じる可能性があります。広範なフィードバックを得ることで、選択肢の中から最も適したデータウェアハウスを見つける手助けとなります。
おすすめのDWH(データウェアハウス)製品
続いては、おすすめのデータウェアハウス製品を紹介します。
AnalyticMart:大量のデータ活用
AnalyticMartは、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社が発売する、大量のデータ活用に適したデータウェアハウスです。最大1億件のデータベースを3秒ほどで処理できる高性能さをアピールしていて、長期的に大量のデータを集約している企業におすすめします。日頃から大量のデータが生成される場合にも検討すると良いでしょう。
また、大量のデータを扱う際に気になりやすいポイントとしてストレージの容量がありますが、独自の圧縮技術によって最大40分の1まで縮小されることが特徴です。他にも、BIツール「DIAOLAP for Microsoft® Excel」と連携できるようになっています。これを組み合わせることでExcel形式でデータをアウトプットできるなどの点もポイントです。
Amazon Redshift:クラウド基盤で各サービスと連携
Amazon Redshiftは、クラウドサービスであるAWS上で提供されているクラウド型のデータウェアハウスです。AWSは並行処理を活用して様々な処理の高速化を目指しており、データウェアハウスにおいても、MPPと呼ばれる仕組みが活用されています。これにより大量のデータをデータベースに格納しても、高速に処理できることが特徴です。
また、各種AWSのサービスと連携して処理を自動化したり、他のサービスに連携したりできます。例えば、Amazon Redshiftで生成したレポートを特定のフォルダーへ格納し、それをメールで送付するなどを自動化できるのです。データウェアハウスとしてだけではなく、関連するサービスも活用しやすいため、AWSを検討する際は多角的な視点を持つと良いでしょう。
SOFIT Super REALISM:気軽に使えて速度重視
SOFIT Super REALISMは日本ソフト株式会社が提供するノーコードで処理を実装できるデータウェアハウスです。ノーコード開発に対応しながら処理速度が非常に高速であることが特徴で、テーブルから最大20億レコードを一気に処理できるようになっています。莫大な件数の処理に対応しているため、中小規模の企業がデータ分析する範囲においては、ほぼ一瞬であると考えてよいでしょう。また、特許技術を活用して、データをデータウェアハウスに取り込む速度も高速化しています。
シンプルな機能を意識しているため、データの入出力はCSVが基本です。複雑なデータソースには対応していないため、その点には注意しておかなければなりません。また、ビジュアライズなどに力を入れたいならば、分析した結果を別に用意したBIツールやExcelなどに取り込む必要があります。
Srush:データ統合とビジュアライズに注力
Srushは株式会社Srushが提供するクラウド型のデータ基盤です。データを収集するだけではなく、BIツールとしての機能も充実しているため、総合的なデータウェアハウスであると考えてよいでしょう。100種類以上のシステムと簡単にデータ連携できるようになっていて、データ収集や分析は用意されたボタンをクリックするだけです。
操作性を意識したデータウェアハウスですが、データ統合とビジュアライズのどちらにも力が入っています。気軽に利用できるシンプルなデータウェアハウスのように見えますが、コアな使い方もできるでしょう。事前に用意されている機能が多いため、求めている機能が実装されていれば、短時間で導入から活用まで行うことが可能です。
b→dash:ノーコードで専門知識が少なくても安心
b→dashは、株式会社データXが開発するノーコードでデータ分析を実現するためのデータウェアハウスです。一般的に、データを分析する際はSQLなどデータを操作する知識が必要ですが、こちらを利用すればその必要はありません。画面の指示に従って、データを取り込んだり分析方法を指定したりすることで、簡単に必要な結果を得られます。直感的に利用できるシンプルなデータウェアハウスであるため、初心者でも扱いやすいといえるでしょう。
ただし、事前に用意された機能の範囲内でのみ分析が可能です。マーケティング関連の機能が豊富に用意されていますが、他の分野については、求めてる分析に対応しているかどうか事前に確認しましょう。
DWH(データウェアハウス)の活用事例
続いて、データウェアハウスの実際の活用事例について紹介します。
富士通:グローバルデータプラットフォーム
富士通は改革のテーマとして「Data Driven」を掲げ、データに基づいた判断を下す戦略を採用しています。近年はビジネスに影響する要素が増えてしまい直感的な判断は危険なものになってしまいました。可能な限りデータという根拠に基づくことが求められているため、データに沿った意思決定を心がけているのです。DXの一環として取り組まれているもので、データを活用する基盤としてデータウェアハウスを導入しています。
また、特徴として日本国内の情報だけではなく、富士通が関係する世界中の情報を集約していることが挙げられます。グローバルデータプラットフォームとしての役割を担っていて、世界中の情報を瞬時に取り出したり分析したりできるようにしているのです。データを集約することによって、探し出す手間を削減できるだけではなく、世界中のデータが一元管理されていることで、分析に必要なデータが不足することもありません。現在は経営の変革という大きなテーマで活用されていますが、これからさらに富士通内で活用が広がるでしょう。
LIXIL:全社で使えるデータ活用基盤の構築
LIXILは、Google Cloudの様々なサービスを活用して、全社向けに展開しているデータ活用基盤を構築しています。日頃の業務はSAPやメインフレーム、Webアプリケーションなど様々なものが利用され、ここのシステムにデータが保存されている状況です。これらのデータをデータウェアハウスに集約し、これをLIXIL標準のデータ活用基盤と位置付けています。
データは日々の業務に活用されていますが、製造業らしい事例として「パーツの製造終了と売り上げの影響分析」が挙げられます。LIXILは大量の製品を発売しているため、一部のパーツを製造終了とすることで、製造・販売できなくなる製品が増えてしまいます。このような状況下で「一時的に売り上げがどの程度減少するか」「後続の製品にどの程度買い替えてもらえるか」などを、データ分析基盤から予測したのです。大量のデータから分析することで、競合他社よりも精度の高い計画を立て、製品の刷新などを進めています。
日清食品ホールディングス株式会社:データドリブン経営への足がかり
日清食品ホールディングス株式会社は、データドリブン経営を実現するための基盤として、データウェアハウスを導入しています。現状、データを活用し始めている過程ではありますが、足がかりとして導入したと考えてよいでしょう。社内に点在していた各種データを集約し、分析した結果はBIツールを利用しビジュアル化できるように段取りしています。
また、効率の良いデータ活用を目指して、生成AIの導入にも着手していることが特徴です。2023年から生成AIを積極的に導入し、グループ全体でデータドリブン経営を実現できるように取り組んでいます。データウェアハウスを社内全体に展開することも考えているなど、これからどのように活用するか注目です。
DWH(データウェアハウス)を有効活用するには
データウェアハウスを有効活用するためにはどうすれば良いか理解を深めていきましょう。
大量のデータを用意する
最初に大量のデータを蓄積しておくことがポイントです。データウェアハウスは、分析や活用に向けてデータを取り出す仕組みであるため、格納されているデータ量が少ないと思うように効果を十分に発揮できません。目的を達成するために、十分な量のデータを用意するように心がけておきましょう。
基本的には、社内のツールなどさまざまなソースをデータウェアハウスに接続し、活用するための準備を整えます。データが宝の持ち腐れとならないように、保有しているデータはなるべくデータウェアハウスへ集約することが重要です。また、社内のデータだけで不足する場合には、外部のデータも取り入れも考慮しましょう。例えば、スクレイピングによってWebサイトの情報を収集し、内部データと掛け合わせることで、より効果的なデータ活用が可能です。
過去のデータも積極的に分析する
現在のデータだけではなく、過去のデータも積極的に分析することが重要です。データウェアハウスの大きな特徴は、過去のデータも含めて同じ系列に集積されている点です。直近のデータだけ分析していては、データウェアハウスの利点を生かせないため過去のデータも視野に入れるべきです。例えば製品の売り上げ状況について、直近1年のデータだけでなく、2年前や3年前も分析対象とします。長期的な視点でデータを分析することで、売上の変化を判断し、極端な増減の原因を分析することで、マーケティングに役立つ情報が得られるかもしれません。
一般的に分析対象となるデータが多くなるほど、分析結果の精度は高まります。しかし、データ量が増えても不要なデータが含まれていると「ノイズ」となりかねません。そのため、データウェアハウスの設定で調節するようにしましょう。
広く開放し幅広い使い方を試す
データウェアハウスにデータを蓄積することで、幅広いデータ分析を実現できます。これを最大限に生かすために、多くのユーザーが利用できるように開放し、様々な使い方を試してもらうといいでしょう。多くの場合、データウェアハウスを導入してもDX推進室や情報システム部門、マーケティング部門など、特定の部門だけが利用する傾向があります。一部のユーザーだけが使い続けると、分析対象のデータや手法が固定化され、偏った使い方になってしまうことがあります。これを回避するために、データウェアハウスを幅広く開放して、自由な発想でデータ分析にチャレンジしてもらうことが大切です。
まとめ
DWHは構築して終わりではなく、業務ごとのデータ統合設計、更新の自動化、そして実際の活用まで見据えた仕組みづくりが欠かせません。
私たちPigDataは、データ分析や業務改善のゴールから逆算し、お客様に最適なDWHやデータパイプラインを設計・構築いたします。SaaSや業務システム、Excelなどバラバラなデータを統合し、“活用できる状態”までご支援させていただきます。