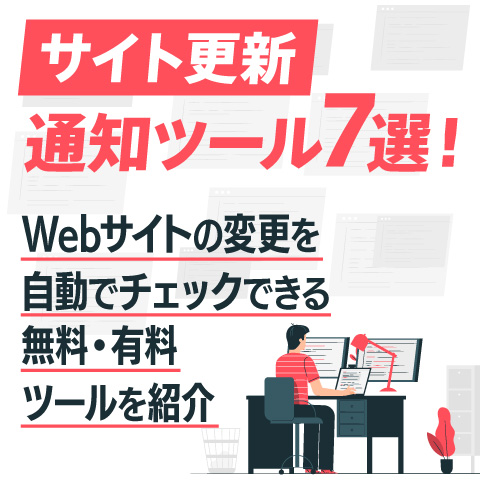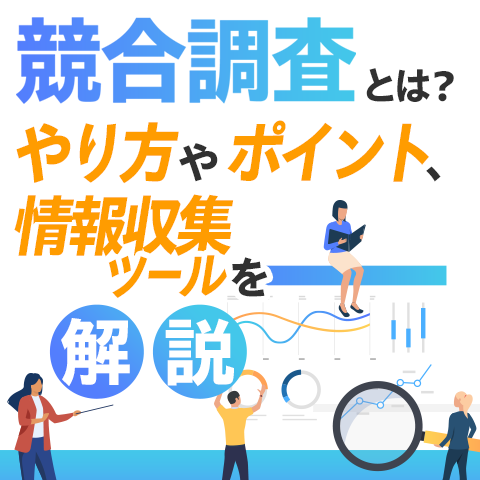大企業を中心にデータを収集したり、活用したりする方法として、データパイプラインが注目されています。皆さんはIT部門の担当者としてデータパイプラインの活用を任されているのではないでしょうか。データの収集から分析などの活用まで効率よくこなしたいと考えていることでしょう。
ただ、データパイプラインが便利とは耳にしていても、具体的にどのような仕組みか理解できていないのではないでしょうか。今回は、データパイプラインの概要や重要性、導入によるメリットや注意点を幅広く解説します。
データパイプラインとは
データパイプラインとは、幅広いデータソースから取得したデータを自動的に収集・変換・補完し、分析や機械学習などの用途に適した状態へ整えるプロセスやツールを指します。一連の処理によって、データ管理や品質維持を効率化し、データドリブンな経営を支援します。また、データパイプラインを活用することでデータ処理の自動化が可能となり、組織内での手作業を削減する効果を生み出します。
このように、組織内に蓄積されているデータを効率的に活用するための仕組みとして、データパイプラインはますます注目を集めています。
データパイプラインの重要性
迅速かつ正確な意思決定のために、データパイプラインは非常に重要です。正確なデータが素早く手に入ることで、より迅速で確実な意思決定ができるようになります。また、品質の高いデータを安定的に供給できるという点でも重要です。データパイプラインは自動的に処理が実行されるため、必要なタイミングで可能な限り新しいデータを参照できます。データが新しいほど正しい意思決定ができるため、この観点でも非常に重要な仕組みなのです。
データパイプラインとETL
| データパイプライン | ETL | |
| システム化の範囲 | データ収集から連携、可視化までの一連 | データ連携や加工のみ |
| データ加工の有無 | 機能を構成するETLなどが担当する | データの加工処理が含まれる |
| データの可視化 | BIツールなどで可視化できる | 可視化の機能はない |
ETL(Extract、Transform、Load)はデータの抽出・変換・保存をバッチ処理で行う手法であるのに対し、データパイプラインはETLを含むリアルタイム処理やストリーミング処理など幅広いデータ処理を扱う仕組みです。
ETLはデータパイプラインの重要な機能の一部であり、データの統合や管理に欠かせません。データパイプラインは、ETLを含むさまざまなデータ処理を行うための包括的な仕組みである、という違いがあります。
データパイプラインのメリット
データパイプラインのメリットを解説します。
データ分析業務の効率化・自動化
データパイプラインによって業務を効率化や自動化できる点は大きなメリットです。データ分析業務は手動で実施している組織も多く、負担に感じている企業が多いでしょう。しかし、データパイプライン構築することで、大量のシステムから自動的にデータを収集できます。分析作業のたびにデータをかき集める手間がなくなり、業務効率を大きく改善できるのです。また、データパイプラインにはデータを可視化する部分も含まれています。定期的に作成するレポートを自動出力処理にすることで、さらに業務を効率化することが可能です。
データ品質の向上
データパイプラインを整備することで、複数のソースから取得したデータの整合性や一貫性を確保でき、データ品質の向上を図れることがメリットです。例えば、ETLを利用することで、連携されたデータのフォーマットを統一したり、重複を排除したりできます。事前に定めたルールに沿って実施されるため、人的ミスなどのトラブルが発生せず、安定した品質を担保できるのです。
また、データを監視することによって、異常なデータの検知や通知ができるメリットもあります。人間では異常値に気付けない可能性が高いですが、システム化することで異常値なども検知しやすくなるのです。
意思決定のスピードアップ
データ収集から分析、可視化までが自動化されるため、意思決定の迅速化を期待できることがメリットです。必要な情報を素早く取得できるため、経営者や現場の担当者が、ほぼリアルタイムにデータドリブンな意思決定を下せるようになります。また、上述のとおりデータの正確性や整合性を担保できるため、意思決定の精度を向上させることが可能です。データ不備があると、意思決定をやり直すなどの手戻りが生じますが、データパイプラインを構築すれば防ぐことができます。
非エンジニアのデータ活用
データパイプラインの整備は、非エンジニアがデータ活用できる環境を整えることに繋がります。例えば、ノーコードやローコードツールをBIツールと連携することで、誰でも容易にデータ活用ができるようになります。経営部門やマーケティング部門など、各々がデータを分析したいときに、自分たちの手でデータを分析し、可視化できます。非エンジニアのデータ活用が進めば、組織全体でデータドリブンな文化を定着させることが可能です。「エンジニアにデータ分析を依頼する必要がある」というボトルネックがなくなり、スムーズなデータ活用を促進できるでしょう。
データパイプラインの仕組み
続いてデータパイプラインの仕組みを紹介します。
1.データの取得
まず、さまざまなデータソースからデータを取得しなければなりません。データの取得は、分析や意思決定に活用するための基盤構築する重要なプロセスです。このプロセスを通じて、企業はデータを一元化し、リアルタイムでの分析レポートを作成することができ、ビジネスの競争力を高めることに不可欠な要因となっています。
データを取得する方法として、下記の方法があります。
- API連携
- ファイル転送
- データベースに接続して転送する方法
- Webスクレイピング
データソースは組織の内外に存在するため、適切なデータソースから最適な方法で連携する必要があります。また、収集頻度の検討・設定や外部攻撃による機密情報の漏洩対策などセキュリティ面を考慮する必要があります。
2.データクレンジング
データクレンジングとは、取得した「生データ」から重複や欠損値、不完全、無関係なデータを検出し、修正または削除する作業です。これによりデータの品質を高め、分析結果の信頼性が高まります。具体的には、以下のような作業をを行います。
- 文字化けの修正
- 不要文字の削除
- タイムスタンプの整形
- 規格外の単位を標準化
データクレンジングは所定のルールを設けて自動的に処理するため、可能な限りルール化することでデータの品質を高めることができます。
3.異常値の排除
異常値の排除は、データクレンジング後により品質を高める作業ために必要な作業です。異常値は、センサーの誤作動やデータ入力ミスなど、さまざまな原因で発生します。異常値を適切に検出し、必要に応じて排除または修正することは、分析結果の信頼性を確保するために重要です。
例えば、入力されたデータのうち、ひとつだけ極端に大きな数字(異常値)があるとします。データクレンジングでは、フォーマットが正しい場合に修正や削除はされませんが、異常値の排除では、値の正常性を確認するため、異常であれば排除します。
4.データモデリング
データモデリングは、データ要素とその関係性を視覚的に表現し、データ構造を体系的に定義するプロセスです。これにより、データの整理・管理・利用が容易にするためデータ活用には必要な作業です。例えば、ツールがデータベースからデータを読み込む仕様なら、ツールがデータを取り込みやすく高速に処理できるテーブルを設計するなどです。
また、モデルの設計のみならず、メタデータの管理なども、このタイミングで実施しておくと良いでしょう。データの加工が終わってからメタデータを付与することで「分析や可視化に今すぐ活用できるデータ」を後から素早く見つけられるというメリットを得られます。
5.データの可視化・共有
データの可視化は、複雑なデータを視覚的に表現し、パターンや傾向を直感的に理解するのに役立ちます。また、データの共有は、関係者間で情報を効果的に伝達し、意思決定を支援することで、組織全体のデータ活用能力が強化されます。また、可視化することにより下記のメリットがあります。
- データ内の隠れたパターンやトレンドを発見しやすくなる
- 専門知識の異なる関係者間での情報共有をしやすくする
- 迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うことができる
また、データパイプラインにリアルタイムのダッシュボードや自動生成レポートなどの機能を組み込めば、最新の情報を素早く把握できます。経営層などが容易に確認できる仕組みを導入すると、データドリブンな意思決定をより促進できるのです。
データパイプライン導入の際の注意点
データパイプラインを導入する際には注意点もあります。
各工程を独立させない
データパイプラインを構築する際に、それぞれの工程を個別に設計しないことが重要です。収集・クレンジング・モデリング・可視化という流れであるため、個別に設計すると、修正や拡張の際に問題が生じる可能性があります。また、障害が発生した際に、原因を特定できないなどの問題にも繋がりかねません。そのため、データパイプラインの構築時は、依存関係や処理内容を相互に意識することが重要です。全体を一元管理しながら構築することで、構築やその後の運用もスムーズになるでしょう。
解決したい課題をまずは洗い出す
データパイプラインを導入するだけでは、効果を得られない可能性があるため、まずは解決したい課題を洗い出しておきましょう。洗い出すことで、構築工程の中でどの作業に注力すべきか判断しやすくなり、作業の無駄を省きます。例えば、「在庫管理の精度を高めたい」「マーケティング施策を最適化したい」など具体的な目標を設定します。これにより「どのデータを収集するか」「どのように分析したいか」が明確になるのです。
効果検証により定期的に改善する
導入時のデータパイプラインは、要件定義に基づいて設計されたものです。ただ、運用を進めていく中で、想定外の問題点や改善点が見つかることもあります。そのため、効果検証を定期的に実施して、改善すべき部分がないか確認すべきです。例えば、全体の処理速度に注目して、遅延による業務への悪影響がないか確認します。また、データ品質に注目して、クレンジングの精度を確かめることも大切です。
このように、データパイプラインを効果的に活用するためには、検証するだけではなく、課題や問題の早期改善が重要です。
データパイプライン導入のポイント
データパイプラインを導入する際のポイントについて解説します。
データパイプライン構築支援サービスを活用する
可能な限り、データパイプライン構築支援サービスを活用しましょう。構築にあたっては、複数のシステムやツールを横断的に理解する必要があり、専門的な知識が求められます。ただ、これらの知識をすべて習得することは現実的ではありません。そのため、専門的な知識を持つ構築支援サービスを活用することをおすすめします。コストは掛かりますが、リスクと比較すると十分に価値のある選択です。
データパイプラインの前提を定義する
データパイプラインを円滑に機能させるために、前提を定義することがポイントです。どのようなデータを、どれくらい、どのような速度で扱うのかなど明確にしておきます。さらに、データの保存形式や品質要件、ライフサイクル管理の方針なども定義すると良いでしょう。リアルタイム分析を前提とするか、バッチ処理で十分かによって、構築する環境に変化が生じます。
他にも、ビジネス上のユースケースを踏まえることで、導入する分析ツールが明確になるでしょう。セキュリティポリシーを考慮することでデータを守るために必要なコストを決定できます。前提となる要素は多岐にわたるため、必要なものをピックアップして定義することがポイントです。
新しいニーズに備えておく
社内でデータ活用を基にした意思決定を進めていくことで、データ活用の新しいニーズが出てくることもあるでしょう。導入時には想定していなかった規模拡大や新たな分析手法の採用などが発生するかもしれません。そのため、データパイプラインは、将来の拡張性を踏まえた設計とすることが望ましいでしょう。
例えば、モジュール化された構成やAPIの活用によって、データソースの増減や分析ツールの変化に対応できるようにします。また、システム全体をコンテナ化することで、スケーリングによる高負荷への対応を実現するのも良いでしょう。
新たなニーズに備えるには、業務的な観点に加え、データ基盤としてインフラ的な観点、その他の観点からも備えることが重要です。
データパイプラインの事例
データパイプラインを構築する事例について紹介します。
DWHやデータマート構築
データパイプラインの代表的な活用例として、データウェアハウスやデータマートの構築があります。複数のシステムに蓄積されたデータをETLで収集・統合し、分析に最適化された形を蓄積します。例えば、営業部門のシステムから顧客データや販売データを収集し、顧客行動をセグメント化しておくことで、必要なときにこのデータを参照し、レポートやダッシュボードとして可視化できます。
また、データウェアハウスだけではなく、特定の部門や用途に合わせたデータセットを提供するデータマートを構築することも可能です。これにより、担当者がより効率的にインサイトを得られるように、システム面で支援します。例えば、ソーシャルゲーム事業を行う株式会社ルーデンは、Google Big QueryとTROCCOを導入し、データ分析基盤の構築を行いました。
大規模データを活かしたリスク分析
大規模なデータを活用してリスク分析を行うこともデータパイプラインの重要な活用例です。多様なデータソースからリアルタイムで大量のデータを取り込み、機械学習や統計モデルで分析します。その結果を専用のツールへ連携することで、発生しうるリスクを早期に検知・評価できます。
例えば、金融機関では不正取引の兆候を検知する仕組みがデータパイプラインで実装されています。また、保険会社では、保険金の不正請求がないかをデータから分析しています。これらは、過去の取引履歴など内部に蓄積されたデータを組み合わせ、リスクの数値化や内容の可視化を実現しています。
データパイプラインを構築することで、状況の可視化やアラート設定などの自動化が可能となり、リスクマネジメントをより正確に実施でき、作業コストの削減にも寄与します。
その他の活用事例
データパイプラインは、他の業界や用途でも幅広く活用されています。
- 小売業 :在庫管理や顧客購買行動の分析
- 製造業 :生産ラインの効率化や品質管理
- ヘルスケア業界:患者データの統合や診断支援
これらの事例から、データパイプラインの構築は、組織のデータ活用能力を高め、競争力の向上やリスク管理の強化に大いに貢献することがわかります。
まとめ
データパイプラインは作るだけでなく、“回り続ける”ことが大切です。データを集める・整える・届けるという一連の流れが、止まらず正確に、現場の意思決定につながることがゴールです。
私たちPigDataは、複数システムからの自動データ収集、変換・統合、BI連携までを一気通貫で設計・構築いたします。属人化や手作業に頼らない、“業務に組み込まれたパイプライン”の構築をご支援いたします。