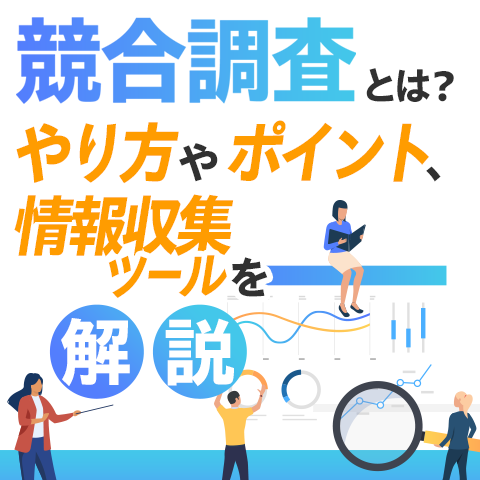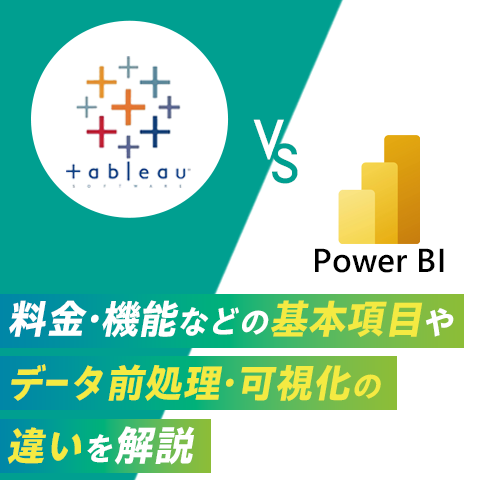社内に大量のデータが蓄積される時代となり、これらを活用したいと考える企業の担当者は増えています。皆さんも、積極的に社内のデータを活用したいと考えているのではないでしょうか。
蓄積されているデータの活用方法はいくつもありますが、その中に、データマートの構築が挙げられます。既に検討を進めている人もいるかもしれません。今回は、社内に蓄積されたデータを有効活用するためのデータマートの概要やタイプ、具体的な製品と導入のメリットやデメリットまで、必要な情報をそれぞれ解説します。
目次
データマートとは
データマートとはデータウェアハウスの一種で、特定の業務や目的に特化したものを指します。企業全体のデータを集約して管理するデータウェアハウスとは異なり、販売や財務、マーケティングなど特定の分野に特化してデータが最適化されていることが特徴です。各部門に必要なデータのみが集約されているため、レポート作成や分析作業を容易に行えるようになります。
似たような言葉との違い
データマートと似た言葉との意味合いの違いについて解説します。
データベースとの違い
データマートとデータベースは、構築の目的が大きく異なります。データベースとは、業務システムや各種ツールなどと連携し、さまざまなデータを管理する仕組みです。多種多様なデータを格納する可能性があり、構築の目的は状況によって大きく異なります。一方で、データマートは特定の業務や目的に特化したデータだけが格納されたものです。データを格納し、管理しているという観点ではデータベースと同じですが、格納されているデータの内容や構築する目的には違いがあります。
データレイクとの違い
データマートとデータレイクは、データの構造や用途に違いがあります。データレイクは、構造化・非構造化データを大量に保存する生データの蓄積基盤で、AI・機械学習や高度な分析など幅広い用途に活用されます。対して、データマートは、特定の業務部門向けに整理・加工されたデータを格納し、分析やレポート作成などが目的です。データレイクは加工する前のデータを保存するツールであり、データマートは整備されたデータを保存するツールであるという違いがあります。
データウェアハウスとの違い
データマートとデータウェアハウス(DWH)は、格納されるデータの範囲や用途が異なります。まず、データウェアハウスは、企業全体のデータを統合・管理するツールです。大規模なデータ基盤なデータ基盤であり、データドリブンな経営を実現するため、幅広い用途に利用されます。対して、データマートは、特定の業務部門向けに最適化された小規模なデータストアです。データドリブンな経営を実現するものの、全社的ではなく、部門や業務単位での最適化に利用されます。一般的に、データウェアハウスからデータを抽出・加工してデータマートを構築します。そのため、全く違うものではなく、データの範囲が違うものと考えればよいでしょう。
データマートのタイプ
データマートには、大きく分けて3つのタイプがあります。
従属型データマート
従属型データマートは、データウェアハウスからデータを抽出・加工して構築するタイプのデータマートです。データウェアハウスで全社的なデータを管理し、そこから各部門の分析ニーズに応じて必要なデータを抽出します。データウェアハウスからデータを抽出するため、データの一貫性が保たれ、全社的にデータガバナンスを確保しやすいことがメリットです。一方で、データウェアハウスを介するため、データの更新や取得に時間がかかることはデメリットになってしまいます。
独立型データマート
独立型データマートは、データウェアハウスを経由せず、業務システムなどから直接データを収集して構築されるデータマートです。特定の部門やプロジェクトのニーズに応じて、迅速にデータ分析環境を整えるために利用されます。ただ、データマートだけが独立しているため、他のシステムとデータ内容に齟齬が出てしまう可能性があります。また、データの重複やサイロ化が発生することがあり、これらにも注意した運用が必要です。
ハイブリット型データマート
ハイブリッド型データマートは、従属型と独立型の特長を組み合わせたデータマートです。一部のデータはデータウェアハウスから取得し、一部は直接業務システムなどから収集できるように設計されています。そのため、データガバナンスと柔軟性を両立できることが特徴です。ただ、データウェアハウスとも業務システムとも連携するため、設計や運用が複雑になりやすいです。データ連携の仕組み作りが難しいなど、注意点もあります。
代表的なデータマート
データマートにはいくつもの製品があり、それらの中でも代表的なものをピックアップして紹介します。
BigQuery
BigQueryは、Google Cloudが提供するフルマネージド型のデータウェアハウスです。パブリッククラウドの中でも、大規模なデータ分析を高速で実行できるため注目されています。クラウドベースのデータマートでサーバーレスアーキテクチャが採用されているため、データのスケーラビリティが高いこともポイントです。また、Google Cloudが提供するAIやBIツールとの連携がスムーズで、データレイクとしての活用もできます。比較的、料金形態がシンプルで、コスト効率が高いこともポイントです。
Redshift
Amazon Redshiftは、AWSが提供する大規模データ向けのクラウドデータウェアハウスです。ここではデータマートとして解説しますが、AWSではデータウェアハウスとして扱われています。データマートの中でも、カラムナストレージと呼ばれる技術が利用されていて、クエリ処理が最適化されていることが特徴です。加えて、Redshift Spectrumと呼ばれる機能を利用して、S3(ストレージサービス)へ格納したデータを分析することもできます。スケーラビリティが高く、大量データの処理にも対応しているものの、BigQueryと異なりクラスタ管理が必要です。適切に運用することが求められ、やや専門的な知識が必要な点には注意しておきましょう。
Synapse
Azure Synapse Analyticsは、Microsoft Azureが提供する統合データ分析基盤です。データウェアハウス(Azure SQL Data Warehouse)とビッグデータ処理を組み合わせたデータマートとして活用できます。SQLベースの分析だけでなく、Apache SparkやPower BIとの連携にも対応していることが特徴です。Microsoftのサービスということもあり、総じてMicrosoft製品やサービスとの親和性が高くなっています。他にMicrosoft製品を使用している場合、Synapseを軸に考えると使いやすいかもしれません。
データマートのメリット
データマートを構築するメリットを解説します。
目的に沿ったデータ分析がしやすい
データマートは、特定の業務部門や目的に最適化されたデータを格納しています。そのため、必要なデータのみを素早く取得でき、分析を効率化できることがメリットです。
例えば、マーケティング部門なら顧客データに特化したデータマートを構築します。また、販売部門なら売上データに特化したデータマートを構築することがあるでしょう。どちらも不要な情報を排除することで、効率的な分析を実現できます。
また、データレイクとは異なり、データマートは事前にデータが整理されています。結果、複雑なデータ処理を必要とせず、スムーズに活用できることもメリットです。
データに関する業務を効率化できる
データマートを活用すると、業務部門が必要なデータを即座に取得できます。その結果、データ抽出やレポート作成の手間が削減されることはメリットです。従来、データ分析には、データを抽出するなどIT部門の後方支援が必要でした。しかし、データマートを構築することで、各部門が自分たちでデータを活用できるようになります。待機時間が削減され、業務スピードの向上に貢献してくれるのです。
構築に時間がかからず安価である
データマートは、データウェアハウスに比べて小規模なシステムで、構築にかかる時間やコストを抑えられます。特に、クラウドのデータマートを活用すれば、インフラ構築が不要で、短期間で導入が可能です。また、特定の業務に特化したデータのみを扱うため、データウェアハウスのように多種多様なデータについて考慮する必要がありません。これによりスモールスタートしやすいことも、安価であることにつながっています。
データマートのデメリット
データマートを構築することにはデメリットもあります。
データセットやデータテーブルの管理が必須である
データマートは特定の目的に最適化されたデータを格納するツールです。そのため、常に必要なデータセットやテーブルを管理しなければなりません。データの正確性を維持したり、業務を効率化したりするためには、継続的なデータの管理が必須です。特に、複数のデータマートを構築すると、データの重複や不整合が発生しやすくなります。
分析の観点は人間が指示する必要がある
データマートを構築する場合でも、分析の観点は人間(ユーザ)が指示することが求められます。自動的に分析するようなツールではなく、人間が一定の知識を持って運用しなければなりません。例えば、データマートに集約されたデータのうちどの指標を重視するかは、人間の判断に依存します。そのため、分析の観点や解釈を誤ってしまうと、意図しない結論を導いてしまうかもしれません。他にも、データマートの失敗事例として「必要なデータが不足している」ということも挙げられます。人間が分析の観点を見極められていないことで、後からデータの不足に気づいてしまうのです。
データマートの活用例
データマートを業務で活用する例を紹介します。
販売データの分析
データマートを活用すると、売上データや在庫データをリアルタイムで分析できます。これを活用し、販売戦略の最適化などが可能です。例えば、店舗ごとの売上傾向や時間帯別の販売動向を把握すれば、商品の補充タイミングを把握することが可能です。また、顧客の購買履歴を分析すれば、リピーター向けのプロモーションを企画するなどもできるでしょう。売上の低い商品について、取り扱いを終了するなどの決断も可能です。
マーケティングキャンペーンの効果測定
マーケティングキャンペーンのデータマートを構築すると、広告のクリック数、コンバージョン率、売上への影響などを詳細に分析できます。例えば、SNS広告やメールマーケティングを実施し、その結果をデータマートに集約します。その後、データを詳細に分析し、どの施策が最も効果的だったかを特定することが可能です。また、ターゲット層ごとの反応を分析し、より訴求力の高いキャンペーンの創出に活かすなどもできるでしょう。
財務データの集約と分析
各部門の財務データを一元的に集約し、リアルタイムでの収支分析や予算管理する使い方も考えられます。例えば、売上、経費、利益率などを集約すれば、視覚化して経営層が意思決定する手助けに活かせるのです。また、過去の財務データを分析することで、将来のキャッシュフロー予測やコスト削減策を立案するなどもできます。総じて、企業全体の財務健全性を向上させることに役立てられるのです。
データマートを活用するポイント
最後に、データマートを活用するためのポイントを解説します。
利用目的を明確にする
データマートを最大限に活用するには、利用目的を明確にすることがポイントです。これがなければ、分析に必要なデータを見極めることができません。例えば、「売上分析を強化する」「マーケティング施策の効果を測定する」といった具体的な目的を設定します。これにより、具体的に連携すべきデータが見えてくるのです。また、分析手法も定めやすくなります。反対に目的が曖昧な場合、不要なデータを収集することになり、処理の複雑化や分析の精度低下が起こるリスクが高くなります。
長期的な予算の策定や確保を意識する
データマートは、構築時だけでなく、運用や拡張のためのコストも考慮すべきです。特にクラウドベースのデータマートでは、データ量の増加に伴いストレージやクエリ処理のコストも増加するため、長期的な視点で予算を確保することが重要です。また、新たな分析ニーズが生じた場合に備えて、スケーラブルなシステムを選択したほうが良いでしょう。柔軟性を高めることで、段階的に予算を確保しながら、機能拡張なども進められます。
品質の良いデータを用意する
データマートの分析精度を高めるには、正確で一貫性のある品質の良いデータを用意することが不可欠です。データの重複や欠損、不整合があると、分析結果に誤りが生じてしまいます。データの品質を高めるためには、データのクリーニングや更新ルールの明確化が必要です。また、ひとつのデータウェアハウスからのみデータを取得するなど、データソースの厳選も求められます。
まとめ
データマートは、データ活用の“第一歩”にすぎません。部門ごとに最適化されたデータを作ることは重要ですが、手作業で更新されたり、統一されていないと、結局“使えない”状態になりがちです。
私たちPigDataは、業務にフィットするデータ構造の設計から、自動更新の仕組み構築まで支援いたします。まずは一部門のデータマートから、将来の拡張性を見据えた土台づくりをお手伝いします。