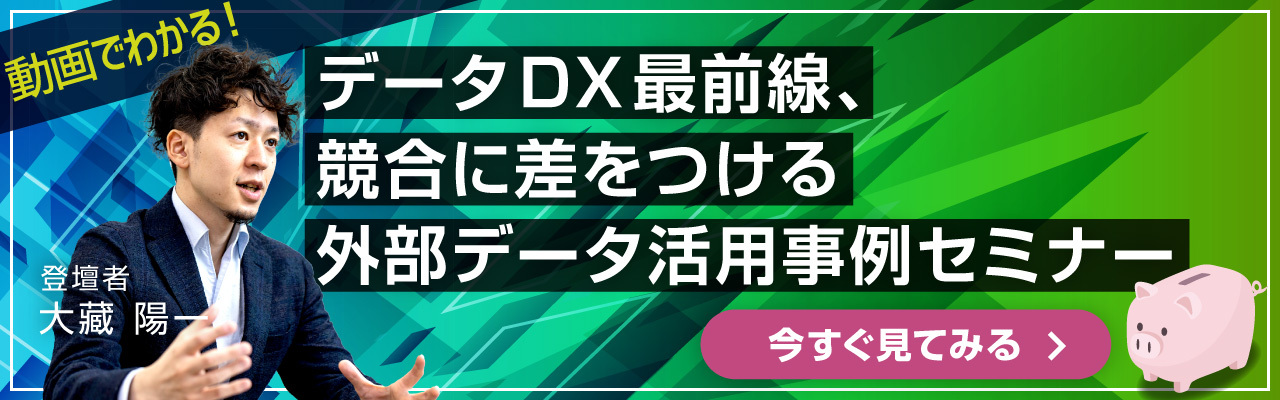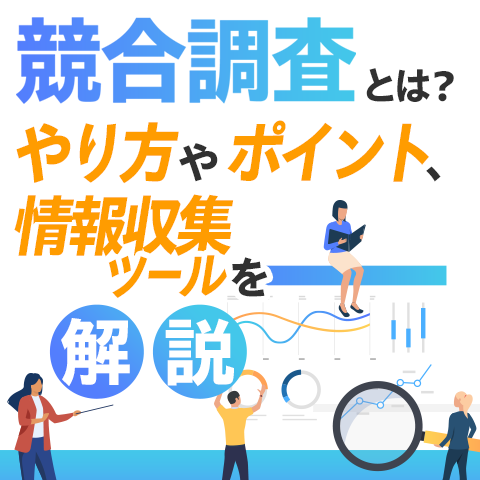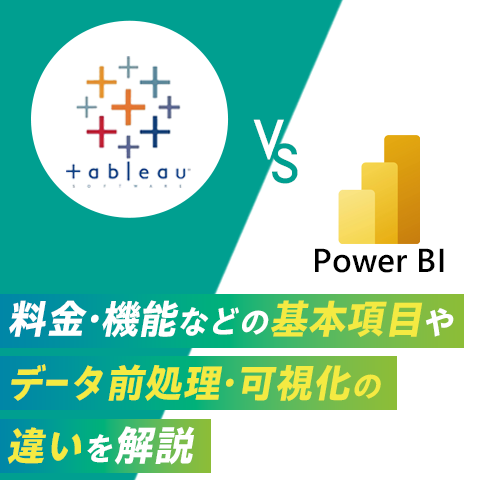データマネジメントは多くの企業で求められる活動であり、注目される時代となりました。特に大手企業のDX担当者やマーケティング担当者、データ活用専門の担当者、データドリブンな経営を実現したい経営者に注目されています。ただ、注目されている活動ではあるものの、データマネジメントやこれを踏まえたデータ活用の詳細は正しく理解されていません。今回は、データを活用したい多くの人へ向けて、データマネジメントについて解説します。
データマネジメントの基礎知識
最初に、データマネジメントとはどのような取り組みであるのか、基礎知識を習得していきましょう。
データマネジメントとは
データマネジメントとは、企業や組織が持つデータを効率的かつ効果的に収集・整理・保存・活用するための技術や方法論を指します。一般的に、データの質を維持しつつ、適切なガバナンスを確保することが目的です。具体例を挙げると、データベースの管理やセキュリティの強化、バックアップによるデータの保護などが該当します。
近年は、データの量が急速に増加し、データの形式も多種多様になってきました。また、データの保存先がオンプレミスのみならず、クラウドストレージなどにも分散されるようになっています。このように分散したデータをデータの種類や保管場所を問わず、一元管理することをデータマネジメントと呼ぶのです。
データマネジメントはなぜ必要なのか
データマネジメントが必要とされる理由は、データの価値が企業の競争力や効率性の向上に大きな影響を与えるからです。例えば、ビジネスの現場では、顧客データや市場動向データなどが意思決定や各種戦略を策定する基盤となります。しかし、データを適切に管理していないと重複や不正確な情報が含まれる可能性があり、誤った経営判断ミスにつながるリスクがあります。ビジネスのパフォーマンスを最大限高めるには、適切なデータマネジメントが求められます。
また別の観点では、各種規制対応のためにデータマネジメントが必要です。例えば、EU一般データ保護規則であるGDPR(General Data Protection Regulation)では、個人データを適切に管理することが求められています。これは一例ですが、データを活用するという観点だけではなく、データを集める立場として責任を持ち、適切に管理することも重要です。データマネジメントは効率性向上と法順守の双方の観点で、企業活動において不可欠な要素となっています。
データマネジメントの全体像
データマネジメントの全体像を国際的なルールを踏まえて解説します。
DMBOKが標準的
データマネジメントにあたっては、DMBOK(Data Management Body of Knowledge)と呼ばれるフレームワークを利用することが一般的です。DMBOKは、データマネジメントにおける標準的なフレームワークで、DAMA(国際データマネジメント協会)が提供しています。主に、データマネジメントの全体像を体系化し、組織がデータの収集、管理、利用を効率的に進めるための指針を提供しています。
このフレームワークは、11の領域から構成され、データガバナンスを中心に据えていることが特徴です。これに関連し、データの品質やセキュリティ、アナリティクスなど、それぞれの領域がどのように相互作用し、組織全体のデータ戦略に貢献するかを示しています。
組織としてフレームワークを活用することで、全社的に一貫性のあるデータ戦略を実現しやすくなるだけでなく、データに基づく意思決定の精度を向上させ、競争力を強化することが可能です。また、複雑なデータマネジメントにも対処しやすくなるため、世界的に採用されることが増えています。
データマネジメントで必要となる11の領域
DMBOKでは、データマネジメントを以下の11の領域に分類しています。
- データガバナンス:データの管理に関する方針や責任の明確化
- データアーキテクチャ:データの構造やフローを設計
- データモデリングと設計:データ構造の論理的・物理的モデルの作成
- データストレージと運用:データの保存と効率的なアクセスの確保
- データセキュリティ:データの機密性、整合性、可用性を保護
- データ統合と相互運用性:異なるシステム間でのデータ連携
- データ品質管理:データの正確性や一貫性の確保
- データウェアハウスとBI:データの集約と分析基盤の提供
- ドキュメントとコンテンツ管理:非構造化データの管理
- メタデータ管理:データの属性や関係の管理
- 参照データとマスターデータ:一貫性のある基盤データの管理
これらの領域を体系的に推進することで、組織はデータを価値ある資産として活用し、意思決定や業務運営を改善することができるようになります。これらの取り組みを通じて、規制対応やリスク管理の向上にも寄与するため、データマネジメントは現在の企業活動において不可欠な要素です。
データマネジメントをするメリット
データマネジメントを実施するメリットについて解説します。
必要なデータを発見しやすくなる
データマネジメントを適切に実施すると、必要なデータを発見しやすくなります。データが適切に整理されるため、データを探す時間を削減し、業務効率が向上します。
例えば、メタデータ管理を導入すれば、データの内容や関連情報がすぐに把握できるようになります。さらに、データカタログや検索機能を導入すれば、企業に蓄積されているデータを迅速かつ簡単に見つけられるようになります。
このように必要な情報をすぐに見つけられることで、データ発見効率が向上し、より積極的なデータ活用が可能になります。
意思決定などにつながる
必要なデータが見つけやすくなるだけでなく、そのデータが正確かつ信頼性が高い場合、事実に基づいた意思決定が可能になります。
例えば、売上データや顧客動向データを迅速に活用できれば、市場の変化に素早く対応する戦略を立てられます。また、可視化ツールなどを用いることで、データを簡素かつ視覚的に分析しやすくなり、戦略的な業務改善につながります。これにより、効率的で的確な意思決定に役立つのです。
非構造化データも管理できる
適切なデータマネジメントによって、画像や動画、テキストデータ、PDFファイルなど非構造化データも管理できるようになります。これらは世界に存在するデータの約80%を占めると言われており、これを適切に整理・管理することは企業の競争力向上に大きく寄与します。専用のツールやストレージを活用することで、大量の非構造化データを効率よく整理し、活用可能な形に変えることができます。
例えば、顧客のフィードバックやSNSデータを分析することで、消費者の行動傾向や新たな需要を発見できる可能性があります。さらに、製品開発やサービス改善に役立つ洞察を得ることで、顧客満足度の向上や市場競争力の強化にもつながります。このように、非構造化データの活用は新規ビジネスチャンスの創出にも寄与します。
コスト削減と業務効率化が図れる
データマネジメントを適切に行うことで、業務の効率化だけでなくコスト削減の効果も得られます。データが整理されていない状態では、必要なデータを探す手間や、不必要なデータストレージの増大がコストを圧迫します。一方、データを統合管理することで無駄を削減し、リソースを最適に配分できるようになります。また、データの重複や不整合を防ぐことにより、不要な作業や修正コストも削減できます。こうしたコスト効率化は、企業全体の生産性向上にも寄与します。
法令遵守とリスク管理の向上
データマネジメントは、各種規制や法令に対応するための基盤を構築する上でも不可欠です。例えば、GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など、データ保護に関する規制に対応するためには、データの適切な収集、保存、利用が求められます。これにより、企業は法令遵守を徹底し、罰則や訴訟リスクを軽減できます。さらに、サイバーセキュリティの観点からも、データの管理体制を整備することで、不正アクセスや情報漏洩といったリスクの回避につながります。
組織全体のデータ活用力を強化できる
データマネジメントを実施することで、部門間の連携が強化され、組織全体でデータ活用力を高めることができます。データの一元管理により、異なる部門が同じデータセットを共有し、整合性のある情報をもとに協力できる環境が整います。この結果、部門間の意思疎通がスムーズになり、より戦略的かつ一貫性のあるアプローチを取ることが可能となります。データ活用が企業文化として根付くことで、持続可能な成長とイノベーションが促進されます。
データマネジメントをする際の障壁
データマネジメントの実施にはいくつもの障壁があります。具体的な障壁を挙げると以下のとおりです。
データの分散やサイロ化
データが分散していたり、サイロ化したりしている状態では、必要なデータを素早く収集・統合できません。部門ごとに異なるシステムやフォーマットでデータを管理していると、全社的なデータ統合に悪影響を与える可能性があります。それぞれのシステムに保存されている内容の整合性の確保や信頼性が低下により、思うように活用できない原因となりうるのです。
例えば、顧客データが営業部門とマーケティング部門でそれぞれ管理されている場合、それぞれの部門で重要な情報を個別に管理している可能性があるため、全体像を把握しながらの統合はしづらくなります。さらに、これらの個別データを一元化することは手間がかかるため難しく、データマネジメントの障壁になってしまいます。
データを処理できる人材不足
データマネジメントを推進するためには、データエンジニアやデータアナリスト、データサイエンティストといった専門的なスキルを持つ人材が必要です。しかし、対応できる人材が不足してしまうことが障壁になっています。
しかも、データを処理できる人材の育成には、一定の期間とコストが生じます。データマネジメントを推進したいからといって、一朝一夕で用意できるものではありません。データに強い人材は慢性的に不足している状況であり、できるだけ早く計画的に確保することが求められます。
経営層の理解不足
データマネジメントを成功させるためには、経営層の支援と理解が不可欠です。しかし、経営層がデータの価値や管理の重要性を十分に認識していない場合、これが障壁となるでしょう。例えば、適切なリソースや予算が確保されないことにより、データマネジメントが頓挫する可能性があります。
特に、データ管理のための基盤構築やツール導入はコストが高く、全社的な支援がなければ導入できません。つまり、経営層に理解してもらうことが非常に重要となります。理解が不足している場合は、データマネジメントの必要性を説明することから始めましょう。
組織間での連携が難しい
組織間でデータに関連する連携が困難なことも、データマネジメントの障壁となりかねません。例えば、部門ごとに異なる目標や業務上の優先順位があると、協力が難しくなります。その場合、組織全体で共通の目標を設定し、部門間の連携を強化することが重要です。
また、仮に組織間で人的な連携が取れたとしても、システム的な連携ができないことが多々あります。例えば、それぞれの部門が異なったシステムを導入していることで、これらを簡単に統合できない場合があります。その場合は、システム間のデータ連携を行うことや、既存システムへ集約、新規システムの構築などの方法が求められます。
データを活用する文化が浸透していない
データを活用しようとする文化が浸透していないと、データマネジメントの意味合いを理解してもらえません。コストの掛かる取り組みであるため、理解を得られないと協力を得られず活動の推進時に大きな障壁となってしまうでしょう。
これを解決するためには、データリテラシーの向上に向けた教育などが必要です。また、トップダウンでプロジェクトを推進するなど、マネジメント力も必要になってきます。
データマネジメントのポイント
データマネジメントにはポイントがあるため、どのような意識が必要であるか解説していきます。
目的の明確化
データマネジメントを成功させるためにはデータ管理の目的を明確化することが重要です。目的が明確にならないままデータマネジメントを進めると、収集するデータや活用方法がバラバラになってしまいます。また、方向性が定まっていないことで、各々が自由にデータを活用しようとするなど、運用が難しくなる原因ともなりかねません。
考えられる目的にはさまざまあり、以下のシーンが考えられます。
- 顧客満足度の向上
- 業務効率化
- 新規ビジネスの創出
具体的な目的を設定しておくことで、必要なデータや管理手法も明確になります。できるだけ内容の具体化を心がけましょう。
また、目的が明確であれば、データマネジメントの効果を評価しやすくなります。例えば「残業時間を3時間削減する」という目的を設定しておくと、データマネジメントの実績から、効果を定量的に判断できるのです。
データ運用の体制を整える
データマネジメントを安定して進めるには、データの運用体制を適切に整える必要があります。例えば、データ管理の責任者を設けたり、部門ごとに対応すべき事柄を定めたりすることが、成功には不可欠です。それぞれの役割を明確にすることで、全体のガバナンスが強化され、運用がスムーズになります。
また、管理体制を整えるだけではなく、データの所有権やアクセス権、セキュリティポリシーなどを整理し、周知することも重要です。すべての従業員が適切にデータを扱える環境でないと、データマネジメントの成功は難しくなります。IT部門を中心に、全社的な取り組みを推進することが、組織としてデータマネジメントの成功につながります。
データの品質を担保し続ける
データマネジメントを継続して行うには、データの品質を担保し続ける必要があります。不正確なデータや重複したデータが含まれると、データ全体の品質が下がってしまい、意思決定や業務プロセスに悪影響を及ぼすことになりかねません。そのため、正確性を保ち、常に最新のものにアップデートする取り組みが重要です。
例えば、データ入力時のエラーを防ぐ仕組みを整えておくことで、不正確な内容や重複したデータを防げるでしょう。また、定期的なデータクレンジングの実施や、ルールの徹底を調査することも重要です。
データマネジメントの進め方
最後に、データマネジメントの基本的な進め方を解説します。
データマネジメントに関する構想の策定
データマネジメントを始める最初の一歩として、全体の構想を策定することが重要です。例えば、データ活用の目的や目標を設定し、必要なリソースやマネジメントまでのステップを具体的に決定します。データ管理方法や管理責任者などを明確にしておかなければなりません。
他にも、データガバナンスやセキュリティ対策について、基本的な方針を明確にすることも重要です。例えば「どの活動にどれだけのコストを割り当てるのか」「外部からの支援を受けるか」などを考えることが該当します。構想の段階で全社的な方向性を一致させておけば、全社的にデータマネジメントを進めやすくなるのです。
データ管理ツールやシステムの導入と設定
構想の策定が完了したならば、実際にデータマネジメントを実施するためのツールやシステムを検討します。また、検討したものを導入し、適切に設定する作業が必要です。構想によって、求められるツールやシステムは変化するため、最適なものを選びましょう。ツールは、データ統合ツールやデータ品質管理ツール、データ分析基盤などが考えられます。
導入にあたり、既存システムとの互換性やカスタマイズの必要性を評価することも重要です。既存システムとデータを連携しやすさは、データマネジメントの推進に大きな影響を与えます。また、業務で必要な機能がツールに標準で搭載されているかは、カスタマイズの必要性などコストを左右する要素となるため、事前に確認することが大切です。
ツールの運用と改善
システムやツールを導入したならば、その運用と継続的な改善が必要です。導入後、業務に合わせて運用する際に新たな課題が見つかることがあるため、これらの課題を少しずつ改善していきます。例えば、データの正当性をチェックする機能に問題があった場合、修正し、よりデータの質を担保できるようにします。
データマネジメントのゴールは、システムやツールを導入することではなく、これらを用いて品質の高いデータを確保し、意思決定などに活用することです。そのため、運用と改善にも力を入れ、変化し続けるビジネスニーズに柔軟に対応していきましょう。
まとめ
近年は大量のデータが活用される時代であるため、効率よく利用するためのデータマネジメントが重要です。ただ、データマネジメントを実施するためにはいくつもの障壁があり、これらをその都度乗り越えていかなければなりません。中には専門的な知識が必要となるものが含まれ、どうしてもデータマネジメントを進める際の壁になってしまいます。
データマネジメントにお困りの場合は、ぜひPigDataにご相談ください。PigDataは、データ活用のパートナーとして、データDXやデータマネジメントのサポートが可能です。データの収集から活用まで一気通貫で支援できるため、お気軽にお問い合わせください。