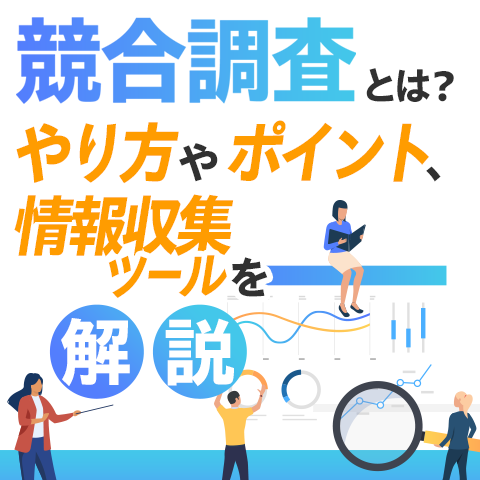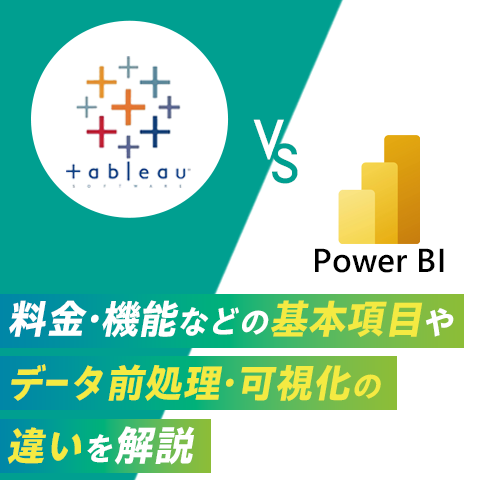近年は業務のデジタル化が進んでおり、それに伴って企業内に蓄積されるデータの量も増加する傾向にあります。皆さんの企業でも、デジタル化によって多くのデータを扱うようになっているのではないでしょうか。
しかし、すでにデータが存在しているにもかかわらず「それをどのように活用すればよいかわからない」と感じている担当者が増えています。今回は、どのように社内でデータを活用していけばよいのか、考え方や進め方について解説していきます。
データ統合とは
データ統合とは、複数の異なるシステムや形式のデータを収集し、統一されたフォーマットにまとめる作業です。大量のデータを一元化することで、データ活用に向けた準備を整えられます。
多くの組織では、部門ごとにデータが分散し、思うようにデータを活用できていないケースが多々見受けられます。これを改善し効率的にデータを活用するために、データ統合が欠かせません。
具体的には、データの重複や不整合を解消し、全体的に正確性や一貫性を高める作業が必要です。これにより、分析や意思決定を効率的かつ正確に進めやすくなります。最終的には、データに基づく迅速な意思決定や、業務の最適化を実現することがデータ統合の目的です。
データ統合をするメリット
データ統合の実施には、さまざまなメリットがあります。
データのサイロ化を解消できる
企業では部門ごとに異なるシステムやファイル形式で管理されることで、情報が分断される「データのサイロ化」が発生しやすくなっています。しかし、データ統合により、こうしたサイロ化の解消が可能です。
例えば、部門ごとにバラバラに存在しているデータを一つのプラットフォームに集約することで、全社的にデータを共有・活用できる体制が整います。部門間のデータ連携がスムーズになり、情報の重複入力や共有にかかる手間を大幅に削減できます。
データ統合により、まず直接的な効果としてサイロ化の解消が期待できます。また、組織全体のデータ最適化が進み、DXの推進につながるなど副次的な効果も見込まれます。
データ品質を高められる
データ統合の過程では、異なるフォーマットや構造で保管されているデータを統一された形式へ変換する作業が必要です。加えて、不整合や欠損、重複データの修正なども併せて実施します。これにより、データの一貫性と正確性を大幅に向上させることが可能です。データ全体の品質が高まり、企業活動や意思決定の信頼性が増すというメリットを生み出します。
また、データを整備しておくことは「データガバナンス」の観点でも重要な活動です。入力ミスによるコンプライアンス違反や業務上のリスクを未然に防ぐ効果も期待されます。
データ分析を進めやすくなる
データ統合によって情報が集約されると、データ分析を効率的に進められる点も大きなメリットです。必要な情報を素早く収集でき、分析の準備時間を大きく短縮できます。
特に、統合されたデータはBIツールやAI分析ツールなどとの相性が良いという特徴を持ちます。これらを活用した、データの可視化やリアルタイムの状況把握、将来予測などに繋げやすいのです。こうした「データドリブン」な意思決定を促進することは、データ統合のゴールに近いといえます。
データ統合の活用事例
データ統合の活用事例を紹介します。
ヤマト運輸
ヤマト運輸では、2021年4月に事業会社を統合すると同時に、データ基盤である「ヤマトデジタルプラットフォーム(YDP)」を構築しました。事業統合に伴うデータの統合にとどまらず、DXの推進にも大きく寄与していることがポイントです。
まず、YDPでは、ドライバーやトラックの運行情報、「クロネコメンバーズ」などの顧客情報など、多種多様な情報を一元的に統合しています。これにより、データの分析と活用が進み、業務効率化を図れるようになりました。また、荷物の現在地などの情報をリアルタイムで顧客に提供することも可能としています。
さらに、統合されたデータを活用することで、データドリブンな経営を実現できるようになりました。過去の配送データをもとに配送ルートを最適化するなど、経営資源の効率的な運用にも役立てられています。
PayPay銀行株式会社
PayPay銀行株式会社では、既存のデータベースの性能不足を背景に、新しいデータベースへのデータ統合が進められました。また、データ加工の仕組みも導入し、蓄積された大量のデータを分析できる環境を整えています。
特徴として、オンプレミス環境で管理されているデータをクラウドサービスと連携させている点が挙げられます。複数のデータベースを継続的に運用し、これらを分析のために、継続的に統合し続けているのです。一過性の取り組みではなく、継続的なデータ活用の基盤として活用されています。
住友商事
住友商事株式会社では、グループ会社間でのデータ共有の効率化を目的に、新たなデータ基盤の構築とデータ統合を実施しました。
現在は、グループの顧客情報を統合し、膨大なデータを一元管理する体制を整えています。その結果、新規口座開設時の与信管理を効率化できるなどの効果を発揮している状態です。
データ統合の進め方
データ統合の進め方を、具体的なステップに沿って解説します。
データを洗い出す
まず最初に、自社内にどのようなデータが存在しているのかを洗い出す作業が必要です。部門やシステムごとに保存されているデータの内容を以下の観点で整理しましょう。
- データの種類
- 保管場所
- 形式
これらの情報をリスト化し、現状の管理状況を可視化することがポイントです。データを洗い出す際は、日報、顧客情報、売上データなど、業務で使われているすべての情報を一旦リストアップしましょう。その上で、どのデータを統合対象とするかを選定します。
なお、データの所有者や更新頻度といった情報も併せて確認しておくことがポイントです。これにより、統合後の運用フェーズでデータの品質を維持しやすくなります。
集めるデータを決める
洗い出したデータの中から、統合の目的に沿って収集・連携すべき対象を決定します。たとえば、売上分析を目的とする場合、POSデータ、商品マスター、顧客情報などが統合対象となるでしょう。このとき、データの粒度や更新頻度、複数の情報源がある場合はどのシステムから取得するかといった点も明確にすべきです。
ただ、社内で洗い出したデータだけでは、データの種類が不足していることも考えられます。たとえば「顧客が自社の製品に対してどのような不満を持っているか」といった情報は、SNSや口コミサイトから「Webスクレイピング」などの技術を用いて収集する必要があります。
データを評価する
統合対象のデータを決定したら、次にその内容を評価するステップに移ります。実際にそのデータが統合や活用に適しているかを、以下のような観点から確認しなければなりません。
- 正確性
- 欠損の有無
- 更新タイミング
- 表記の揺れや形式の違い
評価の結果、質が低いと判断されたデータについては、後のステップで整備が必要です。データの評価をおろそかにすると、統合後の分析や活用に支障が出かねません。
データを整える
評価結果に基づいて、不整合や欠損の修正、形式の統一などデータの整備が必要です。たとえば、以下のような作業が考えられます。
- 日付フォーマットを統一
- 数値の単位を揃える
- 同じ内容でも異なる表記を統一する など
こうした作業によって、重複データの排除や、分析精度の向上が期待できるのです。なお、この工程は「データクレンジング」や「データマッピング」と呼ばれます。専用のツールやデータ統合基盤を活用することで、これらの作業をより効率的に進めることが可能です。
データを貯める
整備が完了したデータは、ストレージやデータベースで一元管理しなければなりません。一般的には、データウェアハウスやクラウドストレージが利用されます。また、単に格納するだけでなく、アクセス権限の設計やセキュリティ対策も並行して実施するようにしましょう。
なお、将来的にBIツールやAI分析ツールを導入する場合、ここで構築したデータ基盤の内容が利便性を大きく左右します。拡張性やデータの取り出しやすさなども考慮しておくことがポイントです。
データ統合ツール
データ統合の場面では、以下のようなツールが活用されます。
ETLツール
ETLとは「抽出(Extract)」「変換(Transform)」「格納(Load)」の頭文字を取ったキーワードです。複数のシステムからデータを取り出し、加工・整形したうえで、データベースやデータウェアハウスへ格納するツールを指します。あらかじめ定義された処理をバッチ処理などで実行し、大量データを一括で処理したい場面に活用されます。
代表的なETLツールには、Informatica や Talend、Microsoft SSISなどが挙げられます。さまざまな機能を持つツールが登場していて、データ統合や大規模なデータ処理など幅広い状況で利用されています。
iPaaS(Integration Platform as a Service)
iPaaSは、クラウド上でアプリケーションやデータの統合を実現するためのプラットフォームです。SaaS間の連携はもちろん、オンプレミスとの接続にも対応しています。結果、リアルタイムでのデータ連携を可能にしていることが特徴です。近年では、ノーコードやローコードで開発できるiPaaSツールも増え、利便性の高さから注目を集めています。代表的な製品には、BoomiやMuleSofなどがあり、中小企業から大企業まで幅広く活用され始めています。
データ仮想化ツール
データ仮想化とは、実際にデータを移動・統合せず、複数のデータソースをひとつのデータベースのように見せる技術です。ユーザは、定義済みのルールに基づいて、統合されているようにデータを参照・活用することができます。
この技術は、物理的な統合を実施せずに柔軟かつ迅速にデータを参照できることから、リアルタイム分析など即時性が求められるシーンで特に有効と考えられます。代表的なツールとしては、Denodoや Cisco Data Virtualizationなどがあり、今後さらに導入事例が増えていくと考えられています。
データ統合するときのポイント
データ統合を成功させるためには、実施時のポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
目的を明確にしておく
データ統合を実施する際は、目的を明確にすることが重要です。例えば、以下のような目的が考えられます。
- 業務の効率化
- 分析の精度向上
- 意思決定の迅速化
目的が曖昧な場合、必要なデータの選定や統合方法が不明確になり、無駄な作業やコストが発生してしまう恐れがあります。そのため、明確な目的を設定すると、統合の方向性やツール選定をスムーズに進められるようにしましょう。
専門家の支援を受ける
専門的な知識を持つ人材や企業の支援が不可欠です。データ統合には、ITツールの運用やデータベース管理、セキュリティ対応など、幅広く高度な知識が求められます。特に複数のシステムが絡む場合は、それぞれの構造や仕様に対する理解が重要です。これをサポートしてもらうために、ITコンサルタントやシステムインテグレーターなど、外部の専門家にサポートを依頼しましょう。
専門家のサポートがあれば、最適なツールの選定や設計などを安心して任せられます。結果的に、プロジェクトが成功する確率を高められるでしょう。
各ステップを確実に行う
各ステップを確実に進めることが成功の鍵です。データの洗い出し、選定、評価、整備、蓄積といった一連のステップを丁寧に実施します。いずれかをおろそかにすると、後工程で手戻りが発生したり、統合の成果が得られなかったりします。たとえば、データの整備に不備があれば、分析結果の信頼性を損なう原因となりかねません。
どの工程も確実に進めるためには、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。また、中途半端な状態で次のステップに進まず、品質を最優先に進行する意識も求められます。必要であればスケジュールを柔軟に見直すなど、品質第一の意識を持つことが、データ統合の成功に必須です。
まとめ
データを活用するためには、データ統合が非常に重要です。すでにデータが存在していても、適切に統合されていなければ、その価値を十分に引き出すことはできません。
ただし、データ統合には専門的な知識が求められ、完了までには多くのステップが必要です。また、それぞれのステップを適切かつスムーズに進めなければ、コストが無駄になる可能性もあります。データ統合を成功させるには、プロフェッショナルの支援を受けるべきです。
PigDataならば、データ統合に必要なすべてのステップをカバーできます。加えて、データ活用のためのコンサルティングも提供が可能です。既存のデータを活用したい、あるいは統合に課題を感じている場合は、ぜひご相談ください。