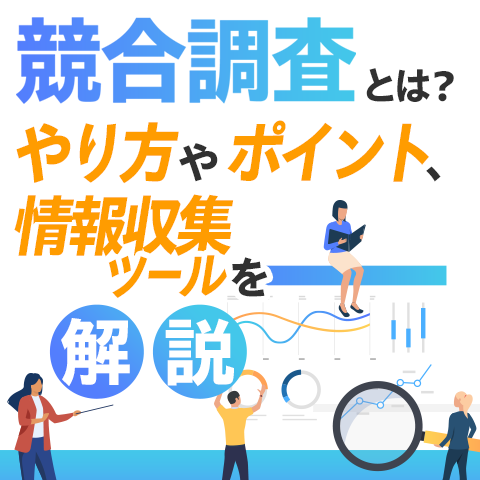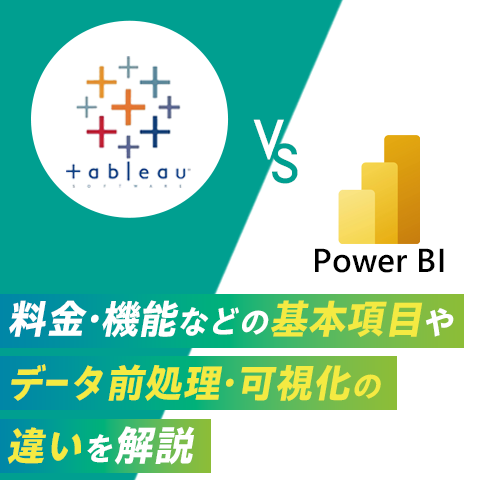データドリブン経営やデータ活用などのキーワードが日本でも注目されるようになってきました。そのため、日々の経営で様々なデータを活用したいと考える、経営者や企業のDX担当者、情報システム部門の人が増えています。
ただデータ活用を進めたいとは考えているものの、何から着手すれば良いのかわからない人も多く見受けられます。これからデータドリブンな経営を進めたいと考えるならば、必要となるものはデータ分析基盤です。データを活用できる環境を整えておくことで、効果的かつ正確にデータを活用できるようになります。今回は、データ分析基盤の基礎知識から構築する際に押さえておきたい情報やおすすめの構築方法などを解説します。
データ分析基盤とは
データ分析基盤とは、データ収集から蓄積、分析までの業務を一気通貫で実施する基盤です。今までは、それぞれの業務が別々に実施されていました。しかし、取り扱うデータ量が増えてきたことで、作業が煩雑になったり、人間では対応が難しくなったりしています。そのため、データ分析基盤というプラットフォームを構築し、ここで効率的に業務を進めるという考え方が広がっているのです。
データ分析基盤は大量のデータを分析して、ビジネスインサイトを得るという用途が中心です。その他には、データを活用して、社内用のAIを構築するなどの使い方も見受けられます。今回は、データ分析を中心に紹介しますが、多様な用途が存在していることも覚えておきましょう。
データ分析基盤の4つの要素
データ分析基盤は、4つの要素から構成されるため、それぞれについて解説します。
収集
データ分析基盤には、分析の対象となるデータを収集する作業が必要です。データは「内部データ」と「外部データ」の2つに大きく分けられます。それらを収集する方法は複数ありますが、例としては以下があります。
- 内部データ:社内システムと接続して日常業務で蓄積されたデータを収集
- 外部データ:Webスクレイピングを利用してWeb上のデータを収集
内部データでも十分分析できますが、外部データを掛け合わせることで分析の精度が高くなります。そのため、どちらも収集する必要があります。
ただし、データ収集の方法や対象は多岐にわたるため、目的に応じた柔軟な対応が必要です。
蓄積(データレイク)
収集したデータはデータレイクと呼ばれるストレージに保存され、繰り返し利用できます。データは削除されず蓄積することで、様々な用途に対応が可能です。これにより中長期的なデータ活用を実現します。
加工(データウェアハウス・データマート)
データレイクに蓄積された「生データ」を分析しやすく加工し、データウェアハウスやデータマートへ保管します。
- データウェアハウス:データ分析に向けて加工した幅広いデータの収集ツールを指します。
- データマート:データウェアハウスから用途別にデータを抽出、分類したものを指します。
まずはデータウェアハウスを構築し、そこから用途別にデータマートも作成します。
可視化・分析
データウェアハウスやデータマートに格納された情報は、そのままでは分析が難しいため、可視化と分析が必要です。
BIツールを活用すれば、大量のデータを分析、グラフやチャートなどに可視化することでビジネスインサイトを迅速に得られます。「Power BI」「Tableau」などの製品が有名で、データを取り込むことで画像やレポートの作成が可能です。また、Excelを利用したシンプルな可視化も有効です。
データ分析基盤の形態
データ分析基盤の形態には大きく分けて2種類あります。
オンプレミス
オンプレミスは自社でサーバーにデータ分析基盤を構築する方法です。この方法には以下のメリットやデメリットがあります。
<メリット>
- 環境を自由に構築でき、自社に最適なデータ分析基盤を構築できる
- ソフトウェアやサーバースペックをカスタマイズできる
<デメリット>
- 運用負荷が高い(メンテナンスや障害対応が必要)
- サーバー設置や運用にかかるコストが発生する
以上を踏まえ、オンプレミスの導入を検討する必要があります。
クラウド
クラウドは、データ分析基盤を提供するベンダーのサービスを契約し、利用する形態です。この方法には以下のメリットやデメリットがあります。
<メリット>
- 自社で環境整備や運用管理が不要で導入しやすい
- トレンドに沿った最新機能を提供してもらえる
<デメリット>
- 自社に最適なデータ分析基盤が構築できない
- ベンダーに依存してしまう
近年、データ分析基盤のサービスが数多く登場しているため、気軽さを求めるならば検討をおすすめします。
データ分析基盤の必要性
データ分析基盤がなぜ求められるのか、その必要性を解説します。
データドリブン経営の促進
データ分析基盤が主な目的の一つとして、データドリブン経営を推進することです。これは、経営者の経験や勘ではなく、データという客観的な根拠に基づいた意思決定を行う経営手法です。
例えば、データを一元化することで、社内の情報を包括的に把握し、偏りのない判断を可能になります。また、複数のデータを関連付けて分析することで、従来では見落としていた洞察を得て、経営に活かすことができます。
業務の自動化
データ分析基盤の導入により、多くの業務を自動化できます。例えば、データを一元管理することで、必要な情報を自動的に抽出し、後続の処理へスムーズに引き繋げます。さらに、AIを用いた分析や、BIツールによるデータの可視化などが自動で行われるため、従来手作業で行っていた工程が効率化されます。
コストの削減
データ分析基盤の導入により、管理や活用にかかるコストの削減が期待できます。データを集約することで検索や処理時間が短縮され、人件費の削減に繋がります。導入前位に削減可能なコストを具体的に試算することで、より効果的な基盤運用が可能です。
属人化の解消
データ分析基盤の導入により、データ分析作業の属人化を解消できます。例えば、データ分析のスキルを持つ人だけがデータを活用する状況から、誰もがデータを活用できる環境が整います。これにより、専門部署への依頼や外部への依頼が不要になり、各部門が自立的にデータを活用できるようになります。これも業務効率を向上させる重要な要素です。
データ分析基盤の構築の流れ
データ分析基盤を構築する際の流れを解説します。
目的を定める
データ分析基盤を効率的に活用するためには、導入目的を明確にすることが重要です。例えば「3年間で原価率を5%削減する」などの具体的な目標を設定することで、必要な機能やデータの種類を絞り込めます。また、経営目標とKPIを結びつけることで、数値目標が明確になり、基盤運用の方向性が定まります。
スケジューリングする
基盤の構築に向けて、スケジュールを立てていきましょう。どのようなツールやシステムの導入においても、スケジュールを立てて進めることは非常に重要です。データ分析基盤の場合、ツールやシステムを導入するスケジュールとデータを集めるスケジュールの2種類を考えなければなりません。
- 導入に向けやスケジュール:ツールやシステムを提供するベンダーの検討や理想的な社内活用開始時期
- データ収集のスケジュール:必要なデータの洗い出しと入手期間
設計する
データ分析基盤を構築する目的を踏まえて、技術的な設計を進めます。例えば、以下の事項を決定しなければなりません。
- データソースやデータの収集方法
- ユースケースの洗い出し
- データ更新のフロー
- 格納するデータのフォーマット
これらを設計段階で明確に決定しておくことで、データ分析基盤の構築をスムーズに進められるようになります。この作業は自分たちで実施することもあれば、データ分析基盤を構築するベンダーへ依頼することもあります。
開発する
設計内容を基に、データ分析基盤を開発します。この段階では、必要なツールの導入や設定だけでなく、社内のデータ移行も行います。例えば、社内システムに大量に蓄積されたデータをデータレイクへ移行します。その後、目的に応じてデータを加工してデータウェアハウスやデータマートに格納します。
運用・改善する
データ分析基盤の開発や構築が完了したら、運用を開始します。運用の初期段階では、基盤の課題を迅速に検討し、改善を進めることが重要です。特に、使い勝手や処理速度などの問題が生産性に与える影響を最小限に抑えるため、PDCAサイクルを用いて継続的な改善を図りましょう。
データ分析基盤を構築する方法
データ分析基盤を構築する方法を具体的に紹介します。
システムを個別に導入する
社内でシステムを導入できる人員がいる場合、システムを段階的に導入する方法も有効です。例えば、最初にデータ収集のシステムを導入し、次にデータを蓄積用のシステム、最後にデータ分析ツールを採用するといった手順が考えられます。この方法は、一度に導入コストがかからず、担当者の負担軽減にもつながります。
ただし、システム同士の連携を自社で設計・実装する必要があるため、技術的な難易度を考慮することが重要です。
クラウドプラットフォーム活用する
クラウドプラットフォームを活用する方法は、迅速にデータ分析基盤を構築したい場合に有効です。多くのプラットフォームは、データの収集、分析、可視化まで一連の機能を一気通貫で提供します。そのため、自社で開発する必要がなく、短期間で運用を開始できます。
ただし、クラウドプラットフォームは、カスタマイズ性に制約があり、自社の業務に完全に適合しない場合もあります。この点を理解した上で、導入を検討することが重要です。
一貫して対応してくれる専門会社に依頼する
データ分析基盤の構築サービスを一気通貫で提供する企業に依頼する方法があります。専門的な企業に依頼することで、社内の担当者が対応する作業量が減り、導入や運用の負荷を下げられます。
PigDataならば、データ分析基盤の構築に向けて、データ収集・蓄積・加工・可視化・分析まで一貫したサービス提供が可能です。加えて、データ分析基盤の活用を前提とした、データ戦略立案やデータ収集計画などもサポートできます。自社だけでは実現が難しい事柄にも対応できるため、まずは相談してみるのもよいでしょう。
データ分析基盤のポイント
データ分析基盤を構築する際のポイントを紹介します。
データのアセスメントを実施する
収集するデータについて、客観的にデータの内容を評価することが重要です。例えば、データマネジメントの知識体系である「DMBOK(Data Management Body Of Knowledge)」を参考にすると、以下の観点からデータを評価することが示されています。
- データガバナンス
- データアーキテクチャ
- データモデリングとデザイン
- データセキュリティ
- データ品質
このように、収集するデータをアセスメントしておくことによって、データの現状などを客観的に把握できます。また、データ分析や分析に向けた加工の過程において、どのような作業が必要であるか把握しやすくなるのです。
ユースケースを調査する
データ分析基盤を構築する際、ユースケースの調査は欠かせません。具体的な利用目的が明確になり、自社に適した基盤設計がしやすくなります。例えば、売上予測を目的とする事例では、時系列データの分析に特化した基盤設計が必要です。また、顧客セグメントの分析では、購買履歴やWeb行動データが必要になることがわかります。
このように、成功事例を参考にすることで基盤の活用方法を具体化できます。
自社に必要な機能を洗い出す
自社で発生するデータ関連業務を把握し、それに必要な機能を備えたデータ分析基盤を選びましょう。製品ごとに搭載機能は異なるため、自社のニーズと照らし合わせて評価することが重要です。Fit&Gap分析とも言われています。
また、機能に優先順位をつけることで、製品選定が効率化します。すべての要件を満たす製品が見つからない場合でも、優先順位が明確であれば判断がスムーズになります。
誰でも利用できるシステムを目指す
データ分析基盤は、専門知識がなくても利用できるシステムを目指しましょう。従来は属人化が課題でしたが、多くの従業員が使いやすいツールを導入することで解消できます。
例えば、データ分析に不慣れな従業員でも、新たなデータの組み合わせや分析を試みることで、今まで気づけなかった洞察を得られる可能性があります。そして、多くの業務でデータを活用することで、企業全体の競争力向上にも繋がるでしょう。ただし、利用者増加に伴うランニングコストの増加も考慮し、長期的な視点で計画を立てる必要があります。
まとめ
DXが推進している中、データドリブン経営の実現には、データ分析基盤の構築が不可欠です。社内外のデータを一元管理することで、効率的な意思決定が可能になります。
データ分析基盤を構築する方法は「システムを個別に導入すること」「クラウドプラットフォームの活用」「一貫して対応してくれる専門会社に依頼する」の3種類あります。特に、専門会社への依頼は、スムーズな環境構築やデータ戦略のサポートが期待できるため、有力な選択肢です。
PigDataは、長年データを取り扱う事業を展開し、データの収集から分析、活用と幅広い知識を有しています。データ分析基盤の構築をご検討の際は、ぜひご相談ください。