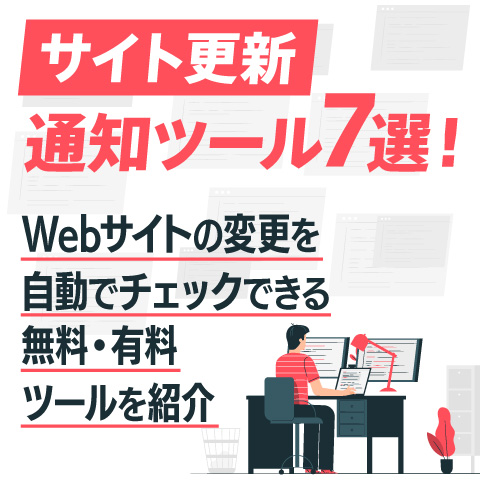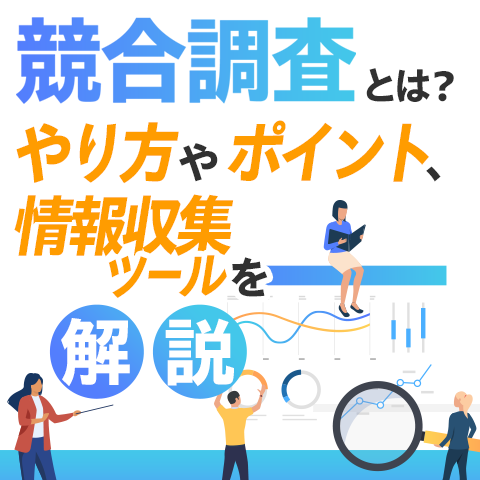BigQueryとは、Googleが提供するデータベースのことです。データを高速で処理できる特徴があり、ビッグデータの集計や分析などで利用されています。専門的な知識やスキルがなくても使いやすく、コストパフォーマンスが高いため、導入する企業が少なくありません。
本記事では、BigQueryの概要や特徴とメリット、利用手順・料金について詳しく解説します。BigQueryについて知りたい方、利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
BigQueryとは

BigQuery(ビッグクエリ)とは、GoogleのクラウドサービスであるGoogle Cloud(旧 GCP:Google Cloud Platform)で提供されているデータベースのことです。Googleの社内では、もともとDremel というツールでビッグデータの解析が行われており、Dremelの機能を一般のユーザーが活用できるように公開したものがBigQueryです。BigQueryを活用すれば、 数TBや数PBのビッグデータも迅速に解析できます。
ここからは、BigQueryに関する以下の項目について解説します。
- できること
- データ分析における立ち位置
- 仕組み
BigQueryでできること
BigQueryでは主に以下のことが可能です。
| できること | 概要 |
| ログの集計や解析 | SQLを利用して、必要な列と行のみの抽出や確認したい統計データの加工・集計・解析が可能です。 |
| データの蓄積 | ビッグデータの保存場所として活用可能です。 |
| BIツールとの連携によるレポーティング | 企業データを分析・見える化して経営や業務に役立てるBI(Business Intelligence)ツールとの連携で、効率的なレポーティングが可能です。 |
| データサイエンス | SQLの実行により、機械学習モデルの作成や実行が可能です。また、統計学をベースにしたモデルの設計もできます。 |
データ分析におけるBigQueryの立ち位置
データ分析において、ビッグデータを高速で解析できるBigQueryはデータウェアハウス(DWH)として機能します。DWHとは、さまざまなシステムから収集した膨大なデータを効率的に統合・整理・管理して、高精度な分析を実現するシステムのことです。
近年、企業は多くのシステムを導入しており、システムごとに多彩なデータが日々生み出されています。企業経営にデータ活用を取り入れる企業も多数ありますが、部門やデータを生み出すシステムごとに情報が分断され、データの統合・共有が上手くできない課題が発生する場合も少なくありません。社内のデータを統合して分析しなければ、誤った結論を導き出してしまう可能性があるでしょう。
DWHでは、部門やシステムを横断して収集したデータを時系列・目的別に整理可能です。データ重複も防止でき、効率的な社内の情報共有やデータ活用につながります。
👉 BigQueryを活用した「データ統合&自動化システム構築サービス」の詳細はこちら
BigQueryの仕組み
BigQueryでは、以下2つの仕組みを採用することで、高速なデータ処理を実現しています。
- カラム型データストア
- ツリーアーキテクチャ
ここからは、上記について詳しく解説します。
カラム型データストア
カラム型データストアとは、データベースがデータを列単位で保存・管理する方式のことです。従来のデータベースでは1行ごとにデータを取り扱い、クエリ処理時には関連する行全体を読み込むため、分析対象以外の不要なデータもロードされていました。
一方、カラム型データストアでは必要なデータ列のみを読み込むことで、データの処理量が少なくなり、データベースのパフォーマンスが向上します。また、データを保存する際の圧縮率にも優れているため、ストレージの使用料を節約でき、データ読み込みの速度を向上させられます。
ツリーアーキテクチャ
ツリーアーキテクチャとは、クエリを受け取るルートサーバー、タスクを分割する中間サーバー、処理するリーフサーバーがツリー構造で広がるもののことです。データを同時に処理することで、効率的かつ高速なクエリ処理を実現しています。
BigQueryの特徴やメリット

続いて、BigQueryの特徴やメリットを解説します。
大量のデータを高速で処理できる
BigQueryにおける最大の特徴は、大量のデータを高速で処理できることです。BigQueryであれば、数十億行のデータであっても数十秒で集計・分析が可能です。同じことをExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトで行った場合、分析はもちろん読み込みもできません。BigQueryを活用すれば、これまで負荷が多くて行えなかったデータも高速で処理できます。
効果的なデータ分析を行うには、さらなるインサイトを得るためのデータそのものが必要です。PigDataのスクレイピング代行サービスを活用すれば、Web上のデータ収集から分析までを効率化できます。
専門知識・スキルがなくても使いやすい
BigQueryは、専門知識やスキルがなくても使いやすいサービスです。多くのDWHでは、利用するにあたり以下の知識やスキルが必要とされます。
- データベースの構築や設定
- 最適化などのチューニング
- 分析に必要なリソースを増減させるスケーリング
- インデックス設計
BigQueryはサーバーレスで利用でき、チューニングなどを行う必要がありません。また、全機能をWebブラウザのユーザーインターフェースで利用できます。
コストパフォーマンスが高い
コストパフォーマンスが高い点も、BigQueryの特徴です。BigQueryは、利用した量に対して料金が発生する従量課金制の料金体系が採用されており、一定量までは無料で利用できます。利用しなかったり、利用量が少なかったりすれば、料金が発生しないケースもあるでしょう。なお、利用料の詳細は後ほど解説します。
SQL操作ができる
BigQueryは、データベース言語であるSQLでデータに関する以下の操作が可能です。
- 抽出
- 結合
- 集計
- フィルタリング
BigQueryの特徴である高速処理とSQLの柔軟性を組み合わせることで、大容量のデータに対して複雑で高度な分析が可能です。また、他のプログラミング言語と比較してシンプルな特徴があるSQLにより、BigQueryがより使いやすくなります。
他のGoogleツールと連携できる
BigQueryは、Googleが提供する他のツールとの親和性が高く、連携が可能です。ここからは、以下ツールとの連携について解説します。
- GA4
- Looker Studio
- Googleスプレッドシート
- Googleサーチコンソール
GA4
GA4は、Webサイトやアプリケーションにおけるデータの一元化と分析が可能なツールです。自動計測や機械学習を用いた予測機能が実装されており、高度な分析にも対応しています。GA4では、BigQueryに対する直接的なエクスポートができ、連携させれば膨大なデータを分析する基盤構築が可能です。
Looker Studio
Looker Studioは、Googleが無料で提供しているBIツールです。Looker Studioとの連携で、BigQueryに蓄積したデータをリアルタイムで分析・可視化できます。また、一度作成したデータセットやレポートを保存すれば再利用ができるため、効率的なデータ分析が期待できます。
Googleスプレッドシート
Googleが開発・提供している表計算ソフトのGoogleスプレッドシートと、BigQueryの連携も可能です。連携させれば自動で更新されるため、人がデータの入力や更新をする必要がなくなり、業務効率化に役立ちます。
Googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、Google検索におけるWebサイトのパフォーマンスをチェックするツールです。Googleサーチコンソールで取得した情報をBigQueryにエクスポートすれば、GA4などのデータとも統合でき、包括的で高度な分析が実行できるようになります。
API連携ができる
BigQueryでは、Google Cloud PlatformのAPIによりさまざまなアプリケーションとの連携やスクリプトの自動化が可能です。Pythonをはじめとする多彩なプログラミング言語を活用したアクセスができます。例えば、Pythonスクリプトを用いてBigQueryからデータの取得と加工・分析を行い、ユーザーにデータ提供するなどの活用ができるでしょう。
BigQueryと他社ツール(Snowflake、Redshift)の比較

BigQuery以外にもDWHは存在するため、自社に合うツールの利用が重要です。BigQueryとSnowflake、Redshiftの違いは以下の通りです。
| BigQuery | Snowflake | Redshift | |
| 提供元 | Snowflake | Amazon | |
| アーキテクチャ | サーバーレスアーキテクチャ | 独自のコンピューティングとストレージを分離したアーキテクチャ | 列指向データベース |
| インフラ管理の手間 | 不要 | 最小だが、仮想ウェアハウスのサイズや使用時間の調整が必要 | クラスタ管理を自動化可能 |
| 他ツールとの連携 | 他Googleツールとの統合・連携が容易 | AWSやAzure、Google Cloudと連携可能 | AWS内のサービスと連携可能 |
| 主な従量課金の対象 | ストレージとクエリ | 仮想ウェアハウスのサイズと使用時間、ストレージ | ノード数と使用期間 |
SnowflakeはクラウドネイティブのDWHです。ストレージとコンピューティングを完全分離させた独自のアーキテクチャを採用しており、必要なリソースに応じた柔軟なスケールが可能です。また、高度なセキュリティとデータ保護機能が実装されているため、安全性の向上と法規制への対応が期待できます。
Redshiftはマネージド型のDWHで、大量のデータを高速で処理・分析できる列指向データベースです。データ圧縮機能が実装されており、ストレージコストの削減とクエリパフォーマンスの向上が期待できます。
BigQueryの利用手順

BigQueryの利用手順は以下の通りです。
- BigQueryの公式サイトにアクセスして「無料で利用開始」もしくは「BigQueryの無料トライアル」をクリック
- Google Cloudの登録画面に遷移するため、画面の指示に従いアカウントや支払い情報を入力
- Google Cloud登録完了後、画面左のメニューバーにある「BigQuery」を選択
- 画面上部の「新しいプロジェクト」をクリックして、プロジェクト名を設定
- 「アクションを表示」のアイコンをクリックして「データセットを作成」を選択後、設定を実施
- データセット同様「アクションを表示」をクリックして「テーブルを作成」を選択後、設定を実施
- データ解析時には、画面上部の「クエリ」を選択後、エディタ画面にクエリ入力し「実行」をクリック
BigQueryの利用料金

BigQueryの利用料金は、以下に基づき計算されます。
- データの分析
- データの保管
- データの取り込み・抽出
最後に、上記の利用料金を紹介します。
データの分析
BigQueryでデータの分析や処理を行うための料金です。以下3つのプランから、利用するものを選択できます。
- オンデマンド クエリ:1TB/月額6ドル
- 月間スロット コミットメント:100スロット/月額2,400ドル
- 年間スロット コミットメント:100スロット/月額2,040ドル
従量課金制であるオンデマンドプランの場合は、毎月1TBまで無料で利用できます。
データの保管
BigQueryでデータを保管するための料金です。以下の合算により料金が決定します。
- アクティブストレージ(90日以内に変更されたテーブル):1GB/月額0.023ドル
- 長期保存(90日以内に変更されていないテーブル):1GB/月額0.016ドル
上記は、データの保存期間に応じて日割りで決定します。なお、どちらも毎月10GBまでは無料で利用できます。
データの取り込み・抽出
BigQueryのデータ読み込み・抽出するための料金です。バッチ読み込みは無料ですが、ストリーミング挿入やBigQuery Storage Write APIの利用には以下の料金がかかります。
- ストリーミング挿入:200MB/月額0.012ドル
- BigQuery Storage Write API:1GB/月額0.03ドル
BigQuery Storage Write APIの場合、毎月2TBまでは無料で利用できます。
まとめ
BigQueryは非常に優れたクラウド型データウェアハウスですが、導入しただけで成果が出るわけではありません。その価値を引き出すためには、事業や業務フローに合わせたデータ構造の設計、収集・変換プロセスの自動化、そして活用現場まで届くデータ連携が欠かせません。
PigDataでは、BigQueryを中核に据えたデータ統合・自動化システムの構築支援を行っております。現場にとって「使いやすく」「管理しやすく」「継続的に運用できる」仕組みを、設計から構築・保守まで一貫してご支援いたします。