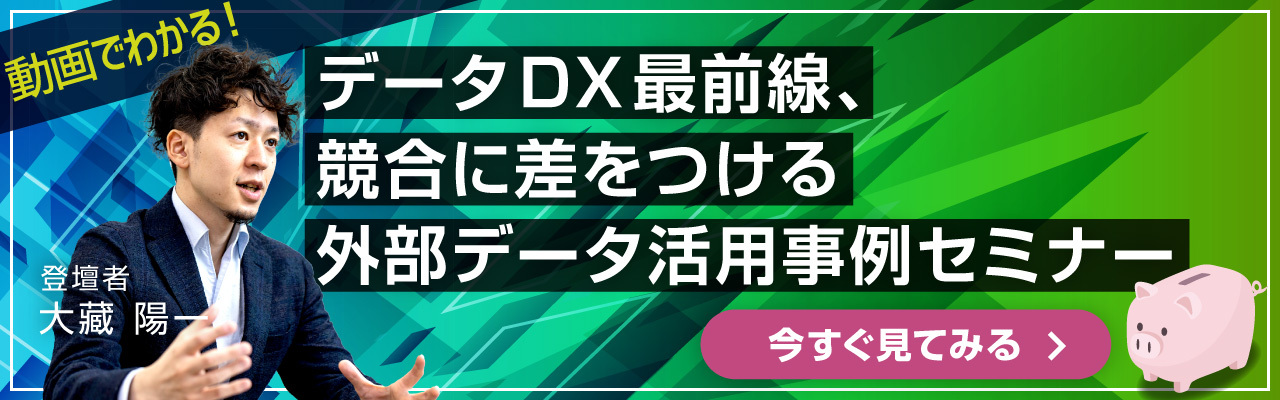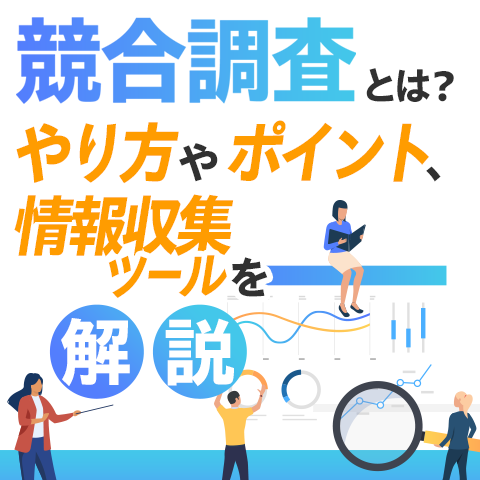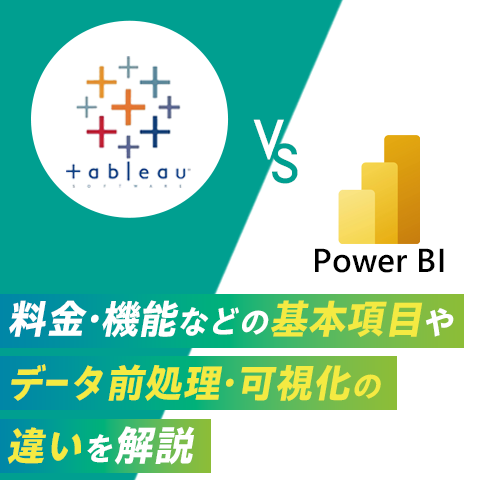近年、企業にはDXの推進をはじめ、データ活用が求められています。特に、意思決定の際にデータを活用すること、つまりデータドリブンという考え方が重要です。この記事では、データドリブンを経営に活かす「データドリブン経営」についてご紹介します。
データドリブン経営とは
データドリブン経営とは、様々なデータに基づいた意思決定を行う手法を活用した経営を指します。属人的な経験や勘に頼るのではなく、定量的なデータに基づいて判断を行うため、高い精度で成果に結びつけられる方法といえるでしょう。
データドリブン経営のメリット
データドリブン経営を行うことのメリットを紹介します。
意思決定の精度を高められる
社内にあるデータを分析し、どういったケースで成功したのか・失敗したのか、それぞれの内容を定量的に把握できるので、根拠のある意思決定ができます。
また、外部データを活用することで、市場動向のようなマクロ指標も意思決定の要素として取り込むことができ、状況に応じた柔軟な判断が可能になります。
顧客のニーズに沿ったサービス開発ができる
顧客の行動履歴・パターン、これまでのやり取りを分析し、今現在顧客が求めているもの、潜在的に今後ニーズが高まりそうなものを予測することが可能になります。
顧客のニーズに応じたサービスを開発することで市場で更にシェアを獲得することにつながるでしょう。
素早い意思決定ができる
データという属人的ではない確固たる根拠を元に意思決定を行うため、会議の際に批判的な意見が出ることを避けられます。そのため、意思決定を迅速に進めることができ、めまぐるしく変化し続けるビジネス市場にも対応することができるでしょう。
新規ビジネスの創出
データドリブン経営を進めていくうえで欠かせないのは多面的なデータ分析です。これまで勘と経験に頼る意思決定をしていた場合、主に確認するのが社内のデータだけである可能性があります。しかし、データドリブン経営のために外部データも活用し、内部データと掛け合わせることで新たなビジネスチャンスを見つけられる可能性があります。
データドリブン経営を実行するためのステップ
データドリブン経営を実行するためのステップを紹介します。以下の流れに沿って進めましょう。
1. 目的・あるべき姿の定義
まずは、目的・あるべき姿を明確に定義します。
自社にとってデータドリブン経営ができている状況とは具体的にどのような状況を指すのか、という共通認識を組織内で共有しましょう。
その上で、まずはどの部署・領域からデータドリブン体制を構築するのか決定します。いきなり全社的にデータドリブン経営が行える組織になるのは困難です。優先度の高いところから、着実に取り組みましょう。
2. データ収集・整備
次に、データ収集と分析のための整備を行います。データは様々な部署に存在しているので、それらを一元管理することが重要です。部署によってはアナログ作業が多く発生している場合もあるので、その際はDXを進めることから始め、デジタルでデータ収集ができる仕組みを構築します。
また、社内データのみではなく、外部データの活用も検討しましょう。市場動向に合わせた意思決定を行う上で、外部データを取り込むことは重要です。
収集したデータは、分析するために加工・整形します。例えば、営業部署であれば、顧客属性ごとにリードを獲得したチャネル、営業フローの進捗率・離脱率などを可視化し、受注・失注に至るケースの傾向を市場動向とあわせて定量的に表しましょう。

3. アクションプランの検討及び実行
得られたデータを分析し、アクションプランの検討・実行をします。データを分析するのはあくまでデータドリブン経営の手段のひとつであり、その分析結果を踏まえたアクションを実行することが重要です。
データを根拠に理想のアクションプランを立てたものの、実行が困難であるケースは多々あります。自社の組織規模、コストなどの観点で実行でき且つ成果につながるアクションを検討し実行しましょう。
4. 効果検証・改善施策の検討及び実行
実行したアクションの効果検証を行い、必要に応じて改善施策を検討し改めて実行するPDCAサイクルを回しましょう。
効果検証は、思った通りの成果につながっていない場合はもちろんですが、一定の成果が得られたとしても実行することが重要です。なぜ、失敗したのか・成功したのかを突き詰めて考えることで、次のアクションにつながるデータが得られるでしょう。
データドリブン経営の成功事例
データドリブン経営の成功事例を紹介します。
ソフトバンク
ソフトバンクは電波のつながりにくさから、ユーザーからネガティブな評価を受けがちであり、顧客満足度の向上を経営課題としてもっていました。そこで、エリアや時間毎の接続率のデータの分析を行い、つながりにくいエリアを特定し、電波改善。また、計測装置による計測ではなく、パケット通信ができたかどうかのログを大手携帯会社3社のユーザーのスマートフォンから無作為に収集し、1日約2900万件、月間9億件のデータを収集・蓄積し、分析した結果をもとに最適な基地局を整備したことで接続率ナンバーワンとなりました。
自社データのみならず、競合他社のデータも活用することでデータドリブン経営を成功させています。
日清食品
従来日清食品のカップヌードルは若者が食べるものという印象が強くなっていたため、シニア世代が増えつつある現代の状況に対応することが難しくなっていました。そこでアクティブシニアが発信するSNS等でデータを収集し、分析することで、シニア層が求める嗜好を把握しました。そこからSNSでは豪華な食事の画像共有が盛んに行われている、ということがわかり、その分析結果をもとに、フカヒレなどの高級食材を用いた商品展開をすることでシニア層の売上を増加させることに成功しました。
旭化成
旭化成は国内外を市場とし、製品の製造、加工、販売に至るまで長く多岐にわたるプロセスを経て顧客へ届けられるため、それぞれのフェーズでどの程度の利益が確保されているのかを俯瞰することが困難でした。
データドリブン経営を取り入れることで、月毎に製品の損益を可視化し、高い利益率を維持しているプロセス、利益を圧迫しているプロセスを可視化し、取り組むべき課題を明確にしました。
データドリブン経営に欠かせないコト
データドリブン経営を効果的に機能させる上で欠かせないコトを紹介します。
継続的なデータ収集
参考にするデータが最新のものでなければ、精度の高い意思決定はできません。そのためには、継続的にリアルタイムデータを収集するための環境・体制を整備する必要があります。
エクセルによる属人管理ではタイムリーなデータ反映は難しいため、データを取り扱うためのシステムやツールを導入するのは必須だといえるでしょう。
外部データの活用
外部データを活用することで、社内では把握しきれていない情報や市場の動向に沿った適切な判断が可能になります。また、分析精度を高めるために必要なデータ量も内部データより多く集められる可能性もあるでしょう。
Webサイト上に存在する外部データの場合、効率良く収集するにはスクレイピングを活用することができます。
データドリブン経営の精度を高めるためには外部データ活用を効率的にできるかどうかが重要となってきます。
データの取り扱いができる人材の確保
データドリブンを行う上で、必要なデータを集め、分析できる人材がいなければ正しいフィードバックを得るのは困難です。参考にするデータが正しいかどうか判断できず、もし誤ったデータであった場合、当然、意思決定の精度を担保することもできません。
適切にデータを取り扱うことができる人材を確保することは、データドリブン経営を行う上で非常に重要な要素です。
データ活用文化の醸成
特に、これまで属人的な経験や勘によって意思決定がなされてきた組織であれば、データを活用した意思決定を始めることに抵抗を持ってしまうかもしれません。組織としてデータドリブンに取り組むという同じ方向性を共有しなければ、最大限の効果を得るのが難しくなってしまいます。
必要性や活用することのメリットを啓蒙し、データ活用の文化を醸成することはデータドリブンを進める上での前提条件になります。
まとめ
この記事ではデータドリブン経営のメリット、進め方、注意点、具体事例を紹介しました。
データドリブン経営を進める際に社内データと外部データの両方を適切に活用することで市場の現状に合った分析ができ、意思決定の精度を高め、効果的なアクションにつなげることができます。外部データは誰でも収集できるWebサイトのデータがおすすめです。PigDataではWebデータを効率的に収集するためのサービスとして「スクレイピング代行サービス」を提供しています。市場動向などを分析するためにWebデータの活用を検討する際は、PigDataにご相談ください。