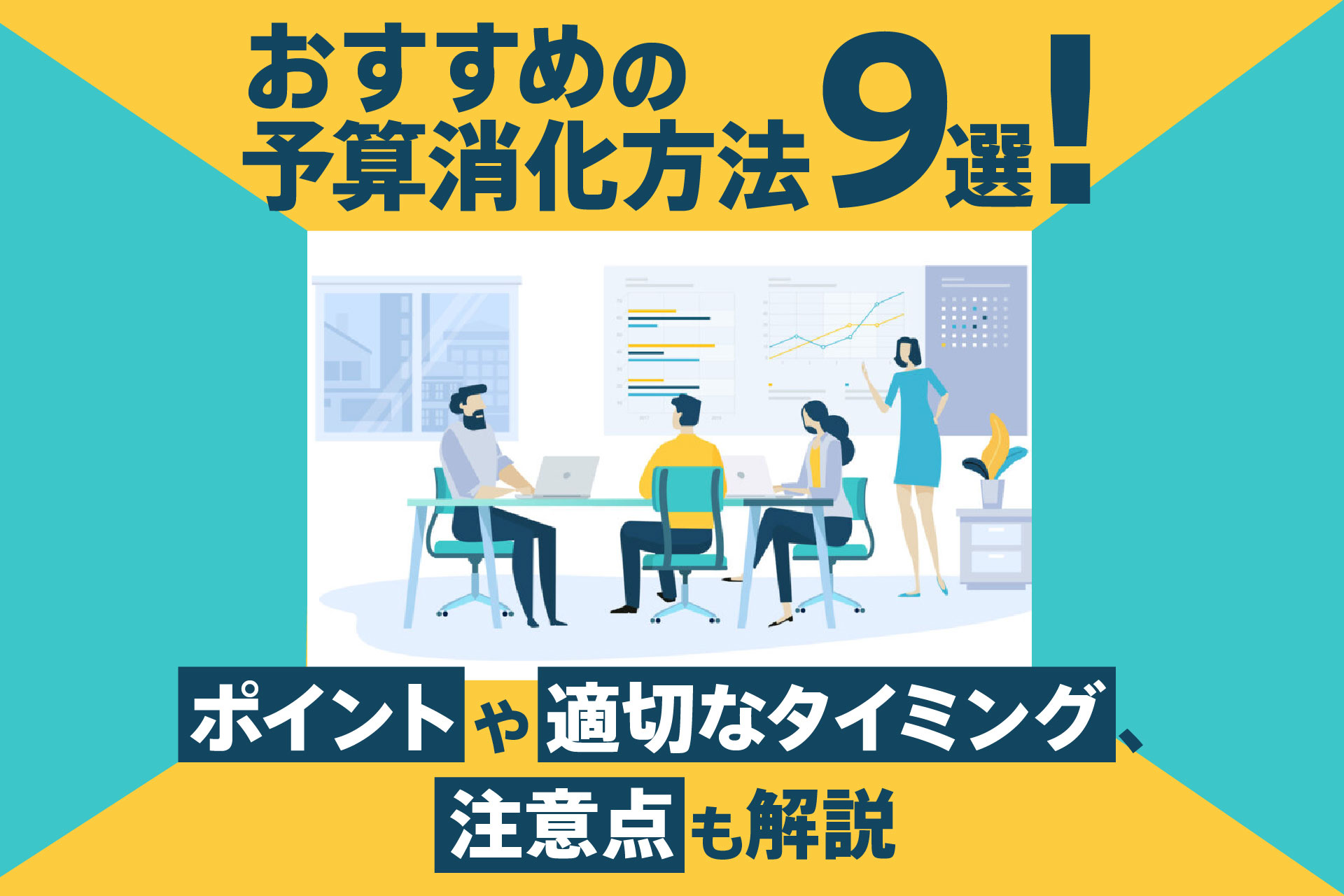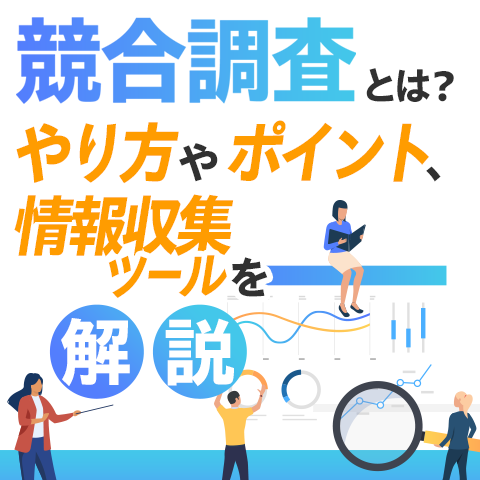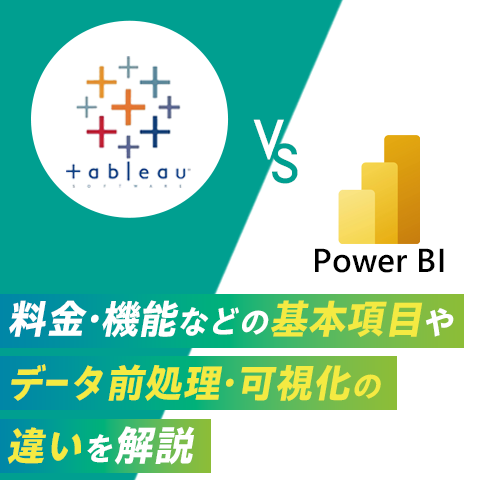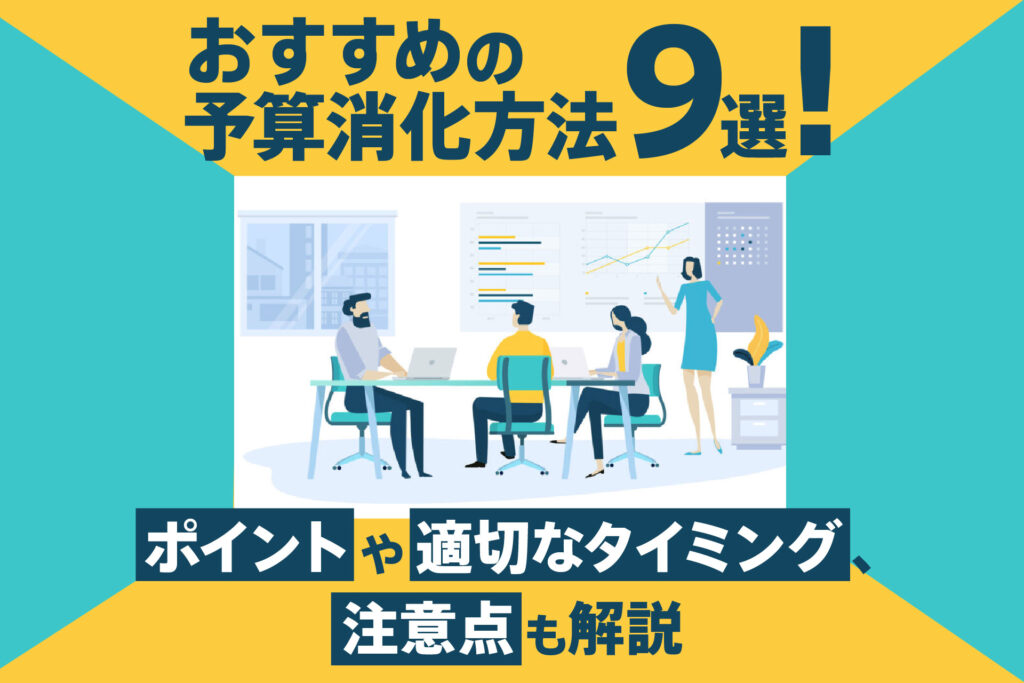
今年度の予算が余っている企業・組織の中には、どのように消化すれば良いか悩んでいるところもあるでしょう。予算消化をしなければ、翌年度の予算が減少したり、評価が下がったりする恐れがあります。翌年度以降に役立つものや、挑戦的な費用への活用がおすすめです。
本記事では、予算消化のポイントとステップやおすすめの消化方法9選、予算消化の注意点について詳しく解説します。予算消化について知りたい方、予算の消化方法を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
予算消化とは

予算消化とは、部署や部門などの組織に割り当てられた予算を、年度末・期末までに使い切ることです。予算は、年度や半期などある一定期間で割り振られますが、余らせてしまうケースもあるでしょう。ここからは、予算消化が必要な理由について解説します。
予算消化をした方が良い理由
予算消化をした方が良い理由は、以下の2点です。
- 翌期の予算が減額される可能性がある
- 評価が下がる可能性がある
順に解説します。
翌期の予算が減額される可能性がある
予算消化をした方が良い理由の1つ目は、翌期の予算を減額される恐れがあるからです。予算が余れば、過剰予算だったと認識されるケースがあります。予算が不十分だと感じている組織は多く、過剰な組織の予算は他の部署や部門にまわされるでしょう。
評価が下がる可能性がある
評価が下がる恐れがあることも、予算消化をした方が良い理由の一つです。予算が余れば、適切な予算やコストの管理ができていないと見なされるケースがあります。とくに、売上や利益などの目標を達成できなかった場合、より評価が下がりやすくなるでしょう。
日々業務を必死にこなしているにも関わらず、予算管理の問題で評価が下がれば、部署や部門のモチベーション低下につながります。昇給・昇進の機会を逃したり、ボーナスが減額されたりするリスクもあります。
予算消化のポイント

では、どのように予算を消化すれば良いのでしょうか。ここからは、予算消化のポイントについて解説します。
期末までに支払いを完了させる
予算は必ず期末までに支払いを完了させましょう。支払いが年度内に完了しなければ、翌年度の予算扱いになります。ただ、支払いを完了させれば良いわけではありません。支払いを今期中にしても、サービスを受けたり納品してもらったりするのが翌期になれば、次年度予算となります。万が一、今期の経費として計上した場合、脱税に該当する恐れがあります。
来期に役立つものに活用する
予算消化とはいえ、無駄にコストを使って良いわけではありません。翌期以降に役立ち、収益の向上につながるものに活用しましょう。おすすめの予算消化方法は、後ほど紹介します。
挑戦的な施策の実施も検討する
挑戦的な施策の実施に、余った予算を活用するのも良いでしょう。予算は限られており、通常はより確実に役立つ方法に利用しがちです。ただ、予算消化の一環であれば確実性が高くなくても、挑戦しやすいでしょう。
予算消化の適切なタイミング

予算消化の適切なタイミングの目安は、以下の通りです。
| 決算時期 | 予算消化時期 | 予算消化方法の検討時期 |
| 2月 | 12月~2月 | 11月~1月 |
| 3月 | 1月~3月 | 12月~2月 |
| 4月 | 2月~4月 | 1月~3月 |
予算消化の検討や決定には時間が必要です。また、期末に予算消化を目的に発注を行う企業も多く、通常より納品や役務提供に時間がかかるケースがあります。期末の数ヵ月前から検討を始め、余裕を持って行動しましょう。
予算消化のステップ
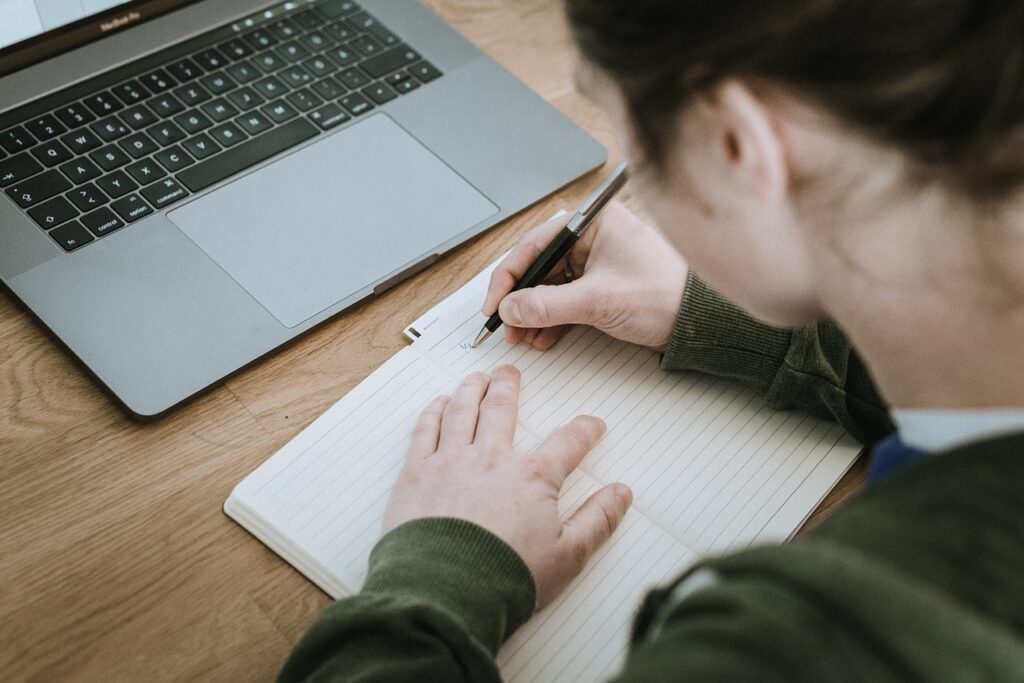
予算消化の具体的なステップは、以下の通りです。
- 余っている予算の確認
- 期末までの猶予とリソースの確認
- 内容の検討
- 納品・請求発行日の確認と依頼
順に解説します。
1.余っている予算の確認
まずは、どの程度の予算が余っているか正確に把握しましょう。使える予算により、実施できる施策や購入可能な物品の選択肢が大きく変わります。正確な予算を把握しなければ、余ってしまったり足りなくなってしまったりするでしょう。
2.期末までの猶予とリソースの確認
続いて、期末までの猶予とリソースを確認します。割り当てられているとはいえ、多くの企業では予算の活用に稟議が必要です。金額や使い方により、稟議の方法やかかる時間が異なるケースもあるでしょう。まず、検討・決定までにどの程度の時間が残されているか、確認が必要です。
また、リソースの把握も欠かせません。コンサルティングや作成物などでプロジェクトを実施する場合には、人的リソースが必要になります。中には、年度末が繁忙期となり、予算消化にリソースを割けない企業もあるでしょう。
3.内容の検討
余っている予算や猶予、リソースが確認できたら、情報を集め実際になににお金を使うか検討します。組織に属するメンバーの意見も聞きながら、課題や要望を把握すると良いでしょう。
また、複数案を出し優先順位を付けるのがおすすめです。納期などタイミングの問題で、必ずしも希望通りに進むとは限りません。
4.納品・請求発行日の確認と依頼
具体的になににお金を使うかが決まった後に、発注先を探し納品・請求発行日を確認しましょう。納品や支払いのタイミングがズレると、翌期の予算になるため注意が必要です。問題がある場合は、発注候補先の企業に相談するか、別の発注先を探します。問題が無ければ依頼しましょう。
おすすめの予算消化方法9選

続いて、おすすめの予算消化方法9選を解説します。
販促品の作成
販促品の作成は、多くの企業や組織が予算消化で行う施策です。具体的には、以下のノベルティグッズ制作に余った予算が活用されています。
- カレンダー
- メモ帳
- ふせん
- ボールペン
- キーホルダー
- 傘
- エコバッグ
社名入りのノベルティグッズは、企業の認知を広げるツールとして効果的です。また、パンフレットやホワイトペーパーなど、営業で役立つツールの作成も良いでしょう。
マーケティングの実施
マーケティング活動に、予算を活用する企業も多く存在します。例えば以下の施策が挙げられます。
- Webサイトの作成や改修
- ランディングページの制作
- メディア記事や動画などのコンテンツ作成
- ディスプレイ広告の実施
- リスティング広告の実施
- SNS広告の実施
上記の取り組みにより、認知の拡大やリードの獲得を行えば、翌期以降の収益向上が期待できます。
情報収集の自動化
情報収集自動化への予算活用もおすすめです。ビジネス環境の変化が激しい現代において、自動化によりスピーディーで正確な情報収集を行えば、以下のメリットを得られるでしょう。
- 情報収集における負担の軽減や業務効率化
- 市場の把握や競合分析による、競争優位性の獲得
- リスクの抑制とチャンスの拡大
PigDataではWebサイトの更新チェックツールである「TOWA」を提供しています。TOWAはサイト確認業務を自動化し、業務効率化やDX推進ができます。監視したいWebサイトをTOWAに登録すると、そのWebサイトが更新された場合に情報の差分を検知し、担当者へ通知を行います。国内・海外サイトの双方を登録できるため、幅広い情報収集に役立ちます。
データ活用
近年は、多彩なデータに基づいた意思決定を行うデータドリブン経営を取り入れる企業が多く、データ活用の重要性が増加しています。以下のデータを活用すれば、企業の現状やリスクを把握でき、ビジネスチャンスの発見にもつながります。
| 内部データ | 外部データ |
ただ、手作業によるデータ収集は、多くの時間と負担がかかります。PigDataではWEB上にある大量のデータを自動で収集する代行サービスの「スクレイピング代行サービス」を提供しています。状況に合わせたさまざまなデータ提供ができ、テキストや画像などの収集が可能です。また、データ収集だけでなく、データ基盤の構築やデータ分析の支援も提供しています。データ収集の手作業を自動化でき、活用の負担を抑えられるため、利用がおすすめです。
なお、データの利活用に関する詳細は以下をご覧ください。
DXの推進
デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを革新するDX推進に予算を活用すれば、以下のメリットを得られます。
- 人手不足の解消
- 企業競争力の向上
- 急速に変化する市場環境や顧客ニーズへの対応
具体的な取り組みとして、顧客・商談管理のシステム化、モバイル決済の導入、AI・ロボットの活用などが上げられます。
DX推進には、データの活用と分析が欠かせません。まずは、データ収集から取り組むと良いでしょう。
人材育成
長期的な企業の成長を望むのであれば、人材育成への投資も有効な手段の一つです。外部から講師を招き集合研修を実施したり、外部の研修・セミナーに従業員を派遣したりすれば、新たな知識・スキルを身に付けられます。また、昨今は動画で学ぶサービスも多く、従業員が自身の都合の良いタイミングで学習できます。
物品や機材の購入
物品や機材の購入に、余った予算を活用する企業も少なくありません。コピー用紙やトナーなど、翌年度に必ず使うものは多くあるでしょう。また、最近はリモートワークを導入している企業が多いため、自宅で活用するカメラやマイクの購入も有効です。リモートワークの環境が整えば、生産性の向上が期待できます。
設備投資
従業員が働きやすい環境を整備する目的で、設備投資に活用するのも良いでしょう。例えば、モニターや複合機などの導入が挙げられます。また、パソコンを最新にするのもおすすめです。日常的に活用するパソコンのスペックが向上すれば、業務効率化につながるでしょう。
福利厚生の実施
福利厚生に予算を活用すれば、従業員のモチベーション向上や社内環境の改善につながります。具体的には以下が考えられます。
- ウォーターサーバーの導入
- 飲食関連サービスの導入
- 食事会の実施
近年は、従業員が格安でお惣菜を購入できるサービスを導入する企業も増加しています。健康の維持につながるなどのメリットもありますが、継続的な契約が基本となるため、注意しましょう。
予算消化の注意点

最後に、予算消化を行う際の注意点について解説します。
コスト計算をしっかり行う
予算消化を行う際には、コスト計算をしっかり行いましょう。例えば、配送費や工事費など物品以外のコストを計算していなければ、予算をオーバーする恐れがあります。
また、単発的な費用だけでなく月額料金や年会費など、ランニングコストが発生する場合にも注意が必要です。継続が前提のサービス利用において、ランニングコストが発生しないように、単発的な利用を考えているのであれば、違約金・解約金が発生しないか確認しましょう。
架空発注や来年度分としての発注は行わない
架空発注や翌年度分としての発注は、絶対に行わないようにしましょう。万が一、実体のない発注を行えば、脱税行為として税務署から指摘を受けます。脱税は、追徴課税など税金の支払いが増えるだけでなく、刑事罰の対象になります。ニュースなどで脱税行為が報じられれば、企業イメージに傷が付くでしょう。
まとめ

予算消化とは、部署や部門などの組織に割り当てられた予算を、年度末・期末までに使い切ることです。予算消化をしなければ、翌年度の予算が減少したり、評価が下がったりする恐れがあります。翌年度以降に役立つものや、挑戦的な施策への費用として活用すると良いでしょう。
予算消化の方法には、販促品の作成やマーケティング施策の実施、物品・機材の購入など、複数の選択肢があります。翌年度以降の収益向上を期待するのであれば、データ活用がおすすめです。上手くデータを活用すれば、翌年度の戦略や方針の検討・決定にも役立つでしょう。