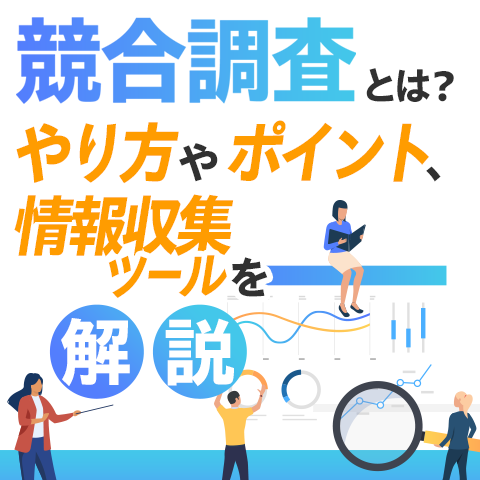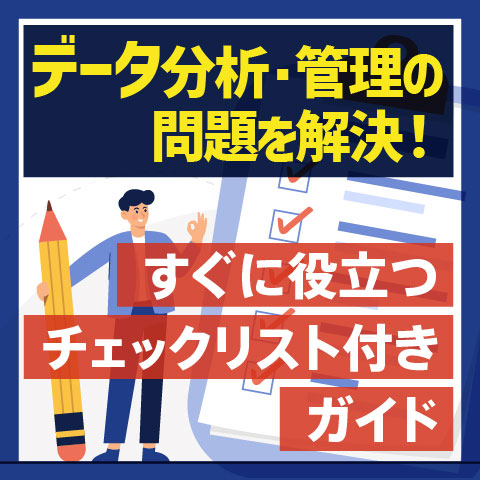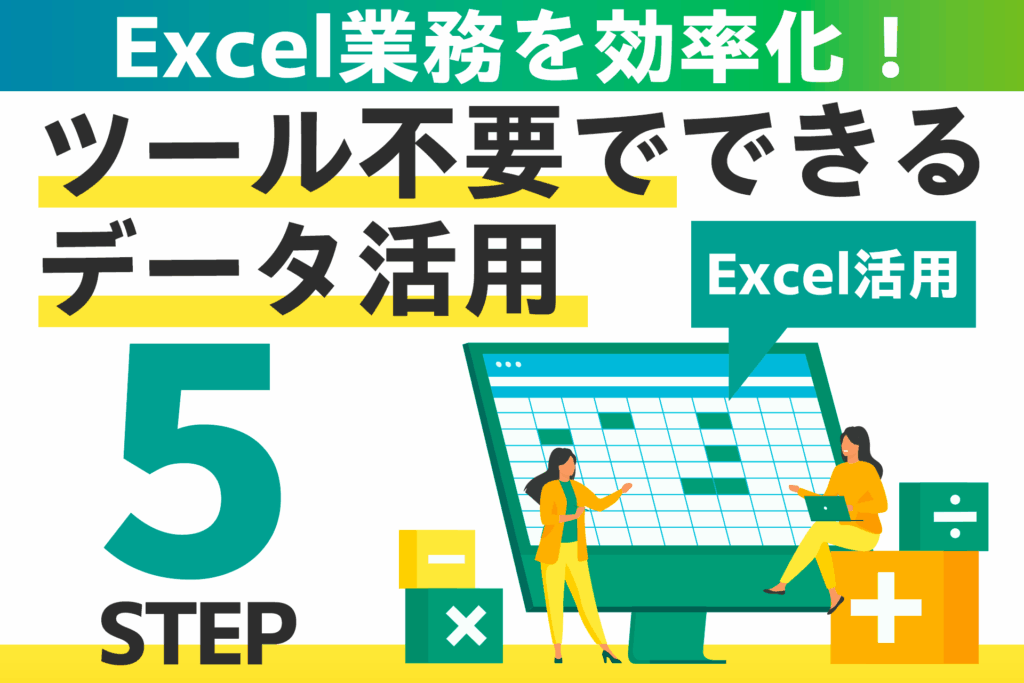
DXやBIツールの導入が話題になる一方で、「そんな大がかりな仕組みを入れる余裕なんてない」「ツールを導入しても結局使いこなせない」という声も多く聞かれます。実は、高価なツールを導入しなくても、今ある仕組みを見直すだけで、データ活用の質は大きく向上します。本記事では、私たちが実際の現場で見てきた「ツール不要で今すぐできるデータ活用改善のコツ」を5つのルールとしてご紹介します。
目次
対象読者
下記のような方向けの記事です。
- ツール導入には踏み切れていないが、Excelやスプレッドシートでの業務をもっと効率化したい方
- 社内で「データ活用を進めたい」という想いはあるが、何から始めればよいか悩んでいる部門のリーダー・担当者
- BIツールや分析基盤の導入検討前に、現場でできる改善策を探している方
「まずは、できるところから変えたい」そんな方のために、誰でも今日から取り組める“ツール不要”の改善ルールをご紹介します。
解決する課題
データの管理や品質周りの課題に集中して解決案を紹介します。データの品質とは、「正しい数値を確認できること」や「必要なデータが必要な時間までに用意できること」などを指します。今回対象になる課題は下記が挙げられます。
- データが正しい値を示しているか分からない
- 必要なデータがどこにあるか分からない
- データの状態を正しく保つための人員が不足している
データ利活用でのよくある課題については下記をご参考ください。
どのように課題を解決するか
本記事では主に「業務プロセスの改善」によって、上記課題を解決します。
主に下記のような解決策が挙げられます。
- 「共通言語」の周知
- 「チーム体制・連絡体制」の整備
- 「タスク管理」と履歴の記録
- 「ドキュメントルール」の可視化
- 「データの加工・利用ルール」の整理
1. 「共通言語」を周知する
日々の業務で扱う「売上」「取引件数」「原価」などの指標。実は、部門ごとに言葉の意味が微妙にズレていて、同じデータを見ていても解釈や意思決定がバラバラになってしまうケースが多くあります。これは、“データにおける共通言語”が整備されていないことが原因です。共通言語を作成し、周知することで売上の認識ずれのような問題を防ぐことができます。
例)立場ごとの「売上」の認識とよく発生するずれ
| 立場 | 売上の認識 | よく起きるずれ |
|---|---|---|
| 営業 | 受注額(契約締め切り日基準) | 未請求分も含むので実際の入金額とずれる |
| 経理 | 請求確定額(発行日基準) | 基準日が異なるので、営業と経理で別々の月の売上として計算される |
| 物流 | 出荷完了額(出荷日基準 | 長納期商品は「請求確定=出荷後」なので営業とずれる |
データの“共通言語”は、専門的なシステムやフォーマットを使わなくても、以下のポイントを押さえればシンプルに始められます。
どのように実行するか
データの“共通言語”は、専門的なシステムやフォーマットを使わなくても、以下の3つのポイントを押さえればシンプルに始められます。
1. 指標の「単語」と「意味」を明文化する
例:「売上=請求書発行済みの金額(税込)」「商談数=当月に完了した商談件数」など
2. 関係者が誰でもアクセスできる場所で管理する
Googleスプレッドシートや社内WikiでもOK。重要なのは「常に見られる状態」であること。
3. 定期的に見直し・周知の場を設ける
四半期ごとに「定義のズレが起きていないか」をチェック。更新したらチーム内で共有する。
2. 「チーム体制・連絡体制」を整備する
データ活用が社内で定着しない原因の一つに、「データを誰が管理するかが曖昧なまま運用が始まっている」ことが挙げられます。まずは、「データに対して誰が責任を持ち、管理するか」を明確にすることが、トラブルの防止・作業の効率化につながります。
▼データ管理が不明確な組織でよく起きる3つの問題
1. タスクの取りこぼしが発生する
- 複数の人やチームに別々にデータに関するタスクの問い合わせが発生してしまう状況では、本来データを管理するべきだった人が認識していない「見えないタスク」が発生してしまいます。
- 見えないタスクは、不正確なデータや重複したデータなどの様々な問題を発生させるため、防ぐ必要があります。
2. データが不明確になる
- データを管理する人が複数人いて、管理が集中していない場合、お互いに情報共有や連携が取れず、別々の作業が発生します。
- 共有されていない別々の作業は、Excelシートの誤った変更のように「不正確なデータ」に繋がります。
3. 重複作業が発生する
- 複数人が同じような指標・数値をExcelで計算し、すでに存在するデータを作成するように「重複したデータ」を作成することに繋がります。
- 重複したデータは、本来複数で別々に管理する必要のないデータのため、作業コストを増大させています。
どのように実行するか
データの責任者を決めたあとは、その人とチームメンバーがスムーズに連携できる“連絡体制”を整えることが重要です。特に、データを活用する現場と、管理・更新する側とのコミュニケーションチャネルの整備が欠かせません。
連絡体制の整備では、下記の2点が重要になります。
「データ管理者がデータに関する問い合わせを把握できること」
「データを利用する人がデータ管理者からデータに関する情報を受け取ることができること」
たとえば社内でチャットツールを使っている場合は、以下のように役割ごとにグループを分けておくと便利です。
- 「データ利用者」→「データ管理者」へ連絡するグループ
- 必要なデータの確認や作成依頼
- データに関する不明点の確認
- 「データ管理者」→「データ利用者」に共有をするグループ
- データ周りのルールの共有
- データの説明・共有
3. データ業務の「タスク管理」の仕組みを整備する
データに関する作業は、「分析」や「資料作成」だけではありません。実際には、日々さまざまなデータの抽出・整形・確認・共有・修正依頼などのタスクが発生します。こうしたタスクをその場しのぎで対応していると、属人化・抜け漏れ・再発防止の難しさなど、データ活用全体に悪影響が出ることがあります。そこで重要になるのが、「タスク管理」の仕組みを整備することです。特に以下の2つがポイントになります。
①データチーム内での担当者の分担と見える化
複数人のデータ担当者がいる場合、タスクを内容別に分担し、役割を明確化することが効率的です。データ種別ごとに担当者を設定することで、以下のようなメリットが得られます。
- 同じ種類のタスクを繰り返すことで担当者の知見が蓄積されやすくなる
- 問題発生時も「誰に聞けばいいか」がすぐに分かる
- データの品質を保ちつつ、対応スピードを上げられる
また、定期的に「タスク一覧」「担当分布」「未対応タスクの進捗」を確認する場を設けると、チーム全体での可視化と責任の明確化にもつながります。
②「いつ・誰が・なぜ・どんな作業を行ったのか」を記録に残す仕組み
データを取り扱っていると、「この数値はなぜ変わったのか」「いつから仕様が変わったのか」といった、過去の作業内容や変更理由を知りたくなる場面が頻繁に出てきます。たとえば以下のようなケースです。
- 月次集計の数値が前月と異なる
- 出力されるデータの形式や定義がいつの間にか変わっている
- 担当者が交代した後、処理内容が引き継がれていない
こうした状況に対応するには、「いつ・誰が・なぜ・どんな作業を行ったのか」を記録に残す仕組みを整備しておくことが重要です。
どのように実行するか
データ関連のタスクをチームで管理する際は、以下の2つを押さえることで抜け漏れや再発防止を減らすことができます。
① 担当者の明確化
・各タスクに明確な担当者名を設定
・タスクごとに、関連するデータの種類・業務・システムを記録
・担当者が不在時の代替対応ルールも併せて決めておくと安心
② タスクの記録テンプレート(例)
| 項目 | 記載内容の例 |
| 依頼内容 | 「月次売上の加工データを作成」 |
| 依頼者 | 経営企画部・田中さん |
| 依頼日 | 2024年6月10日 |
| 対応者 | データ管理チーム・鈴木さん |
| 作業内容 | 役員報告資料作成のため |
| 実施内容 | 売上データの一部列を除外、件数フィルタ適用 |
このようにタスク単位で「ストーリー」がわかるようにしておくことで、後から見たときにも判断や修正の根拠がわかりやすくなります。
4.「ドキュメントルール」を整備する
データ利活用が進む中で、「どんなデータがあるのか」「そのデータは何に使われているのか」が明確でないまま業務が進んでしまう企業も少なくありません。これを防ぐには、データ周りの情報をきちんとドキュメントとして管理・共有する「ルールづくり」が不可欠です。ここでは、最低限整備しておきたい以下の2つの管理項目について解説します。
- データアウトプット(出力物)の一覧管理
- 利用可能なデータセット(テーブル)の一覧管理
データのアウトプット管理ー「何に使っているか」を見える化する
ダッシュボード・レポート・CSV出力など、社内で作成・共有されているデータの「アウトプット」を一覧化しておくことで、トラブル時の対応力と運用効率が大きく向上します。
| アウトプット名 | マーケティングダッシュボード | 週次売上CSV |
|---|---|---|
| 形式 | Looker Studio | CSV |
| 利用者 | マーケティング部 | 経営層 |
| 更新頻度・SLA | 毎日 06:00 自動更新 エラー時 2h 以内復旧 | 毎週月曜 09:00 まで |
| 目的 | 広告 CPA/ROAS 監視 | 週次売上速報 |
| 管理者 | Aさん | Bさん |
| 使用データ | マーケティングデータマート | 日時売上データマート |
このような一覧を整備しておくと、以下のような場面で役立ちます。
- エラー発生時に、該当するアウトプットの管理者へ即時連絡できる
- データマートや基盤側の障害が起きた際に、影響を受けるレポートをすぐに洗い出して通知できる
- 新規レポート作成時に、既存の活用例を参考に再利用が可能になる
利用可能なデータリスト管理ー「何があるか」を可視化・体系化する
もう1つの重要なドキュメントが、「現在社内で利用可能なデータセットの一覧表」です。このリストがあることで、必要なデータを探す手間を削減し、セキュリティや重複作成のリスクも防止できます。
-
データの探しやすさ向上
- セキュリティ管理
どのデータにどのような権限管理がされているのかが分かる
- 重複データの予防
表に記載のあるデータは重複して作成される可能性が低いため、重複データの発生を防ぐことができる
- 運用コスト削減
不要になったデータの確認作業が楽になる
管理シートとして下記のような表を作成します。
▼管理項目の例(データセット一覧表)
| テーブル(データセット) | sales | customers |
|---|---|---|
| 内容 | EC注文単位の売上実績 | 顧客マスタ |
| 更新頻度 | 毎日9時 | 月曜9時 |
| 保存期間 | 直近5年 | 全て保存 |
| 管理者 | Aさん | Bさん |
| 権限 | 分析者全員 | 顧客情報閲覧者(制限) |
| データソース | Shopify API | PostgreSQL(CRM) |
| 加工ロジック | 受注→注文行にフラット化 金額を税抜換算 | 週次全件リロード 履歴保持なし |
このようなリストがあることで下記のようなメリットがあります。
- 「使えるデータがどこにあるか」をチャットで毎回聞かずに済む
- データへの権限管理やセキュリティの確認がしやすくなる
- 重複データの作成を防ぎ、運用コスト削減にもつながる
5. 「データ加工・利用ルール」を整備する
社内でデータを整理・活用していくうえで、データの保管場所や加工ルールがあいまいだと、次のような問題が起こりがちです。
- どのデータが最新かわからない…
- 同じようなデータが何か所にも存在している…
- 加工の履歴や意図が残っておらず、再利用や分析に時間がかかる…
どのように実行するか
こうした課題を解消するためにおすすめなのが、データを「三層構造」で管理するルールを整備することです。これは大規模なデータ分析基盤がなくても、フォルダやスプレッドシートの整理方法として中小企業でもすぐに取り入れられる考え方です。
▼データ三層構造の概要と管理ルール
| 層 | 置き場所(フォルダ例) | 説明 | 権限 |
|---|---|---|---|
| データレイク | 1_lake_raw | 未加工のデータを保存します。(基本的に上書きを禁止する) | データを管理する限られた人にのみ編集権限を付与する。 データウェアハウスでデータを作成する人には、閲覧権限を付与する。 |
| データウェアハウス | 2_warehouse_clean | データを統合・整形し、使用可能なデータを保存します。(個人情報などのデータは除外する) | データを作成・管理する人のみに編集権限を付与する。 |
| データマート | 3_mart_report | データウェアハウスの整えられたデータを元に、利用用途ごとに最適な形に選択・集計したデータを保存します。 | データを作成・管理する人のみに編集権限を付与する。 データを利用(閲覧)する人に対して参照権限を付与する。 |
この三層構造にすることにより、下記のようなメリットがあります。
- データの種類と用途が整理されているため、誰がどこを見るべきかが明確になる
- 未加工のデータとアウトプットが混在しないため、エラーや誤参照の防止につながる
- フォルダ単位でのアクセス権限管理がしやすくなり、セキュリティも強化される
- 利用者は「3_mart_report」だけを見ればよくなるため、業務効率が大幅に向上する
このようなフォルダ構成とルールの共通化を社内で進めることで、属人化の解消だけでなく、チーム全体のデータリテラシー向上や利活用のスピードアップにもつながります。大がかりなシステム導入なしでも実現できる、実践的なデータ活用の第一歩としておすすめです。
まとめ
データ活用を推進したいと思っても、「専用ツールがない」「スキルが社内にない」といった理由で止まってしまう企業も多いと思います。しかし実際には、ツールに頼らず、チーム内のルールや運用の整備だけで実現できる改善ポイントが数多く存在します。本記事で紹介した5つの実践ルールを実践し、“仕組み化”することからデータ活用を始めてみましょう。
- 「共通言語」の周知
- 「チーム体制・連絡体制」の整備
- データ業務の「タスク管理」の仕組み整備
- 「ドキュメントルール」の整備
- 「データの加工・利用ルール」の整理
これらは、今あるフォルダ構成やスプレッドシートでも十分に始められる取り組みです。まずは属人化を防ぎ、誰でも再現できる状態を作ることが、データ活用の第一歩です。それがやがて、より高度な分析や業務改善の土台になります。PigDataでは、自社に合ったデータ活用の仕組み作りのために、中小企業から大手企業まで対応した「データ分析基盤構築サービス」を提供しています。
- どこから着手すればいいかわからない
- 社内に散らばったデータを整理したい
- 手作業のレポート業務を改善したい
そんなお悩みに対し、現場目線に寄り添いながら、データ活用の仕組みづくりをゼロからご支援しますまずはお気軽にご相談ください。